社会学の部屋PartⅡ
年金問題は嘘ばかりジェンダー
ジェンダーgenderという言葉は、生物学で使う性別、セックスsexとは異なった用いられ方をしているようだ。しかし、男女同権やら、男尊女卑等を話題にする際は、セックスではなくジェンダーを意識しているようだ。
英米語におけるgenderには、以下のような用法があるらしい。
1.言語学における文法上の性のこと。
2.生物一般における生物学的性のこと。雌雄の別。
3.医学・心理学・性科学の分野における「性の自己意識・自己認知」のこと。性同一性。
4.社会科学の分野において、生物学的性に対する、「社会的・文化的に形成された性」のこと。男性性・女性性、男らしさ・女らしさ。
5.社会学者のイヴァン・イリイチの用語で、男女が相互に補完的分業をする本来的な人間関係のあり方。イリイチはその喪失を批判している。
6.電子工学・電気工学の分野におけるコネクターの嵌め合い形状(オスとメス)の区別のこと。プラグとジャック、雄ネジと雌ネジなど。
1の意味では、西欧語は男性名詞と女性名詞、さらにはご丁寧に中性名詞まである。動詞や形容詞の格変化にも性がついて回る。これも男尊女卑の思想の表れとして変えて行こうという動きもあるらしいが。
2の生物学的な性を考えると、男女の違いは明白であり、男女の役割が同じだなどということは絶対にありえない。そもそも男は子を孕(はら)むことは出来ないし、乳を与えることもできない。
6の意味は工学の分野なので、差別だなんてことは問題にならない。だからgenderは主に社会科学の分野において使われる、男らしさ・女らしさとその役割分担の在り方を議論しようということになる。
ただ、"gender"という語は生物学的な性を指す単語としても用いられているようだ。単に「sex」の婉曲的表現として使用する場合だ。例えば、女子のスポーツ競技において、生まれつきの性別を確認するために染色体検査が行われることがあるが、これを指す用語として英語ではgender verificationという用語を用いる。 染色体検査は女子にだけ行われる。何かこれも差別だという気もするんだけど。
ジェンダーとは、ある社会において、生物学的男性ないし女性にとってふさわしいと考えられている役割・思考・行動・表象全般を指す。男性にとっては男らしさであり、女性にとっては女らしさである。 ところが、この男らしさや女らしさという概念が、地域、民族、時代で千差万別であり、定義しようもない。論者が自分の勝手に考えている「男らしさや女らしさ」を前提に議論すれば、結果は発散してしまうことは目に見えている。
今、子供の教育で「男らしくしなさい。」とか「女らしくしなさい。」という表現は、だんだん使われなくなっている。こんなことを子供に説明することも難しくなっているし、そもそも適切な表現かどうかも怪しい。
男らしさや女らしさとは、本来、生物的な男性・女性が社会的にいかにあるべきか、という価値観の問題であるのにその価値観が多様では議論は収束しない。生物的性と社会的性は同一視すべきではないものの、相互に深い関わりを持つ。
話を具体的にするため、江戸時代の社会で考えて見よう。武士の家庭では男女の役割分担は明確だ。家の中の仕事はすべて妻の責任。男は藩の役所で仕事をし、給料を運ぶだけ。食事を仕切っているのは女性。「男子厨房に入らず。」出された食事を黙って食べるのが格好いい男。妻は外では「三歩下がって」夫を立てて、内では家計はしっかり握っている。これでバランスが取れていれば、男も女も文句を言わないだろう。町人や農民たちもこれと同じ。しかし、武士と違って女性もビジネス(商売や農作業)に参加している分、女性の立場は間違いなく強い。「かかあ天下と空っ風」か。
しかし、このシステムがうまく回っているのは、家族の中に子供がいる場合だね。男がせっせと給料を運ぶのはひとえに子供のため。家を守るためだね。江戸時代の職業は世襲制。仕事は祖父→父→子と引き継がれていく。子のいない妻はどうしても立場が弱い。養子でももらった方が良い。
このような社会どう思いますか。当時の人達はどう思っていたでしょう。どうも社会の中に女の世界と男の世界があって、交じり合わずに共存してますね。今の世界は男女同権で男の世界と女の世界は、相当に交じり合ってますね。まず、教育の場では小学校から大学まで男女はほとんど同じ教育を受けて育ちます。机を並べて学んだ同級生が、一方が女性だからと就職で差をつけられたら怒るのが当然。入学試験で点数にこっそり男女差をつけていて、問題になった私立医科大学があった。どんな職業でも向き不向きがあるでしょうから、男の方が向く、女の方が向く仕事もあるかもしれません。でも、それは人為的操作しなくても自然の成り行きでバランスが取れるのではないだろうか。でも一方で、力仕事の現場が減ったことでほとんどの仕事では男女の能力にはほとんど差がないことも科学的にも証明されている。
では、男女同権を否定し、男尊女卑を肯定する考え方は、江戸時代のような封建的な時代の遺物なのでしょうか。男女同権運動の推進に熱心な国は欧米の先進諸国です。実は戦前のヨーロッパ諸国では、家族に関する法律(民法)は、非常に権威主義的な物であったとか。ヒットラー政権下のドイツでは、子供が親の言うことを聞くのが当たり前、殴ったり、折檻したりするのは普通のことだったとか。また、労働者は上司の言うことには絶対服従問暗黙の掟が。このような風土が全体主義を助長したのだと反省されています。オランダ統治下のインドネシアでは、妻は家庭内のことで裁判を受ける権利が無かったとか。著しく男尊女卑を肯定する考え方が横行していたらしい。戦前は女性に選挙権などなくて当たり前。
どうも、男尊女卑の考えの根底には、伝統的な秩序が崩れ、工場で労働する男性・女性や戦争のための兵隊が増加し社会が不安定になってくることを防ごうという初期資本主義の思想ではないかと思う。一婦一夫制の核家族を理想とするキリスト教プロテスタントの考えがもとではないか。多数の労働者に均等に女性を分配するには一婦一夫制が良い。妻も子供も男の所有物だ。
しかし、総力戦となった第二次世界大戦時の連合国および枢軸国では、男性が徴兵され戦場に出向いている間、女性が工場労働に従事することになり、女性が労働力として社会参加することの大きなきっかけとなる。しかし、比較的多くの国家で男性に対してのみ徴兵制が課される。男尊女卑の考え方を肯定しないと、このルールは成立しない。
欧米の専業主婦の女性には家計を一切取り仕切る権利はないという。夫と妻の財布は別のようです。端的に言えば、妻も子供も夫の所有物という考えです。西欧のウーマンリブの女性たちが日本に来て財布の紐はしっかりと握っている専業主婦がいる事実を知ってビックリするそうです。西欧の専業主婦の女性は、夫の忠実な僕でないとならないらしい。だからひたすら社会参加を求めることに。専業主婦は同性からも馬鹿にされる。
キリスト教世界では、神が男性であるというイメージが保持されている。かつては神の使者たる天使も昔は成人男性の姿でイメージされていたが、近世以降は赤子や女性のイメージで描かれることも。カトリックやオーソドクスでは聖職者の特定の地位は男性にしか許されていない。プロテスタントでは女性の教職者が認められている教派が多いが。
仏教大乗仏教では、仏陀は男性であるとの主張が法華経の一節の解釈から生じているらしい。女性は成仏しないが来世に男性として輪廻すれば、成仏する可能性があるとの考えも。上座部仏教では、あくまで悟りを目的としており成仏を目的としない。経典では複数の女性が在家、出家を問わずに涅槃に到達している(阿羅漢果という)。仏が必ず男であるという大乗仏教の考えは異端性を示すものともいえる。
神道日本の神道では、明治以降は最高神が女性であるアマテラスとされている。道教道教では、陰と陽はそれぞれ女性と男性の属性であり、女性は月に、男性は太陽に支配されていると考えられている。
男尊女卑の思想は、宗教の影響も大きいようだ。特に、産業革命以降のプロテスタント達の考えは男尊女卑の考えを補強するのに一役買っている。
社会科学・哲学の部屋へ
社会学の部屋PartⅡへ
ミソジニー
ミソジニー (misogyny);
「ミソジニー」という言葉がある。「女性嫌悪」「女性蔑視」などと訳されたりする。女性や女らしさに対する嫌悪や蔑視のことだという。男性が女性に対して持つだけでなく、女性が同性に対して持つこともあると言われる。たまたま新聞の論壇の中で説明なしで使われていたのでWikipediaで調べて見た。しかし、「男尊女卑」等と言う語と何が異なるのかよく分からない。
ミソジニー (misogyny) とは、女性や女らしさに対する嫌悪や蔑視の事らしい。女性嫌悪、女性蔑視などともいう。女性、女性らしさを嫌悪する人物をミソジニスト(misogynist)と呼ぶ。
対義語には、「女性や女らしさに対する愛好」を意味するフィロジニー(philogyny)と、「男性や男らしさに対する嫌悪」を意味するミサンドリー(misandry)の二つがあるようだ。通常「女性嫌悪」「女性蔑視」などと訳される。男性にとっては「女性嫌悪」、女性にとっては「自己嫌悪」。
男性側のミソジニー
男性側のミソジニーの例として、女性に対する性的暴力やセクシャルハラスメント、制度的差別などに加え広告や映画、文学テクストなどにおける女性を憎む表現など。逆に男性に対する制度的差別?や身体的差別?等に対する意思などが挙げられる。
女性側のミソジニー
女性側においてミソジニーは、女性の体に対する羞恥心、拒食症などの摂食障碍、性的機能不全、鬱病、女性であることに起因する劣後感や無価値感。「女性であることが嫌だ」という感情の形をとって表れる。
社会・宗教におけるミソジニー
広く父権制的な社会においては、その社会構造に由来する必然的なミソジニーが見られるという。キリスト教やイスラム教のような父権制的な宗教では、父権的性質の薄い社会における宗教のテクストに比べ明らかなミソジニーが見られるらしい。こうした宗教社会では、女性は負の要素の象徴として、あるいはその元凶として描かれることが多いとされる。
ミソジニーと大衆文化
しばしばヒップホップなどの分野が、激しいホモフォビアの傾向とともにこの傾向を強く帯びる事がある。攻撃的なスラングをもって女性を嘲罵する一方で、当の女性たちからの熱い支持を受けもする。
**ホモフォビア(Homophobia)とは、同性愛、または同性愛者に対する恐怖感・嫌悪感・拒絶・偏見、または宗教的教義などに基づいて否定的な価値観を持つこと。フォビアという語は恐れとか嫌悪感の意味。Acrophobiaは高所恐怖症。Claustrophobiaは閉所恐怖症。Anthropophobiaは対人恐怖症。Female phobiaなら女性恐怖症。対人恐怖症ならSocial phobiaでいいようだね。色々多様な性癖があるのは別にとやかく非難する筋合いは無いが、もし、このような人達やそれに反対する人達の行動や言動が他の人に害を及ぼすならそれは問題だ。
インターネットスラング
インターネットスラングにおいては、ミソジニーは反フェミニズム(いわゆるアンチフェミ)とほぼ同義で使われる傾向があるとか。反フェミニズムを掲げているSNS上のユーザー内に一定数ミソジニストが存在する為か、混用され使われる様になったとか。しかし、反フェミニズム=ミソジニストという構図は成り立たない。アンチフェミニズムはフェミニズムと敵対する思想や人物であるのに対し、ミソジニーは社会や人間の心や行動の中にあるものを指す概念である。
実はここまで調べても「男尊女卑」とミソジニーの違いは何なのかよく分からない。そもそも、ネット上で「私は反フェミニズムだ」と声を上げてなんか意味があるのだろうか。同様に、「私はミソジニストだ」と宣言することに意味があるとは思えない。
ところで例として、「女の子の誰一人として僕に振り向いてくれなかったから、大学の女子学生を無差別に殺した」というような事件があったとする。このような事件は、犯人自身とはまったく関係ない女性たちを、彼女たちが女性であるという理由で殺害したという意味において、ミソジニーという概念にもっとも適合しているように思えるとの意見があった。これなら一種のFemale phobiaなら女性恐怖症の変形か。「男尊女卑」と言われる男性も劣等感の裏返しが差別に繋がるから。
社会科学・哲学の部屋へ
社会学の部屋PartⅡへ
なぜ韓国は日本離れしつつあるのか
なぜ韓国は日本離れしつつあるのか
懸け橋、という言葉がある。
以下は韓国在住の女性の方の投稿から。
“定かではないが、自分で使ってみた記憶(懸け橋という言葉)はほとんどない。かつては特にどうとも思わなかったが、韓国に住むようになってからというもの、積極的に使いたいとは思えない言葉になってしまった。
だが、そう思うようになってから、私の目の前では使う人が増えていったような気がする。「日韓の懸け橋になりたい」 そんなことを言われてしまう。でも、私はすぐに「そんな無理をするのはやめた方がいいよ」と返事。何故??
自己犠牲の精神に何度も驚愕。相談を切り出してくる人の年齢はさまざまだが、若い人が多い。日本語を勉強している大学生、ワーキングホリデーや留学などで韓国で暮らしている日本人もいる。私の教え子(韓国語?)数人もそのなかに含まれる。
彼らが私についついそう言ってしまいたくなる気持ちは、理解できなくもない。私は日本人であると同時に韓国でかれこれ15年も暮らしている。日韓交流おまつり、という交流事業でもそれなりに積極的に関わっていたこともある。
だから、私に「日韓の懸け橋になりたい」と切り出すときに、まさかそれを否定されるだなんて、思ってもいないのだろう。その証拠に、「やめた方がいいよ」と答えると、キョトンとした顔をする。顔というのは、正直だ。
「日韓の懸け橋」なんて、いかにも美しい言葉ではないか。でも、私には、そのいかにもの美しさが、好きになれない。「日韓の人たちは、がんばってでも仲良くしましょう、そのために、自分が近くて遠い2つの国を繋いでみせます!」と、自己犠牲に満ちた表現になってしまうからだ。本人たちに聞いてみても、“人生を捧げます”というくらい強い意味で使っているという(韓国に永住する? 韓国人と結婚する?)。
「日韓の懸け橋」はいかにも不毛である。まず、国通しの関係が良くない。その上、日本には嫌韓感情があり、韓国には反日感情がある。そんな状況は、数十年単位で改善するとは思えないし、それどころか、両国相互の感情はこれからもっと悪くなるだろう。年を重ねてから「私の人生何だったのか」なんて思うのがオチだ。
そんな若者の将来が見え見えだ。「世の中にはもっと楽しいことがあるから、それは考え直した方がいいよ。日韓はきっと、根本的には変わらないから、もっと気楽に日本のことに関わってよ」と、アドバイスをする。
北朝鮮よりも日本に「敵がい心」
とはいえ、そのアドバイスに自信があったわけではない。その根拠としてきた日韓両国民の感情の対立は、あくまでも私が日本人として韓国で生活するなかでの実感として思っていただけだったからだ(**個人的な経験なので一般論として通用するかどうか?)。
ところが、それをデータとして明確に示してくれる記事がつい先日、出た。中央日報による7月8日付の報道。日本に対して敵がい心を抱いている韓国人は71.9%にのぼり、対北朝鮮の65.7%を上回るという(つまり、北朝鮮は今は敵対していても本来は同朋だからね)。
この数字が異様に合点がいく。敵がい心という言葉も微妙な訳だが、原文で使われている「敵対感」は、政治外交上での意味も含む。だから、韓国という国にとって脅威だと思うかを問うアンケートだと考えればよい(もっと端的に言えば仮想敵国)。
韓国人が日本に敵対感情を抱いてしまうの理由の一つに、いわゆる歴史認識問題で韓国に厳しい姿勢をとる安倍首相の存在も大きい。ともかく安倍首相のことは無条件に嫌いな人がほとんど。とくにこの数年は、徴用工裁判の影響もあり、そんな傾向が強い。
では、日本の首相が別の人になれば、対日感情ははっきりと改善するかというと、そうは思えない。というのは、韓国社会が徐々に内向きで排他的になっていることも、記事で指摘されているからだ。
たとえば、中国への敵がい心はこの5年間で16.1%から40.1%に増加した。また、多民族・多文化国になるべきだと考える人は、この10年間で60.6%から44.4%に、つまり、約4分の3まで減少した。さらに、外国人居住者を受け入れるのに限界があると回答した人は増えていて、10年間で48.9%から57.1%に膨らんだ。
また、日本語では報じられていないようだが、この調査に関連する別の記事もある。国際結婚の家庭の子どもたちのことを韓国人だと思えるか、という質問に対して、肯定的な回答をしたのは、10年前の36.0%から17.1%と減少した。さらに、そうした子供を韓国人だと思えないと回答したのは、18.8%から32.4%に増加している。
日本も内向きだと言われているが、韓国も輪をかけて内向き志向。しかもその傾向がまします強まっているのがデータから一目瞭然。
だが、韓国でそれを問題として扱うニュースや論説記事は。私にはその記憶がない。その一方で、我が家では日本の放送はNHKの国際放送しか視聴できないが、日本国内に暮らす外国人の苦労話の報道は何度も見ている(**日本も相当少なくない?)。ということは、韓国社会は、いま、自分たちが内向きに傾いていることに無自覚。あるいは、そこから目を逸らしている(**日本も実際には相当内向きだと思うけど)。
国内に蔓延しつつある内向き志向をどう克服するかは、韓国社会が今後10年以上かけて向き合っていくべき課題となるであろう(**多分当面は克服する意図はなさそう)。そのうえで諸外国の事情を受け止められるようになるのには、もっと時間がかかるし、できるようになるのかでさえ、未知数。
そのなかで、歴史認識問題ですれ違う日韓両国民で、どれだけ理解し合えるのだろうか。ここでは日本の状況を書く余裕はないが、程度の差こそあれ、似たり寄ったりだと思う。だから、無理して付き合いを深めるよりも、興味のある人が肩の力を抜いて往来し、互いに協力できることはそれなりにやればいい。そういうことは、肩に力を入れなくても続けられる。
ちなみに、韓国が好意を寄せる国はアメリカ。敵がい心を持つ人の割合は上昇したが、トランプ政権による韓国への辛めの対応のわりに、10.2%に留まる。ヨーロッパの国々に対してはデータがなかったので不明だが、実感としては、アメリカに近いはずだ。ちょっと皮肉な言い方かもしれないが、韓国社会はいま、脱亜入欧に傾いている。“(JBpress: 2020.7.19)
以上、筆者が主張する“懸け橋”になろうとするのは、止めなさい。“懸け橋”になんかなろうとしても不可能という助言だ。年を重ねてから「私の人生何だったのか」なんて思うのがオチだ。このアドバイスは、理想に燃えた若者たちへ優しいアドバイスだね。
これ、韓国語を習い始めて、だんだん韓国の文化にも慣れてきて、何年か韓国にも在住して、韓国人達の反日感情、逆に日本人たちの嫌韓感情にも嫌気がさし、何とかその溝を埋めたい。その“懸け橋”となれれば。おそらく彼等は、韓国にも親しい友人が出来て、お互いに意見も交換できる間柄になっているのでしょう。だから、それまで問題にもしていなかった両国民感情の深い溝を何とか解消したいとの気持ちが出てくるようだ。
しかし、所詮あなたは日本人、彼等は韓国人、歴史や文化や国際政治のしがらみの中で造れた深い溝は、簡単には解消されないということだ。
でも、もしあなたが韓国に住んで韓国人の男性或いは女性と結婚する。韓国の会社に就職する。逆に日本で韓国の方と結婚する。韓国の人を会社で雇う。なんていう場合は、この深い溝が存在することを前提にお付き合いしないと行けない。そうしないと余計なトラブルに巻き込まれることが多くなる。
韓国語に限らず、語学が好きになるにはその国の全体が好きになってしまうのが語学の習得には手っ取り早い方法だろう。しかし、あまりにも感情移入し過ぎるのは危険な様だ。確かに韓国人達の反日感情、逆に日本人たちの嫌韓感情も中立の立場で見れば根拠も薄い不合理なものが多い。しかし、当人たちにとっては空気のようなもので、理屈抜きで当然のこととして逆らうことが出来ないものだ。
現在新型コロナが世界中で大流行している。そんな情勢下でコロナはチョットした風邪かインフルエンザのようなもの。そんなに危険ではないよ。なんて、うっかり口走れば空気の読めない大馬鹿だと大バッシングを受けること請け合いだ。
これと同じで、韓国内で日本人もいい人多いよ。何て言えばひどいバッシングを受けるらしい。韓流スターたちもこれに苦労しているらしい。
社会学の部屋PartⅡへ
カッコウの托卵
先日話題にあげた、カッコウの托卵の話の補足。
実際の鳥のカッコウは、托卵した後は、親子の縁が完全に切れる。ところがヒトの場合は、変な未練が残るせいか、また復縁し昔の関係を取り戻したいとの妄想が起こる因果な生き物らしい。いわゆる「生みの親か、育ての親か?」の話。現実には時間を逆に動かすことは全く不可能。結局は、現状をひとまず肯定した上で、子供の権利を最優先に考えて関係者全員で子供の将来を熟慮して話し合いで解決する以外にない。
今回の事件は、娘Mの所属を巡って、カッコウ夫婦T&Aが彼等の実の育て親A&Yを裁判に訴え、「娘Mを引き渡せ」の判決を勝ち取った。その結果はどうだったか? 当然前提として肝心の娘が喜んで両親のもとに飛んでくる? そんな夢みたいな話が現実になる訳がない。肝心な娘Mは怒り心頭に達し、断固戦う決心をする。
勿論、裁判所の判決は、そんなこともお見通し。「娘さんMの意志があれば」の条件付き。でも、こんなことすれば、「ああ、そうですか。」で収まりがつくはずがない。
当初、カッコウ夫婦T&Aは、子供を現に養育してくれている自分達の両親を仮想の敵として、彼等が娘Mの意志に反して囲い込んで、自分たちを排除していると勝手な思い込みをする。邪悪な彼等の支配を取り除けば、自分達の娘Mは、喜んで自分達の処へ来ることを大前提にして、弁護士を頼み、上記判決を勝ち取ったつもりだった。ところが娘の意志は明か。彼等は理不尽にも自分を連れ去り虐待を考えている邪悪な鬼達でしかない。
それまでは、彼等は、親権オカルトに基づく勝手な思い込みかもしれないが、一定の囚われの娘を救い出すという大義名分を掲げていた。しかし、判決をいざ実施しようとすると、今度は自分達が、単に理不尽にも娘Mを連れ去り虐待を考えている邪悪な鬼のような存在にしかならない。子供の権利まで侵害しては、親権オカルトを主張しても権利の濫用になることは一目瞭然。しかも、判決が出てみると、取りあげた等勝手な思い込みであることが判明。。そもそも、趣味で子育てする酔狂な人、そんなに多くない。実際のカッコウの育ての親だって、騙されて育てているんだから。
では、どうすれば和解できる。そもそも宣戦布告して戦いを始めたのは自分達。親権オカルトに固執している限り、周囲の人達から見れば、彼等はある意味犯罪者。まず、真摯に反省し、自分の娘に頭を下げて、陳謝の意を何らかの見える形で示さないことには、永久に敵対関係になってしまうぞ。
社会学の部屋PartⅡへ
日本学術会議とは
日本学術会議は、科学に関する重要事項を審議したり、研究の連絡をすることを目的にした科学者の組織だ。政府に対して提言をするのが役割の一つ。210人の会員は非常勤特別職の国家公務員。この210人の半数の105人が3年ごとに入れ替わる。ということは職員は、大学の研究などの本業との掛け持ちということか。
会議は、内閣総理大臣が管轄するが、政府から独立して職務を行う「特別の機関」だ。国費で運営される。原子力三原則など国の大型プロジェクトの元になる「マスタープラン」を策定したり、素粒子実験施設の誘致についてや地球温暖化、生殖医療などについて提言や声明を発表したりする。人文・社会科学、生命科学、理学・工学の全分野の約87万人の科学者を代表し「科学者の国会」とも言われる。
菅首相は10月1日、会議が推薦した会員候補105人のうち6人を除外して任命した。推薦された人を任命しなかったのは、会議が推薦する方式になった2004年度以来初めてのことだ。この除外された6人はどんな学者なのか。
安全保障法制や「共謀罪」法に反対を表明した学者らが含まれている。日本学術会議への人事介入に抗議する というハッシュタグができるなど波紋を呼んでる。確かにこれは問題だ。反対派いることで議論が盛り上がり良いものが出来る。
除外された6人に含まれる加藤陽子教授は、10月1日付の毎日新聞にコメントを寄せた。「なぜ、この1カ月もの間、(学術会議会員の人事を)たなざらしにしたのか。その理由が知りたい。そのうえで、官邸が従来通りに、推薦された会員をそのまま承認しようとしていたにもかかわらず、もし仮に、最終盤の確認段階で止めた政治的な主体がいるのだとすれば、それは『任命』に関しての裁量権の範囲を超えた対応である。念のため、付言しておく」としている。
加藤教授は公文書管理について政権に意見を届けてきた。公文書管理について、小泉純一郎政権で政府の有識者懇談会に参加し、2010年設置の「内閣府公文書管理委員会」委員。現在は「国立公文書館の機能・施設の在り方等に関する調査検討会議」の委員を務めている。
【任命されなかった6人】 (共同通信によると)
1.芦名定道(京都大教授 ・キリスト教学)
「安全保障関連法に反対する学者の会」や、安保法制に反対する「自由と平和のための京大有志の会」の賛同者。
2.宇野重規(東京大社会科学研究所教授・政治思想史)
憲法学者らで作る「立憲デモクラシーの会」の呼びかけ人。 2013年12月に成立した特定秘密保護法について「民主主義の基盤そのものを危うくしかねない」と批判していた。
3.岡田正則(早稲田大大学院法務研究科教授・行政法)
「安全保障関連法案の廃止を求める早稲田大学有志の会」の呼び掛け人。沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設問題を巡って2018年、政府対応に抗議する声明を発表。
4.小沢隆一(東京慈恵会医科大教授・憲法学)
「安全保障関連法に反対する学者の会」の賛同者。安保関連法案について、2015年7月、衆院特別委員会の中央公聴会で、野党推薦の公述人として出席、廃案を求めた。
5.加藤陽子(東京大大学院人文社会系研究科教授・日本近現代史)
「立憲デモクラシーの会」の呼び掛け人。改憲や特定秘密保護法などに反対。「内閣府公文書管理委員会」委員。現在は「国立公文書館の機能・施設の在り方等に関する調査検討会議」の委員。
6.松宮孝明(立命館大大学院法務研究科教授・刑事法)
犯罪を計画段階から処罰する「共謀罪」法案について、2017年6月、参院法務委員会の参考人質疑で「戦後最悪の治安立法となる」などと批判。京都新聞に対し「とんでもないところに手を出してきたなこの政権は」と思ったとインタビューに答えている。
どうも、皆さん立派な方ばかり見たいだ。テレビでいい加減なコメント発している学者とはことなり、極めて地味な活動をしておられるようだ。こんな方々を自分の意見に賛成でないと言って指名を拒否することは立件民主主義の理念にも反する。どう見ても菅首相の頭の中の方が変だね。
社会学の部屋PartⅡへ
アメリカ合衆国憲法修正第12条
マスコミの報道で米国の大統領選挙は民主党のバイデン氏の確定とされて報道されているが、共和党のトランプ氏は選挙に不正があったとして談合を拒否し、敗北宣言を出さない。つまり、現状では次期大統領は決まっていないことに。
だから世界の各国の対応はさまざま。さっそく祝辞をおくりバイデン氏に媚びを売る国(欧州、日本)から、冷静に楽しんで見ている国まで(ロシア、中国、その他)様々な様だ。
結局は法廷闘争に持ち込まれ、最後は最高裁判所と判断となるようだ。しかも、トランプ氏の一見無謀な頑張りも米国の憲法で認められた合法な手続きとなれば、これを感情論で非難することは的外れということに。
アメリカ合衆国憲法修正第12条(Twelfth Amendment to the United States Constitution、あるいはAmendment XII)は、アメリカ合衆国憲法第2条第1節第3項を置き換え、大統領選挙を規定するものである。
憲法の当初の条項では、選挙人団の各自が2票を大統領候補に投じ、過半数を得た者が大統領に、次点の者が副大統領になることになっていた。このやり方の欠点が1796年と1800年の大統領選挙で露呈された。修正第12条は、1803年12月9日にアメリカ合衆国議会により提案され、1804年6月15日に必要とされる数の州によって批准された。選挙人が2票を持つことは同じだが、大統領と副大統領にそれぞれ1票ずつ投票することになった。
**当初の憲法では、次点のものが副大統領は現在の二大政党のもとでは守られていない?
いや、米国大統領選挙は直接国民が選ぶのではなく、誰を選ぶかは選挙人に任されているらしい。
当初の形式での大統領と副大統領に対する投票
アメリカ合衆国憲法第2条第1節第3項では、各選挙人が2票を投ずることになっていた。各選挙人は2票ともに選挙人と同じ州の住人に投票することはできなかった。選挙人票の過半数(50%以上)を得ることが当選者に求められた。
選挙人票の過半数を得た者が1人を超えて存在し、且つ、その得票数が同数の時は、アメリカ合衆国下院がこれらの候補者の中から選択することになっていた。もし、だれも過半数を得られなければ、下院は選挙人票の上位5人の中から選ぶこととされていた。
副大統領の選出はより単純な方法だった。大統領に次いで最高得票をした者が副大統領になった。大統領と違って副大統領は選挙人票の過半数を得る必要がなかった。多くの候補者の中で次点が2人以上いる場合、アメリカ合衆国上院がその中から1人を副大統領に選ぶことになっていた。各上院議員は1票ずつを投じた。当初の憲法のやり方では、候補者の票が同数になった場合に現職の副大統領(上院議長を兼ねる)が最後の1票を投じることができるか否かについて、規定がなかった。
1800年の大統領選挙では当初のやり方の欠陥が露呈され、もし選挙人団のそれぞれが党の公認候補に投票すれば、最も票を集めた者2人が同数になるということだった。下院では大統領を選ぶために何度も投票を重ねることになるということも示された。
さらに、副大統領は選挙人投票で大統領の対抗馬であったという状況では、2人が効果的に協力してことに当たる能力を妨げ、少なくとも理論的には(副大統領は現職大統領の排除もしくは死の場合に大統領職を継ぐことになるため)クーデターの引き金にもなりうるということが徐々に明らかになってきた。修正第12条では、大統領と副大統領を順番に別々に選ぶことで、そうでない場合に比較してこの可能性を排除することになった。
修正第12条での選挙人団
原文:アメリカ国立公文書記録管理局に保管されているアメリカ合衆国憲法修正第12条
選挙人は各々その州に会合し、秘密投票によって、大統領および副大統領を決定する。この二人の内、少なくとも一人は、選挙人と同じ州の住民であってはならない。選挙人は、その投票において大統領として投票する者を指名し、別の投票において副大統領として投票する者を指名する。また選挙人は、大統領として投票されたすべての者あるいは副大統領として投票されたすべての者の表ならびに各人の得票数の表を作成し、これらの表に署名し証明した上、封印をして上院議長に宛て、合衆国政府の所在地に送付しなければならない。
上院議長は、上下両院議員出席の下に、すべての証書を開封し、次いで投票が計算される。
大統領として最多得票を獲得した者を大統領とする。ただし、その数は任命された選挙人総数の過半数でなければならない。もし何人も右の過半数を得なかった時は、大統領として投票された者の内、三名を超えない最高得票者の中から、下院が直ちに秘密投票により大統領を選任しなければならない。大統領の選任に際して、各州の下院議員団は一票を有するものとし、投票は州を単位として行う。この目的のための定足数は、全州の三分の二の州から一名またはそれ以上の議員が出席することによって成立し、また選任のためには全州の過半数が必要である。もし右の選任権が下院に委譲された場合に、下院が次の三月四日まで大統領を選任しない時は、大統領の死亡またはその他の憲法上の不能力を生じた場合と同様に、副大統領が大統領の職務を遂行する。
副大統領として最多得票をした者を、副大統領とする。ただし、その数は任命された選挙人総数の過半数でなければならない。もし何人も右の過半数を得なかった時は、右の表の内、二名の最高得票者の中から、上院が副大統領を選任しなければならない。この目的のための定足数は、上院議員の総数の三分の二とし、また選任のためには総数の過半数が必要である。しかし何人といえども、憲法上大統領職に就く資格のない者は、合衆国副大統領の職に就くことができない。
適用
この修正条項は1804年の大統領選挙から適用され、選挙人団の構成は変えなかった。むしろ、選挙人団が、さらに必要ならば下院が大統領を選ぶ手順を修正した。
修正第12条の下では、選挙人は大統領に2票を投じる代わりに、大統領と副大統領を区別して投票しなければならない。どの選挙人も選挙人と同じ州に住む大統領と副大統領候補者双方に投票することは許されない(住人条項)。しかし、選挙人が同じ州の一人の候補者に投票することは可能である。
修正第12条は、憲法に定める大統領として不適格な者が副大統領になることを明確に排除。その問題は、修正第12条に定める憲法上の不適格者および修正第22条の任期制限が、以前に大統領職を務めた者あるいは大統領を代行した副大統領に適用されるかということであり、合衆国最高裁判所によって裁定が出されておらず、他の憲法修正条項の批准で規定されてもいないために、憲法上不明なままである。
大統領あるいは副大統領として選ばれる者には選挙人投票の過半数が現在も要求されている。誰も過半数に達しない場合、下院が州ごとの投票により、また憲法第2条で要求される定足数で大統領を選出する。修正第12条では当初の憲法で5人の中から選ぶとしていたものを、3人を超えない候補者から選べるようにした。
同様に上院は、もしどの候補者も選挙人投票で過半数に達しない場合、副大統領を選ぶことが出来る。その選択は選挙人投票での「上位2名」にある者に限定されている。もし多くの候補者が同点で2位となった場合、最高得票となった候補者に加えて、同点の者全てを対象にすることができる。修正第12条は、投票を行う時に州または議員の3分の2という定足数要求を導入した。さらに修正第12条は上院の「議員総数の過半数」の票が選出のために必要であると規定している。
国家指導者がいないというような行き詰まりを避けるために、修正第12条では、もし下院が3月4日(当時、大統領任期の初日)以前に大統領を選べないときは、副大統領に選ばれた者が「現職大統領の死もしくはその他の憲法上の不能の場合と同様に」大統領職を代行する。修正第12条では、副大統領がいつまで大統領を代行するか、あるいは3月4日以降に下院が大統領を選出できるかについては、述べていない。憲法修正第20条第3節は、大統領の任期開始日を1月20日に変え、また両院が行き詰まった場合に「誰が大統領職を代行すべきか」を立法によって指示することができるようにすることで、修正第12条の規定に置き換わった。
1804年から現在までの選挙
ヘンリー・クレイ。1824年の選挙で裏取引をやったと非難された。
1804年の大統領選挙以降全ての選挙は修正第12条に基づいて行われてきた。その時以降下院が大統領を選出したのは1度だけある。1824年大統領選挙で、アンドリュー・ジャクソンは選挙人票99票を獲得し、ジョン・クィンシー・アダムズ(ジョン・アダムズの息子)は84票、ウィリアム・クロウフォードは41票、ヘンリー・クレイは37票を得た。候補者全てが民主共和党員であり(候補者の間には重要な政治的違いはあった)、誰もが選出に必要な過半数の131票に届かなかった。副大統領の方は競合が少なく、ジョン・カルフーンが182票を得て即座に選ばれた。
下院は上位3人のみを対象にできたので、クレイは大統領になれなかった。クロウフォードは卒中を患った後の健康が優れず、下院で選ばれる可能性が消えた。アンドリュー・ジャクソンは一般投票でも選挙人投票でも最高得票を得ていたので、下院が自分を選んでくれるものと期待していた。しかし、下院での1回目の投票でアダムズが13州、ジャクソンが7州、クロウフォードが3州という結果になった。クレイがアダムズの大統領を後押しした。クレイは下院議長だったので、クレイの後押しは余剰効果があった。アダムズがクレイをアメリカ合衆国国務長官に指名したとき、多くの、特にジャクソンとその支持者はこの2人を「裏取引」をやったと非難した。他の者は、大統領候補者がその立場を強化するために、その副大統領後者を指名するように、これは政治における通常の連携であると理解した。さらにある歴史家は、クレイが理論的にジャクソンよりもアダムズに近く、クレイ支持者がアダムズの支持に回ったのは自然であるとも言った。
1824年の選挙後、民主共和党は民主党とその後にホイッグ党となるものに分かれた。1836年の大統領選挙では、ホイッグ党が選挙人の票を分散し民主党の候補者マーティン・ヴァン・ビューレンが過半数を取れないようにするために、異なる地域に異なる候補者を指名し、それによってホイッグ党が支配する下院での議決に持ち込もうとした。しかし、この戦略は失敗し、ヴァン・ビューレンが一般選挙でも選挙人選挙でも過半数を獲得したので、それ以降合衆国の主要政党が国政選挙で地域候補を出す戦略を採用することは無かった。
1836年の選挙では、これと同時に副大統領候補が誰も選挙人選挙で過半数を獲得できない選挙になった。民主党の副大統領候補リチャード・メンター・ジョンソンは以前の奴隷との関係ゆえにバージニア州の民主党選挙人の票を獲得できなかったことが原因だった。その結果ジョンソンは147票となり過半数に1票足りなかった。次に来るのはフランシス・グレンジャーの77票、ジョン・タイラー47票、ウィリアム・スミス23票だった。しかし、選出は上院に委ねられ、ジョンソンが33票を獲得し、グレンジャーの17票を破って当選した。
修正第12条では、大統領と副大統領が同じ州から選ばれることを排除していないが、住人条項に対してやや難しくなっている。現代の選挙では副大統領候補が異なるタイプの有権者に訴えるためにしばしば選ばれている。この問題は2000年の選挙でジョージ・W・ブッシュ(副大統領候補はディック・チェイニー)とアル・ゴア(副大統領候補はジョー・リーバーマン)との間で争われた時に起こった。チェイニーとブッシュはどちらもテキサス州住民であり、テキサス州の選挙人が双方に投票することは修正第12条に違背するものだと主張された。ブッシュはテキサス州知事だったのでその住所は問題が無かった。チェイニーとその妻はハリバートンの社長の役割を果たすために5年前にダラスに引っ越した。チェイニーはワイオミングで育ち、合衆国議会はワイオミング州の代表だった。選挙の数ヶ月前、チェイニーは有権者登録と自動車免許をワイオミング州に移し、ダラスの自宅を売りに出した。3人のテキサス州選挙人がダラスの連邦裁判所にこの選挙の異議申し立てを行い、続いて第5巡回控訴裁判所に控訴したが、そこで却下された。
**実に複雑で分かりにくい。本文はWkipediaからの引用で。いずれにしろ米国の次期大統領は簡単には決まりそうもない。簡単に決まらないことが立憲主義のいい所でもああるのですが。
社会学の部屋PartⅡへ
中間層の役割
今までの日本は、「一億総中流」等と言われていたが、今は格差社会で上流国民と下流国民に分かれているんだなんていう論者もいるらしい。中流と中間は意味がやや異なるかもしれないが、下記は古典を元にした政治論的な試論。
 福沢諭吉先生が「学問の進め」で喝破している。
福沢諭吉先生が「学問の進め」で喝破している。
国を豊かで強くするのは国民一人一人の努力と精進にかかっている。
よく見、良く聞き、よく理解して、おのおの天職を通じて、努力することしか国の発展はない。
技術者が頑張らないと良い車は出来ないし、医者が頑張らないと良い医療は出来ない。
教師が頑張らないと良い生徒は育たない。政府が旗振っても国民は動かない。
天職に目覚めた彼等が、自分達の意見を代弁する代表を選び、国を動かす。これが民主主義の基本原理。このように代表を選出する力量を持った人が中間層と位置付けられるのでは?
欧米流民主主義は、権利の拡大として有選挙権者を増やすこと正当化してきた。
でも、これが本当に民主主義が発展したのかと言えば異論があるだろう。
馬鹿でもチョンでも1票は1票だ。その結果生じることは、中間層の没落と衆愚政治。
古代ギリシャ・アテネの成功と没落の構図と同じ。
古代ローマ人は、はっきりと多数決による民主主義は愚劣と認識して採用しなかった。
歴史は繰り返す。1度目は悲劇として、2度目は喜劇として。
History repeats itself. The first as a tragedy and the second as a comedy.
История повторяется. Первая как трагедия, вторая как комедия.
历史总是重演。 第一个是悲剧,第二个是喜剧。
新型コロナは、2度目危機だ。意味も無く都市封鎖して(既に都市内には感染者有)。
、
喜んで自ら在宅規制。マスクして人と距離置き話をしない。絶対に感染したくない(でも誰でも感染する)、何時までもstay home 続けましょう。感染は間違いなく収束しない、コロナとの共生を図るしかない。でもそれはいや。何時までも何時までもstay home。 初めからワクチン何て期待できない。
衆愚う政治の見本そのものだね。
まるで映画「猿の惑星そのものだ。」後世の人から見たら、絶対にお笑い草の喜劇だろう。
【追記】追記
フランスの政治思想家にトクビルという人がいる。彼自身は自由主義の考えの持ち主だったらしけど、親戚かなんかの関係で反革命派とされて米国に亡命する。彼は自身の足で当時の米国各地を視察して手記をまとめている。次の逸話は米国民主主義の理想の形を示すものとして有名なのでは?
学生時代に読んだなんかの本に紹介されていたもので詳細や出典は分からないが。
 トクビルさんが独立後間もない頃の米国のある地で見たことらしい。住民たちが集まっているところに、議員たちの集団が通りかかり。偉そうなそぶりで、「どけどけ議員様のお通りだ。」住民達:「??」「俺たちは市民の代表だぞ!!」「!!」後ろの方から「バッカヤロー。俺たちがその市民だ。」
トクビルさんが独立後間もない頃の米国のある地で見たことらしい。住民たちが集まっているところに、議員たちの集団が通りかかり。偉そうなそぶりで、「どけどけ議員様のお通りだ。」住民達:「??」「俺たちは市民の代表だぞ!!」「!!」後ろの方から「バッカヤロー。俺たちがその市民だ。」
トクビルさん、これぞ民主主義の手本だ! 米国侮れず。
今の米国にも、この精神、共和党の草の根派などに脈々と受け継がれているとか。
**トクビル
アレクシ=シャルル=アンリ・クレレル・ド・トクヴィル(仏: Alexis-Charles-Henri Clérel de Tocqueville、1805年7月29日 - 1859年4月16日)は、フランス人の政治思想家・法律家・政治家。裁判官からキャリアをスタートさせ、国会議員から外務大臣まで務め、3つの国権(司法・行政・立法)全てに携わった。
パリ出身。生家はノルマンディー地方の貴族で軍人・大地主という由緒ある家柄だったものの、フランス革命の際に親戚が多数処刑されたことから、リベラル思想について研究を行っていた。その後ジャクソン大統領時代のアメリカに渡り、諸地方を見聞しては自由・平等を追求する新たな価値観をもとに生きる人々の様子を克明に記述した(後の『アメリカのデモクラシー』)。
30歳の時、家族の反対を押し切り、英国人でフランスに移民した平民階級の3歳年上の女性メアリー・モトレーと結婚。1848年の二月革命の際には革命政府の議員となり、更に翌年にはバロー内閣の外相として対外問題の解決に尽力した。彼の政治的手腕はなかなか鮮やかなものであったが、1851年、ルイ=ナポレオン(後のナポレオン3世)のクーデターに巻き込まれて逮捕され、政界を退くことになる。その後は著述及び研究に没頭する日々を送り、二月革命期を描いた『回想録』と『旧体制と大革命』を残し、1859年に母国フランスで肺結核のため54歳の生涯を終えた。フランスが誇る歴史家・知識人。
社会学の部屋PartⅡへ
反知性主義
トランプ大統領は、「バイデン氏が大統領になったら(大統領は)科学者たちの言うことを聞くぞ」と発言し、支持者の喝采を浴びたそうだ。
アメリカだけではない。日本でも、科学技術や学問に対する疑問、懐疑や非難の声が強まり、研究者たちが不安の声を上げている。反知性主義がこれほど強まって、果たして世界はどうなってしまうのだろうか。多少とも科学技術に興味のあるものにとっては無視できない主張だ。
理不尽?に見える動きにも、何らかの理由があるはず。アメリカや日本で、研究者や科学技術への疑問や批判が一般国民からも少なからず出てくる背景には、実は人工知能関連の言説があるという意見もある。
でも、上の議論は本当に正しいのか。科学技術や学問に対する疑問、懐疑や非難の声が強まるのは、寧ろ専門家の言う説明が合理的に納得できなくなっているからかも知れない。反知性主義が強まることは、論理性合理性を重んじるホモサピエンスとして健全な反応かも知れない。科学技術や学問が細分化されて、彼等の主張が間違っていても誰も反論無しでメディア等に正しいものとしてまかり通ってしまう現状の方が更に問題は大きそうだ。
トランプ大統領が科学者達と言っているのはいわゆるプロバガンダをばら撒く御用学者を非難してのことだ。例えば、「温暖化の原因はCO2」だという主張は、まだ現段階では極めて不確実な仮説段階のものであるし、「covit-19はそれほど危険なウィルスではない。」→今は少数意見かも知れないが、最も検証が必要な科学的課題でもある。
専門家の意見が政治家によって事実と利用され、多数決でまかり通ってしまう事態の方が寧ろ問題だろう。
どんなに当たり前のことと思われることも、一度疑ってみると良い。そこには新しい発見や、新しい世界が開けて来る。反知性主義というものも、人としての論理的な考えを失わない限り有意義なものと言えそうだ。
人工知能を扱う記事は、日々配信されている。特に記事中で「シンギュラリティ」という言葉によく出くわす。いつか人間の知性を人工知能が超えるのではないか、その瞬間を示した言葉だ。でも、一方には人工知能の脳はまだゴキブリにも及ばない等と言う物理学者の意見もあることも一考する必要もある。
記事によっては、シンギュラリティを迎えたときの恐ろしい未来を予想するものが多い。人工知能やロボット技術が雇用を奪い、多くの人々を路頭に迷わせるだろうと。人工知能やロボットが苦手とする創造的能力を発揮できない人間は仕事にあぶれても仕方がない、と言わんばかりの内容だ。人工頭脳が人間の職場を奪うというのだ。
しかし、楽観的な意見もある。人工頭脳は人間の活動範囲を広げ、人の活動をサポートしてくれるから、人間にとってより創造的な仕事が増える。大変望ましいことではないか。
確かに、科学技術や学問に対する疑問、懐疑や非難の声が強まることは寧ろ社会が健全であることの証だ。もともと科学技術の発展は人々の疑問や懐疑を解決することで飛躍的な発展を遂げて来たのだから。疑問や懐疑の無い所には、科学技術や学問の飛躍的な発展はない。
人工知能やロボット技術によって、人が考える力や学びの力、労働の喜びを忘れてしまうことが最も危険な事だろう。
反知性主義の人達の方が、メディアや政治家のいうことを妄信する人達よりは遥かに健全で人間的だということかも知れない。
社会学の部屋PartⅡへ
世界最大のリスク??
米次期大統領、世界の最大リスクと認定されてしまう。
ユーラシア・グループがバイデン次期大統領を10大リスクの1位に(古森 義久:産経新聞ワシントン駐在客員特派員、麗澤大学特別教授)
2021年の国際的な最大リスク(危険)は、米国46代目の大統領となるジョセフ・バイデン氏だ。こんな予測を国際的に著名な米国の政治学者イアン・ブレマー氏が1月冒頭に打ち出した。同氏が代表を務める国際情勢分析機関「ユーラシア・グループ」が、「2021年のトップリスク」という報告書で発表した。
この予測では、新しい年の国際リスクが1位から10位まで挙げられ、そのトップが「第46代アメリカ大統領」と明記されていた。ちなみに2位は「新型コロナウイルス」、3位は「気候変動」、4位は「米中緊迫の拡大」、以下は「サイバーの混乱」や「中東の低油価危機」「メルケル首相後の欧州」などと続いていた。
カーター以来、最も弱い大統領に?
日本でも広く知られ、評価の高いブレマー氏は、はたして本気でバイデン氏を大きなリスクと考えているのか?
こう訝(いぶか)しまざるを得ないのは、同氏が政治的には民主党支持、トランプ大統領批判で知られる人物だからだ。であるからこそ、この診断は吟味しておく必要があるだろう。
ただしこの報告書が公表されたのは1月4日、つまりトランプ支持者の一部が米国議会に乱入して、トランプ大統領への非難が全米に広がった直前である。とはいえ、バイデン氏への評価はトランプ氏評価と必ずしもゼロサムではない。トランプ支持が減れば、その分、バイデン支持が増す、というわけではないのだ。ましてバイデン氏の大統領としての地位がトランプ氏の命運と反比例の関係になっていることはない。
この報告書を読むと、トランプ氏の振る舞いとは関係なく、バイデン氏自身が抱えた問題や現在の米国の特殊な状況が米国と世界の今後に多大なリスクの要素を注入しているという構図が説明されていた。
その一例として同報告書は、「バイデン次期大統領は米国民からの信託という点では1976年に当選したジミー・カーター大統領以来、最も弱いといえよう」と述べ、米国内の極端な政治分裂の状況に加えて、バイデン氏は高齢のため2期目はないとの予測をマイナス要因として強調していた。
確かにカーター大統領は近年の米国の歴代大統領のなかでも失政を重ね政権として弱体だったことで知られる。つまり、失政を重ねたのは彼が無能だったのではなく、政権が弱体だったためか。それは強い与党が望ましいという、立憲主義に反する考えでもあるが。
私自身がワシントンに特派員として初めて赴任した時期が、まさにカーター政権の発足時であり、それ以後の4年間、カーター政権の失態を目の当たりにすることになった。ジミー・カーターという人物は、人間的には大いに好感の持てる誠実な人柄だったが、国内、国外の政策は歴史に残る失敗の連続だった。
カーター政権下の米国経済は沈滞をきわめ、「マレーズ」(不定愁訴)と称される暗い雰囲気が米国社会をおおった。対外関係ではソ連のアフガニスタン大侵攻を許し、イランの過激派に米国人外交官約50人を1年近くも人質に取られた。
**経済や外交の問題だとすると、カーターさんはたまたま運の悪い時に大統領になっただけなのか?
経済が沈滞している時は、誰が担当しても運営は難しく、経済が好転すれば誰がリーダになっても国民は満足するものだから。
でも、そんなカーター大統領を引き合いに出されるほどバイデン政権が弱体化するという予測をまだ始まる前から、まさかブレマー氏から受けるとは、私には驚きでもあった。
国際的な信頼度が低下した米国
ブレマー氏はこの報告書で以下の骨子を指摘していた。
・もはや化石のように固まった米国内の政治的分断と国際的な米国の地位や指導力の低下によって、バイデン大統領は手足を縛られた状態となり、バイデン氏自身の能力や活力の限界によって統治は大幅に制約される。
・バイデン氏自身は国際情勢に対して指導力を発揮しようと試みるだろうが、まず米国が新型コロナウイルスの世界最大の感染に効果的に対処できないという現実が、国際的な信頼度を激しく低下させるだろう。
・中国の無法な行動を非難し、抑止するというバイデン政権の基本方針は、共和党と一致する部分も多い。だが、ヨーロッパがつい最近、中国との投資の包括的な合意を成立させたように、国際的には、米国の強固な対中政策を阻む要因も多い。
強固なトランプ支持層の存在が政権運営の支障に
また、同報告書はバイデン氏が大統領候補として約8000万票という米国史上最多の得票を記録した(オバマやクリントンより多かった)ことを取り上げ、バイデン新大統領は国民の支持という点では自信を保てるはずだ、と指摘する。でも、このことが郵便投票のインチキ選挙の噂を消せない最大の理由。そうしたバイデン氏への国民多数の支持は、トランプ氏への支持の広範さと、トランプ支持者の間でのバイデン氏の勝利を認めないという「確信」の激しさで相殺され、正常の大統領としての職務遂行が難しくなるとも述べていた。
その部分の骨子は以下のとおりである。
・トランプ大統領も米国の歴史では2番目に多い7400万という票を獲得し、共和党は上下両院や州議会の多くで総得票を伸ばした。またヒスパニックや黒人からの得票も増えた。トランプ氏自身が前回の選挙よりも1100万票も多い得票を記録したことも、支持層に勢いをつけた。
・トランプ支持層では70%以上とみられる多数派がトランプ氏の「バイデン陣営の不正選挙」の主張を支持し、バイデン氏が「大統領ポストを盗んだ」という認識を隠さない。この種の主張のほとんどは裁判の場などで排除されたが、連邦議会の合同会議では上院8人、下院130余人の議員が最後まで「バイデン陣営の選挙不正」を主張し続けた。
**つまり、新型コロナを武器にして無益なロックダウンを続け、感染者を沢山増やして、郵便投票に持ち込んで、大統領選挙まで奪った張本人との疑惑が何時までもつきまとうことに。
・世界の主要各国の首脳を見わたしても、その首脳の座につくための選挙の結果が国民の多くに否定されるという指導者はまず存在しない。その特殊な状況がバイデン氏の内外での統治の深刻な足かせとなる。また政策面でも、「アメリカ第一」主義はトランプ大統領の退陣にもかかわらず米国民の広い層で支持され、バイデン政権への制約となる。
ブレマー氏は以上のように「トランプ効果」がバイデン政権にとって今後の大きな負の要因になると強調する。
まだまだ予断は許せないが・・・
この予測は、その発表後に起きたトランプ支持層の議会乱入や、それに伴う民主党側のトランプ大統領に対する弾劾追及によって、どれほどの影響を受けるのか。バイデン政権にとって、どれほどの明るい材料となるのか。まだまだ予断は許さないだろう。
だが、いずれにしてもバイデン政権の発足間近というこの段階で、民主党支持のブレマー氏のような著名な専門家からこんな険しいバイデン政権への予測が発せられた事実は注視しておくべきだろう。
**ただし、ブレマー氏がリスクという言葉を使っている点を注意して欲しい。つまり、適切な対応を取らないとこうなると言っている警鐘だ。バイデン政権を批判して、やっぱり、トランプさんの方が良かったと言っている訳では無い。つまり、身内からの警鐘だね。
他の、2位以下のリスクも、どうも世界全体のリスクではなく、米国にとってのリスクのようだ。
2位の新型コロナも同様。バイデン政権は、新型コロナのお陰で大統領選に勝ったので、今後さらなるロックダウン政策を強行していく可能性が高い。ワクチンが行きわたるまで「自粛を続けろ」だろうが、本当にワクチンを皆が受けて、その結果感染は収束するのか。ワクチンが実用化してもロックダウン政策が解除されなければ、本当に暴動が生じてしまうだろう。
3位の気候変動が何故リスクか? バイデン氏は脱炭素社会を始めて認めた米大統領。その結果は、米国の産業に大きな負の影響を。オイルシェールは、環境問題で破綻し、米国はまた石油を輸入する立場に。EVカーは中国製? 米国のメリットはなさそうだ。
社会学の部屋PartⅡへ
先進国と開発途上国
“Fact Fullness- Hans Rosling” という本が出た。一見世の中の常識の様な事柄も、データを見て自分の頭で考えれば実はとんでもない誤解であったということが多数ある。この本の最初の方にあった意外な事実。多分衝撃的だ。
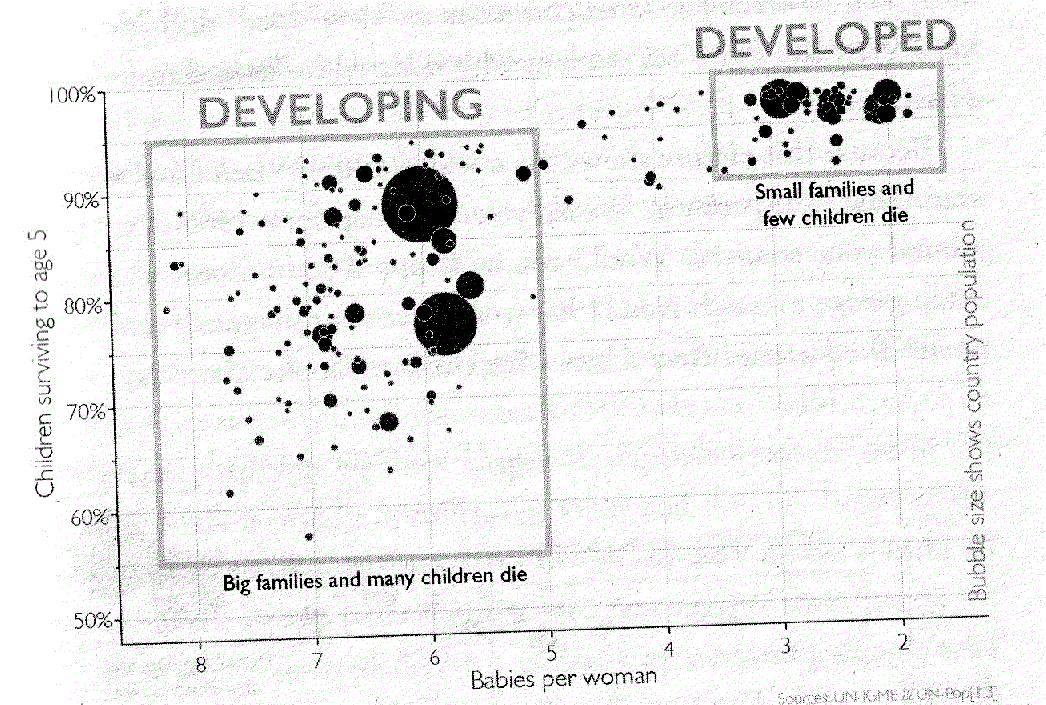 まず、右のグラフを眺めてみよう。横軸は女性一人当たり何人子供を産むのか。縦軸は生まれた子供が5歳まで死なずに生き残る確率だ。
まず、右のグラフを眺めてみよう。横軸は女性一人当たり何人子供を産むのか。縦軸は生まれた子供が5歳まで死なずに生き残る確率だ。
このグラフは各国を人口の比率でプロットしている。世界の国々はごく大雑把に2つのグループに分けられる。その間に位置する国は少ない。左の四角は開発途上国(developing countries)で右が先進国(developed countries)という訳だ。左側の大きな丸はインドと中国だろう。開発途上国は、貧しく沢山の子供を産んで多くが無くなる。先進国は少子化で死亡率も小さい。これ多くの人の固定概念だろう。
日本だって戦前や戦後すぐは正に子沢山で幼児の死亡率も高かった。でも待て、中国は今一人っ子政策の為子供を5人も生む女性はいないぞ。
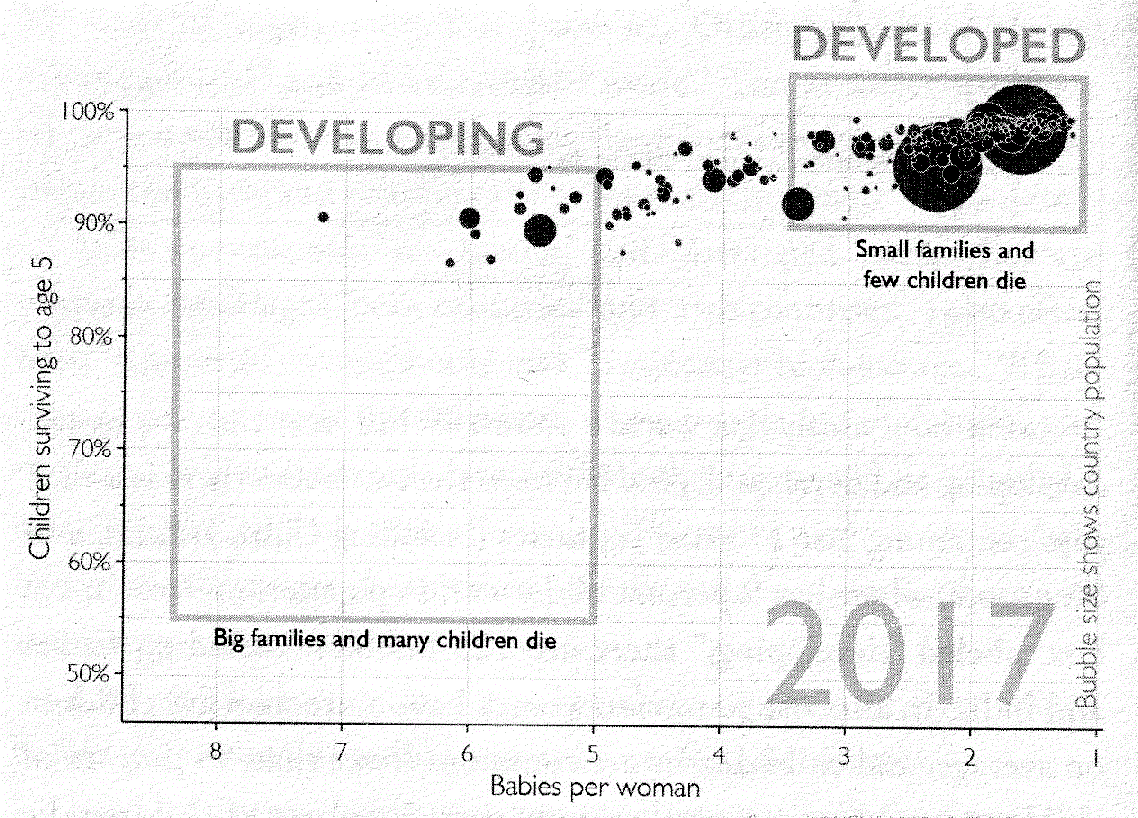 そうなのだ、このグラフは1965年当時の世界の状況だということ。では、改めて2017年時点のグラフはどうなったのか。著しい変化が見られる。少なくとも子供の生存率は著しく向上。5歳まで死なずに生き残る子供は、大抵の地域で9割近い。子供の数は減ってくる傾向にあることは分かるが、貧富の差とは関係なさそうだ。
そうなのだ、このグラフは1965年当時の世界の状況だということ。では、改めて2017年時点のグラフはどうなったのか。著しい変化が見られる。少なくとも子供の生存率は著しく向上。5歳まで死なずに生き残る子供は、大抵の地域で9割近い。子供の数は減ってくる傾向にあることは分かるが、貧富の差とは関係なさそうだ。
2つのグラフの間の年代差は52年しかない。一体全体何があったんだろう。グローバル社会の進展だ。米国は欧州の戦後復興のため、ドルを大量に発行してものを買いまくる。
1971年にはドルは金との交換も無くなり、ドル紙幣の世界への垂れ流しが始まる。基本的には超インフレになるはずだけど、ユーロも円も人民元もドルに合わせて紙幣の増刷に応じたため、世界の為替相場は一見安定しているかに見えた。
でもこれは、開発途上国の多数の中間層の生活レベルを著しく引き上げ、一方先進国の中間層の生活レベルを著しく低下させる力となって働いた。
先進国へ集まる富は一部の富裕層にだけ集中するためこのグラフには反映されない。開発途上国でも富の偏在はあるものの全体としての生活の向上は著しい。資本はより労賃の安い地域を求めて世界を回り、その結果世界中の中間層の富を均一化する方向に働いたようだ。
このことは多くの日本の人達は気づいていないかもしれない。現在、米国でも欧州でもアジアでもアフリカでも中間層の人達の生活レベルはそんなに変わらない。羨んだり差別したりは総て偏見のなせるわざ。基本的に対当だ。米国人の多くが豊かだと思うのは間違いだ。富裕層はほんの一握り。先進国(多分開発途上国も)の方が富の偏在は著しい。1%の一握りの人達が残りの99%の人達の富と同じだとしたら?
少なくとも我々は、1965年とは全く異なった世界の住んでいることに。社会は富裕層を除いてフラットになりつつあるのか。もちろん世界には取り残された極貧困層も存在していることも忘れてはならないが。
社会学の部屋PartⅡへ
上からの社会主義
 社会主義と言えば、革命やストライキ、住民運動と言った下からの改革と言ったイメージがあり、
多くの富裕層にとっては、著しく危険な思想と見なされていた。
社会主義と言えば、革命やストライキ、住民運動と言った下からの改革と言ったイメージがあり、
多くの富裕層にとっては、著しく危険な思想と見なされていた。
しかし、グローバル社会の進展で、欧米等の先進国の普通の労働者は雇用が亡くなり、もし雇用があっても「やりがいの無いつまらない仕事しかあり付けなくなって来ている。」
逆に、1%の超富裕層の多国籍企業にとっては、欧米先進国で、無能でプライドだけ高く高賃金を要求する自国の労働者を雇うより、安い賃金でも有能でまじめに働く開発途上国??の人達の働いてもらった方が遥かに効率が良い。つまり、自国の労働者は皆年金生活者にしてしまった方が世界の経済もより活性化するぞ。
でも、現実には、開発途上国の生活水準は著しく向上して、先進国と生活水準はあまり変わらなくなっているのが現実のようだ。つまり、このプランが成功するかどうかは、欧米以外の国々の今後の動向が無視できない。世界は何時までも欧米中心で動いている訳では無い。
私は、社会主義者ではないが、マルクスの予言は一理あるようにも。
個人的には、政府与党やマスメディアを全面信頼し、「パンとサーカス」の生活に99%の国民が
満足するような社会が健全な人類の未来像とは思えないのですが。ただ、いずれにしても
現在のグローバル資本主義社会が曲がり角に来ていることは確かだね。
社会学の部屋PartⅡへ
ネオコン(新保守主義)
新保守主義(Neoconservatism)とは、旧来の保守と新しい保守の分別のために使われてきたが、特に明確な定義は存在しないらしい。概念は時代と共に変容し、国によっても異なっている。でも、よくネオコンという言葉聞く。過激な外交戦略で戦争も辞さないと言う立場のようにも。少なくとも日本には自らネオコンを自称する立場の人達は少ないと思うが。
 米国で「ネオコン」と呼ばれる勢力は、元来は1930年代に反スターリン主義左翼として活動した後に「ニューヨーク知識人」と呼ばれるトロツキストたちによるグループであったらしい。ニューヨーク知識人の多くは、アメリカの公立大学の中で最も歴史のある大学の1つであるニューヨーク市立大学シティカレッジ(CCNY)を根拠地として活躍していたが、アメリカの消極的な対外政策に失望した集団である。アメリカの伝統的な保守主義の対外政策はモンロー主義に則った孤立外交を重視し、他国の人権問題には関心を示さない、あるいは自国の利益のためには(中国などの)独裁国家とも同盟を結ぶとの姿勢であったが、ネオコンの場合は民主主義、ひいては自由主義の覇権を唱え、独裁国家の転覆を外交政策の目的に置くという極めて革新的な思想および外交政策を標榜する。中東においては、唯一の近代民主国家であるイスラエルを基盤に周辺の独裁国家を滅ぼすことが中東問題の解決策であると主張する。
米国で「ネオコン」と呼ばれる勢力は、元来は1930年代に反スターリン主義左翼として活動した後に「ニューヨーク知識人」と呼ばれるトロツキストたちによるグループであったらしい。ニューヨーク知識人の多くは、アメリカの公立大学の中で最も歴史のある大学の1つであるニューヨーク市立大学シティカレッジ(CCNY)を根拠地として活躍していたが、アメリカの消極的な対外政策に失望した集団である。アメリカの伝統的な保守主義の対外政策はモンロー主義に則った孤立外交を重視し、他国の人権問題には関心を示さない、あるいは自国の利益のためには(中国などの)独裁国家とも同盟を結ぶとの姿勢であったが、ネオコンの場合は民主主義、ひいては自由主義の覇権を唱え、独裁国家の転覆を外交政策の目的に置くという極めて革新的な思想および外交政策を標榜する。中東においては、唯一の近代民主国家であるイスラエルを基盤に周辺の独裁国家を滅ぼすことが中東問題の解決策であると主張する。
ネオコンはユダヤ思想と同根であり、社会主義、リベラル、新自由主義も同根である。ユダヤ人自身が、「これらはみなユダヤ思想である」と述べているとのこと。
**トロッキー
レフ・ダヴィードヴィチ・トロツキー(Лев Давидович Троцкий1879年~1940年8月21日)は、ウクライナ生まれのソビエト連邦の政治家、ボリシェヴィキの革命家、マルクス主義思想家。ソ連邦においてはレーニンの正当な後継者と目されていたがレーニンの死後スターリンに追放され、メキシコに亡命。トロツキーは第四インターナショナルを結成し、官僚制に反対し続けたが、1940年、スターリンの刺客ラモン・メルカデルによって同地で暗殺される。
ネオコンには東欧系、ロシア系、アシュケナジユダヤ人をルーツに持つものが多く、一定の政治勢力を持っていても不思議はなさそうだ。彼等が外交問題に熱心なのはトロツキーの世界同時革命論の信者でもあるからか。
1950年代には、保守反動を避けつつ漸進的政策や社会福祉の再分配政策を行っていこうとする保守党の路線が新保守主義と言われ、1980年代には、アメリカ合衆国やイギリスなどで、1970年代の社会民主主義や自由主義に代わり誕生したニューライトを稀に新保守主義と呼ぶこともあった。
ディープステートの実戦部隊として東欧のカラー革命(2003年-2005年)、アラブの春(2010年-2012年)の背後にいたのが彼ら。運動の指導者に莫大な資金援助を行い、革命手法を教え、選挙に不正があったとしてデモを扇動し、選挙で選ばれた政権を少数者が転覆させた革命の、影の主役がネオコンである。
東欧のカラー革命の延長として今のウクライナのオレンジ革命、マイダン革命、ゼレンスキー革命が続いているようだ。(2022.4.7)
彼らは1970年代に相次いで民主党を離れて共和党へ向かい、第1期レーガン政権で台頭し、主に外交や軍事の分野で強い影響力を持った。レーガン大統領はネオコンのジーン・カークパトリックを外交顧問に指名し、ソ連を「悪の帝国」と呼び、ネオコンの師であるアルバート・ウォルステッターの限定核戦争を採用し、SDI構想など軍備増強を推し進めた。しかし、2期目に入ってからレーガン政権は柔軟姿勢に転換し、カークパトリックらネオコンは事実上追放された。
ネオコン達の特定が難しいのは彼等は党派を形成せず正体を見せずに権力機構のどこにでも入り込んで、意図的に過激な主張をすることだ。
ブッシュ政権はネオコンの主張を容れてイラク戦争を始めたとされる。口実にした大量破壊兵器は、イラク占領後も見つからず、代わりにアメリカ資本がイラクの石油を押さえた。
残る石油大国はロシア、イラン、リビアなどとなった。リビアにはネオコンのヒラリー・クリントン国務長官が謀略を巡らし、ガダフィを失脚、殺害させたといわれる。
イラクとの開戦に導いた、ネオコンの代表的人物ジョン・ボルトンは、その後もイラン爆撃や北朝鮮攻撃を主張している。
これが一見米国の国益になったように見えるが、その後の中東ではイスラミックステートの台頭や、米政権のシリア敵視等の内戦が継続し、米国は結果的には中東の石油利権の殆どを放棄する結果になってしまった。
アメリカ合衆国における新保守主義(Neoconservatism、ネオコンサバティズム, 略称:ネオコン)は、政治イデオロギーの1つで、自由主義や民主主義を重視してアメリカの国益や実益よりも思想と理想を優先し、武力介入も辞さない思想。1970年代以降に米国において民主党リベラル派から独自の発展をした。それまで民主党支持者や党員だったが、以降に共和党支持に転向して共和党のタカ派外交政策姿勢に非常に大きな影響を与えているとされる。しかし民主党内にもかなりの勢力を保持し続けているらしい。
**確かに今のバイデン政権の人権外交も極めてネオコン的だ。調整型のバイデンさんの理想にはそぐわないようだ。
【追記】
確かに、ネオコンと言う言葉ニュースでも良く聞く。妥協を許さない過激な発言で戦争も辞さないという姿勢。トランプ政権のポンペイオさんなんかどうなんだろう?
でも、彼等の実態は? Wikiで歴史的なことを調べて見てビックリ!
何と彼等の母体は、ソ連からスターリンのクーデターで追い出された、トロッキーの支持母体に発すると。
なるほど、異常なまでのソ連敵視もそれで納得。多くは東欧系、ヨーロッパ系ユダヤ等の出身者が多いとか。米国内での赤狩り旋風も反ソ連ということで見逃されてきたようだ。
表面的内は、ウルトラ右翼のようで、実はマルクスの正当な後継者ということか。
イスラエル建国の際には、積極的にかかわりを持ったようで、今でもイスラエル・ロビーとは密接な関係?
合言葉は世界同時革命。covit-19は絶好のチャンスでもある。
無知蒙昧な民衆にはstay homeさせてマスクをさせて、その間に一機に革命を進めてしまおう。
社会主義は死んではいなかった。米国を共産化して中国と手を組ませれば、同時革命も可能かも。
社会学の部屋PartⅡへ
パンとサーカス
パンと見せ物/パンとサーカス
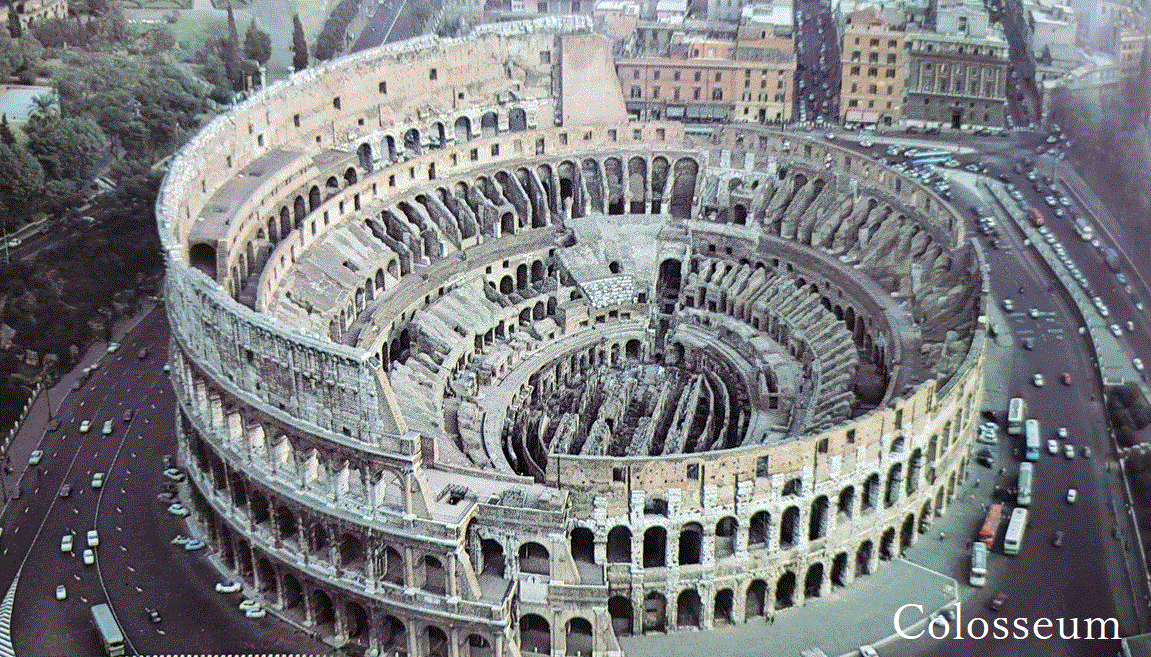 ローマ共和制末期に増加した無産市民が有力者に要求したこと。パンは食糧、見世物(サーカス)とは円形競技場などでおこなわれる剣闘士試合などの娯楽。共和政時代、権力を狙う有力者が市民に提供することで人気を得た。帝政時代の歴代皇帝も盛んに提供した。
ローマ共和制末期に増加した無産市民が有力者に要求したこと。パンは食糧、見世物(サーカス)とは円形競技場などでおこなわれる剣闘士試合などの娯楽。共和政時代、権力を狙う有力者が市民に提供することで人気を得た。帝政時代の歴代皇帝も盛んに提供した。
ローマ共和政が前3世紀ごろから中産市民が没落して無産市民(プロレタリア)となっても、市民であるので平民会の選挙権はもっていた。彼らは国や有力者に食料と娯楽を要求し、それらを提供してくれる政権や人物を支持した。「パンと見世物(パヌム=エト=キルケンセス)」のパンとは穀物つまり小麦のこと。穀物の特別価格での販売とか、無料配布が国や有力者の手で行われていた。見世物はサーカスともいわれるが現在のサーカスのことではなく、競技場での戦車競争とか、円形闘技場での剣闘士試合、ライオンと剣奴の闘いなどのことで、これらも国や有力者が主催して無料で市民に提供されていた。剣闘士試合が行われた円形競技場として最も有名なものがローマのコロッセウムであった。
 前1世紀の「内乱の一世紀」の時代には、カエサルなどの有力者が盛んに剣闘士競技や戦車競争を開催して市民の人気を集めた。また属州から多くの穀物がローマにもたらされるようになると、ローマ市民の特権として穀物(小麦)が配給されるように。ローマ帝国時代になると、アウグストゥス以降の皇帝たちは、市民に対する穀物の提供と見世物などの娯楽の提供が政治の安定につながるので、盛んにそれを実施した。しかし、それらは帝国の財政を苦しめることにもなるので、後には緊縮策を採る皇帝も。
前1世紀の「内乱の一世紀」の時代には、カエサルなどの有力者が盛んに剣闘士競技や戦車競争を開催して市民の人気を集めた。また属州から多くの穀物がローマにもたらされるようになると、ローマ市民の特権として穀物(小麦)が配給されるように。ローマ帝国時代になると、アウグストゥス以降の皇帝たちは、市民に対する穀物の提供と見世物などの娯楽の提供が政治の安定につながるので、盛んにそれを実施した。しかし、それらは帝国の財政を苦しめることにもなるので、後には緊縮策を採る皇帝も。
参考:パンとサーカス 柳沼重剛『ギリシア・ローマ名言集』によると、この言葉はユウェナリスという人の『諷刺詩』第十番80に、(民衆が)熱心に求めるのは、今や二つだけ:パンとサーカス。
とあるという。パンとサーカスとは「食べ物と娯楽」ということ。サーカスは円形劇場のことだった、ここでは「見世物」のこと。昔は国のために身も心も一兵士として砕いたローマの民衆も今や堕落して、本気になって要求することといったら、食べ物と娯楽だけという有様になってしまったと嘆いている。
小麦の配給
ローマ市民に提供する小麦を確保するために、属州のエジプトやヒスパニアから小麦を運ぶ海運が盛んになり、歴代の皇帝は造船や港湾などの海上輸送力の増強に努めた。その他に食糧供給のための施設の整備も必要であった。カリグラ帝の乱脈な政治で財政再建が急務となったクラウディウス帝は次のような対策を立てた。
(引用)アヴェンティヌス丘とテヴェレ川のあいだに穀物倉庫を建設し、カンブス・マルティウスのミヌキウス回廊を小麦配給所に改築した。当時、小麦の無料配給を受ける市民は、その資格を証明する無料配給資格証を各自所持しており、毎月指定された日に配給所へ小麦を受け取りに行った。クラウディウスは、ミヌキウス回廊に45の配給窓口を設け、毎月の指定日に、指定された番号の窓口に出頭することを義務づけた。無料配給を受けていた市民の正確な数字はわからないが、30万人とし、指定日が毎月20日あるとするなら、一つの窓口は一日約300人を処理すればよかった。しかも、配給所が一ヶ所にまとめられたので、業務上の効率も飛躍的に向上したはずである。
見世物(サーカス)とは
サーカスとは、直接的には戦車競技場を意味するキルクス circus(サーカスの英語もcircus) から来た言葉で、英語のサーキット circuit の語源になったもの。つまりもともとは戦車競技場でおこなわれる戦車競走のことであったが、それが広く円形競技場(円形闘技場)で行われる剣闘士の試合を含めて、民衆に提供される娯楽(見世物興行)全般を指すようになった。
***********
ローマ社会で何故、「パンとサーカス」のような状態が生じたか。ローマの歴史を見ないと分からない。この点、塩野七生先生の「ローマ人の物語」は非常に良くできている。ただ、いかんせん力作であるが大作だ。一度読んで見たけど、もう一度読むにはやはり勇気がいる。
ローマは、ある意味軍事国家で、周辺の国と比べて圧倒的に強い。その強さの一つに重装歩兵の密集戦法がある。王政を取らずに元老院の貴族たちの共和制を敷いていたローマだが、戦力の主体は平民であり、兵役の義務と引き換えに平民の権利は向上し、平民会の選挙権を獲得し、平民会は元老院と対等の力を持つようになる。
カエサルを始めとし、歴代皇帝は平民会を利用し、貴族たちの元老院を抑え込むことに成功していく。元老院の中ではある程度話し合いによる民主的な手続きもあったが、平民会の圧倒的支持を得たカエサルやオクタビアヌスの前には元老院の政治的な権力は極めて限られたものに。以後、ローマ皇帝は、ずっとローマ市民達の世論に気を配り続けなければならない羽目に。世論の最大の関心事はローマ帝国の領土の拡大と維持である。これによりローマ帝国には世界中(当時の尺度で)の富が集まる。グローバル経済の実現。これにより旧ローマ領の産業は皆空洞化。多くの平民達は職を失う。総てのものは海外(ローマの属州)から買った方が安価で良質。「パンとサーカス」のような状態になるのも一理ある。
これ、今の世界の先進国の置かれた立場に似てないかしら?
でも、ローマ皇帝の立場も大変。軍の最高司令官として常に馬上で辺境地帯を走り回っていたとか。「パンとサーカス」の平民と言えども、緊急事態に備えての兵役の義務だけは持っていたと思われるが。
で、歴史的に見て、成功者はローマ皇帝なのか平民の側なのか。働かなくなった平民の中からは、色々な文化や思想が誕生してくる可能性も。でも、平民の側には歴史を変えるような政治への発言権は全く失われている。
社会科学・哲学の部屋へ
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
韓国起源説
これまで韓国人は様々な韓国起源説を主張してきた。日本関連だけでも相撲や歌舞伎、醤油、日本酒、うどんなど、例を挙げればキリがない。寿司やカラオケまで韓国起源説を主張するのはまさに噴飯ものだけど。民族としての劣等感の裏返しとしか見えないが、うっかり議論しようとすると、彼等は本気で怒りだすから始末に負えない。
ところで、韓国のアイデンティティとも言えるキムチを巡り、中韓でキムチ起源論争がわき起こっているらしい。
2020年11月、中国四川省の塩漬け発酵野菜「泡菜(パオツァイ)」の製法や保存法が国際標準化機構(ISO)の認証を受け、中国共産党の機関紙「環球時報」は「キムチ宗主国の屈辱」と報道した。**キムチ宗主国=韓国ということで喧嘩を売っているのか?
韓国の人気モッパン(飲食の様子を撮影した動画)ユーチューバー Hamzyさんは「中国人がキムチやサムなどを自国の伝統文化だと主張する」とコメントしたが、すべてのコンテンツが中国のSNSや動画共有プラットフォームから突然削除されるなど、韓中間でキムチ起源論争が巻き起こったという。
キムチはパオツァイの派生形
キムチと聞くと唐辛子で漬けた赤いキムチを連想するが、元来、キムチという語は漬物の意味で使われた言葉だ。1760年代の韓国の飢饉時に、高騰した塩の代替品として唐辛子が使われたのが現在の韓国キムチの始まりらしい。
中国がISO認証を受けた「泡菜(パオツァイ)」は「塩に漬けた野菜」という意味だが、高麗時代の書物『高麗史』に記述された韓国最初のキムチは祭祀のお供え物「沈菜(チムチェ)」で、塩漬けした野菜に、ニンニク、ショウガを入れて作られている。記述だけを見れば、パオツァイとキムチの元祖であるチムチェは何ら変わりがない。それぞれの国でそれぞれの風土や国民性、生活習慣に合わせて少しずつ変化したに過ぎない。
キムチが日本で知られるようになったのは、1910年の韓国併合以降だ。朝鮮漬けと呼ばれ、辛くて臭いものという認識から、それほど普及はしなかった。そのキムチが日本で普及したきっかけは、1988年のソウル五輪に伴う韓国ブームだ。テレビや新聞、雑誌などが韓国特集を組んだことで韓国に「好感」を持つ人が増え、2002年の日韓ワールド杯がキムチブームに火をつけた。
さらに、2003年に韓国のテレビドラマ「冬のソナタ」が放映されて、第一次韓流ブームが巻き起こり、エンターテインメントと韓国料理のブームが始まった。これを契機に新大久保のコリアタウンの日本人客が増加。オールドカマーのコリアンタウンとして知られる東上野のキムチ横丁や大阪・鶴橋駅付近にも日本人客が押し寄せた。「近くて遠い国」といわれていた日韓の距離が近づいた瞬間である。
台風19号で「辛ラーメン」だけが売れ残った理由
北朝鮮に対する日韓のベクトルが同じ時、両国の距離は近づく。北朝鮮に強硬に対応した朴政権と対北朝鮮圧力路線を取る安倍政権は強い連携関係を作ったが、対北朝鮮融和政策を取る現政権下で日韓の距離が遠のくのは必然だ。
日韓関係が悪化した2019年、韓国内で日本製品不買運動が広がる。「NO Japan」「NO 安倍」が叫ばれた2019年10月、50年に一度と言われる大型台風19号の来襲で、日本人は食べ物を確保するため、スーパーやドラッグストアに駆け込んだ。この時、韓国の「辛ラーメン」だけが売れ残り、韓国では日本人が韓国製品の不買運動をしていると報じられた。実際の理由は「辛い韓国ラーメンは、辛い食べ物に慣れていない日本人の非常食として合わない」からだが、韓国人は事態を深刻に捉えていたらしい。「こんなうまいものを我慢して食べないのは不買運動」?
日本人が嫌韓というのは韓国人の杞憂? もちろん、嫌韓族がいることは否定できないが。2019年の日本政府による「外交に関する世論調査」で、「韓国に親しみを感じる」という回答は、18~29歳は45.7%、70歳以上は17.4%と3倍近い差があった。その結果を反映するように、10~20代の若者を中心に第三次韓流ブームがSNSで拡散し、余韻が冷めやらぬ2020年、「愛の不時着」「梨泰院クラス」が人気となって第4次韓流ブームが巻き起こった。
生まれた時から韓国ドラマや韓国料理が身近にある世代は、韓国の化粧品やグルメにお金を使う。不買どころか積極的に消費する動きを見せている。報道に左右されず、自分で判断したい日本人の意識の表れだ。日本製品不買運動が今でも続く韓国と違って、現在の日本で、政治情勢が個人の行動に大きな影響を与えることはないだろう。
新型コロナウイルス感染症の拡大以降、発酵食品の需要が増え、韓国のキムチ輸出量は過去最大となった。韓国農水産食品流通公社のキムチ輸出入情報によると、2020年8~12月(5カ月間)のキムチの輸出は3万9748トン、1億4451万ドル(約158億円)に上っている。主な輸出国は日本、米国、香港だ。
過去最大という言葉だけを聞くと素晴らしい数字に見えるが、実際は異なるらしい。日本で韓国産キムチは中国産キムチに押されているが、韓国内も同様だ。韓国の飲食店では注文した料理と別にお代わり自由のキムチが必ず提供される。飲食店経営者にとってこのキムチの無料提供の原価負担は大きく、外食産業が韓国のキムチ輸入量の増加を後押しする。
そして、輸入元は主に中国だ。2020年8~12月(5カ月間)の韓国のキムチ輸入量は 28万1000トンで、同時期のキムチ輸出量の約7倍。それにもかかわらず、輸入金額は約1億5242万ドル(約167億円)で輸出金額と大差はない。韓国は安価な中国産キムチ無しには食生活を維持できないらしい。
韓国が攻撃的にならず、歩み寄りや共存の姿勢を示せれば新しい関係を生み出していけると信じるが、果たしてその日はやってくるのだろうか。このまま反日不買運動が続けば国内の韓国産キムチが中国産に代わられているように、韓国製品が別産地の製品に取って代わられるのも時間の問題か。
ところで、「辛い」のもとになる唐辛子、そもそもは中南米原産。コロンブスが1493年にスペインへ最初の唐辛子を持ち帰ったが忘れられ、ブラジルで再発見をしたポルトガル人によって伝播され、各地の食文化に大きな影響を与えた。韓国起源説等主張してもそんなに古い伝統とも言えそうもないね。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
GAFAはなぜ邪悪に堕ちたのか
GAFAはなぜ邪悪に堕ちたのか
ビッグテックは素晴らしい理念と私たちを裏切った 前編(著者は米国の人)
どうしてこうなってしまったのだろう
2007年以降、金融業界に注目してきた人は、当時と今の状況がとてもよく似ていることに気づくだろう。みるみるうちに、排除するには大きすぎ、管理するには複雑すぎる、新たな業界が発生した。その業界は歴史上のどの業種よりも富を集め、高い時価総額を誇る一方で、過去のどの巨大企業よりも雇用機会を減らしつづけた。私たちの経済と労働を根本からつくりかえたと言える。何しろ、人々の個人データを集めてそれを売り物にすることで、いわば人間を商品にすることに成功したのだから。
**自由主義の経済に取って独占は最大の悪である。アダム・スミスの原点に戻ればそうだ。でも、国益を言い訳に彼等の独占を許して来たのが各国の政府だ。つけは払わねばならない。
つまり、事実上まったく規制を受けずにきたのである。そして、2008年ごろの金融業界と同じで、この業界も、今の状態が続くように、政治と経済の分野に大いに口出ししている。
2016年の大統領選で予想外の結果が出たことをきっかけに、これらの企業に批判が集まりだした。そこで私はビッグテックについて詳しく調べてみることした。すると、いろいろなことがわかってきた。今では誰もが知っているように、フェイスブック、グーグル、ツイッターをはじめとする世界最大級のテクノロジー・プラットフォーム企業が、ドナルド・J・トランプを大統領選で勝たせようとするロシアの工作員によって悪用されていたのだ。国際政治を意のままに操り、国家の運命を揺さぶるための手段になっていた。
→**とりあえず、これはあり得ない前提だね。トランプ大統領は、ロシアに取って有益なこと何一つやってないように見えるが。また、ロシア疑惑は大騒ぎしたのに何も出てこなかった。
しかも、そのように利用されることを通じて、経営陣や株主は財をなしていたのである。でも、テクノロジー業界は、これまでずっと金銭的な利益だけを追求してきたというわけではない。実際のところ、シリコンバレーは1960年代の反体制運動の影響を大いに受けていて、事業を立ち上げた人の多くは、テクノロジーが世界をよりよく、より安全に、より豊かにする未来を夢みていたはずある。***確かにインターネットが普及し始めた当初はそのような夢に満ちていたかも。
デジタルの世界に理想郷を求めた人々は、自らのビジョンを人々に伝えながら、まるで福音のように、こう繰り返した。情報は無料であるべきで、インターネットは民主化を推し進める力であり、私たちのすべてにとって公平な場所だと。
だからこそ、問わずにはいられない。どうして今のような状況になってしまったのだろうかと。かつては野心的で、革新的で、楽観的だった業界が、わずか数十年のあいだに、欲深くて、閉鎖的で、尊大になってしまったのはなぜだろうか?
私たちはどうやって「情報は無料であるべき」だった世界を、データが金儲けの手段になった世界に変えてしまったのだろう? 情報を民主化することを目指していた運動が、民主主義の構造そのものを壊しているのはなぜ? そして、地下室でマザーボードをいじくり回していたリーダーたちは、どんな理由があって政治経済の世界を支配する気になったのだろうか?
私たちは消費者ではなく製品である
その答えは、ある時期を境に、最大級のテクノロジー企業と、それらが奉仕する相手である顧客や一般人の利害が一致しなくなったことにあると、私は調査を始めてまもなく確信するようになる。
ビッグテック企業の問題については、個別で論じられることは多いものの、実際にはすべてが複雑に絡み合っていて、その根底には一つの避けられない問題が潜んでいる。シリコンバレーの人々の多くは認めようとしないだろうが、「人々をできるだけ長い時間オンラインに釘付けにして、彼らの関心を利益に変える」ことがビジネスモデルになっている、という問題だ。
コロンビア大学のティム・ウーはビッグテック企業を「関心の商人(アテンション・マーチャント)」と呼んだ。関心の商人は行動信念、大量の個人データ、そしてネットワーク効果を利用して、独占的な力を手に入れようとする。独占的な地位を得ることができた企業は政治的な力も手に入れ、それがまた、独占を維持する力に変わる。
過去、フェイスブック、グーグル、アマゾンの3社が規制上“何をやっても自由(フリー)でおとがめなし”権を手に入れた。結局のところ、この論理の延長線上で、グーグルは検索を“無料(フリー)”で提供するし、フェイスブックは“無料(フリー)”でメンバーになれる。アマゾンは価格を切り下げ、製品を無料に近い値段でたたき売る。
これは、消費者にとって“ありがたい”ことなのだろうか? 問題は、ここで言う「フリー」は実際にはフリーでも何でもないことだ。確かに、デジタルサービスのほとんどで私たちは現金を支払わないが、その代わりにデータや関心を大いに差し出している。“人間”が金儲けの手段なのだ。
私たちは、自分のことを消費者だと考えている。だが実際には、私たちこそが製品(商品?)なのである。
いいことをしているのになぜ不満を持つのか
グーグルの創立者であるラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンは、スタンフォード大学のコンピュータ・サイエンスの博士課程にいるころ、ヒューマン・コンピュータ・インタラクション・グループに入った。学生のほとんどは“ポータル”づくりにいそしんだが、ブリンとペイジはまったく違う道を選んだ。彼らが目指すべきは、ハイパーリンクの数を集計する能力をもつ検索エンジンにほかならない。そこでペイジとブリンはほかの文章へのリンクを追跡するプログラムをつくり、それをバックラブと名付けた。
ペイジとブリンにとって、彼らのやり方にやましい部分は何一つない。彼らにしてみれば、全国のコンピュータ・アーカイブに保存された知識を、人類に利益をもたらすために集めようとしただけなのである。その結果として自分たちにも利益がもたらされるなら、それはそれでありがたい。
これがのちに、合法的窃盗と呼ばれる最初のケースになった。誰かが文句を言うたびに、ペイジは困った表情を浮かべた。「どうして明らかに善良なことをしている人の活動に、不満をもつことができるのだろうか?」とでも言いたげに。彼らは許可を求める必要を感じなかった。ただ、やりたいようにやった。
「もしあなたが全員の許可を得ようとすれば、ラリーとセルゲイはそれを物事の実現を妨害する行為だとみなす」と、スタンフォード大学のコンピュータ・サイエンス教授であり、ペイジの論文指導者でもあったテリー・ウィノグラードが2008年の記事で語っている。「もしあなたがそれをやってのければ、二人が昔ながらの好ましくないやり方にこだわっていることに、ほかの人たちも気づくだろうに・・・。今のところ、二人が間違っていることを証明した者はいない」 これがグーグルのやり方になった。
許可を求めるな、謝罪せよ
ジョナサン・タプリンが著書『Move Fast and Break Things(素早く動き、破壊せよ)』で指摘したように、Gmailの最初のバージョンを公開したとき、ペイジは「利用者に恥ずかしい過去を削除する力を与えるよりも、グーグルがすべてのメールを保持して利用者のプロファイルをつくる能力を得るほうが重要だ」という理由で、エンジニアに削除ボタンを実装することを禁じた。
同じように、グーグルは誰の許可を得ることもなしに、ストリートビュー用に人々の自宅の写真を撮り、それを住所と一致させて、もっと多くの広告を売るために利用している。彼らが守りつづける方針は、「許可を求めるよりも赦しを請うほうがいい」だ──実際のところは、許可も赦しも求めたりしないのだが。
これは特権を求める態度だと言える。過去数年にわたりさまざまな問題を引き起こしてきたにもかかわらず、この態度はいまだに変わらない。2018年、ある大きな経済会議に出席したとき、私はグーグルのデータサイエンティストと同じタクシーに乗る機会があった。彼女は国民と国民が生む膨大なデータの多くを監視することが許されている中国企業がうらやましいと漏らした。また、彼女がAIの研究を行っている大学が、学生に関する情報を集めるためのデータ記録センサーを彼女が希望するほど使わせてくれないことに、心から憤慨しているようでもあった。「情報を集めるのに5年もかかったわ!」と彼女はいらだたしげに言った。
このような不信感は、シリコンバレーの住人に広く浸透している。彼らは自分たちのやりたいことは人々のプライバシーや市民の自由、あるいは他人の安全よりも大切だと思い込んでいる。自分たちは何でも知っていると考えて、自分たちの動機に疑問をさしはさもうとする者がいるなんて、想像もできないのだ。
ビッグテックはやっかいな政府や政治、市民社会、さらには都合の悪い法律からも解放された自由な存在でなければならない。この考えがあるため、テクノロジー業界の巨人たちはシリコンバレーをアメリカからもカリフォルニアからも独立した存在とみなし、ほかの地域がシリコンバレーの足を引っ張ってはならないと主張する。
「そんなコードは書けない、だからできない」
結局のところ、シリコンバレーの王(そして女王)たちの考えでは、自分たちはある種の予言者であり、テクノロジーは未来なのである。問題は、未来の創造者たちの多くが、過去から学ぶ必要をほとんど感じていない点にある。
フランク・パスカーレはメリーランド大学の法学教授で、ビッグテック批判家として『The Black Box Society(ブラックボックス社会)』──政治と経済に対するテクノロジーの影響を理解するための必読の書──を書いた人物でもあるのだが、その彼がとてもわかりやすい例を挙げている。
「以前、私はシリコンバレーのコンサルタントを相手に、検索の中立性[検索エンジンは自社のコンテンツをほかよりも優遇すべきではないとする考え方]について話をしたことがある。すると彼はこう言った。『そんなコードを書くことはできない』。私は、これは法的な問題であって技術的な話ではない、と指摘したのだが、彼はどことなく見下すかのようにこう繰り返した。『ええ、でも私たちにはそんなコードを書くことができない。だから、中立性は実現できない』と」。要するに、問題について論じるなら技術者の視点から、それができないのなら問題そのものが存在しないという言い分なのである。
選挙で選ばれたワシントンのリーダーたちも含む多くの人が、この言い分を支持する側に買収されてしまった。だからこそ、最初から消費者ではなく業界に有利なルールが敷かれてきたのだろう。
商用インターネットの初期、つまり1990年代の半ば、シリコンバレーは何度も繰り返して、インターネットは街の広場のような場所だと主張した。したがって、考えや行動が自由に繰り広げられるべき中立の場所なのである。つまり、オンライン・プラットフォームは公共の広場なので、運営する企業はそこでの出来事に責任を負う必要はない、と言いたいのだ。
自動化できないことはやりたくない
この主張の根底には、自宅の地下やガレージでオンライン掲示板やチャットルーム、あるいは初期の検索エンジンを立ち上げたばかりの起業家たちには、資金的にも人材的にも、ユーザーの行動を監視するだけの余裕がなかったという事実がある。監視に力を割けば、インターネットの発展にブレーキがかかったかもしれない。
しかし時代は変わった。今では、フェイスブックも、グーグルも、ほかの企業も、ユーザーのオンライン活動のすべてを監視“できる”し、実際に監視している。それなのに、彼らのプラットフォームで繰り広げられるヘイトスピーチ、ロシアの資金による選挙広告、あるいはフェイクニュースなどの責任という話題になれば、どっちつかずの態度をとろうとする。
『邪悪に堕ちたGAFA ビッグテックは素晴らしい理念と私たちを裏切った』(ラナ・フォルーハー著、長谷川圭訳、日経BP)
彼らは私たちが何を買ったか、どの広告をクリックしたか、どんなニュース記事を読んだか、すべて容易に追跡できるのに、その一方で、ウェブサイトからいかがわしい陰謀論を取り除くのも、反ユダヤ的なコメントをブロックするのも、ロシアのボットによる不正を特定するのも、とても難しいと主張するのだ。***いかがわしい陰謀論を取り除く難しいことは分かる。陰謀論かどうかの判断は読み手に求められる性質のものだろう。ただユーザーのクリックを追跡する行動や止めて欲しいと願う。
ビッグテックは分裂状態に陥っている。会社という意味でも、社会の一部としても、その本質において相反する表情を見せている。メディア会社? 報道機関? プラットフォーム企業? 小売業? 物流? 本質が何であれ、彼らが自らに課している現在のルールは──その多くはルールと呼べる代物でもないのだが──うまく機能していない。
グーグル、フェイスブック、アマゾンをはじめとするプラットフォームはあまりに巨大になったため、彼らのリーダーたちを一般的な考えや倫理規範、あるいは普通の市民に適用される法律などを超越する存在に押し上げてしまった。
後編では、そのようなビッグテックに振り回されないため、私たちがとり得る方策について検討する。→後編を期待しよう。
邪悪なGAFAから世界を救うには
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/63733
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
大学の歴史
大学の誕生
大学を単に高等教育機関と定義するならば、紀元前7世紀創設のタキシラの僧院が最古の大学とする説がある。タキシラ僧院では、学位に相当するものが卒業生に与えられていた。世界遺産のタキシラ遺跡がある現在のパキスタンのイスラマバード北西にあったが、6世紀に街とともに破壊された。古代インドにはかつて学問の中心地として、タキシラ、ナーランダ、ヴィクラマシーラ、カーンチプラムがあったとされる。
紀元前387年に古代ギリシアの哲学者プラトンが作ったアカデメイア(アテーナイ)では、数学、哲学等が教えられており、十字軍以降、イスラム世界を通じて中世ヨーロッパの大学成立に多大な影響を及ぼした。その他にもギリシアでは、ヒポクラテスの故郷コス島に医学校、ロドス島に哲学の学校があり、アレクサンドリアには博物館(ムーセイオン)と図書館(アレクサンドリア図書館)があった。
中国では前漢代の紀元前124年に官吏養成学校である太学が設立された。『漢書』儒林伝に「夏は校と曰い、殷に庠と曰い、周に序と曰う」とある。周代には辟雍と呼んだともいう。『礼記』王制篇には「天子命之教然後為學。小學在公宮南之左、大學在郊。天子曰辟雍、諸侯曰頖宮」とある。隋代以降は国子監が最高学府としての役割を担った。
5世紀設立のナーランダ大学はインドのナーランダに所在し、仏教を中心とした学問研究で有名で、仏教だけでなく天文学などの知識も教授していた。学位に相当するものの授与のほかに、今の大学院に相当するコースもあり、西域、ペルシア、アラブ世界からも人々が学びに来ていた。地元の熱心な仏教徒らの寄進・布施によって運営費や学生らの食費などがまかなわれ、最盛期には学生の数はおよそ1万人、教師数1000人、蔵書数500万冊にも達しており(世界最大級)、建物群は仏教を大切にした歴代の王たちによって増築が重ねられ、キャンパスの広さはおよそ10km×5kmほどにも達し、中央には大きな塔もあった。12世紀頃のイスラム教徒による破壊まで続いた。
6世紀にはサーサーン朝ペルシャにグンデシャープール大学(ジュンディーシャープール)があった。
日本では、7世紀の天智天皇の治世に官僚養成を目的とした「大学寮」が創設された。
カロリング朝では、シャルルマーニュがアーヘン(現在のドイツのノルトライン=ヴェストファーレン州の街)に scola palatina (宮廷学校)という名の学校を作った。アカデミー・ブレクスガタ大学 (Brexgata University Academy) もカロリング朝指導者により、798年、今のフランスのノワイヨン近郊に設立された。学者、統治者、聖職者、シャルルマーニュ自身などが参加して、一般市民の教育について、統治者の子どもの(次世代の統治者としての)教育、統治、侵略者からの領地の防衛、浪費を防ぐ術など議論していた。これらの活動は大学 (universitas) の下準備となった。
ヨーロッパにおける中世最初の大学は、849年にビザンツ帝国アモリア王朝3代皇帝ミカエル3世の摂政バルダス・マミコニアン (Bardas Mamikonian) によって建てられたコンスタンティノープル大学(あるいはマグナウラ宮殿の大学)で(次代のマケドニア朝ルネサンスの先駆)、9世紀にはサレルノ大学が作られた。
988年創設のアル=アズハル大学(966年設立のモスクに由来)はエジプトのカイロに所在し、イスラーム法学、プラトン、アリストテレスなど古代ギリシアの研究が行われ、大学院に相当するコースも行われていた。
大学を近代西欧語の大学(伊: università、英: university、仏: université、独: Universität)という意味で捉えるならば、その歴史は12世紀-13世紀に始まるとされる。もともとはラテン語の "universitas" (ウニベルシタス)を起源とし、学生のギルド(組合)から始まる。世界最初の校則は、学生のギルドから教師達への規則(「学生ギルドに無断で授業を休まない」「学生ギルドに無断で都市からでない」など)として作られた。その後、教師のギルドも作られ、連合体を意味するようになる。ギルド=組合を意味する大学は、学生間で上下関係がなく、日本語の訳語としては「大学」ではなく「組合」とした方が原義に近い。ウニヴェルシタスという語はもともと団体全般を指していたが、特に「教師と学生の団体」を指すように。
中世の大学の中でも最初期の代表的なものはイタリアのボローニャ大学とフランスのパリ大学である。ボローニャ大学は自由都市国家ボローニャで生まれた。11世紀末以来、『ローマ法大全』を研究したイルネリウスをはじめとして多くの法学者が私塾を開いていたボローニャは、法学校のある学都として有名になり、ここに各国から集まってきた学生たちが市民や市当局に対して自分たちの権利を守るために結束して作った組合が大学の起源である。
この意味での大学は自然発生的に成立したものであるため、創立年を明確に示すことはできない。一方、12世紀のパリにはノートルダム司教座聖堂付属学校や聖ジュヌヴィエーヴ修道院付属学校をはじめとして多くの学校があり、アベラールもパリでよく講義を行っていた。12世紀末までにこれらの教師たちが権力者の介入に対抗して結集したのがパリ大学の始まりである。私塾の連合体としてのパリ大学がいつ成立したかを明確にすることはできないが、1200年にフランス王の勅許を得、1231年の教皇勅書『諸学の父』によって自治団体として認められた。イングランドのオックスフォード大学とフランスのモンペリエ大学もこのように自然発生した大学である。こうした初期の大学では、何らかの事情により教師と学生が集団で他の都市に移住することがあり、それによってオックスフォード大学からケンブリッジ大学が、パリ大学からオルレアン大学が、ボローニャ大学からパドヴァ大学が生まれた。さらにローマ教皇によってトゥールーズ大学が、王権によってサラマンカ大学やナポリ大学が設立された。14世紀に入ると神聖ローマ帝国の領邦君主らによってプラハ大学、ウィーン大学、ハイデルベルク大学が相次いで創設された。
中世の西ヨーロッパにおいて、大学は、神学部(キリスト教聖職者の養成)、法学部(法律家の養成)、医学部(医師の養成)の3つの上級学部と自由学芸学部との4学部からなり、専門職を養成することが大きな役割であった。12世紀から13世紀の間の社会の専門職化の増大に伴って、同様の要求が職業的聖職者に対しても増大した。12世紀以前には、ヨーロッパの知的生活は修道院に託されていた。修道院は、もっぱら典礼と祈りの研究に関わっており、少数の修道院が本当の知識人を誇ることができた。教会法と秘蹟の研究についてのグレゴリウス改革の重点化に従って、司教は、教会法に基づいて聖職者を養成するための、さらに説教と神学的議論で使うための論理学や論争、より効果的に財務を管理するための会計学をふくむ教会運営のより世俗的側面においても聖職者を養成するための司教座聖堂学校を組織した。西方ラテン教会圏で中世末までに生まれた多くの大学は、カトリック教会の後援により、教皇や世俗君主の主導で設立された。これらの大学は、ボローニャ大学やパリ大学が「自生的大学」であるのに対して、「創られた大学」と呼ばれる。
学習は、教会のヒエラルキー内での昇進に不可欠になり、同じように教師は名声を集めた。しかしながら、需要はすぐに、本質的に一人の教師によって運営されていた司教座聖堂学校の容量を越えた。なお、そのうえ、司教座聖堂学校の学生とより小さい町の市民との間で緊張が高まり、司教座聖堂学校はパリやボローニャのような大都市へ移転した。
13世紀に、教会における最高位の職務の約半数が修士学位所持者によって占められ(大修道院長、大司教、枢機卿)、次に高位の職務の三分の一以上が修士によって占められていた。加えて、中世最盛期の何人かの偉大な神学者、トマス・アクィナス、ロバート・グロステストは、中世の大学の出身者であり、スコラ学はその産物といえる。中世の大学の発展は、ビザンツやユダヤの学者からのアリストテレスの広くいきわたった再導入や、アリストテレス主義の思想を支持してのプラトン主義や新プラトン主義の人気の衰えと符合する。
中世の大学は、キャンパスを持たなかった。授業は教会や家のように場所が使える所ならどこでも行われ、大学は物理的な場所ではなく、学生のギルドと教師のギルドが1つにまとまった組合団体として互いに結び付けられた諸個人の集まりだった。この呼称で知られる高等教育機関としての大学は、まさに中世ヨーロッパの産物であり、それ以外の世界各地にあったという古代の教育機関とは直接的な関係はない。
大学は一般に、教師に給料を支払う者に依存する2つのタイプに従って構成されていた。最初にできたタイプはボローニャにおけるもので、学生が教師を雇い給料を支払う。第二のタイプはパリにおけるもので、教師は教会から給料を支払われる。この構造的な違いは他の特徴を作り出した。ボローニャ大学においては学生が全てを運営した。事実しばしば教師は大変な重圧と不利益のもとに置かれた。パリでは教師が学校を運営した。したがって、パリではヨーロッパ中からの教師にとって第一の場所になった。パリでは、教会が給料を払っていたので、主題的な事柄は神学だった。ボローニャでは、生徒はより世俗的な研究を選び、主な主題は法学だった。
大学の研究は学士号のために6年かかり、修士号や博士号のためにはさらに12年に及んだ。最初の6年は、リベラル・アーツ(=自由七科)(算術、幾何、天文、楽理、文法、論理、修辞)を研究する学芸学部 (faculty of the arts) に学んだ。当時ポピュラーな教授法だったスコラ学との緊密な結びつきがあるために、最も重視されたのは論理学だった。
ひとたび学士 (Bachelor of Arts) を取得すると、学生は修士や博士となるべく三つの学部―法学部、医学部、神学部―から1つを選ぶ。神学は学問のうち最も名望のある領域で、かつ最も難しい領域だった。
課程は主題やテーマによってではなく書物に従って設けられる。例えば、ある課程はアリストテレスの書物あるいは聖書からの書物に基づいてあるかもしれない。課程は選択ではなく、課程の設置は固定され、全員が同じ課程をとらなければならなかった。しかし、どの教師が使用するかにしたがって臨時の選択があった。
学生は大学に14、5歳の時に入った。授業は、午前5時か6時の開始が普通であった。
学生は保護を与えられた。学生に特権を与えたのは、皇帝フリードリヒ・バルバロッサの勅令ハビタによってである。だれも学生に肉体的な危害を与えることを許されず、学生は教会裁判所において犯罪のために審問されるのみであり、従っていかなる身体刑からも免れていた。このことは学生に都市環境においてとがめなく世俗法を犯す自由を与えた。実際、多くの乱用がなされ、盗み、強姦、殺人は、聖職者でありながらもゆゆしい結果を直視しない学生の間では珍しくはなかった。このことは世俗的権威とともに不安な緊張へと導いた。学生は時々都市を去り何年も戻らないことによって「ストライキ」した。これは、(学生によって始められた)暴動が多数の学生を死に至らしめた後、1229年のパリ大学でストライキにおいて起こった。学生はストライキしつづけ、二年間戻らなかった。学生は法律上も準聖職者として扱われ、女性が大学に入学することは許可されなかった。12-13世紀には、大学から大学へ渡り歩いたり、ドロップアウトして浪々の身となった学生が方々で見られた。かれらは教会の定職を得られない放蕩無頼の聖職者で、ゴリアールまたは遍歴学生 (clerici vaganti) と呼ばれる。
大学の研究のためのポピュラーな教科書は、ペトルス・ロンバルドゥスの『命題集』と言われる。神学生や修士はカリキュラムの一部としてこの教科書について広範な注釈を書くことを要求された。哲学と神学における中世思想の多くは、スコラ的な文献注釈に見出される。なぜならスコラ学は非常にポピュラーな教育法だったからである。
ヨーロッパにおける国際的な卓越性をもつどの大学も神聖ローマ帝国によって「ストゥディウム・ゲネラーレ」(Studium Generale)として登録された。この施設の構成員は、異なったストゥディウム・ゲネラーレにおける講義課程をしばしば与えるので、ヨーロッパ中にかれらの知識を広めるよう奨励された。
「都市の論理」の著者として有名な羽仁五郎氏の理想とする大学は、自由都市国家で生まれた学生ギルトを元にした、自由を重んじたものなんでしょう。学ぶ権利を最大の売りにすれば、案外このような形式の大学がベストかも。
キリスト教に根差した大学は、世俗的な権力者が、既存の宗教権力に対抗させるため保護育成を図って来たそう面もありそうだ。
また、今後の大学教育を考える上では、西欧以外の他の国の例も研究した方が新しい知見を得られる可能性もありそうだ。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
大学の歴史(2)
近代の大学
米国では1636年にハーバード大学(最初はHarvard Collegeとして)が誕生する。
イギリスでは、英国国教会の主導の下、中世のギルド的な大学の伝統に従った貴族による教育が大学で行なわれており、研究は民間のアカデミーで進められ、発表されていた。
フランスでは、1806年に、ナポレオン・ボナパルトによって、かつての地方大学が専門学校へと引き下げられ、新設された帝国大学(L'Université impériale)が指導監督し、国家が国民の教育にあたるというモデルが採用され、研究はやはりアカデミーで進められるものであった。
特に重要なのは、言語学者でプロイセンの政治家としても有名だったヴィルヘルム・フォン・フンボルトがその骨格をつくったベルリン大学である。ベルリン大学は、国家からの「学問の自由」の標語の下に、研究者と学生が自主的な研究に基づき、真理と知識の獲得を目的として、法学、神学、医学といった伝統的な学問領域を軸として、哲学がこれら3つの学問のみならず、自然科学を含めたすべて学問の理論的な研究を指導するというモデルを採用した。ベルリン大学は、研究と教育の一体化を図るとの革命的な発想の転換により各国の大学のモデルとなり、その産業形成を支えた。19世紀に至ると、歴史学、社会学、教育学、民俗学など新たな学問分野が生じ、数学、物理学、化学など既存の学問分野も急速な発展を遂げただけでなく、哲学から心理学、哲学史が分離するなどして今日の大学の基本的な諸分野が、ほぼその骨格を現すことになった。
イギリス・アメリカでは大学院教育が重視されるようになる。ジョンズ・ホプキンス大学はその代表的な大学である。
20世紀になってからは、欧米以外の世界の各国でも多くの大学が誕生してくるようになる。
ヨーロッパでは、人文科学・社会科学・自然科学でも理論的な学問研究が、大学の主要学部とみなされた。また、経営学や音楽、美術、工学などでの単科大学はやや差別的な位置づけをされていたが、徐々に大学の構成学部として認知されるようになってきた。
21世紀に入ると、情報科学、社会福祉、都市開発などで従来にはなかったような新しいコンセプトの学部も、世界各国のそれぞれの国内事情に対応して誕生するようになってきた。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
ジョンズ・ホプキンズ大学
ジョンズ・ホプキンズ大学(Johns Hopkins University)は、メリーランド州ボルチモアに本部を置くアメリカ合衆国の私立大学である。1876年に設置された。世界屈指の医学部を有するアメリカ最難関大学の一つであり、脳神経外科学、心臓外科学、小児科学、児童精神医学などの学問を生み出した。附属のジョンズ・ホプキンズ病院は世界で最も優れた病院の一つとして認知されている。また世界最古の公衆衛生大学院を有し、US Newsの格付けが開始されて以来ランキング1位を保っている。医学部が最も有名で、10年以上US No.1ホスピタルの地位を継続してきたが、他学部においても各種の大学ランキングでは常に最上位に位置する名門校で、政財界から学術分野まで幅広い分野で指導的な人材を輩出しつづけている。そのため、卒業生からの寄付金も莫大であり、NIHの競争資金とともに、大学の研究活動に多大な貢献をしている。
スタンフォード大学と共にヒドゥン・アイビーの一校として知られ、これまで36名以上のノーベル賞受賞者を輩出。2019年の合格率は9.2%。
ボルティモアのクェーカー教徒の実業家ジョンズ・ホプキンズ(1795年 - 1873年)の遺産を基に、1876年に世界初の研究大学院大学として設立された。それまでのアメリカの大学教育は教養中心の学部教育であったが、新たに研究を中心とした専門教育を行うことを目的とし、大学院教育のシステムを確立した。大学院教育と奨学金を組み合わせることによってPh.D.(博士)の学位の授与制度の改革を行ない、この制度を他の多くの大学が取り入れることによってアメリカ全土に広まったとされる。全米で初めて実験室での科学実験を行った?、また、公衆衛生大学院 (School of Public Health) を初めて設置したのもこの大学。附属のピーボディ音楽学院(Peabody Institute)も北米で最初の音楽学校であり、この大学には「アメリカで最初」と言われるものが多い。
前述の通り医学・公衆衛生学の研究に優れ、US Newsのランキングで医学大学院は常に全米1-2位、公衆衛生大学院は格付けが開始されてから一度も陥落することなく全米1位を保っている。同じメリーランド州に位置するアメリカ国立衛生研究所との関わりが深く、多くの研究資金を獲得している。特に公衆衛生については同研究所の予算の25%近くを獲得するなど他大学の公衆衛生大学院を圧倒しており、このような豊富な研究資金が高い研究レベルを支えている。
工学分野では医用生体工学が世界的に有名で、長きに渡り全米1位(US News)にランキングされている。国際関係学及び国際経済学では、ワシントンD.C.に設置された高等国際問題研究大学院(Paul H. Nitze School of Advanced International Studies(SAIS))が実務家向けの修士プログラムとして常に全米上位にランキングされ、米国内で特に高い評価を得ている。また、医療経営のノウハウをアメリカ国外の医療機関に提供する組織、ジョンズ・ホプキンス・メディスンを有する。
スポーツではラクロスが有名で大学チームのブルージェイズ(Blue Jays)は何度も全米優勝をしている。キャンパス内に米国ラクロス協会の事務局、ラクロス博物館、ラクロスの殿堂(Lacrosse Hall of Fame)がある。また、大学のマスコットはアオカケス(Blue Jay)であり、学生からは"Jays"と呼ばれている。
最近ではマイケル・ブルームバーグ (2000億円相当)やビル・ゲイツ(23億円相当)の多額な寄付がアメリカで話題となった。
実は、日本の新型コロナ対策を歯に衣を着せず正論で批判する木村盛世元厚生労働省医系技官もこの大学の卒業生。1965年、開業医の家に生まれる。1990年3月、筑波大学医学専門学群卒業。1998年、ジョンズ・ホプキンス大学公衆衛生大学院疫学部修士課程修了。
どうも、日本のマスコミには出演する機会が少ないようだ。口にマスクをされているのかも。
一方の、ジョンズ・ホプキンズ大は今欧米系のメディアで大活躍。世界の感染状況などのマップをネット上でも公開している。都市ロックダウン派の司令塔のような存在だ。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
ナーランダ大学
ナーランダ大学(ナーランダだいがく、Nalanda University、 ナーランダー大学)は、インドビハール州、ナーランダ(नालंदा、Nālandā)中部にある427年に建てられた世界最古の大学の1つ。北部インド仏教の最重要拠点であり、後期以降はヴィクラマシーラ大学(Vikramaśīla University)等と共に、インド仏教が終幕を迎えるまでそれを支えた。ナーランダ僧院(ナーランダー僧院)、ナーランダ大僧院(ナーランダー大僧院)、那爛陀寺とも。
「ナランダ」は " 蓮のある場所 " という意味。蓮は知恵の象徴であるため、“知恵を与える場所、知恵を授ける場所”と解釈される。(ナラン=蓮、ダ=与える) また玄奘三蔵は『大唐西域記』で " 施無厭(せむおん) "という意味にとっている。この場合は“惜しみなく与える処、倦まず授け続ける場所”という解釈になる。(ナ=ない、否定、アラン=十分、ダ=与える)
ゴータマ・ブッダ が訪れ、"Pavarika" と呼ばれるマンゴーの木立の下で説法した。仏教を学ぶ重要な場所となり、10,000人までの人が滞在した(最古で、それまでの歴史で最大の居住型の学校、最多で1万人の生徒と、1,500人の教員がいた。高い塀と、1つの門、図書館は9階建ての建物にあり、多様な分野の教科が行われていた)。
チベットの記録によると、インド仏僧龍樹(ナーガールジュナ)(150 - 250年頃)が講義を行ったとされるが、グプタ朝(427年成立)時代に、クマーラグプタ1世によって大学が出来たと思われる。
645年(唐時代)に、唯識派のシーラバドラ(中: 戒賢)は玄奘三蔵に唯識を伝え、玄奘は657部に及ぶ経典を中国に持ち帰った。
**
761年に中観派のシャーンタラクシタ(中: 寂護)がチベット仏教を起こし、774年にはニンマ派の開祖パドマサンバヴァ(中: 蓮華生)が密教をチベット仏教にもたらした。サムイェー寺の宗論(792年 - 794年)では、インド仏教のカマラシーラと中国仏教の摩訶衍が宗教論争を行い、チベット仏教の方向性を決定した。
1193年に、アイバク靡下の将軍 ムハンマド・バフティヤール・ハルジー 率いるトルコイスラム人の侵略によって大学は破壊された。インド仏教の衰退はグプタ朝時代から始まっており、イスラーム侵入以前にはほぼ衰退していた。イスラーム勢力によるナーランダー大学の破壊はインド仏教の滅亡を決定づけた。
1957年、中華人民共和国の周恩来総理によるインドのジャワハルラール・ネルー首相への提案で大学に玄奘の舎利が分骨された。
ナーランダーに関連した仏教
大乗仏教 (Mahayana):ナーランダ大学で学究が進められ、その成果がヴェトナム、中国、韓国、日本に伝わった。
チベット仏教 (Vajrayana):ナランダ後期(9ー12世紀)の教え、伝統から来ていると思われる。
現在ナーランダには人は住んでおらず、遺跡が残っている。バラガオン村 (Baragaon) が近接。 現在ナーランダー全地域を衛星写真で記録する作業が行われている。ナーランダー博物館には発掘された写本、遺物などが展示されている。現在ナーランダーの名は3つの学校と修道院に付けられている。 ビハール州、スリランカ、トロント、フランスの修道院にもナーランダーの名前が使われている。
新ナーランダ大学の建設は「ナーランダ大学復興構想」と呼ばれるインドの国家プロジェクト。 新ナーランダ大学は2014年9月1日、800年の時を経て授業を再開した。40ヶ国の1000人の申請者の中から15人を募集して新学期を開始した。ナーランダ大学の副学長よると2020年までに大学院を7つ設立して科学、哲学、心理学、社会学科を開設する予定である。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
自虐史観
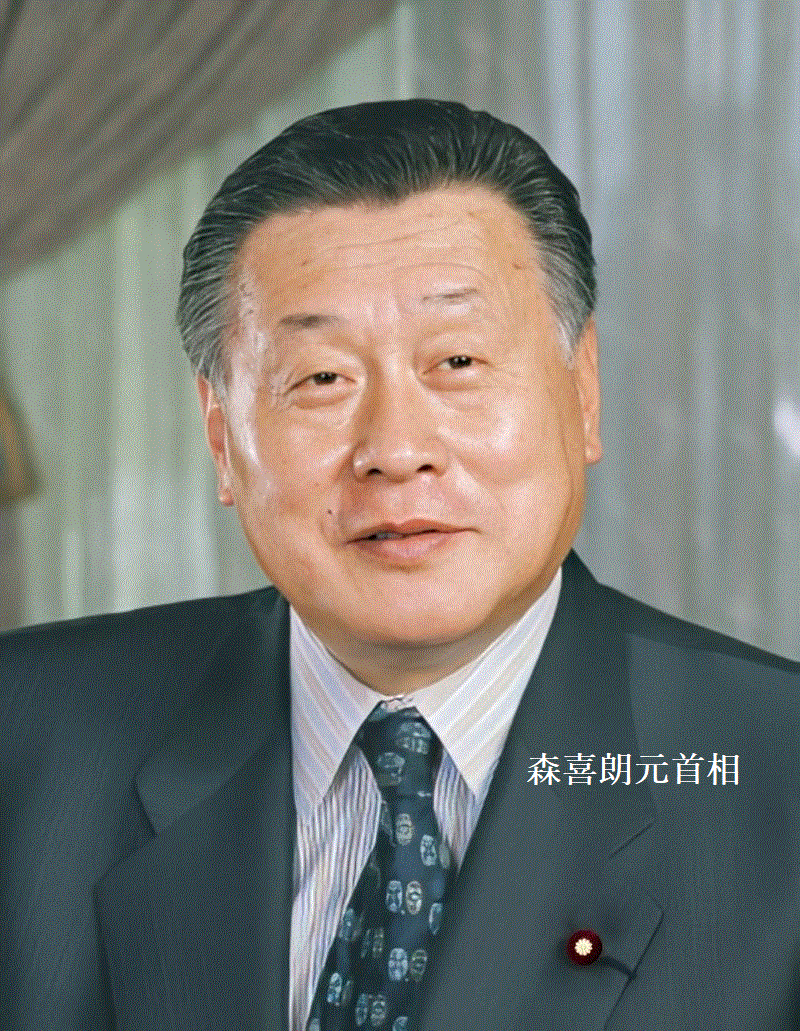 この度の、森喜朗のオリンピック会長辞任を巡って、日本のマスコミがいかに自虐史観に取り憑かれているかがはっきり分かった。卑しくも日本の総理も務められたお方だ。
森氏の発言は、少なくとも内輪の議論の一環で、話だけ見ても女性蔑視論を展開している訳では無い。要するに内部の人間のリークで、話を部分的に切り取って意図的に流した陰謀であることは明かだろう。
この度の、森喜朗のオリンピック会長辞任を巡って、日本のマスコミがいかに自虐史観に取り憑かれているかがはっきり分かった。卑しくも日本の総理も務められたお方だ。
森氏の発言は、少なくとも内輪の議論の一環で、話だけ見ても女性蔑視論を展開している訳では無い。要するに内部の人間のリークで、話を部分的に切り取って意図的に流した陰謀であることは明かだろう。
そもそも発言自体が不適切であったかどうかも不明だし、森さん本人も謝罪し発言を取り消し(無かったことにした)、IOCを認めたものをわざわざ問題視して、大騒ぎすること事態、明かに欧米諸国の陰謀であると気がつかないほどマスコミは馬鹿なのか? 本来マスコミは、日本の立場をしっかりと説明する責任があったはずだ。
どんなリーダでも、発言内容は100%正しいとは限らない。でも、勇気を持って発言し間違ったら周りのものに修正してもらえばよい。マスコミは言論の自由すら抑圧したいのだろうか。
結局、欧米の主張は、日本は女性蔑視の国だから、オリンピックを開催する国としては相応しくない。だから誰が会長をやっても同じだから中止すべしと言っているのだ。確かに朝日新聞も、NHKもかなり前から中止論を展開していた。
つまり、マスコミの主張は、「米国のいうことだから、日本は本当に女性蔑視の国なんだろう。米国のいうことだから聞いた方が良い。」という変な思い入れがありそうだ。
でも、日本は本当に女性蔑視の国で欧米より遅れている?? 確かに欧米では女性の社会進出は数値目標を実施しているのか日本より進んでいる面もある。
しかし、歴史を学んでみれば分かる。女性蔑視の伝統は欧米キリスト教プロテスタントの思想だ。伝統社会の男女の役割分担とは全く異なったルーツであることを見抜かないといけない。都市労働者が増え、一婦一夫の核家族の誕生から生まれたもの。家の中心には夫がいて家内労働は主婦の役割。だから欧米の男女平等は戦いの歴史となる。日本の方が進んでいる面も沢山あることにも注意して欲しい。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
温暖化問題の虚構
温暖化対策の問題は、我々がまだ会社員勤めの時代からずっと続いている超長期的な課題だね。
もうかれこれ40年前から、ずっと技術開発やって来た。自然エネルギーの利用、太陽光、風力、波発電、水力、バイオマス。どれもうまくいかなかった。政府の補助金なしではどれも成立しない。要は原油が安過ぎて需要が無い。だったら脱炭素で需要を作ればいい?
CO2が温暖化の原因だということは、ずっと証明できない。温室効果と言っても、空気中で0.04%以下の超微量成分が温室効果に大きな役割を果たすとは物理的に説明不可能。だから小中学生にも理解できる説明は今後も出ない。環境学者は、CO2悪玉論を前提(仮定)にして、これを疑わないことして先に研究を進めているらしい。結局自分達だって分からない。
科学者の態度としては大変危険なことだ。科学の基本は、仮説を疑うことで始めて新しい発見が出来る。仮説に仮説を積重ねて行っても得られるものは無い。
脱炭素を進めようと本気で動いているのは欧米の政治家だけ。残りは追従組だね。そう言う意味では、今のcovit-19と同じ構図。
ところで、地球上の直物(動物よりマスが巨大)にとっては、CO2は貴重な栄養素のもの。
過去の歴史を見ればCO2はもっともっと多かった。今の植物達にとっては、CO2の長期的減少は
看過できない危機なのかもしれない。
大森林→草地化→農耕→イネ科植物→砂漠化(CO2零)→生態系の絶滅
(2021.02.21)
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
G7サミット
G7サミットとは、主要国首脳会議もしくは先進国首脳会議は、国際的な首脳会議の一つ思われて来た。現時点では、その実態はほとんどない。代わりに出て来たのがG20だ。
日本では、未だにニュースなどで大きな会議のように報道されているが。日本のマスコミはG7が大好きらしい。
ロシア連邦が参加していた1998年から2013年までは、G8、主要8ヶ国首脳会議などと呼ばれていが、ロシアも中国も排除してしまったら主要国・先進国とは羊頭狗肉の状態だろう。
主な参加国→米国、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、日本の7カ国。何のことはない、第二次大戦の戦勝国と敗戦国(ドイツ、イタリア、日本)の戦後復興のための協力会議。戦勝国のイギリス、フランスだって、相当ダメージを受けていたのだから。戦前の旧先進国の再構築が目的か? 東西冷戦の時代には大きな役割を果たして来た。ただこれらの国が今、世界の主要国かつ先進国と言えるだけの経済力もリーダーシップも全く持っていないことも事実であることだ。
バブル経済崩壊寸前の米国、EUとしてのまとまりを欠くドイツとフランス、EU離脱を決めた英国、東アジアを重視しなければならない日本、一体何を話し合おうというのか?
G7のまとまりを結び付けているのは、軍事同盟。NATOと日米安保協定。この2つがメリット亡くなった今、G7に拘ることは百害あって一利無し。化石の様な存在なのか?
しかも、G7で決められたことは、何の国際法的な権限もないため、G7諸国間の談合と言う意味しか持たない。
代りに登場したのが、G20。構成国は、アメリカ合衆国、イギリス、フランス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ、EU、ロシア、中華人民共和国、インド、ブラジル、メキシコ、南アフリカ共和国、オーストラリア、大韓民国、インドネシア、サウジアラビア、トルコ、アルゼンチンである。20か国・地域首脳会合(G20首脳会合)および20か国・地域財務大臣・中央銀行総裁会議(G20財務相・中央銀行総裁会議)を開催している。
ただ、これも旧G7に、非欧米諸国を追加したもの。だったら、国連の場で話し合いをすれば良いのでは。G7もG20も多くの政治団体やNGOからの反対の声も大きい。
確かに、日本もメディアでは、G7サミットはG20より取り扱いが大きい。G7諸国間の談合とは言え、国際政治で談合の果たす役割は無視できないかも。
今回のコロナについても、G7サミット主要国とその支援国にだけワクチンが供給されるとか。ワクチンは恵んでもらうのか無理やり買わされるのか?
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
送別会は悪いこと??
職員23人が午前0時近くまで送別会を開いていたことが明るみに出た厚生労働省では、ほかにも3月下旬に2部署で、政府が自粛を求める5人以上の会食を開いていた。
厚労省は今回の問題を受け、2度目の緊急事態宣言が出た今年1月7日以降、本省と中央労働委員会事務局で「職員5人以上の会食」が開かれていないかを調べた。
その結果、職業安定局の建設・港湾対策室で管理職含む5人、子ども家庭局の保育課で6人の会食がそれぞれあったという。いずれも緊急事態宣言が解除された後の3月下旬で、東京都が飲食店の時短要請をしている午後9時までに終わったとしている。
厚労省は30日、全職員にメールで「歓送迎会等の会合は控え、自覚ある行動をとること」と指示した。
職員23人で送別会を開いていた老健局老人保健課については、厚労省は会合を提案した同課の真鍋馨課長を減給1カ月とした上で大臣官房付として事実上更迭するなど、計22人を処分した。田村憲久厚労相も給与を2カ月間、自主返納する。
以上、朝日新聞のニュース。朝日自身はこれに対して論評を控えているが、一体何が問題で厚労省の役人たちは処分されねばならないのか。公務員の倫理規定に違反する者とは思えない。政府が求めたのはあくまでも自粛であって、法令に違反する行為をしたわけでもない。
日頃、超過勤務の多い本庁の職場で、仲間の移動に伴う送別会はある意味仕事を円滑に進めるうえで必要なことだろう。仕事の都合上夜になることは今までもそのようにしていたためでしょう。出来れば勤務時間中にやりたいのでしょうが。その意味ではこの職場の上司の判断は適切で、部下達の尊敬を集めてしかるべきだろう。マスコミの人達がタカリで酒飲むのとは全く次元の異なる話だ。人数だって高々23人、これが感染の拡大と何ら関係ないことなど一目瞭然ではないか。
「歓送迎会等の会合は控え、自覚ある行動をとること」→明かに自覚ある行動の範囲内でしょう。
田村憲久厚労相も態度がいい加減だね。いい仕事してもらおうと思ったら部下を庇わねばならない立場だ。謝って済む問題ではない。愚劣な指示出していた政府の責任。田村1人が辞任すれば何の問題も無いことだろう。
「職員5人以上の会食」もそもそも、理不尽極まりない、何ら根拠のない非科学的なスローガンだね。4人ならOK? こんなクソ馬鹿なスローガンなんて厚労省の役人でなくても守る気がしない。市井の民間人だって馬鹿にしている。
確かに、テレビなどの報道では感染者が増えたことにはなっている。しかし、日本全体の感染者の数? 大体6,000人に1人の感染者がいることになっているようだ(Googleで調べて見れば分かる)。23人の中に誰が感染者いる確率? ほとんど零だね。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
Kフェミニズム
(オセラビ:作家・コラムニスト;出典JBpress)
文在寅政権の発足と軌を一にして燃え上がる韓国のフェミニズム運動「Kフェミニズム」(*KはKorea)。女性運動家の中心は「反米・反日・自主統一運動」を基調とするNL系(*北朝鮮の主体思想を受け入れる一派)であり、これとラディカルフェミニズムを結合したものが「Kフェミニズム」の本質だとか?女性の生活向上ではなく、上層部のエリート女性の権力と権限を強化する手段に過ぎない。
**でも、反米・反日・自主統一だけでは北朝鮮シンパかどうかは分からない。
**これ、寧ろ米国のバイデン政権の人権主義と同じ傾向では。政府の要人にやたらと女性を活用。それによって反対派を排除できる。日本の森発言に意義を唱えたのもその一派では?
オセラビさん
1958年生まれ。女性作家、コラムニスト。仁川市在住。長期にわたり社会運動に身を投じ、老境に入って旺盛な著述活動に励む。現在NGO団体「未来代案行動」の共同代表を務める。メディアにコラムを寄稿しながら週2回、読書討論会を主催。2018年に出版されたフェミニズム批判書『そのフェミニズムは間違っている』が社会的反響を呼ぶ。著書に『そのフェミニズムがあなたを不幸にする理由』(2019)、『フェミニズムはどのようにして怪物になったのか』 (2020)、『性認知感受性トラブル』共著(2020)、『ギャンブルに溺れた青少年』共著(2020)など。
韓国の作家でコラムニストのオセラビ氏がKフェミニズムを斬る。↓↓↓
ソウルと釜山(プサン)の市長補欠選挙が4月7日に行われた。結果は、巨大与党である「共に民主党」の惨敗。この結果を巡り、韓国社会は大きく揺れ動いている。一つの事件とも言えるほど、社会に大きな波紋を投げかけた。
**共に民主党=共に民主党(더불어민주당)は、韓国のリベラル政党である。2017年から大統領を務める文在寅(文在寅政権)を擁立する与党であり、国民の力と並ぶ二大政党のひとつ。対抗馬はセヌリ党。
今回の投票における特徴は、20代男性と20代女性の投票行動が対照的だった点が挙げられる。注目すべきは20代男性だ。前回の記事(韓国社会を引き裂く「Kフェミニズム旋風」の病理)で書いたように、韓国にフェミニズム旋風が巻き起こってからの7年間、ジェンダーを巡る議論で守勢に回っていた20代男性が野党に票を投じることで、親フェミニズム政策を掲げてきた民主党に痛撃を与えた。
**多くの国民は、親フェミニズム政策にNo!と理解できるか?
20代、30代男性の野党候補への投票率は、それぞれ72.5%、63.8%と高水準だった。一方、20代女性の投票率は親フェミニズム政党である与党で44%、フェミニストの候補者で15.1%という結果だった。
今回の補欠選挙は、2020年4月と7月に、ソウル市長と釜山市長が相次いでセクハラ事件を起こしたために実施されたもの。釜山市長は辞任し、ソウル市長は訴えられて自ら命を絶った。朴元淳(パク・ウォンスン)ソウル市長は、韓国で最初の男性フェミニストであり、韓国の女性人権運動に大きく貢献した人物である。だからこそ、彼の自殺は世の中に大きな衝撃を与えた。ちなみに、彼は歴代最年長のソウル市長であり、次期大統領選挙に出馬する準備をしていた。
朴元淳市長の死は、左派フェミニスト陣営全体を驚愕させた。女性運動の永遠のパートナーであった朴元淳市長のセクハラ事件が発覚すると、与党のフェミニスト女性議員たちは一斉に沈黙を通した。この「選択的MeToo運動」、あるいは「味方のセクハラ事件は知らんぷり」という態度は非難の的になった。言うなれば「悲しいアイロニー」だ。フェミニズム運動の先頭に立っていた与党の女性国会議員の偽善的な性倫理に対するダブルスタンダードは多くの人々に非難されるに値する。
この補欠選挙の結果は、20代、30代の男性による明白な反撃(バックラッシュ)であり、20代、30代の女性の分裂といえる。もっとも、社会的現象にはさまざまな要因が複合的に作用している。事実、文在寅(ムン・ジェイン)政権の高位公職者たちによる不正腐敗が相次ぎ、2020年5月には元慰安婦の支援団体、正義記憶連帯(正義連)の不正会計疑惑も起きた。
正義連の前身である挺対協は1990年、37の左派女性団体が集まって発足した。挺対協や左派女性団体からは、20人以上の国会議員が輩出されている。中には長官になった人間もいる。
そんな正義連の理事長であり、旧挺隊協のトップを務めた尹美香(ユン・ミヒャン)議員(民主党の比例代表選出議員)は、現在8件の罪名で在宅起訴されている。罪名は補助金管理法違反、地方財政法違反、詐欺、寄付金品法違反、業務上横領、準詐欺、業務上背任、公衆衛生管理法違反である。
今回の補欠選挙で女性議員たちは、その二重性と選択的・選別的女性運動を批判された。フェミニズム運動に対する全体的な審判の結果でもある。このような局面を迎え、親フェミニズム政策に力を注いできた民主党とフェミニスト陣営は困惑している。
フェミニスト新聞である「女性新聞」は補欠選挙直後、座談会を開いた。この席でフェミニストの女性教授は、20代男性が野党に票を投じたことについて「フェミニズムに対するバックラッシュと見ることはできない」と指摘。加えて「20代男性がフェミニズムを嫌って与党に背を向けたという解釈を民主党は下さないでほしい」と強調した。
フェミニズムに対する不満と批判を男性たちが吐露するたびに、フェミニストたちは「バックラッシュ現象」だと言い、嘲笑してきた。だが、今回の選挙結果は、激しいジェンダー対立と男性を悪者に追いやったフェミニズム運動に対する、明らかなバックラッシュである。にもかかわらず、フェミニストたちは再び確証バイアス(自分に都合のいい情報ばかりを集めてしまうこと)の習性を捨てずにいる。
----------------------------------------------
国家フェミニズムとは、女性の権利、地位向上および権限強化を国家主導で進め、政策として採択することを指す。文在寅政権下では女性に偏った政策と予算投入、そのような社会雰囲気の造成という国家フェミニズムの傾向が露骨になっている。ここで2016年に時を戻してみよう。
当時、大学には多くのフェミニスト団体が誕生し、全国で150もの団体ができた。これらの団体と、左派政党内のフェミニスト団体、ツイッターなどのソーシャル・ネットワーク・サービス(SNS)で活躍する「ネットフェミ」集団、そして既存の女性団体が連合し一大勢力を形成した。
**新しい政権の支持母体を作るのが目的の国家フェミニズムでは、破綻するかも?
このような中、ある事件をきっかけに新進フェミニスト勢力が結集する。2016年5月、ソウルの江南(カンナム)駅付近にある店の男女共用トイレで、23歳の女性が殺された事件だ。警察は、統合失調症患者の男性による通り魔殺人との結論を下したが、フェミニスト陣営はこの事件をきっかけにフェミニズムを再び強調する。「すべての男性は潜在的加害者」「女性は潜在的被害者」という構図がこの時期、明確に作られたのだ。これにより、男女間のジェンダー対立が本格的に展開され始めた。
ヤングフェミニストは「王子はいらない(Girls do not need a prince)」「女性はどんなことでもできる(Girls can do anything)」を叫んだ。ところが、2017年に文在寅政権が発足すると、フェミニストたちはスローガンとは異なることを言いだした。女性は社会的弱者、被害者であるゆえ、女性に配慮した政策を取るよう政府に要求し始めたのだ。こうして、女性家族部とその傘下機関の女性関連予算が急増し、女性専用サービスが大幅に増えた。
**この問題は、生物学的な大きな課題だ。子孫を残すことが人類の使命なら、少数の精子提供者の男性だけがいれば良く、女性だけの世界にすれば良い! でも生まれる子供は半数が男性? 生まれる前に間引きして数減らせばいいか?
逆に世界を動かしているのが男性なら、女性は社会的弱者となるか。子供を産み育てさせられる被害者と言う論理のようだが。本当にそういえるのかな?
--------------------------------------------------------
こうなると、男性は逆差別を受けていると認識するようになる。女性家族部の予算は女性たちのために使われるからだ。
例えば、2021年度の女性家族部の予算のうち、出産や育児によりキャリアが途切れた「経歴断絶女性」の就職支援に、702億ウォンが組み込まれた。反面、男性失業者や「経歴断絶男性」には政府レベルの支援がない。この点を挙げ、女性家族部の存立自体が男性差別の象徴という不満は現在も渦巻いている。大統領府の国民請願(国民が政府への要望や苦情を書き込む掲示板)には「女性家族部の廃止」が多く寄せられ、文在寅政権発足後、請願件数は1500回に達する。
一方、大学の教壇に立つ女性学者にとっては好機となった。新聞や雑誌へのコラム寄稿、セミナー、討論会、著述活動など、女性団体と連携してさまざまな仕事が舞い込んだ。2017年に韓国のフェミニズムはジェンダー対立が激化し、大衆文化の領域へと広がっていった。
ヤングフェミニストたちは、ゲーム、ウェブ漫画、ヒップホップなどに目をつけた。大衆歌謡、特にヒップホップのラップから女性嫌悪や性差別などの表現を探し、ラッパーたちと摩擦を起こした。それだけでなく、バンドが歌っていた過去の曲からもそれらの表現が含まれた歌詞を見つけ出し、攻撃した。有名なウェブ漫画家は、連載中の作品のシーンが標的になり、女性嫌悪主義者として追い込まれた。
ゲームも同様である。ゲームに出てくる女性キャラを巡り、女性蔑視や性的対象化に関する議論が相次いだ。女性キャラのセリフが性差別的だの、特定の体の部位を強調するポーズを描写しているだのとの批判に、男性ゲーマーたちが反発する事例も珍しくなかった。そのほかにも、チームプレーをしていた男女間で起きた性差別、セクハラ発言や言葉の暴力など、頻繁に問題が生じた。
**確かに、欧米流の資本主義社会では、女性の体の特定部位を強調するファッションが多い。女性の体の特定部位が商品に転化されているためでもあるか。しかし、ミニスカートも化粧も、女性側が好んで取り入れている面の方が大きい。イスラム社会ではあり得ないファッションだ。でも、こんなことに男性側が反発すれば、逆にセクハラとされてしまいそうだね。
フェミニストたちは文化・芸術界とサブカルチャー系の検閲官となり、気に入らないもののリストを作り続けた。これにより、韓国社会のあちこちで男女間の溝が深まり、捜査機関に対する通報や告訴が横行するようになる。
2017年の半ばになると、社会が求める女性らしさへの抵抗、いわゆる「脱コルセット運動」に火がついた。この運動の主役は女子大学生だったが、中学生の女子まで参加し、女性が追い求める「美」に挑戦した。
女性は美しくあることを強要されており、これは社会的に男性の権力に規定された家父長制的コルセットだとフェミニストたちは主張する。若い女性は化粧品を捨て、花柄の服をはさみで切り刻み、髪を短くカットしたり剃ったりして、脱コルセット運動に参加した。大学の掲示板に張り紙をし、SNSにハッシュタグをつけることで、この運動は急速に拡散した。
おかげで騒動が絶えなかった。一編のブラックコメディ、お騒がせ喜劇のような脱コルセット運動は、これに同調しない大多数の女性を苦しめたのだ。ラディカルなフェミニストたちはまるで軍隊の将校のように振る舞い、脱コルセット運動をリードする。これは2017年から2018年にかけて続いた。
そして、2018年の新年早々起きたMeToo運動は、韓国社会の地雷となった。2017年10月、セクハラが暴露されたハリウッドの大物プロデューサー、ハーベイ・ワインスタイン氏による事件に触発されたMeToo運動は、すぐさま韓国に上陸。折しもフェミニズム運動が頂点に向かって走っていた時期だった。
韓国型セクハラ暴露の特徴は、被害者がテレビ番組に出演し、有名人のセクハラを暴露することだ。衝撃的な事実が次々と明かされた。例えば、次期大統領の有力候補だった道知事がしていた女性秘書への性的暴行。道知事は刑務所に入れられた。その後、有名政治家、文学者、映画俳優、映画監督、役者、テレビタレントなど、名前を聞けば誰もが知っているような人たちが次々とMeTooの対象になった。皮肉なことに加害者は全員、左派の人々だった。
一方、「スクールMeToo」と呼ばれる学校内のMeToo告発も、全国で起きた。MeToo運動に便乗した虚偽告訴の事件も、相次いで発生する。
**日本でも、マスコミや弁護士達が協力。例え潔白でも連日繰返して同じ報道を繰返していれば、裁判を待たずに既成事実化されてしまう。
嘘のセクハラを教え子に訴えられ、身の潔白を訴えて自殺を図った大学教授、セクハラの容疑をかけられて命を絶った中学教師──。この中学教師の場合は、夜間学習(半強制的に夜10時まで教室で自習を行わされる)をサボった女子生徒が親に理由を問われ、教師が友人の太ももを触ったり暴言を吐いたりするから、と嘘の言い訳をしたことから事件が起きた。
2018年5月には、社会の雰囲気がさらに険悪になった。5月初め、男性の裸体写真がラディカルフェミニズムのインターネットコミュニティー、ウーマドにアップされた。ソウルの弘益(ホンイク)大学絵画科で行われたヌードクロッキーの授業中に盗撮された、ヌードモデルの写真である。
写真をアップした女性は、男性と一緒にヌードモデルをしていた女性であり、ウーマドの会員だった。10日後、容疑者は警察に逮捕される。ここでヤングフェミニストたちは怒りを露わにした。「女性だから早く捕まえた」というスローガンを掲げて臨時団体を作り、「偏った捜査糾弾デモ」を繰り広げたのだ。
**「女性だから早く捕まえた」は、確かに明らかにコジツケけだね。「女性だから放置した。」なら理由として通るけど。
フェミニスト界は待ってましたとばかりに「姉妹愛」で団結した。デモ現場に登場したプラカードやスローガンは、想像を絶するほど男性嫌悪に満ちていた。ウーマドの被害者である男性モデルへの残忍な人格殺人だった。
**被害者が悪者にされる傾向、最近多いね。芸能人の麻薬等も犯人は寧ろ被害者のようでもあるし。
今でもポータルサイトで「恵化(ヘファ)駅デモ」を検索すると、ヤングフェミニストたちの男性嫌悪や男性を卑下する悪口が、どれほどひどかったか確認できる。「性差別による偏向捜査」と主張したフェミニストたちの恵化駅デモは、5月から12月にかけて6回開かれた。すると、男性の政治家など政界の人々は、まるで罪でも犯したかのように降伏の姿勢を取り、ヤングフェミニストたちをなだめたのだ。
このように2018年は韓国フェミニズム運動のピークだった。Kフェミニズムの最大の弊害は、女性たちに被害者意識を植え付けたことにある。このようにして、男性の剥奪感や憤りは少しずつ蓄積されていった。20代の男性は、自分たちが二等国民にでもなったかのような恥辱を感じた。
20代男性の最大の悩みは、兵役義務の遂行である。韓国人男性は憲法によって軍服務が定められている。20代という黄金期の3割を国家のために奉仕するのに「補償のない義務」を果たしているという不満がある。
実は、兵役を済ませた者には、公務員試験で軍加算点が与えられていた。しかし、梨花(イファ)女子大学の学生たちが根気強く軍加算点廃止請願を行い、2001年に同制度は廃止された。最近では公共機関(340カ所)でも、昇進審査の際に軍の経歴を認めるという規定は男女差別に当たるという理由で廃止されている。男性の逆差別の不満はさらに増幅した。
前述したように、社会運動には累積された複合的な社会的要因が存在する。フェミニズム運動が猛威を振るい、韓国の若い男性たちは危機に面している。フェミニズム運動は、女性には寛容、男性には無寛容の時代を作り上げた。
2018年は男女別自殺死亡率において、男性と女性の差が最も大きかった年である。自殺者全体のうち、男性の割合が72.1%を占めた。しかし、世間は男性の自殺には関心がない。政府が「国家フェミニズム政策」をトップダウン方式で拡散させているうえ、フェミニストの女性たちを筆頭に関連団体などが、予算と公共政策の主導権を握っている。彼女たちの権力と影響力は弱まりそうもない。
この7年間のフェミニズム運動の結果が、今回の市長補欠選挙で投じた若い世代の票で明らかになった。20代男女の投票結果は、ジョン・グレイの『男は火星人、女は金星人』を連想させた。韓国の男女の距離が火星と金星ほどあるとしたら、これは大変なことである。なぜこうなったのだろうか。
**ジョン・グレイ『男は火星人、女は金星人』の内容説明
「思わせぶりな態度ばかりで、彼はなぜ「好き」と言ってくれないの?優しかったり冷たかったり、気持ちが読めない彼に困っています…―世界中から寄せられる恋の悩みに答える心理学者ジョン・グレイは確信する!恋がうまくいかないのは、男は火星人、女は金星人と言えるほどもかけ離れた存在で、思考回路、感じ方から、行動パターンまで、まったく違うためだ、と。火星人である男性と金星人である女性が、お互いを理解することができれば、恋の悩みはすべて解決!」幸せな恋を手に入れるためのヒントがぎっしり詰まった恋愛Q&A集。
前でも述べたように、20代男性たちは異口同音に、これまでの激しいフェミニズム運動によってもたらされた男女間の葛藤が問題だという。今後、当分の間、男女の対立は続くだろう。韓国社会が今後、解決すべき課題である。(翻訳:金光英実)
*******************************************************
{感想}:
1. 差別の問題は、どうしても政治問題に転化されやすい。でも、実際は社会全体の問題でもあるし、経済活動とも密接した分野だ。政治の分野では機会均等は法制度の整備で対応できるが、結果の平等は下手にいじるとかえって混乱を招く。日本もオリンピックで、欧米から指摘された結果の平等がなってないと言われ、政治的解決? 米国流の人権主義には無理がありそうだが。
2. 韓国では、未だに兵役の義務が残っている。男女平等を言うなら兵役の義務も平等でないと不公平感はぬぐえないだろう。世界的には女性の兵士もいるから能力の違いとは言えないだろう。世界一の軍事大国米国ですら徴兵制は廃止されている。つまり、韓国は北朝鮮とは未だに戦争状態の国家的危機が継続しているという認識だ。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
疑わしきは無罪
マリス博士は、ある刑事事件の証人を頼まれて引受けた経験を書いている。彼は、この経験から中立公正な立場の証言はあり得ないと皮肉な結論を出している。検事側の遺伝子捜査の結果に異議を唱えてくれが依頼された内容。現場に残された血痕と被疑者の血液がDNA鑑定で同じだと推定されると大抵の場合、有罪とされるケースが多い。しかもそれを決めるのはDNA鑑定なんて全く知らない陪審員達だ。そこで彼なりに作戦を立てて現場にのぞんだ(その件は彼の著書に書かれている)。遺伝子捜査の瑕疵が一つでも発見されれば、その結果は総て無効になる。
ところが、検察側は、巧みに遺伝子捜査の件をはぐらかして、マリス博士は、何も語る必要は無かった。その結果被告は無罪となってしまった。遺伝子捜査の結果が唯一の決め手だった訳だ。つまり、マリス博士がその場にいなければ、検察側は長々と遺伝子捜査の結果を説明し、陪審員も裁判官も有罪判決を出せたということだ。
検察側のスタッフ達がテレビ前で判決の場面を見て号泣していたとテレビが報じていたとか。マリス博士は、そこにいるだけで何もせずに立派に役割を果たしたという逸話。マスコミも不当な判決だと騒ぐかもしれないが。
疑わしきものは罰せず
勿論、この原理は科学の世界にも厳密に適用されなければならない。マリス博士は、同じ理屈で「オゾンホール説」、「地球温暖化説」、「温暖化二酸化炭素説」、「エイズHIV説」これらの、一見科学界の常識とされている仮説にもすべからく異を唱えている。仮説のもととなる証拠が不十分という訳だ。つまり、明確な証拠が見つかるまでは信じてはいけないということだ。仮説に仮説を積重ねて行けばいずれ大崩壊する。
新型コロナで重要な彼の忠告は、
1. 無自覚無症状の感染者いない。
2. PCR検査は感染症の診断に使ってはならない。
感染症の歴史を辿れば1は明白だ。PCR検査が使われる前は、感染症の存在すら気がつかれない。そもそも生命の歴史は、20億年前から生物とウィルスの間では当初から遺伝子をやり取りしながら進化してきたことが分かって来た。PCR検査で発見される遺伝子の断片は、元から体内にあったものかもしれないし、いわゆるレトロウィスルの働きかもしれないし、さてまたジャンク遺伝子と言われている働きの無い遺伝子と言われているもの起源かも。つまり、病気の者の体から発見されたRNAの断片が何処から来たのかは全く特定できないということだ。
「無自覚無症状の感染者いない。」は感染症に関しての定理に近い絶対的な真理だろう。
唯一の例外が、HIVとcovit-19 だけ。HIVはマリス氏自身が強く疑って否認しており、covit-19に関しては、彼は亡くなった直後に大流行したものだ。
だから、HIVとcovit-19は、感染症ウィルスとしては実在せず、PCR検査を利用して人為的に作られた偽のウィルスということになる。
**実はこのようなウィルスはマリス博士の死後、どんどん増えており、エボラ出血熱、SARSやMARS等もそんなものかも。感染症には潜伏期間と言うものがあるので、潜伏期間中に他人に移す可能性があるかどうか、今後の解明すべき課題だろう。
繰返すと、感染病患者の体内からたまたまある遺伝子断片が見つかったことは、その遺伝子をたまたま持つウィルスが、感染病の原因とは全く言えないということだ。つまり、そのウィルスは人類と共生してきた普通のウィルスで、感染病の原因は別のところにある可能性が高い。つまりウィルスは無罪だ。ということは、ウィルス対策は一切無駄。
PCR検査は、彼自身の発明品であり、感染症の診断に使えないかどうかは本人が最も熱心に考えていたはずだ。だから、HIV発見に対しては、「嘘だ。そんなはずはない。」とピンと来たようだ。PCR検査を感染症診断に使うには解決すべき課題が山ほどある。時期尚早ということか。引用文献に使うとして、米CDCとノーベル賞学者フランスの学者モンタニエ等に問い合わせたところオリジナルの文献が見つからない(所持していないと回答)。オリジナルの文献があれば、それをもとに追試をすれば事の真偽は解明される。解明されては困るので米CDCが渡さないように仕組んだ? でも、もしオリジナルの文献が無ければノーベル賞は何を根拠に与えられたか。科学の事実は追試が可能なことで初めて認められる。つまり、現時点ではHIVは感染症のウィルスではない。つまり無罪とする他はない。では、未だに使われているエイズ検査は何なのか。エイズ治療に色々な薬剤が開発されている。製薬会社は相当の利益を出している。しかし発症もしていない陽性者が治療を受けることに果たしてどれだけ意味があるか? 有害無益だろう。つまり、HIV抗体検査は人為的に感染者を造り出しているのか?
つまり、PCR検査で発見されるウィルスの断片は、ウィルスが犯人だとは未だに決まっていないということだ。つまり推定無罪。これはエイズウィルスもcovit-19も同じことだ。新型コロナの場合、PCR検査で陽性と診断されても、その人が感染者であると断定する証拠は一つもない。つまり、感染者とは言えないということ。いくら怪しいと疑っても証拠不十分で無罪。
では、covit-19が犯人でもないのに、マスクをかけさせたり、在宅規制をすることはまさしく人権侵害に当たる不法行為ではないか? 多分ね!
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
バンクシー
 バンクシー(Banksy, 生年月日未公表)は、英国を拠点とする匿名のアーティスト(路上芸術家)、政治活動家、映画監督。色々憶測があるが、要は正体不明。
バンクシー(Banksy, 生年月日未公表)は、英国を拠点とする匿名のアーティスト(路上芸術家)、政治活動家、映画監督。色々憶測があるが、要は正体不明。
彼(彼等)の政治および社会批評の作品は、世界各地のストリート、壁、および都市の橋梁に残されている。ただし、その作品がいつどのように描かれたのかも不明。バンクシーの作品は、アーティストとミュージシャンのコラボレーションを伴う、ブリストルのアンダーグラウンド・シーンから生まれた。バンクシーは、後に英国の音楽グループマッシヴ・アタックの創設メンバーとなったグラフィティアーティスト、3Dに触発されたとされている。ブリストル市が発祥の地であることは確認されている。
**ブリストル市:イギリス西部の港湾都市。ロンドンから西に169キロ、カーディフから東に71キロの位置。人口46万人、隣接地域も併せると約72万人と推定される。これはイギリス全体で8番目に人口が多い都市。
バンクシーは彼の作品を壁のような、わざと公共に見える場所に展示。彼の公開された「展示」は高値で転売されているらしい。バンクシーのドキュメンタリー映画『イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ』(2010年)は、2010年のサンダンス映画祭で公開されている。2011年1月に、彼の映画はアカデミー賞ベストドキュメンタリー部門にノミネートされた。2014年に、Webbyアワード2014で年間最優秀賞を受賞した。
ステンシルアートと呼ばれる、型紙を用いたグラフィティを中心とする。街中の壁などに反資本主義や反権力など政治色が強いグラフィティを残したり、メトロポリタン美術館や大英博物館などの館内に無許可で作品を陳列したりするなどのパフォーマンスにより、「芸術テロリスト」と称する者も散見される。
 街頭などのグラフィティにこだわり、企業や音楽家などの依頼は全て断っている。2002年に日本のファッションブランド「モンタージュ」にTシャツの図案を2種類、 2003年にブラーのアルバム『シンク・タンク』のジャケットをそれぞれ提供して以後、ソニー、ナイキ、マイクロソフト、ミュージシャンのデヴィッド・ボウイ、オービタル、マッシヴ・アタックなどの申し入れを断っている。あくまでも顔の見えない芸術家として振舞うんだね。
街頭などのグラフィティにこだわり、企業や音楽家などの依頼は全て断っている。2002年に日本のファッションブランド「モンタージュ」にTシャツの図案を2種類、 2003年にブラーのアルバム『シンク・タンク』のジャケットをそれぞれ提供して以後、ソニー、ナイキ、マイクロソフト、ミュージシャンのデヴィッド・ボウイ、オービタル、マッシヴ・アタックなどの申し入れを断っている。あくまでも顔の見えない芸術家として振舞うんだね。
多くは街頭の壁面などに無断で描かれ、落書きとして行政が清掃などの際に消去するのが本来であるが、描かれた壁面をアクリル板で保護する建物所有者も見られた(付加価値の向上か)。2007年2月のサザビーズオークションで作品6点が372000ポンドで落札された。
2009年6月13日から8月31日までブリストルの市営美術館で大規模展「Banksy versus Bristol Museum」が催された。
2010年にドキュメンタリー映画『イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ』を監督してアカデミー長編ドキュメンタリー映画賞にノミネートされた。
2015年に英国で期間限定のテーマパーク「ディズマランド」を演出した。
2020年には日本の横浜駅前にあるアソビルで「バンクシー展 天才か反逆者か」が開催された。
『バンクシー・ダズ・ニューヨーク』『セービング・バンクシー』『バンクシーを盗んだ男』などドキュメンタリー映画が多数制作されている。
政治的・社会的テーマ
バンクシーはかつて落書きを、下層階級の「復讐」、またはより大きくより良い装備をした敵(公権力)から、権力、領土、そして栄光を奪うことを可能にする「ゲリラ戦争」の一つの形と表現していたらしい。バンクシーの作品は、中央集権権力をあざ笑いたいという庶民の切望も表しており、また彼の作品は公衆に対して、権力が存在してそれがあなたを抑圧する一方で、その権力は非常に効率的ではなく、欺かれる可能性があり、騙されるべきであることを示すことを願っていると解釈されているようだ。
バンクシーの作品は、反戦、反消費主義、反ファシズム、反帝国主義、反権威主義、アナキズム、ニヒリズム、実存主義など、様々な政治的社会的テーマを扱ってきた。加えて、彼の作品が一般的に批判しているという人間の状態の要素は、欲、貧困、偽善、退屈、絶望、不条理、そして疎外である。 バンクシーの作品は通常、メッセージを出すために視覚的イメージと図像学に頼っているが、バンクシーは様々な本の中でいくつかの政治的に関連したコメントをしている。彼の 「銃殺されるべき人々」のリストにおいて、彼は「ファシスト、宗教原理主義者、(そして)リストを書き誰が銃殺されるべきかあなたに話す人々」をリストしている。バンクシーは自身の政治性をおどけた調子で説明しながら、「時々私は世界の現状についてとても気分が滅入ってしまい、二つ目のアップルパイを食べ終えることさえできない」と描画している。
バンクシーは2017年の英国総選挙において、ブリストル北西、ブリストル西、ノースサマセット、ソーンベリー、キングスウッド、およびフィルトンの各選挙区に立候補している保守党候補者に反対する投票をした有権者に対し、無料で彼の作品のプリントを提供すると申し出た。 バンクシーのウェブサイトに投稿された記述によると、保守党候補者以外の候補者に印を付けた投票用紙の電子メール写真を送れば、限定版のバンクシーのアート作品を郵送されると説明していた。 2017年6月5日、エイボンとサマセット州議会は、汚職の疑いのある贈収賄行為についてバンクシーの調査を開始したと発表し、翌日、バンクシーは「無料プリントの提供を行えば、選挙は無効になると選挙管理委員会から警告された。そのため、私は残念ながらまずい発想の法的に疑わしいプロモーションがキャンセルされたことを発表する。」と述べ、プリントの提供を取り下げた。
確かに投票の代償に物を送るというのは、選挙活動としては贈収賄行為に当たるかもしれない。では、その送ったものが無償で経済価値の無いものなら?
ユーモア好きのイギリス人の事。犯人何て本当は捕まらなくてもいいと思っているのかもしれない。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
推定無罪
推定無罪とは、「何人(なんびと)も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という、近代法の基本原則である。簡単に記されているが運用面では色々問題がありそうだ。
では、有罪と宣告するには誰がどうすれば良いのか。Wiki に説明があるが、司法や法律だけの問題では無いようだ。
狭義では刑事裁判における立証責任の所在を示す原則。「検察官が被告人の有罪を証明しない限り、被告人に無罪判決が下される(=被告人は自らの無実を証明する責任を負担しない)」ということを意味する(刑事訴訟法336条など)。
**被告人が自らの無実を証明することは、多くの場合、科学的にも論理学的にも無理があるらしい。
広義では(建前としては)、有罪判決が確定するまでは、何人も犯罪者として取り扱われない(権利を有する)ことを意味する(国際人権規約B規約14条2項など、「仮定無罪の原則」という別用語が用いられることもある)。
**でも、政治家のスキャンダルなんてマスコミが大騒ぎして、裁判で有罪判決が出る前に責任取って辞任なんてことが日常的に行われている。 有罪判決が出るまでは明かに無実と規定されいるなら堂々と振舞えばいいはずなのに。
「無罪の推定」という表現が本来の趣旨に忠実であり(presumption of innocence)、刑事訴訟法学ではこちらの表現が使われるが、近時、マスコミその他により、推定無罪と呼ばれるようになった。
**推定有罪と言う語もあるのか? マスコミなんかは推定有罪を造るのが大好きみたいだ。
この原則は刑事訴訟における当事者の面から表現されている。これを裁判官側から表現した言葉が「疑わしきは罰せず」であり「疑わしきは被告人の利益に」の表現から利益原則と言われることもあるが、上述の通り、「疑わしきは罰せず」より無罪の推定の方が広い。
日本国憲法第31条の「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」に推定無罪の原則(狭義)が含まれると解釈されている。 法律の定める手続によれば証拠が無くても有罪に出来る? それも変だね。
裁判で有罪判決が出るまでの期間は推定無罪。
もっとも、「無罪の推定」(英語: presumption of innocence)は、「疑わしきは被告人の利益に」(ラテン語: in dubio pro reo)の原則より広く、被疑者・被告人は、有罪の犯人と区別し、むしろ無辜の市民として扱われるべきだという意味として捉えられており(広義の推定無罪の原則、別名「仮定無罪の原則」)、国際的にも定着している。
これは、国際人権規約にも明文化されており、日本も批准している。そのB規約第14条2項は「刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する。」と、権利の形で明確に保障している。
歴史
近代法制以前、推定無罪の原則を定めたのは、バビロニア(現イラク南部)のハンムラビ王が公布した世界最古の法典『ハンムラビ法典』であり、これが他の文明社会にも伝播していった(参考・クリストファー・ロイド 訳・野中香方子 『137億年の物語 宇宙が始まってから今日までの全歴史』 文芸春秋 (1刷2012年)18刷2014年 p.158.)。したがって、西アジアに始まる法原則であり、ヨーロッパ発祥ではない。
**ちょっと待って。ハンムラビ法典と言えば、「目には目を」の原則が有名だけど。これはこれで「法は公平に」の原則を定めたある意味画期的なものだ。推定無罪の原則も ある意味法の公平性を担保する重要な原則だろう。民主主義や人権と言ったものが何でもヨーロッパ発祥で欧米は進んだ国と言う偏見はもうやめた方が良いね。推定無罪の原則は、人類が狩猟生活をしていた時代からずっとあったんではなかろうか。
フランス人権宣言(1789年)第9条で
「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される。ゆえに、逮捕が不可欠と判断された場合でも、その身柄の確保にとって不必要に厳しい強制は、すべて、法律によって厳重に抑止されなければならない。」と規定されたのに始まり、現在では、市民的及び政治的権利に関する国際規約第14の2や、人権と基本的自由の保護のための条約第6条など各種の国際人権条約で明文化され、近代刑事訴訟の大原則となっている。
**逮捕されれば、ほとんど有罪になるような法制度では、こんな人権宣言は無意味だ。しっかりした司法制度が確立されていて、裁判官が推定無罪の原則に従ってくれないと困る。推定無罪の原則は、ハンムラビ法典より更にずっと遡った狩猟採集生活の時代からの人類共通の認識と見た方が良いか。ハンムラビ法典は推定無罪の原則を再確認したものだろう。つまり、フランスの人権宣言は、ハムラビ法典に比べればかなり見劣りのするものとしか言いようがない。革命下では、市民達の憎悪の感情からかなり無罪の有力者が多数殺されたことであろう。
日本では「被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない」と定める刑事訴訟法第336条は、「疑わしきは被告人の利益に」の原則を表明したものだと理解されている。
また、法律の適正手続(デュー・プロセス・オブ・ロー)一般を保障する条文と解釈される日本国憲法第31条の「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」に推定無罪の原則(狭義)が含まれると解釈されている。
もっとも、「無罪の推定」(presumption of innocence)は、「疑わしきは被告人の利益に」(ラテン語: in dubio pro reo)の原則より広く、被疑者・被告人は、有罪の犯人と区別し、むしろ無辜の市民として扱われるべきだという意味として捉えられており(広義の推定無罪の原則、別名「仮定無罪の原則」)、国際的にも定着している。
これは、国際人権規約にも明文化されており、日本も批准している。そのB規約第14条2項は「刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する。」と、権利の形で明確に保障している。
報道・一般国民の感覚と無罪推定
推定無罪は、元来、国家と国民との関係を規律する原則であり、報道機関を直接拘束しないとも考えられている。しかし、推定無罪は、裁判所・検察官を規律する、証明責任の分配ルールである「疑わしきは被告人の利益に」の原則に留まらず、「有罪判決が確定する」までは容疑者・被告人は無辜の市民に近づけて扱われるべきだという人権保障の原理であるとの理解が一般的で、かつ国際的にも定着していることから、私人である報道機関による報道被害も推定無罪との関係で語られるようになってきている。
また、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律5条では原因企業について「推定で有罪」と判断する条文が存在する。
**公害犯罪の場合、確かに原告側が企業の有罪を立証することは難しいだろう。無罪の立証責任が企業側にあると考えれば良いのか。例えば、イタイイタイ病で原因物質カドミウムが微量ならは人体に被害を与えないとかの臨床実験とか。実際の被害が出ていることが立証されれば「推定で有罪」は、多くの人の了解を得られるかもしれない。
でも、色々な事件の犯罪で無罪を証明、有罪を証明ということは結構、論理的数学的な高度な判断が要求され簡単ではなさそうだ。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
殺人事件
実は僕は推理小説お宅ではない。でも、推理小説ではこの所の論理展開がしっかりしてないとサビ抜きの寿司。全然面白くない。逆に論理展開の巧妙さが作品の価値だ。でも、考えれば考える程、殺人事件で犯人と特定し有罪判決を出すというのは極めて困難な作業だと思う。
「AがBを殺した。」 まず、これが基本か。Bは被害者。自殺でなければ他殺か。自殺の場合、犯人はいない。Aは犯人ではない。部屋に多量の睡眠薬が。多量の睡眠薬を服用すれば死に至る可能性は高い。AがBに睡眠薬を飲むように仕向けた?
Aが睡眠薬を勧めた。Bはそれを信じて睡眠薬を服用した。では、Aは犯人か? Aは善意で睡眠薬を進め、Bはそれを信じた。Bには飲まない選択肢もある。多分この件は明かにAは無罪だろう。Aが殺意を持ってBに睡眠薬を進めた。あるいは睡眠薬中にある毒薬を仕込んだ。毒薬を仕込んだのがAだと確証が取れればAが犯人とは特定できるかも。
犯人決定の一つにアリバイと言うものがある。現場不在証明とでも訳されるのか。少なくとも殺人(自殺でないとして)現場にAがいなければAは無罪となる可能性も。
AがBに何らかの理由で渡した毒物をお手伝いさんのCが睡眠薬に誤って(あるいはわざと)混入させた。お手伝いさんのCはそれが毒物とは知らなかったと証言。勿論その証言が正しいかどうかは判定できない。Cが無罪かと言えば必ずしもそうとも言えない。
CがAを殺害しなければならない動機は無い? これは簡単に立証できないだろう。普段からBがCにつらく当たっていた何てことCが言うはずもない。
殺人事件の場合、関係者の証言は普通大変あてにならないものだ。最悪の証言は本人の自白だ。過去の事例では、警察によって拷問によって自白を強要された例は数知れない。ただ、自白によって新たな証拠が発見されるケースも無いわけでもない。推理小説では、犯人の説明に一貫性を求めるために自白を要請するケースは多々ありだね。自白しないとますます不利になる。これが探偵小説のサビみたいなものの一つだ。
殺人では、実際に凶器で人を殺すケースも多そうだ。ナイフや包丁で人を刺す。ピストルで射殺する。紐で絞殺す。「AがBを殺した。」 多分殺人事件だろうが、全く自殺の可能性が無いわけでもなかろう。三島由紀夫の割腹自殺何て言うケースもある。現場には死体が。でもどうやって犯人を見つければいい。まずは、身近な関係者の動機を洗い出すか。誰が殺意を抱くかだね。でも、最近多い無差別殺人では動機は誰でもいい「人を殺したい」だね。つまり、犯人はどこに潜んでいるかも全く未知の状態だ。
現場の証人の存在はどうだろうか。殺人の現場を目撃した。携帯などで写真まで撮影してあれば信憑性は増すかもね。でも、詮索を深めれば目撃者自身が犯人の可能性は無いだろうか。或いは目撃者が犯人の協力者。
そこで最近注目されているのがDNA鑑定だろう。鑑定される対象は現場に残された血痕だね。あるいは、性行為が絡んでいれば精液何て言うのもありかも。
この分野は、PCR検査なんていう凄い技が登場して、盛んに利用されるようになっている。しかし、この技術の発明者マリス博士自身が次のように忠告を発している。
「AがBを殺した?」という事件の場合、被害者Bの血痕がAの服に。あるいは加害者=容疑者Aの血痕が被害者Bに残されていた。鑑定の結果、残された血痕とサンプルの血痕の遺伝子情報が一致していたことが分かるだけだ。これをもって、AがBを殺害したと結論付けるにはあまりにも飛躍があり過ぎると言うのだ。
まず第一にやらねばならないのは、鑑定自体の正当性。鑑定検査が正確に実施されたかどうかだ。高度な専門性が要求され、方法手順が間違うととんでもない結果出る。鑑定自体の正当性を立証するには中立な立場の高度に専門性を有した立会人が絶対的に必要だ。中立な立場ということは、鑑定側が検察側なので被告側の立場で監査しろということだ。
マリス博士は、自身が被告側の立場での承認を依頼されて、これに気づいた。検察側はマリス博士の存在を知り、鑑定結果を証拠として取り上げることを断念。被告は無罪となりマリス博士の出番はなかったらしい。
米国でも多くの裁判では、DNA鑑定結果だけで、陪審員達や裁判官すら説得できてしまう可能性が高い。つまり、推定無罪の者が有罪にされてしまうケースが多発する問題がある。
マリス博士は、同じ理論で、エイズ~HIVウィルス説を否定するに至っている。PCR検査で発見されたとされるHIVウィルス、米CDCが認知し、とりあえず犯人とされ多くの医薬品の開発競争が行われている。「無自覚無症状の者が感染者のはずはない。」
HIVウィルスは、犯人でない可能性が高い。でも、現実には犯人との前提の上で感染対策が実施されている。日本の薬害エイズ訴訟、もしHIVウィルスが犯人でなければ日本の厚生省は無罪判決を勝ち取っていいたはずだ。見直しが必要だね。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
毒入りカレー事件
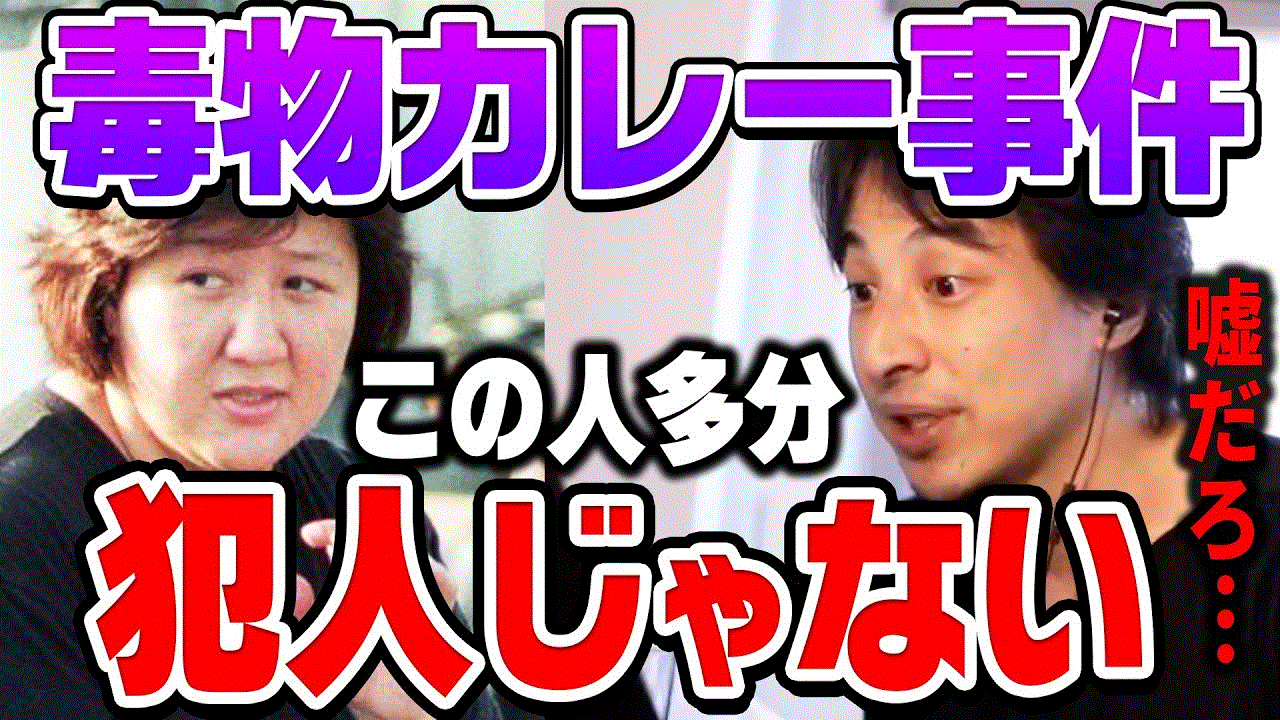 林死刑囚が今でも再審を求めている。ある意味、これは司法のスキャンダルだ。
林死刑囚が今でも再審を求めている。ある意味、これは司法のスキャンダルだ。
毒の発生源を巡って、超大型の質量分析計を使って、カレーに入っていたヒ素がある特定の会社で売られている。シロアリ退治の製品と同じものであることが決め手にされた。
たまたま林被告の家にシロアリ退治の薬品が見つかった。→だから犯人、チョト飛躍だ。
チョットどころが大幅な飛躍だね。
シロアリ退治の薬品を買うことは別に非合法でも何でもない。必要だから購入したというだけ。
また、林被告以外の第三者も自由に入手可能。つまり特定することは困難。他に容疑者は見つからない。つまり消去法で犯人特定?
もし、それ以外に決め手がないなら、当然推定無罪以外はあり得ない。
いくら、専門家が質量分析計の精度の高さをアピールしてもこれでは直接の証拠にはならない。
世論を忖度した判決を出したとしたら裁判官の資質が疑われる。司法の独立制を著しく棄損する。
ホームズ:「そう思わないかね?ワトソン君」ワトソン:「こんなことが証拠とされるなら僕たちの存在価値はないよ。」
【事件の概要】
1998年(平成10年)7月25日、和歌山市園部地区の新興住宅地にある自治会が開いた夏祭りで出されたカレーライスを食べた未成年者30人を含む合計67人が腹痛や吐き気などを訴えて病院に搬送された。異変に気付いた人が「カレー、ストップ!」とスタッフに提供を直ちに止めるよう命じ、一連の嘔吐がカレーによるものと発覚した。
中毒症状を起こした被害者67人のうち、園部第14自治会の自治会長男性A(当時64歳)および副会長男性B(当時53歳)和歌山市立有功小学校4年生の男子児童C(当時10歳)と、私立開智高校1年の女子生徒D(16歳)の計4人が死亡。被害者は会場で食べた人や、自宅に持ち帰って食べた人などで、嘔吐した場所も様々だった。
和歌山県警察および和歌山市保健所は事件発生当初、集団食中毒を疑っていたが、和歌山県警科学捜査研究所が被害者の吐瀉物や容器に残っていたカレーを検査したところ、青酸化合物の反応が検出された。和歌山県警捜査一課は「何者かが毒物を混入した無差別殺人事件の疑いが強い」と断定し、和歌山東警察署に捜査本部を設置した。
【毒物】
当初、死亡した自治会長Aの遺体を和歌山県立医科大学において司法解剖した結果、心臓の血液や胃の内容物から青酸化合物が検出されたため、死因を青酸化合物中毒と判断。また、事件発生直後の鑑定では、青酸化合物を使った農薬などの二次製品に含まれる他の物質は検出されなかったため、県警は混入された毒物を「純粋な青酸化合物」に絞り、県外も含めて盗難・紛失事件がなかったか否かを捜査していた一方、ヒ素など他の毒物の検査は行っていなかった。しかし、A以外の死者3人の遺体からは青酸化合物は検出されなかった一方、Aの胃の内容物や、Bの吐瀉物、Cの食べ残しカレーからそれぞれヒ素が検出され、8月2日には捜査本部が「食べ残しのカレーからヒ素が検出された」と発表。同月6日には「混入されたヒ素は、亜ヒ酸またはその化合物」と発表された。
これを受け、捜査本部から「死因はヒ素中毒だった疑いがある」と報告を受けた警察庁科学警察研究所が新たに鑑定を実施した結果、4人の心臓および自治会長以外の3人の心臓から採取した血液から、それぞれヒ素が検出された。これを受け、捜査本部は10月5日、4人の死因を当初の「青酸中毒(およびその疑い)」から「ヒ素中毒」に変更した。**自治会長は「ヒ素中毒」ではない?
毒物学の専門家である山内博(当時、聖マリアンナ医科大学助教授)によると、厚生省(現:厚生労働省)からの要請で、山内が和歌山市中央保健所へ向かったのは中毒発生9日目で(事件発生の当日、山内はアメリカに滞在)、山内が患者の尿を検査して急性ヒ素中毒であると正式に確定したのは中毒発生10日目だった。原因解明までの10日間、被害者に対して急性ヒ素中毒に有効な治療薬・BAL(British Anti Lewisite)の投与は行われず、対症療法のみであった。
山内によると、急性ヒ素中毒の原因は、カレールーを作る鍋に混入された三酸化ヒ素(無機ヒ素に属す,iAs)であった。三酸化ヒ素は無味無臭で刺激性がない毒物である。鍋に投入された三酸化ヒ素の結晶は大部分が溶解し、カレールーに含有していたヒ素は約6 mg/gと極めて高濃度であった。三酸化ヒ素の致死量は成人でおよそ300 mgとされるので、わずか50 gのカレールーを口にしただけで致死量に達する計算になる。被害者のヒ素摂取量は、重症者では200 mg以上のヒ素摂取者が確認され、軽症者では20 mgから30 mgであった。
1998年10月4日、知人男性に対する殺人未遂と保険金詐欺の容疑で、元保険外交員で主婦の林 眞須美(はやし ますみ、1961年〈昭和36年〉7月22日 - 、事件当時37歳)が、別の詐欺および同未遂容疑をかけられた元シロアリ駆除業者の夫・林健治とともに和歌山県警捜査一課・和歌山東警察署による捜査本部に逮捕され、2人とも同月25日に和歌山地方検察庁から起訴された。
10月26日には、眞須美が別の殺人未遂および詐欺容疑で、健治も眞須美と同じ詐欺容疑でそれぞれ再逮捕され、11月17日に追起訴された。11月18日、眞須美は健治らに対する殺人未遂容疑などで、健治も詐欺容疑で再逮捕され、12月9日には眞須美と健治がそれぞれ詐欺罪で起訴されたほか、眞須美は健治らを被害者とする殺人未遂罪でも追起訴された。
さらに12月9日には、カレーの鍋に亜ヒ酸を混入した殺人と殺人未遂の容疑で眞須美が再逮捕された。同年末の12月29日に眞須美は和歌山地検により、殺人と殺人未遂の罪で和歌山地方裁判所へ起訴された。
当局が、眞須美をカレー毒物混入事件の犯人と断定した理由は
カレーに混入されたものと組成上の特徴を同じくする亜ヒ酸が、眞須美の自宅等から発見された。眞須美の頭髪からも高濃度のヒ素が検出され、その付着状況から亜ヒ酸等を取り扱っていたと推認できる。
夏祭り当日、眞須美のみが上記カレーの入った鍋に亜ヒ酸をひそかに混入する機会を有しており、その際、眞須美が調理済みのカレーの入った鍋のふたを開けるなどの不審な挙動をしていたことも目撃されている。
さらに眞須美は、カレー毒物混入事件発生の約1年半以内という近接した時期に、保険金取得目的で、1997年(平成9年)2月6日から翌1998年3月28日まで合計4回にわたり人の食べ物にヒ素を混入したが、どれもカレー事件前には発覚せず、まんまと保険金をせしめることに成功した。当局は、眞須美が「カレー毒物混入事件に先立ち、長年にわたり保険金詐欺に係る殺人未遂等の各犯行にも及んでいたのであって、その犯罪性向は根深いものと断ぜざるを得ない」と考えた。
**「犯罪性向は根深いものと断ぜざるを得ない」→チョット立件には証拠不十分ではないか。悪いことする人だから悪いでは同語反復だ。
刑事裁判・第一審
眞須美は、容疑を全面否認したまま裁判へと臨み1999年(平成11年)5月13日に和歌山地方裁判所(小川育央裁判長)で開かれた第一審の初公判では、5,220人の傍聴希望者が傍聴券抽選会場の和歌山城砂の丸広場に集まった。これはオウム真理教事件の麻原彰晃、覚せい剤取締法違反の酒井法子に次ぎ、犯行前に無名だった者としては最多である。裁判で和歌山地検が提出した証拠は約1,700点。1審の開廷数は95回、約3年7か月に及んだ。2002年(平成14年)12月11日に開かれた第一審判決公判で和歌山地裁(小川育央裁判長)は被告人・林の殺意とヒ素混入を認めた上で「4人もの命が奪われた結果はあまりにも重大で、遺族の悲痛なまでの叫びを胸に刻むべきだ」と断罪し、求刑通り被告人・林に死刑を言い渡した。
**自治会の夏祭りでカレーに毒入れる動機は。マスコミが騒ぐので誰かを犯人に仕立て上げねばならない。「林の殺意とヒ素混入を認めた」→本人が否認している以上証拠は見つからないのではないか。
被告人・眞須美は判決を不服として、同日中に大阪高等裁判所へ控訴。同月26日、身柄を丸の内拘置支所から大阪拘置所へ移送された。
一方、保険金詐欺事件3件の共犯として、詐欺罪で起訴された健治は、2000年(平成12年)10月20日に和歌山地裁(小川育央裁判長)で懲役6年(求刑:懲役8年)の実刑判決を言い渡された。判決は、眞須美の中心的役割を認めながらも、健治も保険金を支払わせる目的で大きな役割を果たしたと認定した。和歌山地検、健治ともに控訴せず、確定した。滋賀刑務所に服役し、2005年(平成17年)6月7日に刑期を満了、出所。→こちらは一件落着だね。
控訴審
大阪高裁(白井万久裁判長)での控訴審初公判は2004年(平成16年)4月20日に開かれ、結審まで12回を要した。2005年6月28日の控訴審判決公判で、大阪高裁第4刑事部(白井万久裁判長)は「カレー事件の犯人であることに疑いの余地はない」として、一審判決を支持し、被告人・林側の控訴を棄却した。被告人・林は判決を不服として同日付で最高裁判所へ上告した。
**「カレー事件の犯人であることに疑いの余地はない」と言えるのか。科学的論理的に。疑わしきは罰せずの大原則に違反しないかな?
上告審
直接証拠も自白も無く黙秘権を行使し、動機の解明も出来ていない状況の中、弁護側が「地域住民に対して無差別殺人を行う動機は全くない」と主張したのに対し、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は2009年(平成21年)4月21日の判決で「動機が解明されていないことは、被告人が犯人であるとの認定を左右するものではない」と述べ、動機を解明することにこだわる必要がないという姿勢を示した上で、「鑑定結果や状況証拠から、被告人が犯人であることは証明された」と述べ、林側の上告を棄却した。
**自白も無く黙秘権を行使し、動機の解明も出来ていない状況で現行犯でも無ければ被告人が犯人であることを証明することは著しく困難なはず。鑑定結果はヒ素剤に出荷元だけで、市販されて誰でも入手可能。ここのところが明確でないと冤罪の可能性はぬぐえない。
被告人・眞須美は、2009年4月30日付で死刑判決の破棄を求めて最高裁第三小法廷に判決の訂正を申し立てたが、申し立ては同小法廷の2009年5月18日付決定で棄却され、翌日(2009年5月19日)付で林の死刑が確定。これにより林は、戦後日本では11人目の女性死刑囚となり、同年6月3日以降は死刑確定者処遇に切り替わった。
再審請求
死刑囚・林は2020年9月27日時点で死刑囚として大阪拘置所に収監されている一方、2009年7月22日付で和歌山地裁に再審を請求した(第1次再審請求)。
第1次再審請求は、和歌山地裁(浅見健次郎裁判長)の2017年(平成29年)3月29日付決定により棄却され、これを不服とした林は2017年4月3日までに大阪高裁に即時抗告した。しかし、大阪高裁第4刑事部(樋口裕晃裁判長)は2020年(令和2年)3月24日付で死刑囚・林の即時抗告を棄却する決定を出したため、林はこれを不服として同年4月8日付で最高裁に特別抗告を行ったが、後述の第2次再審請求に一本化するため、2021年(令和3年)6月20日付で特別抗告は取り下げられ、第1次再審請求は棄却決定が確定した。
一方、特別抗告取り下げ前の2021年5月には、「事件は第三者による犯行」として和歌山地裁に第2次再審請求を行い、同月31日付で受理された。
冤罪疑惑
本事件の最たる特徴として、被告人・林眞須美による犯行動機が一切なく、直接的な証拠も存在しないという点が挙げられる。→では、何故推定無罪にならなかったのか?
そのため、例えば「実際には家族や知人が毒を入れた可能性」や「被告人がその家族や知人を庇っている可能性」、「誰かに陥れられた可能性」などを否定できず、冤罪の疑惑がある事件として有識者からも問題点を指摘されている。
証拠も動機もない
「批判を承知であえて言えば、本人が容疑を否認し、確たる証拠はない。そして動機もない。このような状況で死刑判決が確定してよいのだろうか?」(田原総一朗)。→当然推定無罪だね。
「私のわだかまりも、この『状況証拠のみ』と『動機未解明』の2点にある。事件に、林被告宅にあったヒ素と同じ物が使われたことは間違いない。ただし、そのヒ素に足があったわけではあるまいし、勝手にカレー鍋に飛び込むわけがない。だれかが林被告宅のヒ素をカレー鍋まで持って行ったことは確かなのだ。だが、果たしてそれは本当に林被告なのか、どうしたって、わだかまりが残るのだ。」(大谷昭宏)。
「動機未解明で有罪にすること自体はありえますが、動機というのは非常に有力な状況証拠です。動機がないなら証拠が一部欠けているということなので、他の証拠はそのぶんしっかりしてないといけません。しかし、他の証拠をみても、自白はなく、鑑定に問題はあり、原則禁じられた類似事実による立証をやっている。本件の場合は動機がないなら、全体的な証拠構造が問題です」「人は普通、動機がないと人を殺しません。しかもこの事件の場合、犯人が誰を殺そうとしたのかもわからない。動機がないと真相がわからない事案だけに、余計に、動機なしでいいのかな、と思いますね」(白取祐司)
黙秘権の侵害
「2審判決は『誠実に事実を語ったことなど1度もなかったはずの被告人が、突然真相を吐露し始めたなどとは到底考えられない』と言ったが、これは実質的に黙秘権侵害です」(小田幸児 - 林の1審、2審、上告審弁護人)
曖昧な目撃証言
事件当時から目撃証言などの状況証拠を積み重ねてきたが、その中には不自然でつじつまの合わない証言も多く、関係者から疑問視されるケースもある。
被告の次女は、「林死刑囚がカレー鍋の見張りを離れた時間が20分以上あり、他の人物が毒物を入れる機会はあった」と主張している。なお、身内による証言ということもあり、和歌山地裁はこの証言を証拠に採用しないことを決定した。
「林眞須美しか、カレーにヒ素を混入する機会がなかった」という結論は、警察が住民らの証言をもとに1分刻みのタイムテーブルを作成し、「消去法」によって導き出したものであった。ところが事件直後の朝日新聞の報道では、時間の証言に裏付けのある人はまれで、総合すると最大で50分前後の開きがあった。ここから、1分刻みのタイムテーブルを作ったことが疑問視されている。
事件発生直後、カレーライスを担当した主婦のうち1人が、「知らない人も出入りしたが、当番でコンビを組んだ相手の知り合いと思った」(朝日新聞)と述べている。それにも関わらず、「犯人は夏祭りの関係者の中にいる」という前提で、「消去法」による捜査が行われた。
眞須美が「調理済みのカレーの入った鍋のふたを開けるなどの不審な挙動をしていた」という目撃証言についても、服の色や髪の長さなどから、目撃者が見たのは眞須美ではなく、次女である可能性が高い。しかも次女がふたを開けた鍋は、2つあったカレー鍋のうち、ヒ素が混入されていない方であった。ヒ素が混入された鍋は、目撃者からは死角になり見えなかったことが、死刑確定後の再調査によって明らかになっている。
鑑定の不確かさ
裁判で林の犯行と断定される上での唯一の物証で決定的な証拠となっていた亜ヒ酸の鑑定において、犯行に使われたとみられる現場付近で見つかった紙コップに付着していたヒ素(亜ヒ酸)、林宅の台所のプラスチック容器についていたヒ素、カレーに混入されたヒ素の3つが東京理科大学教授の中井泉による鑑定の結果、組成が同一とされた。しかし、中井は鑑定依頼内容を、林宅のヒ素と紙コップのヒ素とカレーのヒ素の3つにどれだけの差違があるかを証明することではなく、3つの試料を含む林宅周辺にあったヒ素のすべてが同じ輸入業者経由で入ってきたものだったかどうかを調べることだと理解し、それを鑑定で確認したに過ぎなかった。このため有罪の決め手となった3つの試料の差違を詳細に分析はせず、3つの試料を含む10の試料のヒ素がすべて同じ起源であることを確認するための鑑定を行っていたにすぎなかった。林が自宅にあったヒ素を紙コップでカレーに入れたことを裏付けるためには、3つのヒ素の起源が同じであることを証明しただけでは不充分であり、その3つがまったく同一でなければならない。
2012年、弁護側の依頼で鑑定結果の再評価を行った京都大学大学院教授の河合潤により、この3つの間には重大な差違があることがわかり、3つは同一ではないと評価された。また、河合は最高裁でも林を有罪とした根拠とされる、被告人の頭髪からも高濃度のヒ素が検出されたとする鑑定結果についても、過誤があったと指摘している。
毒入りカレー事件の真相は神のみぞ知るだろう。しかし、被告人は正当な裁判を受ける権利を有すすことは憲法でも保証されている。その点今回の裁判官達の判決理由は独断と偏見の塊りで、世間の多くの識者達が異論を唱えるように極めて問題の多いもの見たいだ。また、このような動きを先導してきたマスコミにも要注意だね。何とか再審請求が認められ事実が明らかになること期待したい。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
ヴィーガニズム
ヴィーガニズム(veganism)は、人間ができる限り動物を搾取することなく生きるべきであるという主義。英国にあるVegan Societyの定義によるとヴィーガニズムとは、「衣食他全ての目的に於て‐実践不可能ではない限り‐いかなる方法による動物からの搾取、及び動物への残酷な行為の排斥に努める哲学と生き方を表す。」脱搾取主義とも言う。
でも、それ日本の仏教思想とも似ているね。僧は極力肉食を排すべし。でも、動物なら駄目で植物ならいいのか? キノコはどっちだ? 健康志向での菜食主義。個人で実施しているなら問題ないが、これをマスメディア使って他人にも強制しようとするなら問題は大きい。日本にも信者いるらしいが。
その範囲は単に動物性食品を食べることを避けることから、あらゆる動物製品を避けることを含む(革、ウール、毛皮等々)。動物性食品を食べない、もしくは追加して動物製品を使わないということの実践とされる。食生活においてはほかの菜食主義(ベジタリアン)の食生活とは異なり卵や乳製品も避ける。pure vegetarianとも。
エシカル・ヴィーガニズムが動物の商品化を否定し、あらゆる目的での動物製品の使用を拒否するのに対し、ダイエタリー・ヴィーガニズムは食事から動物製品を排除するだけにとどまる。また、エンバイロメンタル・ヴィーガニズムと呼ばれる別の一派は、畜産業が環境を破壊しているため持続可能でないという考えから拒否している。
英国ビーガン協会の定義によれば、「Veganisimとは、可能な限り食べ物・衣服・その他の目的のために、あらゆる形態の動物への残虐行為、動物の搾取を取り入れないようにする生き方」である。
ヴィーガン (vegan) という単語は、1944年のイギリスにおいてヴィーガン協会の共同設立者であるドナルド・ワトソンによって造語され、ヴィーガン協会は卵や乳製品の摂取にも反対していた。1951年、ヴィーガン協会は「ヴィーガニズム」の定義を拡大し、「人間は動物を搾取することなく生きるべきだという主義」の意味だとした。1960年、H・ジェイ・ディンシャーはアメリカ・ヴィーガン協会を設立し、ヴィーガニズムをジャイナ教のアヒンサー(生物に対する非暴力)の概念に結びつけた。
ヴィーガン向けレストラン
ヴィーガニズムの運動は年々拡大を遂げている。ヴィーガンのレストランも増加しており、ボクシング、柔術、テニス、サーフィン、陸上競技、アメリカンフットボールなど、ありとあらゆるスポーツ選手が実践している他、アイアンマン・トライアスロンやウルトラマラソンなどの耐久競技のトップ選手の中にも、ローヴィーガニズムやヴィーガニズムを実践する者がいる。
→**これ英国だけの話、欧州社会、或いは世界的?
アメリカ栄養士協会とカナダ栄養士協会は、栄養のバランスが充分考慮されたヴィーガン食は、ライフサイクルのどの段階でも適合できる食事だとしている。バランスを充分考慮したヴィーガン食は、心臓病など数多くの慢性疾患に対して予防効果があることが知られている。
ヴィーガン食は、食物繊維、マグネシウム、葉酸、ビタミンC、ビタミンE、鉄分、フィトケミカルの含有量が高く、カロリー、飽和脂肪、コレステロール、長鎖オメガ3脂肪酸、ビタミンD、カルシウム、亜鉛、ビタミンB12が低い傾向がある。
ビタミンB12は、土壌に含まれている場合も多く、温室栽培、室内栽培、水耕栽培など管理されきった場所で栽培された植物性の食物には、ビタミンB12がほとんど含まれていないため、ヴィーガンはビタミンB12が強化された野菜などを意図的に摂取する必要があるとされている。同時に、栄養強化食品やサプリメントを摂取しない場合であってもビタミンB12欠乏症の症状がみられないとする研究もある。
ベジタリアンという言葉の誕生
初期のヴィーガンの共同体であるフルーツランズ(英語版)は、1915年マサチューセッツ州ハーバードに設立された。
菜食主義は古代インドや古代ギリシアまでさかのぼることができるが、肉食を避ける人々の呼び方として「ベジタリアン」(vegetarian、菜食主義者)という英語が使われるようになったのは、19世紀に入ってからである。『オックスフォード英語辞典』では、この単語の初期の使用例として、1839年にイングランドの女優ファニー・ケンブルが米国のジョージアで使用した例を挙げている。この時期のベジタリアンという言葉では、肉だけでなく卵と乳製品も避けたり、いかなる目的でも動物の利用を避ける人々を指す言葉として使われ、より厳格な完全な菜食主義者も指していた。
どうした訳なんだろうね。牛肉崇拝の欧米人がどういう風邪の吹きまわした菜食主義。ベジタリアンなら東洋にはいくらでも掃いて捨てる程いる。しかも西洋人の悪さは他人にも強制しようとする。これぞ神の教えか? クジラはもともと牛やカバと同じ偶蹄類の哺乳動物。それが何故か脳が大きいから食べてはいけない。だったら、牛を食べることは犯罪か。それは神様が食べるために造ったものだから。馬鹿言う出ない。そんなもの大地の神が作るはずもない。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
七不講(Qī bù jiǎng)
とある大手証券会社からSDGs(持続可能な開発目標)関連銘柄(SDGsに取り組む企業の株式)を中心に運用した投資信託を強く勧められたことがある。だが、その運用先を見てみると、「好未来教育集団(TAL)」など中国の新興オンライン教育企業が複数含まれており、私はつい、TALのどこがSDGsなのか? と担当者を問い詰めた。
目下の中国習近平体制は、「改毛超鄧」(毛沢東路線を焼き直して鄧小平路線を超える)という時代に逆行した路線をひた走っている。経済では民間企業に厳しい計画経済への先祖帰りを求め、西側の普遍的価値観を否定し、中国の社会主義核心価値を押し付け、文革時代のように徹底した共産党の指導による管理監視社会の実現を目指している。そんな中国の企業に、そもそもSDGsの概念が当てはまるのか。
さら教育界では12K(幼稚園から高校までの教育)および大学に、イデオロギー教育の徹底が指示されており、「七不講」(注)が2013年に各大学に通達されて以来、人文系学問の自由が大幅に制限された。これに背く教授や講師、教師が学生、生徒に密告されて職を失う事例も1つや2つではない。
(注)「七不講」は次の「七つの口にしてはならないテーマ」のこと。(1)普遍的価値、(2)報道の自由、(3)市民社会、(4)市民の権利、(5)党の歴史的錯誤、(6)特権貴族的資産階級、(7)司法の独立。
以上は、フリージャーナリストの福島 香織さん、元産経新聞記者の北京特派員の記事から。中国では、管理社会が強化され言論弾圧が進んでいるという前提で書かれているようだ。
七不讲→七つの言ってはいけない事
维基百科,自由的百科全书→中国語版Wikipedia
跳到导航跳到搜索
***検索=搜索(Sōusuǒ)、中国共産党=中國共產黨(繁体字を使っているところから書き手は大陸の人間ではなさそう。台湾かな?)
七不讲,又称七个不要讲,是华东政法大学教师张雪忠在新浪微博上提及、声称是中國共產黨提出的政策,随后得到一些学者和教授的旁证及批判。BBC中文網称,该指示沒有書面寫出,是由相关領導在開會時口述通知,可能会得到長期執行,便請大家互相遵守以免麻煩。2014年1月13日,中国共产党官方网站中国共产党新闻网刊文否认曾存在此说法。
Qī bù jiǎng, yòu chēng qī gè bùyào jiǎng, shì huádōng zhèngfǎ dàxué jiàoshī zhāngxuězhōng zài xīnlàng wēi bó shàng tí jí, shēngchēng shì zhōngguó gòngchǎndǎng tíchū de zhèngcè, suíhòu dédào yīxiē xuézhě hé jiàoshòu de pángzhèng jí pīpàn.BBC
華東政法大学のチャン・シュエジョン教授が新浪微博で、中国共産党が提案した政策であると主張し、「Seven Don't Talk: セブン・ドント・トーク」について言及した。 、その後、一部の学者や教授から状況証拠や批判を受けました。 BBCの中国のウェブサイトによると、指示は書面ではなく、会議中に関係するリーダーから口頭で通知されました。それは長期間実施される可能性があります。トラブルを避けるためにお互いにフォローしてください。 2014年1月13日、中国共産党の公式ウェブサイトである中国共産党ニュースは、この主張の存在を否定する記事を公開しました。
背景Bèijǐng
2013年5月13日,中共中央办公厅印发了非公开发表的《关于当前意识形态领域情况的通报》,并下发到县团级供相关干部学习。通报提到“要切实加强对当前意识形态工作的领导,把加强意识形态领域的工作列入重要议事日程,做到有载体、有活动,形成学习制度”,要求相关官员同“危险的”西方价值观作斗争。文件中称,要“确保新闻媒体的领导权,始终掌握在同以习近平同志为总书记的党中央保持一致的人手中”。
2013 Nián 5 yuè 13 rì, zhōnggòng zhōngyāng bàngōng tīng yìnfāle fēi gōngkāi fābiǎo de “guānyú dāngqián yìshí xíngtài lǐngyù qíngkuàng de tōngbào”, bìng xià fā dào xiàn tuán jí gōng xiāngguān gànbù xuéxí. Tōngbào tí dào “yào qièshí jiāqiáng duì dāngqián yìshí
→2013年5月13日、中国共産党中央委員会の総局は、非公開の「イデオロギー分野の現状に関する通知」を発行し、関連する幹部が学ぶために郡連隊レベルに配布しました。 。 通知には、「現在のイデオロギー活動のリーダーシップを効果的に強化し、イデオロギー分野の強化を重要な議題に置き、学習システムを形成するためのキャリアと活動が存在するようにする必要がある」と述べられています。 「危険な」西側諸国と協力すること。価値観との闘い。 文書によると、「報道機関の指導力は、習近平同志を書記長とする党中央委員会と連携する人物の手に常に委ねられるようにする」必要がある。
BBC中文网称,涉及该通报的互联网内容都被删除或封禁。张雪忠因曾在2012年9月发表对香港国民教育的看法,遭华东政法大学取消其对本科生的授课资格。他还曾致信中国大陸教育部长袁贵仁,要求将马克思主义、毛泽东思想,邓小平理论等课程从大学公共课中去除。
BBC zhōngwén wǎng chēng, shèjí gāi tōngbào de hùliánwǎng nèiróng dōu bèi shānchú huò fēngjìn . Zhāngxuězhōng yīn céng zài 2012 nián 9 yuè fābiǎo duì xiānggǎng guómín jiàoyù de kànfǎ, zāo huádōng zhèngfǎ dàxué qǔxiāo qí duì běnkē shēng de
BBCの中国のウェブサイトによると、通知に関連するすべてのインターネットコンテンツが削除またはブロックされています。 Zhang Xuezhongは、2012年9月に香港の国民教育に関する見解を発表したため、華東政法大学の学部教育を失格としました。 彼はまた、中国本土の教育大臣である袁貴仁に、マルクス主義、毛沢東思想、鄧小平理論などのコースを大学の公開コースから削除するよう要求した。
内容Nèiróng
张雪忠在新浪微博发表“七不讲”,指控此为中共官方发布的言论控制政策:
Zhāngxuězhōng zài xīnlàng wēi bó fābiǎo “qī bù jiǎng”, zhǐkòng cǐ wéi zhōnggòng guānfāng fābù de yánlùn kòngzhì zhèngcè
→張雪中(Zhang Xuezhong)は、中国共産党が発行した公式の言論管理政策を非難し、SinaWeiboに「SevenDoNotTalk」を公開しました。
1. 普世价值不要讲Pǔ shì jiàzhí bùyào jiǎng
→普遍的な価値観について話さないでください
2. 新闻自由不要讲Xīnwén zìyóu bu yào jiǎng
→報道の自由について話さないでください
3. 公民社会不要讲Gōngmín shèhuì bùyào jiǎng
→市民社会は話さない
4. 公民权利不要讲Gōngmín quánlì bùyào jiǎng
→公民権について話さないでください
5. 中国共产党的历史错误不要讲Zhōngguó gòngchǎndǎng de lìshǐ cuòwù bùyào jiǎng
→中国共産党の歴史的な過ちについて話さないでください
6. 权贵资产阶级不要讲Quánguì zīchǎn jiējí bùyào jiǎng
→豊かで強力なブルジョアジーについて話さないでください
7. 司法独立不要讲Sīfǎ dúlì bùyào jiǎng
→司法の独立について話さないでください
其账号后遭到删除。Qí zhànghào hòu zāo dào shānchú.
→司法の独立について話さないでください
→彼のアカウントは後で削除されました。
→司法の独立について話さないでください
“七不讲”也成了新浪微博的搜索敏感詞。“Qī bù jiǎng” yě chéngle xīnlàng wēi bó de sōusuǒ mǐngǎn cí→「SevenDoNot Talk」は、新浪微(SinaWeibo)のデリケートな検索用語になりました。
其他回应Qítā huíyīng→その他の回答
曾任中共前任总书记赵紫阳政治秘书的鲍彤表示不能确定“七不讲”内容是否属实,如果是真的,现任总书记习近平提出的“中国梦”将一夜回到“辛亥革命”之前的“皇帝梦”。若不是事实,《人民日报》和新华社应宣布这是谣言,若不进行辟谣,又在高校当中流传,这就说明主旋律混乱。
Céng rèn zhōnggòng qiánrèn zǒng shūjì zhào zǐyáng zhèngzhì mìshū de bào tóng biǎoshì bùnéng quèdìng “qī bù jiǎng” nèiróng shìfǒu shǔshí, rúguǒ shì zhēn de, xiànrèn zǒng shūjì xíjìnpíng tíchū de “zhōngguó mèng” jiāng yīyè huí dào “xīnhài gémìng” zhīqián de
趙紫陽元政治書記、元中国共産党書記長の鮑彬氏は、「七つのこと」の内容が正しいかどうかわからないと述べた。本当なら「中国の夢」現在の習近平(XiJinping)書記長が提案したものは、一夜にして辛亥革命以前に戻るでしょう。「皇帝の夢」。 それが真実でない場合、「人民日報」と新華社通信はこれを噂であると宣言する必要があります。
历史学者章立凡称中共当局喜欢将口号“数字化”,如“四项基本原则”、“五不搞”、 “三个自信”等。这些口号也体现出中国共产党一成不变的执政思维,这种僵化的统治必将引发自下而上的社会变革。章立凡认为在互联网时代,因为人们的思想没那么容易被钳制,“七不讲”不会给执政者带来期盼的效力。[1]他表示「七不講」其實是「兩個凡是」的發展,當局推出七個不能觸及的禁區,實際上反而是在提醒大家,這是中國大陸現今體制上的七個關鍵弊端。「兩個凡是」即為「凡是毛澤東說的都是對的,凡是毛澤東的指示必須堅決執行」。報道說,2013年是毛澤東冥誕120年,中國大陸當局近來多次收緊言論被指與此有關。
Lìshǐ xuézhě zhānglìfán chēng zhōnggòng dāngjú xǐhuān jiāng kǒuhào “shùzìhuà”, rú “sì xiàng jīběn yuánzé”,“wǔ bù gǎo”, “sān gè zìxìn” děng. Zhèxiē kǒuhào yě tǐxiàn chū zhōngguó gòngchǎndǎng yīchéngbùbiàn de zhízhèng sīwéi, zhè zhǒng jiānghuà de
→歴史家の章立凡は、中国共産党は「4つの基本原則」、「5つのいいえ」、「3つの信頼」などのスローガンを「デジタル化」するのが好きだと述べた。 これらのスローガンはまた、中国共産党の不変の与党思想を反映しており、この厳格なルールは確実にボトムアップの社会的変化を引き起こすでしょう。 章立凡は、インターネット時代では、人々の心はそれほど簡単に抑制されないため、「セブン・ドゥ」は権力者に望ましい効果をもたらさないと信じています。 [1]彼は、「Seven Do Not Talk」は、実際には「Two Whats」の開発であると述べました。当局は、触れることができない7つの制限された領域を導入しました。実際、これらが7つの主要な欠点であることをすべての人に思い出させています。中国本土の現在のシステム。 「二つのこと」とは、「毛沢東が言ったことはすべて正しいことであり、毛沢東のすべての指示は断固として実行されなければならない」という意味です。 報告書によると、2013年は毛沢東生誕120周年であり、中国本土の当局は繰り返し発言を厳しくしている。
民主党人士查建国称“七不讲”的内容非常荒谬可笑,若此事属实,必将遭高校知识分子群起反抗,他说“我怀疑这种消息的真实性,因为七不讲的内容太惊人、太可笑了,而且不可能执行。若是真的,必会遭到抵制,遭到大规模的反对,这是一个很大的倒退。”
Mínzhǔdǎng rénshì chá jiànguó chēng “qī bù jiǎng” de nèiróng fēicháng huāngmiù kěxiào, ruò cǐ shì shǔshí, bì jiāng zāo gāoxiào zhīshì fēnzǐ qúnqǐ fǎnkàng, tā shuō “wǒ huáiyí zhè zhǒng xiāoxī de zhēnshí xìng, yīnwèi qī bù jiǎng de nèiróng tài jīngrén, tài kěxiàole, érqiě
→民主党の趙建国氏は、「セブン・ドント・トーク」の内容は非常にばかげてばかげていると述べた。これが本当なら、大学の知識人に反抗されるだろう。セブン・ドント・トークの内容はすごすぎる。、ばかげていて、実行するのは不可能だ。それが本当なら、抵抗されて大規模な反対に直面するだろう。これは大きな後退だ。」
北京学者莫之许说:“以前虽然没有明文规定,但他们的教学方针就是这样子,因为没有明文规定,有些老师讲这些东西不太会受到惩罚。但现在这样规定的话,若有教师讲这些东西的话就会被处罚、不让上课等等。”北京理工大学教授胡星斗认为中共当局“一切工作的出发点都是为了维稳”,估计是由于现在社会形势非常严峻,中国大陸百姓不满的声音非常大,所以向大学传达称“7个不要讲”精神,“可是这样也就等于走进了死胡同”。他表示也許是中共感到社會危機愈來愈嚴重,所以要從意識形態方面維穩,「但我認為這樣只會陷入更大的危機」。
Běijīng xuézhě mò zhī xǔ shuō:“Yǐqián suīrán méiyǒu míngwén guīdìng, dàn tāmen de jiàoxué fāngzhēn jiùshì zhèyàng zi, yīnwèi méiyǒu míngwén guīdìng, yǒuxiē lǎoshī jiǎng zhèxiē dōngxī bù tài huì shòudào chéngfá. Dàn xiànzài zhèyàng guīdìng dehuà, ruò yǒu
→北京学者のMoZhixu氏は、「これまで明確な規定はなかったが、指導方針はこのようになっている。規定がないため、こう言っても罰せられない教師もいる。しかし、今そのような規定があれば、これらのことを言う教師がいます。何かをすると罰せられたり、授業に行けなくなったりします。」北京理工大学の胡興堂教授は、CCPの「すべての仕事の出発点は現在の社会情勢は非常に厳しく、中国本土の人々は不満を持っていると推定されています。彼の声は非常に大きいので、彼は大学に「セブン・ドント・トーク」の精神を伝えました。行き止まりに等しい」と語った。中国共産党は社会的危機が悪化していると感じているので、イデオロギーの安定を維持したいと述べた。「しかし、これはより大きな危機に陥るだけだと思う」。
法律學者徐昕引述網民的評論:「民主是一種很複雜的東西,複雜到這是中國人唯一沒能山寨成功的東西。」中国大陸知名地产商任志强听闻后砲轟:“要把权力关进笼子,就不能没有新闻自由”。
Fǎlǜ xuézhě xú xīn yǐnshù wǎngmín de pínglùn:`Mínzhǔ shì yīzhǒng hěn fùzá de dōngxī, fùzá dào zhè shì zhōngguó rén wéiyī méi néng shānzhài chénggōng de dōngxī.' Zhōngguó dàlù zhīmíng dìchǎn shāng rènzhìqiáng tīngwén hòu pào hōng:“Yào bǎ quánlì
→法学者の許キン(徐昕?)は、ネチズンのコメントを引用した。「民主主義は非常に複雑なものです。それは非常に複雑なので、中国人がコピーに成功しなかったのはそれだけです。」有名な不動産、Ren Zhiqiang中国本土の開発者は、これを聞いて爆撃しました。電力がケージに閉じ込められている場合、報道の自由はないはずです。」
**網民=ネチズン、山寨=コピー、
どうも北京政府がこのようなガイドラインを明確に示したという証拠は無いようだ。ただ、中国政府はwikipediaに対して、あまり好意的でないようで、勝手な投稿は削除され本当のことは伝わらない。ただ、「武漢日記」の中国の作家方方によると、ネット社会は沢山のサイトがやりたい放題に運営されているらしく、投稿した記事も削除されてしまうことも頻繁にある、しかしそれをまた拾い上げるサイトもあるとか。
ただ、記者が批判したい毛沢東は、言論を統制する代わりに民衆を洗脳して、世論を利用して改革しようという考えだ。国民が不満を持つようなガイドラインを明示的に発表するはずは無いと思われるが。寧ろ国民に媚びを売り、人気を落とすような方式は取らないだろう。
毛沢東は、文化大革命で多くの共産党内の政敵や知識人を粛正し、毛沢東個人が崇拝されるようにしたが、習近平も新型コロナ対策で多くの共産党の幹部を粛正。
古代ローマに例えれば、カエサルは平民会の力を利用して元老院の共和制を壊して、帝政ローマの礎を造った。習近平の理想も中国が世界のリーダとして繁栄していた「明」の時代の理想国家の建設ということかも知れない。民意が反映されれば、民主政治でも皇帝でも良い。中国的な発想かも知れない。
「安倍晋三さんは、総理大臣になるために自民党員となった。習近平氏は主席になるために共産党員になった。」共産党は既に、国を動かす存在ではなくなり、単に政治家になるための資格程度の重みになってしまったようだ。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
帝国の墓場
アフガンは「帝国の墓場」とも言われる。何それ?
古来、アレキサンダー大王、モンゴル帝国、チムール大王、大英帝国、ソ連などが介入し、長期の武装抵抗に悩まされ結局撤退を余儀なくされたという歴史がある。大英帝国以降は分かるけど、過去の話はどうかな?
今回は米国がその轍を踏んでしまった。アフガンはユーラシア大陸のハートランドとも言える戦略要域でもある。でも、かってのアフガンは、東西南の交流の拠点で経済的にも文化的にもそれなりに栄えた土地だったのでは?
世界の屋根と言われるパミール高原から西に流れるヒンズークシ山脈により南北に分断された、内陸の山岳国家であるが、その部族と宗派は複雑に入り組み部族間の争いが絶えない。外敵が侵略して来れば果敢なゲリラ戦を執拗に続け追い出す頑強さを持つ半面、外敵が撤退すると部族間の武力闘争が起きるのが常である。でも山岳民族何てそんなものでしょう。尾根一つ越えれば、言葉も文化も歴史も全く異なる人達同士、統一が難しい地域でもある。
確かに交通の要衝。でも、道路網は限られ国土の大半は高度数千メートルの山岳地帯である。その面積は約65.2万平方キロメートルと、日本の約2倍の比較的広大な国土面積を占めている。人口約3,890万人の民族構成は極めて複雑である。人口は決して少なくない。日本の江戸時代だってこんなものでは?
人口の最大数を占めるのは、パシュトゥン人。彼らは、パキスタン北西部のペシャワールなどを中心とする地域にも居住する民族だが、英国の恣意的な国境線の線引きにより、2つの国に分断されてしまった。つまり、半数近いパシュトゥン人はパキスタンに棲んでいる。クルド人に近い。彼らだけの統一国家を造りたい。
他方のヒンズークシ山脈以北の北部は、トルクメニスタン、タジキスタン、ウズベキスタンなどのトルコ系の諸国と国境を接し、これらの諸民族が居住している。パシュトゥン人に対抗するため北部同盟を結成。これらの部族は同一国家でありながら、パシュトゥン人とは対立関係。国家統一を困難にする一因になっている。
このようなまとまりのない多民族国家として無理やり誕生させた背景には、英露両帝国による緩衝地帯としての国境線画定という歴史がある。19世紀に大英帝国とロシア帝国は「グレート・ゲーム」と言われる覇権争いを、イランからチベットなど清国周辺領土に及ぶユーラシア大陸全域で繰り広げていた。その覇権争いの焦点の一つがアフガンだったことは世界史の常識。英露は直接陸地国境を接するのを避けるため、アフガンを緩衝地帯とすることで妥協した。
実質的には、大英帝国の「保護国」ではあったが王政は残された。タイがそうだね。タイは英仏の緩衝地帯だった。その際に、ヒンズークシ山脈が中央を走る不自然な国境の線引きを地元住民の意向や民族分布の実態を無視して英露両国により一方的にされてしまった。
ワハン回廊と呼ばれる東西約200キロの細長い地形が東に伸びて、中国領の新疆ウイグル自治区と接している。米国がウイグル地区の人権問題を大騒ぎする理由もこれらしい。
これも英露が直接国境を接するのを避ける緩衝地帯とするために引かれた国境線であり、かつ清国の力が衰えていたこともあり、中国とアフガンの国境は極力狭められることになった結果である。中国に言わせれば、新疆ウイグルは元々中国領(清)だったんだから米国の干渉は余計なお世話ということか。
またアフガン西部は、歴史的にペルシアの影響下にあったために、イスラム少数派のシーア派が浸透しており、他の地域の多数派のスンニ派とは対立関係にある。イランは当然シーア派の保護を求めるだろう。
しかも、モンゴル帝国やチムール支配の末裔であるモンゴル系のハザラ族が東部から中部山岳地帯に居住しており、彼らはシーア派でもあり、アフガンを3分する勢力の一角をなしている。また、アフガン南部では、パキスタン南西部、イラン南東部とともに、バルチスタン解放軍がバルチスタン独立を目指し武装闘争を展開している。
アフガンは地形的にも民族・宗教の面から見ても、相対立する部族が高度数千メートルの険峻な山岳地帯に割拠する状況にあり、統一した統治は極めて困難な地政学的環境に置かれている。サービス産業、農業、建設業、鉱業・採石業などの産業があるとされているが、1人当たりGDP(国内総生産)は530ドルに過ぎず、世界最貧国の一つでもある。ただし、世界的な金、銅、レアアース、鉄鉱石、リチウム、ウランなどの鉱物資源に恵まれており、その価値は1兆ドル以上に相当するともみられている。世界のレアアース市場の約7割を占める中国にとり、アフガンの鉱物資源支配はその独占体制を確固としたものにするとともに、電気自動車用電池、その他の先端産業、軍需用に不可欠なレアアースやリチウムなどは極めて魅力のある資源と言えよう。
でも、実際にもっと貴重な資源がここにはある。ここは世界で最も芥子栽培の盛んな土地だ。芥子とは阿片の原料だ。各国で違法薬物に指定されているが、どこの大手薬品会社も喉かから手が出る程、欲しいもの。多くの地域軍閥の大きな資金源となっている。アフガンが真の独立を達成してしまうと、欧米諸国で最も利権を失うのはどこなのだろうね。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
関羽像撤去
関羽像撤去
 【北京共同】中国湖北省荊州市に建てられた三国志の英雄、関羽の巨大な像が違法建築と認定され、7日までに撤去作業が始まった。高さは約57メートルと、20階建てのビルに近い。建設と撤去に計3億2790万元(約55億円; 1元=16.8円)がかかり、無駄な公共事業の象徴として批判されている。
共産党の発表や中国メディアによると、関羽像は湖北省や荊州市が投資するプロジェクトとして2016年(5年前)に1億7290万元かけて建設された。昨年になり、歴史的な町並みを保護する規定に反していると中央政府が認定した。1週間ほど前に取り壊し作業が始まり、既に頭部がなくなった。撤去に1億5500万元かかる。
【北京共同】中国湖北省荊州市に建てられた三国志の英雄、関羽の巨大な像が違法建築と認定され、7日までに撤去作業が始まった。高さは約57メートルと、20階建てのビルに近い。建設と撤去に計3億2790万元(約55億円; 1元=16.8円)がかかり、無駄な公共事業の象徴として批判されている。
共産党の発表や中国メディアによると、関羽像は湖北省や荊州市が投資するプロジェクトとして2016年(5年前)に1億7290万元かけて建設された。昨年になり、歴史的な町並みを保護する規定に反していると中央政府が認定した。1週間ほど前に取り壊し作業が始まり、既に頭部がなくなった。撤去に1億5500万元かかる。
単に馬鹿馬鹿しいニュースと言うにはあまりにも馬鹿馬鹿しい。習近平氏の思想教育の一環とは思われるが。そもそも何のためにこんなものが造られたか?
これがもし、毛沢東の銅像か何かだったら? 習さんも破壊しろとは言えないか。習さん自身の偶像なら? ソ連邦崩壊後の旧ソ連国では、多くのスターリンの偶像が破壊された。
関羽は歴史上の人物で単なる武将。政治家でも思想家でもない。しかし、道教では神格化されて崇拝の対象とはなっているようだ。共産主義思想も原点に返れば、偶像崇拝も個人崇拝も悪だ。習近平氏は、毛沢東も鄧小平の公平に国家の英雄にすると。
でも、やはりこの話はこれでは終わらない。
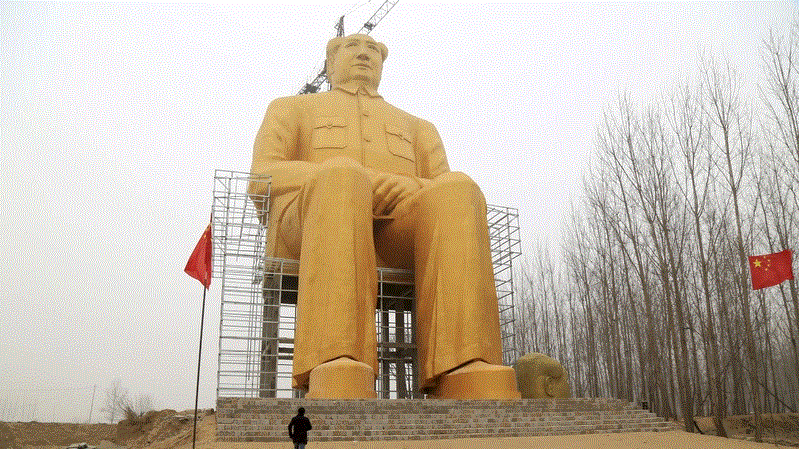
【河南省、巨大な毛沢東像建造と撤去――中国人民から見た毛沢東と政府の思惑】
Yahooニュース; 遠藤誉中国問題グローバル研究所所長、筑波大学名誉教授、理学博士、2016/1/11(月) 7:00
河南省農村の空き地に300万元を使って建てられた36.6メートルの毛沢東像が1月8日に取り壊された。庶民はなぜ毛沢東の巨像を建て、そして中国政府はなぜ取り壊しを命じたのか?人民と習近平政権にとっての毛沢東とは何か?
◆総工費300万元(約5400万円)かけて建てた毛沢東巨像
2016年1月4日、中国のネットユーザーがアップした情報に基づいて、翌5日に香港の鳳凰資訊が伝えた。河南省開封市通許県孫営郷朱氏崗村という片田舎の空き地に、中国建国の父である毛沢東の巨像が建てられたというのだ。その高さは36.6メートルで表面は金色に塗られている。村の数名の企業家と現地村民の有志たちが300万元を拠出して建造したという。
ここは荒地の非農耕地なので、村役場に届け出をせずに、2015年3月に着工し、年末にほぼ出来上がった。地元当局は登記や審査を経ていない「違法建造物」であるとして、1月8日に、いきなり取り壊しにかかってしまった。その取り壊し現場を報道した画像(同じく香港の鳳凰ウェブサイト)があるので、それをご覧いただきたい。こちらは金額的にはさほど馬鹿げているとは思えないが。中国共産党内でも毛沢東自体未だに国父の存在を保っているようだし。それをいきなり取り壊すというのも、ちょっと「あり得ない」動き方だ。
未登記であるなら罰金でも科して、登記再申請でもさせればいいではないかと思うが、そうしないところに、現在の中国の「毛沢東に対する微妙な思い」がある。県の文化局によれば、「朱氏崗村は観光地では片田舎なので、そのように地における彫像建築は、決して観光文化管理規定には触れず、したがって行政の文化部門が審査に当たる対象ではない」と責任の追及を逃れている。現地の園林部門はまた、「われわれは城鎮(都市と町)における彫像なら審査対象とするが、農村に関しては管轄外だから…」と、ここも責任逃れをしている。取り壊したのは、県の監察大隊であるという。
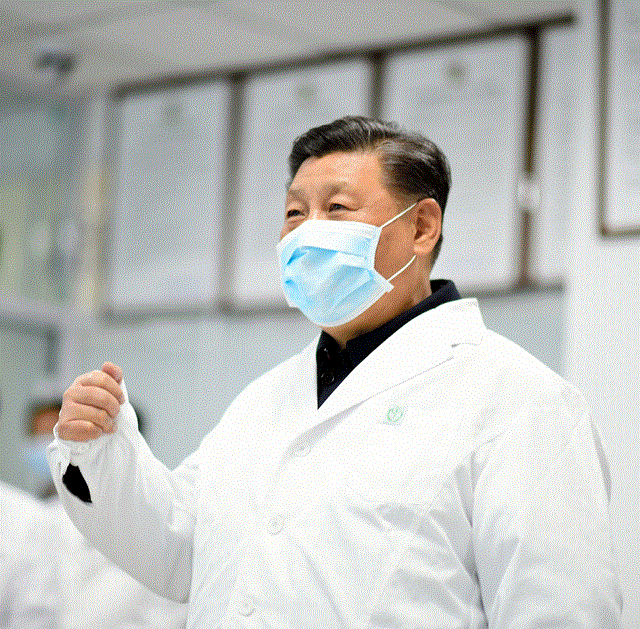
◆人民の中における「毛沢東」
毛沢東がどれほど多くの中国人民を殺戮したか、今さら言うまでもないだろう。中国人による推計によって、5千万人とも7千万人とも言われている。それも中華人民共和国(現在の中国)が建国されたあとの、「戦争のない時代」に殺した人民の数だけだから、すべて政治闘争あるいはイデオロギー闘争のためだったと言えよう。
「喉もと過ぎれば熱さ忘れる」ではないが、その毛沢東を中国人民が懐かしみ始めたのは、90年代末、あるいは2000年に入ったころのことだった。毛沢東が1976年に他界すると、1978年12月から改革開放が始まった。
**毛沢東の中国人民の殺戮は、朝鮮戦争の時が最大と言われている。勝ったとされる中国人民軍は国連軍の何倍もの死者を出している。でも、この戦いのおかげて毛沢東の党内での地位は一機に向上したのだから歴史とは皮肉なものだ。
それまで金儲けをする人は反革命的大罪人として投獄されていたのに、トウ小平は「先に富める者から富め」という先富論を唱えて金儲けを奨励した。自由競争が許される中で一党支配体制だけは崩さなかったので、当然のことながら貧富の格差は拡大し、「苦しむ貧しい人民の味方」であったはずの中国共産党の幹部が巨万の富を謳歌する極少数の利権集団と化し、「人民中国」は消えた。
そのため、富から取り残された多くの人民は「毛沢東時代は貧乏だったけど、平等で良かった」と懐かしむようになり、毛沢東の小さな銅像をお守り代わりにしてネックレスにしたり、車にぶら下げたりすることがはやり始めた。
もっとも顕著な動きは、健康のために朝の公園で太極拳などをする高齢者たちが、あちこちに輪を作って革命歌を歌うようになったことだ。革命は「紅い」ので、これを「紅歌」と称する。
「唱紅歌(革命歌を歌う)」現象は、全国的に広まっていき、やがて社会現象となり始めた。筆者はこれを「紅いノスタルジー」と命名し、その行動を追いかけてきた。2007年に薄熙来(はく・きらい)が、チャイナ・ナイン(中共中央政治局常務委員9名)に入れず、重慶市書記になると、この「唱紅歌」現象に目をつけ、自らを「毛沢東の再来」として毛沢東回帰により人民を惹きつけた。
人民に対する人気を見せ付けて、「これでも、この俺様をチャイナ・ナインに入れないつもりか?」とチャイナ・ナインを威嚇し、個人崇拝をあおって結局逮捕されてしまった薄熙来。人民のボトムアップの「紅いノスタルジー」を自らの野心に利用した失敗例だった。
◆薄熙来を真似て(?)「毛沢東回帰」をしている習近平国家主席
個人崇拝をあおった薄熙来は、「文化大革命の再来を招く危険人物」として、今は牢獄で終身刑の身を噛みしめている。だというのに、いま習近平は薄熙来の真似をしているのではないかと噂されている。薄熙来よりも「毛沢東回帰」が激しく、まるで自分は「第二の毛沢東だ」という言動ばかりしている。
そもそも「虎もハエも同時にたたく」という反腐敗運動は、毛沢東の「大虎も子虎も同時にたたく」の言い換えであり、風紀を正すための「四風運動」は、毛沢東が延安時代に行った「整風運動」の模倣である。「整風運動」は「形式主義、官僚主義、享楽主義」を取り締まって風紀を正そうという運動で、「四風運動」とは「形式主義、官僚主義、享楽主義、ぜいたく主義」を取り締まって党内の風紀を正そうとする運動である。毛沢東の「整風」に「ぜいたく禁止令」を付け加えただけで、すべて毛沢東の物真似だ。)。
**でも、本当に毛沢東の物真似だろうか? 日本の徳川時代の3大改革だって、こんなスローガンではなかったか? いまだ、習近平さんが毛沢東思想の後継者がどうかは分からない。
「虎の威を借る狐」よろしく、まさに毛沢東の権威に頼って、何とか自分の「紅い皇帝」としての権威を保とうとしているとしか思えない。こうしてボトムアップだったはずの庶民の「紅いノスタルジー」は政治利用されて、上から「大衆路線教育」という形で、毛沢東時代の思想教育が施されるようになった。
これまで貧富の格差に対する不満から抱いていた「毛沢東への紅いノスタルジー」は、一種の「反政府的ベクトル」を持っていた。ところが、それが政府によって許可されたとなると、金持ち連が「自分がいかに政府を肯定しているか」を見せようとして、中国全土に「毛沢東像建造熱」を招き始めたという側面も出てきた。2015年12月26日、山東省寧鄒(すう)城市后八里村に12.26メートルの毛沢東像が建てられ開幕式も盛大に行われた。建てるための費用は后八里村が集めた資金だという。12.26メートルという高さは、毛沢東の誕生日である「12月26日」にちなんだものだ。
河南省の毛沢東像は取り壊されたのに、なぜ山東省の銅像は取り壊されていないのだろうか?もちろん中国政府系列のメディアは、「河南省の毛沢東像は建造のための登記審査を受けていなかったから」というものだが、どうもその辺はしっくり来ない。
本当の理由は、「習近平の権威よりも遥かに上に行き、毛沢東への個人崇拝を過度に強調しすぎるのは好ましくない」ということではないかと、筆者には思えるのである。
さもなかったら、何も壊す必要はなく、再登記させて審査を受ければいいだけのことである。繰り返しになるが、罰金でも科せば済んだのではないだろうか。この辺のさじ加減は微妙だ。
◆宗教になりつつある共産主義思想
中国の履歴書には「信仰」という項目があり、そこに「共産主義」と書くのが模範解答だ。どんなに「先に富む者が先に富んでも」、現在の中国に存在するのはチャイナ・マネーに対する熱情であって、本当の心の支えになるものは存在しない。モラルなど、どこかに行ってしまった。「共産主義」=「信仰」は頂けないね。「宗教は阿片だ」ではなかったのか。
**でも、ソ連邦が崩壊した後のロシアではロシア正教の会員が増加している。やはり宗教は必要なのかな。鄧小平下の自由化の進んだ中国でも宗教は自由になってきたようだが。「共産主義」と書くのが模範解答かどうかは分からないけど、空欄では無神論者と疑われてしまうから仕方がないのかも。
さらに、自由と民主が許されない中国においては、心の支えになるものとして、キリスト教徒か仏教といった本当の宗教が水面下で蔓延しつつあるが、それは共産党政権の好むところではない。彼らは共産主義をこそ「信仰の核心」にしてほしいのだ。そのために「毛沢東を信仰する」ことは歓迎的だ。しかし、それは「習近平への個人崇拝」を超えてはならないのである。そしてそれはまた、虐げられた貧困層が、反政府的な象徴として「毛沢東」を位置づけてもならないのである。「毛沢東」をどのように位置づけるかは、中国にとって実に微妙なコントロールを要する対象である。それが今回の河南省の毛沢東の取り壊しにあると考えるべきだろう。
**心の支えと言う意味では、日本の天皇制は見直されるべきだね。君臨すれども統治せず。日本は毛沢東も習近平も全く必要が無い。今のロシアも中国も確かに権力の一極集中が進んでいるようだが、これまでの動乱の歴史を見れば、ある程度の国民の信頼の上に成り立ってもいることも事実だ。強権的な思想教育が必要な程、国民の不満が溜まっているとは見えない。欧米諸国の偏見的な見方かもしれない。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
改正種苗法
改正種苗法
コロナ危機のどさくさに紛れて野党の反対を押し切り成立を見た改正種苗法だけど、今までどんな問題があり、この法律でどう変わるのか。農水省側の説明を聞いてみよう。
そもそも種苗法とは
種苗法は、品種の育成者の権利を守るための法律だ。育成者が持つ「育成者権」の保護を定めていて、1998年の全面改正以降、育成者権を強化する改正を重ねてきた。育成者権は、農業版の著作権のようなものだ。この育成者権を得るために、育成者は農林水産省に品種登録の出願をする。
**そもそも農産物は、いいものはどんどん世界的に広まることで人類の幸福に貢献して来た。小麦、米、トウモロコシ、トマト、etc.、etc.
「育成者権」とは耳慣れない言葉だが、一体どういう内容を含むのだろか? 育成するものとは農民以外にはいないはずだけど。
審査を経て登録された品種は「登録品種」になる。育成者はその種苗や収穫物、一部の加工品を利用する権利を専有する。育成者以外の人が登録品種を業として、つまり事業として使うには、育成者の許諾が必要だ。このため、販売される登録品種の種苗には通常、育成者への許諾料(ロイヤルティー)が含まれている。
**そもそも何のために審査をして登録までする必要があるのか。どんなカボチャでもカボチャはカボチャ。違いは、ほんのわずかのゲノムの塩基配列の違いで偶然できたものだ。そもそもこの偶然の出来事を人為的に加速して作った品種が特許として認められるというのも非常に不合理の考えだね。農民の立場からすれば、いい品種が出来て収穫が増えたり品質が向上すればハッピーで、これを多数の人が喜んで使ってくれればなおハッピーではないか。
品種の登録期間、つまり育成者権の存続する期間は、最長で25年または30年(果樹や鑑賞樹といった木本の植物のみ30年)だ。この期間が過ぎたり、期間内でも育成者が毎年払う登録料を払わなかったりすると、登録が取り消される。
**こんな登録を農家や農協が喜んでするのだろうか。単に大手種苗会社を丸儲けさせるだけの仕組みが「育成者権」に含まれているらしい。でも、大手種苗会社は単に種を改良するだけで作物の育成は全くしない。彼らに「育成者権」なんて初めからあるはずもない。では、法の趣旨は?
登録品種には、ゆめぴりか、シャインマスカット、あまおうなどがある。登録品種以外のそもそも登録されていない品種(伝統的に栽培されてきた品種や、あきたこまちなど)や登録が取り消されたもの(はえぬき、とちおとめなど)は「一般品種」と呼ばれる。種苗法が対象とするのは登録品種のみで、かつ家庭菜園のような自家消費が目的の場合は対象にならない。
**だからどうしたというんだ。消費者側からは何の関係も無いこと。上記の登録3品種はそれぞれ、米、葡萄、イチゴだったね。確かに美味しいとの評判はあるけど、別に特別という訳でもない。
なぜ改正するのか。今までの法律の何か問題があったのか?
国会で審議中の改正案で、何が変わるのか。主な改正は下の二つだ。
①農家による登録品種の「自家増殖」に育成者の許諾が必要になる
②育成者は登録品種を許諾なく輸出できる国や栽培地域を指定できる
ほかにも、品種登録の出願料や、登録の維持に必要な登録料を引き下げるといった細かな改正はあるけれども、議論が集中しているのはこの二つだ。
**やはり、ここでは「育成者」という用語が、この法律では特別な意味で使われている。一般の庶民の理解では、「育成者」とはあくまでも農民であって、決して種苗業者にはならない。確かに種苗の販売までには実証実験等の育成実験は行われるだろうが。
自家増殖とは、種を取る自家採種や、接ぎ木などにより、収穫物から次の世代を生み出すことをいう。ジャガイモやサツマイモといったイモ類は、収穫して種イモに回すことができるし、バジルや一部の観葉植物は、枝を切ってさしておけば立派に成長する。これまで農家による自家増殖は自由だったけれども、改正により、育成者の許諾を得る許諾制に変えようとしているのだ。そのため、「農家の権利を制限するのはおかしい」という反対の声が上がっている。
なぜ許諾制に変えるのか。品種の海外への流出が、主な原因だ。育種家は、国や県といった公共団体、民間企業、個人の三つに大きく分けられる。中でも「地方公共団体などにとって、都道府県や国の境界を越えた流出が、一番大きな悩みになっている」(農林水産省知的財産課種苗室)のだ。
多くの都道府県は、産地振興のために魅力的な品種を生み出そうと競い合ってきた。ところが、県内に栽培を限定したはずの品種が県外に広がったり、甚だしくは海外で産地化されたりしている。特に果樹とイチゴで海外への流出が多い。一般社団法人や研究機関などで構成する「植物品種等海外流出防止対策コンソーシアム」は9月、中国と韓国のWebサイトで、日本で開発された品種らしい名前で売られているものが36品種分見つかったと発表した。
**全く結構な話ではないか。日本の農業技術が海外でも認められた。開発した新品種が海外にまで普及しているとしたら開発研究者に取ってこれほど仕事冥利はない。原産地の認定さえもらえればとてもハッピーなことだ。
海外流出への対策として、海外での品種登録が進められている。品種の登録は国ごとに行うためで、農水省は登録推進の予算をつけている。花形の品種をデビューさせるに当たって、海外での登録を進める都道府県も増えてきた。とはいえ、海外での登録や権利侵害が発生した際の対応には労力もお金もかかる。そこで、そもそもの日本からの流出を阻む手段として改正に至ったというのが、種苗室の説明だ。育成者による輸出先や栽培地域の限定に加え、農家の自家増殖を許諾制にし、育成者がどこでどんな増殖が行われるか把握することで、流出の監視を強めようというのだ。
**海外流出への対策なんて全く無意味だ。そもそも相手国だって流入を止めようとしても不可能な話だ。農水省は登録推進の予算をつけている。農水省はこんな愚劣な施策に国費を浪費して事業をしている。何を考えているのかね。こんなこと全国の農民も消費者も納得できるはずが無い。
反対が多い理由と種苗をめぐる知財の考え方
種苗法の改正は実務的で地味なものに思われるのだけれども、反対の意見が特にネット上で盛り上がっている。一番の理由は、これまで自由にできた自家増殖が許諾制になるからだ。「自家増殖の一律禁止だ」とする主張もあるが、育成者の許諾を得ればいいので、正しくない。許諾料が生じることで、農家の経営を圧迫するのではないかという不安が、反対につながっているようだ。
**確かに育成者=種苗業者とすれば、著しく農民の権利が阻害される。なんで自分の畑に種を撒くのに大手種苗会社の許諾が必要なのか。あまりにも理不尽だ。まして許諾料何てとんでもない話だね。
ただし、農水省によると流通する種苗の9割は一般品種で、改正の影響を受けない。作物によっては、登録品種の割合が高いものもあるけれども、影響は限定的だと思われる。一般的に生産費に占める種苗費の割合は数パーセントのはずで、種苗費に占める許諾料の割合はそのまた数パーセントだろう。許諾料が増えて経営が立ち行かなくなるという事態は、考えにくい。
**だったら、こんな法律始めから必要ない。将来遺伝子改良種子特許化を狙った米国の陰謀であることが丸見えだね。
登録品種の割合が高い作物の一つが、サトウキビだ。沖縄県を例にとると、栽培されているほとんどが、農水省系の研究機関である農研機構と県が開発した登録品種だ。かつ、自家増殖が欠かせないので、改正案が通れば、許諾を得る手続きが必要になる。そのため、これまで以上に許諾料が発生して大変になるという主張もある。ただ、開発元は公的機関で、営利よりも産地の振興を目的にする。許諾料の設定や許諾を得る手続きは、生産者の負担にならない形になるだろう。
**許諾料の設定や許諾を得る手続き自体が従来の方の観点から見て違法だ。「育成者」=農民であって、間違えても種苗の研究機関ではない。種苗の研究機関は、農民や消費者の為に開発を行っているのあって、米大手薬剤会社のように特許料収入だけを目的とした営利集団であってはならないはずだ。
ほかに影響が大きいと思われるのは、果樹だ。自家増殖する農家もいるので、改正案が通れば許諾料が増える農家も出てくるだろう。ただ、果樹は先に紹介したように国外や地域外への流出が最も深刻だ。許諾の手続きや許諾料が増えても、育成者権が守られ、流出に歯止めが掛かれば、最終的に農家の利益になると種苗室は考えている。
**そもそも流出が何故問題なのかの分析が無い。米大陸原産のトマトもジャガイモも世界中で利用され食料の確保の大いに貢献している。
農業分野では、知的財産権があまり重視されてこなかったように感じる。一つの品種を生み出すには、ふつう10年はかかる。にもかかわらず、育成者が得られるインセンティブ(見返り)は、あまりに少なくなかったか。
**農業分野では、知的財産権があまり重視されてこなかったはある意味当然で全く必要が無かったからだ。知的財産権は、産業革命以降欧米で培われて来た思想。資本主義の発達とともにやみくもに拡大解釈されるように。脱工業化時代には抜本的に見直される必要がありそうだね。
シャインマスカットを例にすると、開発には13人の研究者が関わり、18年を要した。親に当たる系統の開発から数えると、実に30年以上かかっている。種苗室によると、成木になれば1本あたり年間20万円近い売り上げを生むのに対し、苗1本当たりの許諾料は1回きり60円程度に過ぎない。
**開発には多大な補助金と給料も支払われている。開発終了後まで末永く利益をむしり取ろうとする魂胆がやましいね。
農家にとって、食味が良い、病気に強いといった優れた品種がもたらす経営上のメリットは大きい。メディアやネットに書かれるほど、許諾料を払いたくない農家は果たして多いのか。筆者は疑問を感じている。
**農家だけでなく、消費者の国民もこんな不法な搾取を許してはならないと思っているでしょう。優れた品種かどうかは市場が判定すべきことで審査を官がやってはならないことだ。知的財産権を過度に適用し独占企業の横暴を許せば自由競争を阻害し健全な開発を著しく遅らせる要因となることも銘記しなくては。
【米国の種苗会社】
モンサイトという、巨大薬剤会社があった。今も形を変えて残っているだろう。遺伝子改良型の種子を販売して巨利を上げている。小麦やトウモロコシは、風媒花と言って風邪で花粉が運ばれる。だから近くの農家にはどうしても遺伝子改良種子に汚染されてしまう。
モンサイト社の会社の社員が各農家の作物のサンプルをこっそり盗み出し、ゲノム解析を行い、農家の作物に改良種子の遺伝子が混入していることを突き止める。
モンサイト社は、周辺の農家に対して、特許侵害の申し出をし、特許の使用料を請求したそうだ。何と米国ではモンサイト社が裁判で勝利したとか?
遺伝子改良種子の特許化にはこのように多数の問題点がある。遺伝子改良作物を食べても多分安全だろう。食べてもヒトの消化器の中ではアミノ酸に分解されてしまうから。ただ、農薬や病害に強い遺伝子は、生態系に対して予測できない環境破壊をもたらす。
多くの人達が遺伝子改良食品を口にしないのは、健康問題からではなく環境保護の観点からだ。農産物に対して知的所有権を振り回すのは大変危険なことと認識した方が良い。
知財重視の考え方は農業でも広がりつつあり、和牛をめぐって、種苗法改正とよく似た法改正と新法の制定があった。和牛の遺伝資源を知的財産とみなし、不正な持ち出しを規制するものだ。和牛の遺伝資源が海外に流出するのを食い止めようと、2020年3月、通常国会に提案され、4月に成立、10月に施行された(「家畜遺伝資源不正競争防止法」と「改正家畜改良増殖法」)。
**知財重視の考え方は農業でも広がりつつあるとは思えない。何故和牛の遺伝資源の海外流出を止めたいのかその根拠がはっきりしない。和牛の遺伝資源がどう転べば知的財産となり得るのかね。全く牛の勝手でしょう。進化系統学的には和牛のルーツを探ることは研究テーマとしては面白い。
実は種苗法改正案も同じ3月に国会に提出されている。審議が先だった和牛関連法案はすんなり通った一方、種苗法改正案は審議の順番が遅かったのに加え、反対論が盛り上がり、かつ他の法案の影響で与党への風当たりが厳しくなって、最終的には時間切れとなり、審議が秋の臨時国会に持ち越された。
自家増殖が許諾制になるということは、農家がこれまで認められてきた権利を規制するもので、育成者権と農家の権利の保護が相反する部分は確かにある。育成者権と農家の自家増殖の権利を、一方が勝てば他方が負けるゼロサム・ゲームと捉えるからこそ、反対論が盛り上がるのだろう。
しかし、長い目で見れば、育成者へのインセンティブが高まり、優れた品種の開発が活性化するほど、農家は恩恵を受ける。種苗法改正の議論をきっかけに、品種登録の件数が右肩下がりを続ける現状を直視し、知財で日本農業を活性化することを考える方が、建設的ではないだろうか。
**種苗業者を利するだけの法案を考えているのが今の農水省か。同じ農学部出身の人間として情けないね。昔、農業経済の教授が言っていた言葉を思い出す。「昔の農家は肥料としての人糞の良し悪しをなめて確かめた。」昔の農林省の役人さん達は一にも二にも農民の為しか考えていなかった。農水省役人さんは育成者権なんていう妙な権利を振り回す前に、農業の現場での実習を必須事項とすべきかもね。
☆注)
1.「あまおう」は商標で「とちおとめ」は品種名だと。農業分野で商標登録する場合は、品種登録についても理解しておく必要がある。品種登録した名称は商標登録できないという思わぬ落とし穴があり 、品種登録と商標登録の仕方で、ブランド展開の方向性も変わってくるようです。品種登録と商標登録の関係について、まあ一般の消費者にはどちらでもいいことだけど。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
戦国策
元前漢の学者が紀前1世紀にまとめた「戦国策(せんごくさく)」はことわざの宝庫だといわれる。『戦国策』(せんごくさく)は、戦国時代の遊説の士の言説、国策、献策、その他の逸話を国別に分類し、編集した書物(全33篇)。前漢の劉向の編。「戦国時代」という語はこの書に由来するとのこと。
**【戦国時代】
戦国時代 (中国)の時代区分。下限を秦の天下統一の年(BC・222)とすることは一致している。上限を趙・魏・韓の三国が晋を三分した年(BC・453)や同三国が周の威列王(いれつおう)に依って諸侯と認定された年(BC・403)とする説等。だから、戦国時代とは、一般に春秋時代(BC・722〜481)に接続する周王朝末期の二百数十年とされる。また、戦国時代という呼称は、春秋時代が、孔子の著したと言われる史書の名『春秋』、 に因んで附けられたように、「戦国策」という書名に拠って附けられたことも注目すべき点。二つ合わせて春秋戦国時代としておけばいいか。
春秋時代を経て戦国時代に入ると、周の封建制度が瓦解し、小国は大国に吸収、併呑され各国が領土の獲得に狂奔し、いたるところで侵略戦争が行われていた。しかし、各国は武力での侵略を極力回避した。なぜなら、武力による侵略では勝敗にかかわらず国力の疲労をもたらし、他国に乗ずる隙を与えるからで、西周、宋、衛などの小国はもとより、秦、斉、楚などの大国も、極力、平和的外交手段により打開しようとした。その一方で様々な思想が生まれ、法家の商鞅や儒家の孔子などの学者、思想家や、また諸国を遊説し外交を論じる縦横家(または遊説家)などに活躍の場を与えた。『戦国策』中で活躍しているのは、概ねこの縦横家(説客)である。中国の戦国時代は決して弱肉強食の時代ではなかったようだ。寧ろ諸子百家等の多様な思想がうまれる活気に満ちた中国史上最も輝いていた時代であった可能性も高い。
前漢の学者が紀元前1世紀にまとめた「戦国策(せんごくさく)」はことわざの宝庫だ。「蛇足(だそく)」「百発百中(ひゃっぱつひゃくちゅう)」「禍(わざわい)を転じて福(ふく)となす」。多くは中国古代の戦国時代に、比喩を交えて外交策などを説いた弁舌家の言葉が元になっている。
「漁夫(ぎょふ)の利」もその一つ。似た成句に「山に座して虎の闘(たたか)いを観(み)る」がある。2頭の争いを座視していれば双方が傷つき、漁夫の利を得られる。虎を米中に見立てて、このことわざを使ったのがプーチン露大統領だった。
冷戦時代にニクソン米大統領が進めた「三角外交」にも通じる。中ソ対立の激化を知った米政府はソ連とのデタント(緊張緩和)を進める一方、中国との歴史的な和解に動いた。この結果、米国は中ソ双方に対して有利な立場を築いた。
中国の兵法書「孫子」だって負けてはいない。熱い戦争は避けるの最良の戦略。「戦わずして勝つ。」長期戦に持ち込み相手方の自滅を誘うのは最良の策だ。現代の国際政治にも十分に応用でき実際に機能している。ただ、権力者たちの思惑通りにはことは運ばないけど。
【山に座して虎の闘(たたか)いを観(み)る】
ジュネーブでの米露首脳会談では、中国をにらみ、対露関係を安定化させたいバイデン米大統領の思惑が浮き彫りになった。ロシアによるクリミア編入、米企業へのサイバー攻撃、反体制派の弾圧と対立点は多いが、批判より対話を重視する姿勢が目立った。
かといってプーチン氏が高姿勢だったわけでもない。かつてメルケル独首相を4時間、安倍晋三前首相を3時間近く待たせた「遅刻魔」がバイデン氏より先に会場入りした。やはり対米関係を重視しているのだ。さて中国がどう動くか。中露の蜜月ぶりを示したいのではないか。3大国の関係の行方は日本にも大きな影響を及ぼす。「戦国策」由来の言葉でいえば、「長久之計(ちょうきゅうのけい)」(長期戦略)も必要になる。
新型コロナに関しても中国の対応は、面白い。「山に座して虎の闘(たたか)いを観(み)る」。欧米諸国では、ゼロコロナを目指すハト派?と経済優先対策解除のタカ派?とが水面下で大激闘している。WHOを利用して過激な感染対策、ワクチン接種を推奨させ、自らも必至で対策している振りを続けている。ゼロコロナを目指して限りなき戦いを続けて行けばいずれ欧米社会は社会も経済も崩壊する。中国は今は当然ハト派支援だ。
阿片戦争以来の西欧諸国によって植民地化された恨みは当然忘れていない。イスラム諸国も同じだろう、十字軍以来不条理な攻撃を受け続け植民地化された恨みは今も残っている。「臥薪嘗胆」。毛沢東主義も鄧小平主義も究極の目的は同じだ。西欧諸国が没落して米国の覇権が亡くなれば、中国としては覇権など欲しくない。世界は多極化して平和になる。多極化した世界は世界史上最も輝く時代となるかもしれない。
【禍(わざわい)を転じて福(ふく)となす】
武漢市で発生した新型コロナ、これは明かに大災難だ。亡くなった方には心からご冥福をお祈り申し上げます。だから、米国の主張するように中国政府が意図的に世界にばら撒いたの説には簡単には同意できない。中国側から見れば欧米が武漢市にばら撒いた可能性の方が高いと思っているはずだ。
でも、これが欧米に拡散することで何倍にも仕返しが出来たことになった。
新型コロナの恐怖を煽ることで、感染の恐怖は雪だるまの如くふくらんで留まるところはない。米国の一極覇権の時代は終わった。民主主義の理念は大崩壊し、米国民はマスクして毎年ワクチン打って終わりなきコロナとの戦いを続けて自滅への道をまっしぐら。資本主義のグローバル経済は中国がそっくり頂きだ。中国は欧米のコロナ対策に応援の旗を振り続けていれば良い。感染対策甘すぎる。中国を見習え!
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
上有政策、下有対策
中国には「上有政策、下有対策」という有名な言葉がある(2010年11月01日 アジアンインサイト・範 健美氏)。確かにかなり昔にこのことわざ聞いたことがある。範氏は最近の中国の傾向を指して語っているようであるが、これは中国独特の物でもなく、世界中に成り立つ真理と言うべきものかもしれない。
上有政策、下有対策(Shàng yǒu zhèngcè, xià yǒu duìcè)
上に政策あり、下に対策あり。→和文
There are policies at the top and countermeasures at the bottom. →英語
상단에 정책이 있고 하단에 대응책이 있습니다.→韓国語
Вверху есть правила, а внизу - контрмеры.→ロシア語
**вверуху=adv. 上の方、внизу=adv. 下の方、ともに語尾にアクセント
**правило=n. 規則、контрмера=n. 対策
元々は国に強権的な政策があれば、国の下にいる国民にはその政策に対応する策があるという意味だが、現在は「決定事項について人々が抜け道を考え出す」という意味でも使われる。
でも、いい言葉だね。例え強権的な愚策が強硬されても、現場がそれを有名無実の骨抜きに出来る知恵のある社会は強靭で持続可能性がある。いずれ政策の方が折れるしかなくなる。これも一種の民主主義の形ともいえるかも。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
インスタレーション
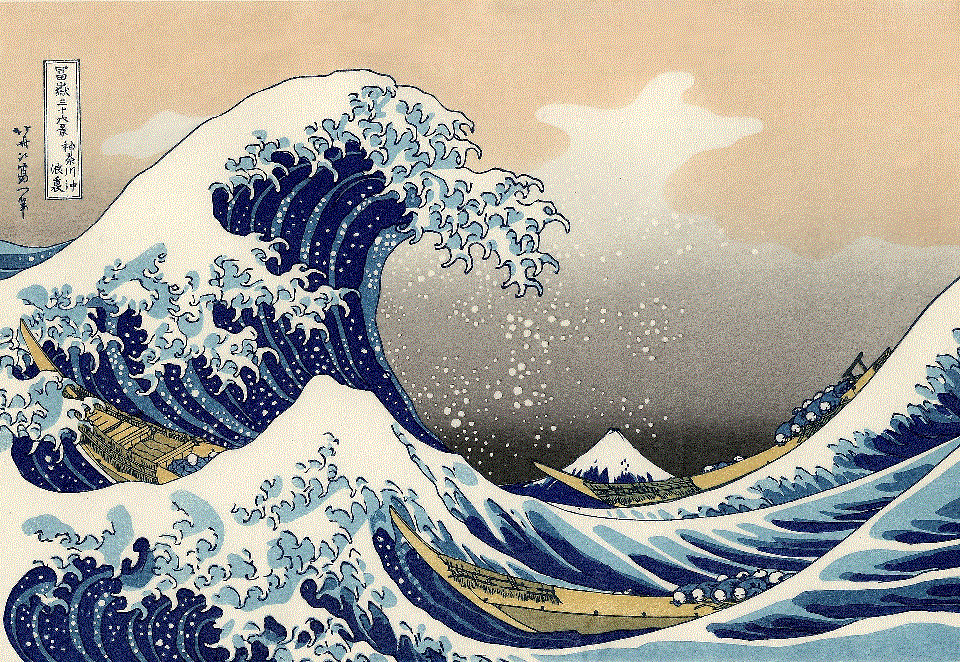 インスタレーション
インスタレーション
インスタレーション (Installation art) とは、1970年代以降一般化した、絵画・彫刻・映像・写真などと並ぶ現代美術における表現手法・ジャンルの一つ。ある特定の室内や屋外などにオブジェや装置を置いて、作家の意向に沿って空間を構成し変化・異化させ、場所や空間全体を作品として体験させる芸術。空間全体が作品であるため、鑑賞者は一点一点の作品を「鑑賞」するというより、作品に全身を囲まれて空間全体を「体験」することになる。鑑賞者がその空間を体験(見たり、聞いたり、感じたり、考えたり)する方法をどのように変化させるかを要点とする芸術手法である。
ビデオ映像を上映して空間を構成することもあれば(ビデオ・インスタレーション)、音響などを用いて空間を構成する(サウンド・インスタレーション)こともある。
最初はおもに彫刻作品の展示方法の工夫や、ランドアート・環境芸術の制作、パフォーマンスアートの演出に対する試行錯誤から誕生したが、次第に彫刻などの枠組みから離れ、独自の傾向を見せるようになったため、独立した表現手法として扱われるようになった。
インスタレーションの意味
インスタレーションとは、元の意味は「設置」「取付」「インストールする」という意味。古くから美術館の壁面などへの作品展示も「インスタレーション (installation) 」と呼ばれていたが、壁や床一面に絵画や彫刻を飾り付けていた時代はインスタレーション(設置)の方法はあまり問われなかった。
展示方法の工夫を通して鑑賞者への見せ方を意識することはロダンら一部の彫刻家が先駆的に取り組んだが、やがて展示方法によって空間自体を作品化することが美術の一手法として認識されはじめ、彫刻や絵画などから独立した。
中国や韓国では「装置芸術」「設置芸術」などと呼ばれることもあるが、日本では一般に「インスタレーション」の名称が用いられる。
インスタレーションを制作するにあたり、映像、彫刻、絵画、日常的な既製品(レディメイド)や廃物、音響、スライドショー、パフォーマンスアート、コンピュータなど、どのようなメディアを使用するか、また美術館や画廊などのギャラリースペース、住宅など私的空間、広場・ビルディングなどの公的空間、人のいない自然の中などどのような場所を用いるか、などは特に制約はない (もちろん、建築基準法などに違反した場合は刑罰の対象となる)。
古典美術はどちらか言えば、自然物(風景、人物、建築物)をいかに忠実に作品に再現するがの技法が問われていたと思う。我々はその路線に沿って作品を楽しみ鑑賞することが出来る。ところが、写真やCG三次元画像等の技術の進歩によって、アーティスト達の出番が失われて来た。作者達の磨き上げた他の追従を許さない高度な技巧をどのような形で発揮すれば良いのか。
アイスランドの氷山のカケラを都市に並べ、溶けるのに任せて人々にそれを触らせて、地球温暖化の警鐘を鳴らす? これがアートの役割ということだろうか。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
今年のノーベル賞
 ノーベル物理学賞にプリンストン大学上級研究員の真鍋淑郎さんが選ばれた。温暖化問題のCO2犯人説を正当化するための政治的なものでは断じてなさそうだ。スーパーコンピュータを回し、可能な限りのデータを取り扱う超巨大シミュレーション技術と言えるかも。大変お金のかかる研究であったことも本人が認めている。
ノーベル物理学賞にプリンストン大学上級研究員の真鍋淑郎さんが選ばれた。温暖化問題のCO2犯人説を正当化するための政治的なものでは断じてなさそうだ。スーパーコンピュータを回し、可能な限りのデータを取り扱う超巨大シミュレーション技術と言えるかも。大変お金のかかる研究であったことも本人が認めている。
そもそも気象現象は典型的な複雑系=カオスの世界で、非線形問題、ちょっとデータを変えるだけで全く異なった結果となってしまう。今でも気候の予測は難しいとご本人も明言。まして政治的な判断は「もっとも難しい判断ですね。」
近年、物理学賞は、ヒッグス粒子だの、ニュートリノだのと人間生活からかなり離れた分野に集中していた。しかし、先端の物理研究は、理論だけでなく何らかの実験的の裏付けが必要だ。となると、今回の受賞はどのような実験的な裏付けがあったのだろうか。どのような解釈が試みられていたのかは今後の楽しみかも。
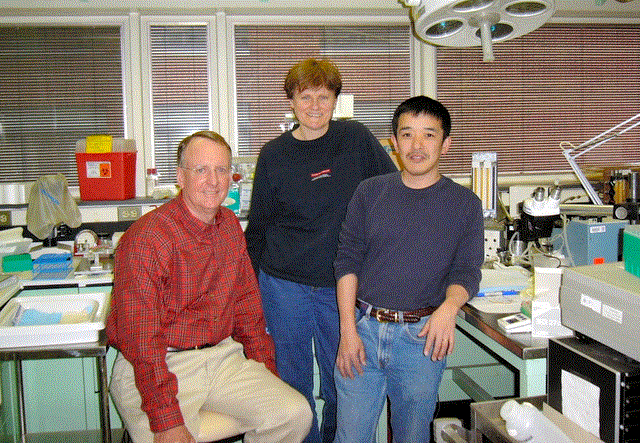 いっぽう、ノーベル医学・生理学賞の最有力候補と見なされていたカタリン・カリコ博士は今回は受賞に至らなかった。遺伝物質「mRNA」を活用した全く新しいタイプのワクチンの発明者ということだったが。核遺伝子(DNA)→mRNA→tRNA→リボソーム?→タンパク質生産という、生命現象において、外部からのゲノムを改造mRNAを注射することで、任意のタンパク質を製造させることが出来ると言う画期的方法の発明者。これによってファイザー社やモデルナ社等がmRNAを開発できたと言うものだ。実際これらのワクチンは緊急事態の大義名分で臨床的実験を省略して使い回されているので、ノーベル賞を与えて正当化したかったという政治的意図は感じられる。勿論研究者自身はそんな意図は無いでしょうが。ただワクチンが授賞理由なら、開発ワクチンが本当に人々を感染の恐怖から解放できる(マスクが不要になる)かどうかを見てからでも遅くはないでしょうね。
いっぽう、ノーベル医学・生理学賞の最有力候補と見なされていたカタリン・カリコ博士は今回は受賞に至らなかった。遺伝物質「mRNA」を活用した全く新しいタイプのワクチンの発明者ということだったが。核遺伝子(DNA)→mRNA→tRNA→リボソーム?→タンパク質生産という、生命現象において、外部からのゲノムを改造mRNAを注射することで、任意のタンパク質を製造させることが出来ると言う画期的方法の発明者。これによってファイザー社やモデルナ社等がmRNAを開発できたと言うものだ。実際これらのワクチンは緊急事態の大義名分で臨床的実験を省略して使い回されているので、ノーベル賞を与えて正当化したかったという政治的意図は感じられる。勿論研究者自身はそんな意図は無いでしょうが。ただワクチンが授賞理由なら、開発ワクチンが本当に人々を感染の恐怖から解放できる(マスクが不要になる)かどうかを見てからでも遅くはないでしょうね。
研究としての意義は、生命の細胞が自己と非自己をどのように区別するかの解明のための極めて基礎的で重要な研究であることは間違いないはずである。
で、実際は?
 10月4日、スウェーデンのカロリンスカ研究所は、2021年のノーベル生理学・医学賞を、カリフォルニア大学サンフランシスコ校のデビッド・ジュリアス博士と、スクリップス研究所のアーデム・パタプティアン博士に授与すると発表した。受賞理由は、「温度と触覚の受容体の発見」だ。
10月4日、スウェーデンのカロリンスカ研究所は、2021年のノーベル生理学・医学賞を、カリフォルニア大学サンフランシスコ校のデビッド・ジュリアス博士と、スクリップス研究所のアーデム・パタプティアン博士に授与すると発表した。受賞理由は、「温度と触覚の受容体の発見」だ。
「受容体」とは、私たちが外界や体内で発生した「刺激」に反応するために細胞に備えられた「センサー」。私たちが日々の食事でさまざまな味を感じることができるのも、私たちの「舌」に、甘み、酸味、塩味、苦味、うま味といった5つの「味センサー」のおかげ。
これと同じように、「刺激」を認識できるのは、刺激に対応した「センサー」を持っているから。では、私たちが沸騰したやかんに触れたときに「熱い」と感じることができるのはなぜか。氷に触れたときに「冷たい」と感じることができるのはなぜなのか。さらに、なにかに接触したときに「触れた」、あるいは「痛い」と感じることができるのはなぜなのか。
2021年のノーベル生理・医学賞の受賞者として選ばれた科学者は、まさにそのセンサーの発見に大きな貢献をした2人だ。
生命の科学は、まだこんなことも解明されていいないのだ。物理学賞と比べてみると面白い。この後、文学賞など他の賞の発表が続く。楽しみですね。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
人口ピラミッド
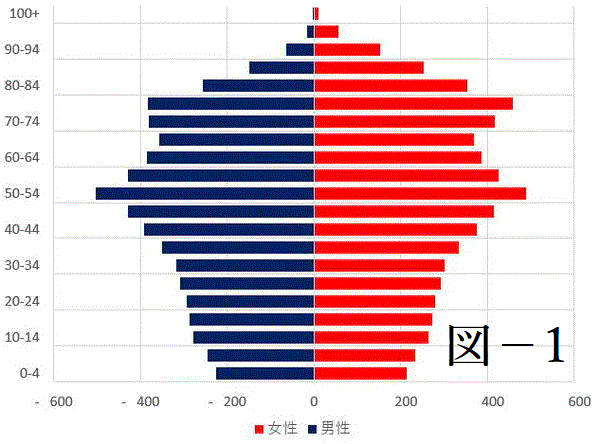 現在言われている少子高齢化。現状に至る過程は下記に良く説明されている。
現在言われている少子高齢化。現状に至る過程は下記に良く説明されている。
記
日本の人口ピラミッド(図1)には団塊世代と団塊ジュニアが存在。2025年になると団塊世代は全てが後期高齢者になり、日本は本格的な高齢化社会を迎える。就職氷河期を経験した団塊ジュニアも50代になり、老後はすぐそこという状態になる。日本の高齢化はのっぴきならない状況に追い込まれているとされている。
図1 日本の2025年の人口ピラミッド(縦軸:年齢、横軸:万人)データ:国連推計(中位)
でも、これが日本だけの問題化と言えばそうでもない。お隣の韓国も大変らしいし、中国だって他人ごとではなさそうだ。
お隣の韓国はどのような状況にあるのだろう。図2を見ると韓国の人口ピラミッドはお腹の膨れた中年男性のようになっている。韓国の人口ピラミッドの形状は朝鮮戦争(1950~1953)と漢江の奇跡(1960年代後半から1970年代)がもたらしたものだ。
日本では太平洋戦争で多くの命が奪われたけど、韓国では朝鮮戦争の動乱の中で多くの命が失われたようだ。
 図2 韓国の2025年の人口ピラミッド(縦軸:年齢、横軸:万人)データ:国連推計(低位)
図2 韓国の2025年の人口ピラミッド(縦軸:年齢、横軸:万人)データ:国連推計(低位)
韓国には現在75歳以上の老人が少ない。これは戦争で多くの人が死亡するとともに、その時期には出生率も低下していたからだ。しかし、戦争が終わると日本で団塊世代が生まれたように、韓国でも出生数が増加した。日本の団塊世代は1947年から1950年に集中するが、韓国では出生数の増加は80年代半ばまで続いた。それは朝鮮戦争の終了とともに、日本の明治時代がそうであったように「国家として独立した」という高揚した気分が続いたためと考えられる。韓国の団塊の世代は約30年間にわたって生まれ続けたようだ。
しかし、1980年代に入ると韓国は急速に少子化の時代を迎える。日本の70年代前半の合計特殊出生率(TFR)は2.13、80年代後半には1.65に低下。一方、韓国では同時期に4.0から1.57にまで急低下している。70年代の韓国は、人口爆発が続いているアフリカ諸国と同じような状態にあったが、それから約15年が経過した80年代後半になると、一転して少子化が問題となる社会になってしまった。
その後も韓国の出生率は低下し続けて、国連推計では2015~2020年のTFRは1.11と世界で最も低くなっている。新型コロナ感染症に襲われた2020年には0.84にまで落ち込み、同年の出生数は27.4万人でしかなかった。死亡者が30.5万人であったことから、韓国の人口は戦後初めて減少に転じた。2020年は我が国も新型コロナ感染症に襲われたがTFRは1.34に踏み留まり、韓国ほど落ち込むことはなかった。
現在、韓国の団塊世代のピークは50代になっている。韓国は日本と同様に賃金が年功により上昇する傾向が強いが、人口の多くが50代であることは、韓国の平均賃金が日本よりも高くなったことに一役買っている。
現在の韓国は、団塊世代のピークが50代にあることから、高齢化を実感することができないが、もう10年もすれば団塊世代が60代を迎えて高齢化問題は急速に深刻化する。
世界を俯瞰すると、少子高齢化が深刻な状況になっているのは、韓国、台湾、日本、香港、シンガポールなど中国周辺の国や地域である。
話はそれるが、中国政府は21世紀になってもTFRが1.6を保っていると発表している。だが周辺諸国の状況を考える時、実際のTFRはもっと低いと思われる。中国政府は農村部のTFRはいまだに高いと言っているが、そのような言い訳が通じるのは2000年頃までであろう。農村から都市へ若者が大量に流出したこの20年、中国のTFRは周辺諸国のように低下していたと思われる。中国の人口は14億人に達していないと言われる所以である。
ちなみに韓国には団塊ジュニアが存在しない。それは漢江の奇跡以降、韓国が非常に激しい競争社会、学歴偏重社会になったためと考えられる。日本では団塊世代が結婚適齢期に達した1970年代後半から1980年代前半にかけて1億総中流社会が出現したが、その微温的な雰囲気の中で団塊世代は子作りに励んだ。しかし韓国の団塊の世代は激しい競争社会の中で、子作りに励む余裕がなかったようだ。その結果として、韓国では若者世代の人口は一直線に減少している。
2025年の人口ピラミッドを示すにあたり、日本については中位推計(1.37)、韓国については低位推計(0.83)を用いた。これは、そのほうが実情に合うためである(**何故そうかの説明は無い)。2025年の0~4歳までの人口は日本が440万人、韓国は134万人になる。日本でも少子化は深刻な問題であるが、韓国の少子化はそれを大きく上回る。
ちなみに韓国の常備兵力は約50万人であるが、0~4歳の男子が69万人(女子が65万人)しかいないことを考えると、2040年頃には20~25歳の男子の7割以上を兵役につけない限り、常備兵力が維持できなくなる。だが、そんなことをすれば街から若者がいなってしまい、社会は活力を失う。
少子化の原因は複雑多岐にわたり、一言で言い表すことは不可能である。だが、世界の中でも特に中国の周辺の諸国で深刻な状態に陥っていることを踏まえると、儒教文化に根ざした男系を重んじる家族形態が大きな要因になっていると考えるのは自然であろう。少子化問題の解決は簡単にはいかない。日本と韓国は歴史認識問題ではなく、少子化問題を改善するために、その文化の根底を一緒に考えてもよい時期に来ているのではないだろうか。
手をこまねいていれば、そう遠くない未来である2040年には、両国ともに人口の4割が60歳以上という社会が出現する。両国の活力は衰え、極東は世界の中で取るに足らない存在になってしまう。歴史認識などで争っている場合ではない。そんな時代に突入している。
【出典;2021.11.21(日)川島 博之氏、JPpress】
*************************************************************
以上、何故少子高齢化が進んでいるかは理解できる。少子化の原因は複雑多岐とか言っているけど本文にきちんと理由も説明できている。しかも、東アジア諸国全体で生じている現象だ。あるいは将来は世界全体の傾向となるかもしれない。SDGs(持続可能な社会)の立場からはそうならざるを得ないかも。有限な地球環境において確かに今の人口は多すぎるのかも。つまり、少子化問題は改善すべきテーマではなく、どう共生していくべきかが問われているのでは。軍事力や経済力で覇権を争う時代は終わった。少子化問題を改善するために政府が何らかの施策をすべしとの意見にはあまり賛成できない。母親になりたくないという女性も増えている。高齢者の経験から発せられる知恵や文化、そのようなものを大切に育てて行く社会に変わらないといけないのでは。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
アーミッシュ
【アーミッシュ】
アーミッシュとは、アメリカ合衆国のペンシルベニア州や中西部、カナダのオンタリオ州などに居住するドイツ系移民の宗教集団である。 移民当時の生活様式を保持し、農耕や牧畜によって自給自足生活をしていることで知られる。原郷はスイス、アルザス、シュワーベンなど。人口は20万人以上いるとされている。
アーミッシュとメノナイトはルーテル派(ルター派)とツヴィングリ派の新教再組織から分かれてスイスのチューリッヒで生まれた一派で、宗教的迫害を受けたのちにドイツ南西部やフランスのアルザス地方に移住した。キリスト教と共同体に忠実である厳格な規則のある派で、創始者のメノ・シモンズの名前をとってメノナイトと呼ばれた。そのメノナイトの一員であったヤコブ・アマンは、教会の純粋さを保つために、ほかのグループから離れて暮らすことを考え、更に保守的な一派を作った。アーミッシュという呼称は彼の名に由来する。ライフスタイルは少し違うが、メノナイトもアーミッシュも基本的信条は同じで、ひとくくりにアーミッシュと呼ばれている。
規律
アーミッシュには「オルドゥヌング」という戒律があり、原則として快楽を感じることは禁止される。なお、オルドゥヌングは各地のコミュニティーごとに合議によって定められるので各地で差異がある。 以下のような規則を破った場合、懺悔や奉仕活動の対象となる。改善が見られない場合はアーミッシュを追放され、家族から絶縁される。
☆屋根付きの馬車は大人にならないと使えない。子供、青年には許されていない。
☆交通手段は馬車(バギー)を用いる。これはアーミッシュの唯一の交通手段。(自動車の行き交う道をこれで走るために交通事故が多い)。
☆アーミッシュの家庭においては、家族のいずれかがアーミッシュから離脱した場合、たとえ親兄弟の仲でも絶縁され、互いの交流が疎遠になる。
☆怒ってはいけない。
☆喧嘩をしてはいけない。
☆読書をしてはいけない(聖書と、聖書を学ぶための参考書のみ許可される)。
☆賛美歌以外の音楽を聴いてはいけない。
☆避雷針を立ててはいけない(雷は神の怒りであり、それを避けることは神への反抗と見なされるため)。
☆義務教育以上の高等教育を受けてはいけない(大学への進学など)。
☆化粧をしてはいけない。
☆派手な服を着てはいけない。
☆保険に加入してはいけない(予定説に反するから)。
☆離婚してはいけない。
☆男性は口ひげを生やしてはいけない(歴史的に口ひげは男性の魅力の象徴とされることがあったため)。ただし、顎ひげや頬ひげは許される。
信仰
政治的には、「神が正しい人物を大統領に選ぶ」との信条から積極的に有権者として関わることはなかった。しかし、2004年アメリカ合衆国大統領選挙では激戦州となったペンシルベニア州やオハイオ州のアーミッシュに共和党が宗教的紐帯を根拠とし支持を広げたという。
彼らは専用の教会をその集落に持たず、普通の家に持ち回りで集い神に祈る。これは教会が宗教を核とした権威の場となることを嫌って純粋な宗教儀式のみに徹するため。学校教育はすべてコミュニティ内だけで行われ、教育期間は8年間である。1972年に連邦最高裁において独自学校と教育をすることが許可された。教師はそのコミュニティで育った未婚女性が担当する。教育期間が8年間だけなのは、それ以上の教育を受けると知識が先行し、謙虚さを失い、神への感謝を失うからだとされる。教育内容はペンシルベニアドイツ語と英語と算数のみとか。
生活
アーミッシュは移民当時の生活様式を守るため電気を使用せず、現代の一般的な通信機器(電話など)も家庭内にはない。原則として現代の技術による機器を生活に導入することを拒み、近代以前と同様の生活様式を基本に農耕や牧畜を行い、自給自足の生活を営んでいる。自分たちの信仰生活に反すると判断した新しい技術・製品・考え方は拒否するのである。一部では観光客向け商品の販売などが行われている(アーミッシュの周辺に住む一般人が、アーミッシュのキルトや蜂蜜などを販売したり、アーミッシュのバギーを用いて観光客を有料で乗せたりする例もある)。
基本的に大家族主義であり、ひとつのコミュニティは深く互助的な関係で結ばれている。新しい家を建てるときには親戚・隣近所が集まって取り組む。服装は極めて質素。子供は多少色のあるものを着るが、成人は決められた色のものしか着ない。洗濯物を見ればその家の住人がアーミッシュかどうかわかるという。
アーミッシュの日常生活では近代以前の伝統的な技術しか使わない。そのため、自動車は運転しない。商用電源は使用せず、わずかに、風車、水車によって蓄電池に充電した電気を利用する程度である。移動手段は馬車によっているものの、ウィンカーをつけることが法規上義務付けられているため、充電した蓄電池を利用しているとされる。しかし、メノナイトは自動車運転免許を持つことが許されており、家電製品も使用している。
アーミッシュは現代文明を完全に否定しているわけではなく、自らのアイデンティティを喪失しないかどうか慎重に検討したうえで必要なものだけを導入している。アーミッシュがあまり生活について語らないため謎に包まれている部分もある。写真撮影は宗教上の理由から拒否されることが多い。ただし、これらの宗教上の制限は成人になるまでは猶予される。
アーミッシュの子供は、16歳になると一度親元を離れて俗世で暮らす「ラムスプリンガ」という期間に入る。ラムスプリンガでは、アーミッシュの掟から完全に解放され、時間制限もない。子供達はその間に酒・タバコ・ドラッグなどを含む、多くの快楽を経験する。そして、18歳成人になる(ラムスプリンガを終える)際に、一年の間、アーミッシュのコミュニティから離れた後にアーミッシュのコミュニティに戻るか、アーミッシュと絶縁して俗世で暮らすかを選択する事が認められているが、ほとんどのアーミッシュの新成人はそのままアーミッシュであり続けることを選択すると言われている。この模様は『Devil's Playground』というドキュメンタリー映画の中で語られている。ただし、2004年のアメリカのテレビ番組『アーミッシュ・イン・ザ・シティ』の中で、アーミッシュの子供達をアーミッシュの居住地域から離れた、大都会であるロサンゼルスに連れて行き大学生の生活をさせると、自分の人生の可能性に気付き、彼らの内9割以上が、俗世に出ることを選択したという出来事もある。
このような反文明的な精神世界がその対極とも言える米国社会の中に存在していること自体が大変貴重なことかも。ある意味SDGsの模範的生活かも。持続可能性を徹底的に追求すればこのような社会にならざるを得ないかも。
実は、今流行している新型コロナに関して、人口は20万人以上と言われるアーミッシュ世界の人達は一人も感染者を出していないという事実が知られている。当初は無自覚無症状の感染者も発見されていたかもしれないが。勿論、彼等の信条から、PCR検査なんか進んで受けるものなどいないし、ワクチンに至ってはそんなもの神への冒涜以外の何物でもない。でも、結果としてそれが良い方向に進んでいるのは事実だ。やはり、新型コロナは人類が勝手に作り出した虚構の産物だった可能性が高い。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
Qアノン
Qアノンあるいは単にQとは、反証され信用されていない情報を流す団体とか。日本ではその中身の正体は全く分からない。そもそもQアノン主張もそれに対する反証も日本では何も伝わっていない。アメリカの極右の陰謀論と言われているがどうも実態は不明。この陰謀論では、世界規模の児童売春組織を運営している悪魔崇拝者・小児性愛者・人肉嗜食者の秘密結社が存在し、ドナルド・トランプはその秘密結社と戦っている英雄であるとされており、神に遣わされた救世主として信奉者に崇拝されている。もし、そうだとすればかなり荒唐無稽で面白い話だけど。英雄して戦っている!だったら大変結構な話だ。ただ米マスコミでQアノンはけしからんとの論調だけが流されている。
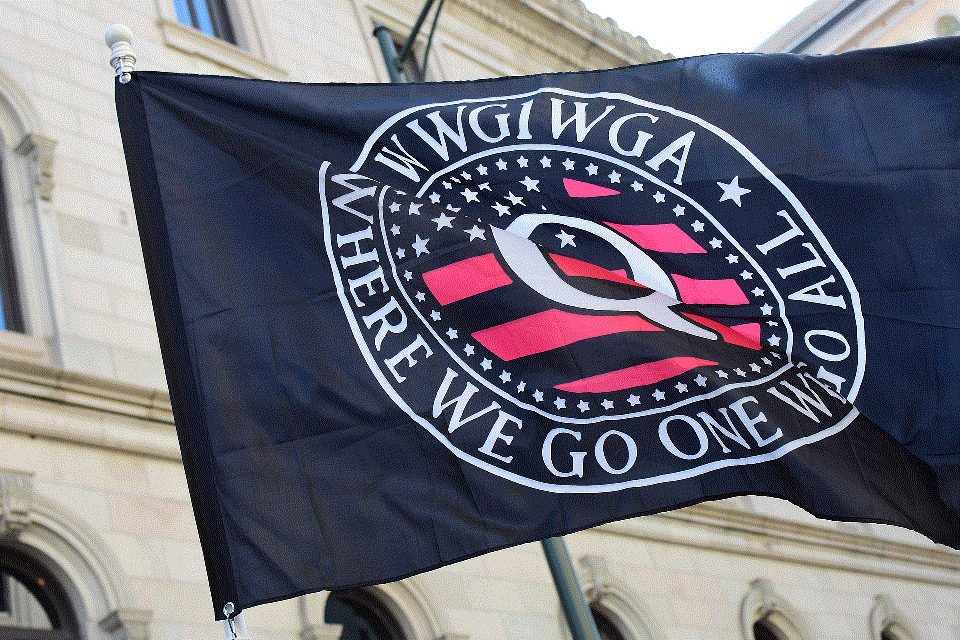 この陰謀論で仮定されている秘密結社は、一般的にディープ・ステート(deep state、影の政府)やカバール( cabal、直訳で「陰謀団」)と呼ばれている。この陰謀論の信奉者は、自由主義的(リベラル)なハリウッドセレブや民主党の政治家、および政府高官の大多数をその秘密結社のメンバーであるとして非難しており、トランプが計画している「嵐」(The Storm)と呼ばれる報復の日には、秘密結社のメンバーが大量に逮捕されると信じている。また、バラク・オバマ、ヒラリー・クリントン、ジョージ・ソロスによるクーデターを阻止するために、トランプはロシア人との共謀(ロシア疑惑)を装ってロバート・モラーに児童売春組織の存在を暴露し、彼に協力を仰いだと信奉者は主張している。Qアノン陰謀論は、ロシア政府の支援を受けたソーシャルメディア上の荒らしアカウント、およびロシアの国営メディア(ロシア・トゥデイやスプートニクなど)によって拡散されている。
この陰謀論で仮定されている秘密結社は、一般的にディープ・ステート(deep state、影の政府)やカバール( cabal、直訳で「陰謀団」)と呼ばれている。この陰謀論の信奉者は、自由主義的(リベラル)なハリウッドセレブや民主党の政治家、および政府高官の大多数をその秘密結社のメンバーであるとして非難しており、トランプが計画している「嵐」(The Storm)と呼ばれる報復の日には、秘密結社のメンバーが大量に逮捕されると信じている。また、バラク・オバマ、ヒラリー・クリントン、ジョージ・ソロスによるクーデターを阻止するために、トランプはロシア人との共謀(ロシア疑惑)を装ってロバート・モラーに児童売春組織の存在を暴露し、彼に協力を仰いだと信奉者は主張している。Qアノン陰謀論は、ロシア政府の支援を受けたソーシャルメディア上の荒らしアカウント、およびロシアの国営メディア(ロシア・トゥデイやスプートニクなど)によって拡散されている。
選挙でトランプがジョー・バイデンに敗れると、Qの投稿は著しく減少した。Qアノンは選挙結果を覆そうとする試みの一部となり、連邦議会議事堂襲撃事件で最高潮に達し、ソーシャルメディアによるQアノン関連コンテンツの規制強化が急速に進んだ。バイデン大統領の就任式が執り行われた日、8chanの元管理人であり、Qアノン信奉者の事実上のリーダーであるロン・ワトキンスは、「できる限り元の生活に戻るべきときがやってきた」ことを示唆した。他のQアノン信奉者は、バイデン大統領の就任は「計画の一部」であると考えている。
以上は、ウィキペディアの説明からだけど、Qアノンが何なのか問題は全く不明だ。上の説明自体相当荒唐無稽な感じだ。多様な意見が許容されるのは社会が健全な証拠で日本のオウム真理教だって、殺人などの反社会的行為を行うまでは信仰の自由で活動を保証されていた。ドナルド・トランプだって国民の半数近い支持者を獲得しているのだから、神の如く敬う崇拝者がいても当然で、それを支持する人達の発言は当然許容されるべきと考えるのは民主主義の原理だろう。
ただ、今の新型コロナに関して言えば、新型コロナはPCR検査を利用した偽の感染症で都市ロックダウンなど過激な対策は全くのフェィクだと信じている多数の者が存在していることは事実であろう。過激な対策が全くのフェィクだったか或いは多少は本物だったかは、科学による実証的な研究を待たねば結論は出ない問題だし、多数決で真偽を決める話ではない。ポリメラーゼ連鎖反応や発明者マリス氏の著作からはPCR検査では感染症ウィルスも感染者も見つけ出せない可能性は極めて大である。つまりPCR検査を拡散することそれ自体が感染拡大の原因だった可能性が極めて大であることが分かって来た。もし、Qアノンの連中が新型コロナをフェィクと信じ、トランプが新型コロナを収束させようとしていたと信じていれば、現在の政府の感染対策に異を唱える運動が起こって来るのはある意味当然だろう。
事実、今の民主党政権のワクチン義務化は、明かに人権侵害以外の何物でもない。極めて異常な発想だ。これこそが陰謀論とされる所以だろう。人類総家畜化計画。バイデン大統領の就任は「陰謀計画の一部」かも知れない。
日本や中国、インド等感染が収束している中で欧米だけが異常に感染者(50万人超)を拡大させ、ワクチンの義務化を進めている状況を見れば、これが秘密結社の陰謀と見られるのはある意味当然のことだ。PCR検査の義務化は当然感染者の増加となる。となればある意味コロナ大好き派のメンバーが今後大量に逮捕される可能性が無いとは言えないね。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
一水会
一水会(いっすいかい)とは
日本の思想探求団体。日本の新右翼系民族主義団体の一つと言われている。かってに右翼だ左翼だとレッテルを貼る主張は良くない。どんな主張なのかよく見て自分の頭で考えないといけない。何時も通りネット百科事典wikipediaで概要を把握しよう。でも、多くの百科事典にも執筆者の個人的意見も紛れ込んでいるので気を付けないと。
三島由紀夫の思想を継承している唯一の団体との話が気になったので調べて見た。
 概要
概要
1970年(昭和45年)11月25日、陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地の東部方面総監部で楯の会会員5人が起した「楯の会事件」。自衛隊員に蹶起を促し、痛烈に戦後日本を批判して自決した。
5人の行動を"戦後体制打破"へ向けた果敢な行動と位置付け、「両烈士らの魂魄を継承する」為、1972年(昭和47年)5月30日、創設された思想探求団体。
三島由紀夫・森田必勝等の行動、彼等は何故このような行動に走ったのかを考えようという会か。
三島由紀夫・森田必勝等を"戦後体制打破"へ向けた果敢な行動と位置付け、「両烈士らの魂魄を継承する」為、1972年(昭和47年)5月30日、創設されたとか。阿部勉、鈴木、阿部勉、犬塚博英(1980年脱退)、四宮正貴らで設立。翌年鈴木は逮捕された(何したの?)ことで勤め先を解雇されて、一水会の専業活動家となる。
三島由紀夫は反共の立場でありながらもアメリカに押し付けられた憲法を合法的に改正して軍隊を持つことは当時の世論から不可能と判断していたことから、自衛隊員に軍事クーデターを呼びかけたものだった。でも安倍晋三さんなんか何とか可能にしたいと頑張っているのにね。
三島由紀夫は事件前の1969年に論壇誌『20世紀』4月号で発表した自衛隊二分論という論文にて、現日本国憲法下の自衛隊員のうち、陸自の9割、海自の4割、空自の1割を日本政府管轄の「国土防衛軍」として残し、それ以外の隊員は「国連警察予備軍」の名で国連軍の管轄下にする思想を主張していた。
**三島由紀夫氏の上の主張は、一つの案としては当時の国際世論から見て全く荒唐無稽とも言えない。戦争放棄を謳っても「国連警察予備軍」なら軍事力保持も正当性は持つだろう。ただ今の国連は世界を一つにする正当性は持つことは不可能で、今となっては全く実現性は無い。これが三島氏の決起の理由にはならないだろう。いや、そもそも国際連合はそのような理念で設立されたもの。今の、国連はチャーチル~ルーズベルトの冷戦構造政策で骨抜きにされたか。国際連盟で活躍された新渡戸稲造氏-武士道の著者、が目指した国際連盟、これなら三島由紀夫氏の理念と一致する。
日本国憲法第9条の2条項を「敗戦国日本の戦勝国への詫証文」と非難し、一刻も早く憲法改正し自衛隊を正規軍に再編すべきと訴えていた三島と、憲法改正を強く主張せずに日米安保破棄と「対米自立」を訴える一水会と思想的には一致しない。
**憲法の草案に当たっては、GHQも相当苦労して拵えたもので、ある程度日本の関係者にも根回しはあったと思われる。さほど支離滅裂な詫証文との非難は当たらないだろう。ここは文学的レトリックとしよう。はっきり言って詫証文とされる部分は日本の再軍備の禁止条項だけだろう。日本と戦った米国やアジアの周辺諸国らは、当時は日本の再軍備の悪夢だけは絶対に許したくなとも思いを代弁している。
しかし、「対米自立」を目指すなら再軍備は不可欠? 何時までも核の傘を理由とした日米安全保障体制の欺瞞性打破。対米従属一辺倒では未だ植民地。「対米自立」が目的で再軍備はその手段。でも、軍備何て元々自衛のためが目的だ。他国を侵略するという理由で軍備を拡張する国などどこにもない。現実には日本の軍事力は既に世界第5位との話もある。自衛隊は戦力ではないと思っているのは日本人だけで世界はそうは見ていない。これ以上軍備を増やすとすれば、後は核兵器の開発を進めるだけだ。だとすれば、憲法改正は文言だけの話なのか。
日米安保体制の打破と「対米自立」を訴える一水会と「自衛隊を正規軍に再編すべき」との三島の主張は何ら矛盾していない。
1982年、木村三浩を中心に一水会メンバーの見沢知廉が統一戦線義勇軍書記長に就任し、「清水浩司」を名乗り、日本IBM、イギリス大使館等への火炎瓶によるテロ活動を行う。これ大学紛争の頃の左翼系と言われた学生達と同じでは。組織の存在アピールか。
同年9月12日、見沢らが右翼団体を新たに設立しようとする中で、一人のメンバーを公安のスパイと疑い、清水ら4名が1名をバールで殴打し、青木ヶ原の樹海に埋めるスパイ粛清事件を起こした。鈴木は遺体処理相談を受け、清水らは木村三浩の協力のもと、遺体を青木ケ原樹海から静岡の朝霧高原に埋め直した。9月18日に3名が逮捕され、9月23日に見沢も逮捕された。この事件で、鈴木も任意同行を何度も求められたが、逮捕を免れている。赤軍浅間山荘事件と同じだ。見沢は殺人罪ならびに火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反で懲役12年の判決を受けた。
**結構過激なテロリスト集団見たいな時期もあったようだ。
その他の日本国主流の右派団体は憲法改正による対米自立を訴える団体を「主張は異なる右翼団体」と見なしているが、一水会のように憲法改正と軍事増強を訴えずに「日米安保破棄」「対米自立」を訴えるのは机上の空論で、左翼と変わらないとして右翼団体と見なされていないらしい。1991年時点でも日米同盟・日米安保体制堅持派が右翼系の日本国民の大半を占めており、自衛隊を米軍の穴を埋められるほど増強するとは訴えない民族派・反米右派団体は全て会員数減少が続く退潮傾向であり、一水会も基本的に連帯しているのは非親米の親右翼系か左翼系のみである。1972年の創設以来、鈴木邦男が代表を務めてきたが、1999年(平成11年)、書記長だった木村三浩に交代した。鈴木は顧問となり、文化人として、言論活動を行っている。木村は池子米軍住宅建設反対運動を行ったり、「対米自立」の観点を堅持し、湾岸戦争以降のイラク、北大西洋条約機構(NATO)空爆後のユーゴスラビア連邦共和国(現:セルビア)等を訪問。フランス、ドイツ、ロシア、リビア、シリア、マレーシア等各国の政党・団体と交流した。
**確かに今の日本のマスコミは、対米従属一辺倒を国是とする団体を右翼団体と定義している空気はある。でも、それでは太平洋戦争で血を流した多くの英霊たちに合わす顔が無かろう。対米従属を唱えながら憲法改正や自衛隊の正規軍化を叫ぶのは、明かにインチキ右翼だね。対米従属やるなら憲法改正など全く百害あって一利無しの愚行だ。
2003年(平成15年)イラク戦争の際、「ブッシュ政権のイラク攻撃に反対する会」を結成。リーダーの木村三浩が同年2月13日記者会見。2月15日出発。2月24日帰国。3月4日記者会見。 2006年に処刑されたサッダーム・フセイン大統領の追悼会を日本で唯一開催。2007年(平成19年)顧問鈴木邦男、代表木村三浩は北朝鮮による日本人拉致問題で冷え切っている北朝鮮を訪問した。木村は北朝鮮に残置されている日本人軍人・軍属の遺骨2万2千の返還を提案した。 2009年(平成21年)2月5日から4週にわたり『週刊新潮』に掲載された、「実名告白手記 私は朝日新聞『阪神支局』を襲撃した!」の記事で、児玉誉士夫・野村秋介について、事実に基づかない虚偽の報道がなされた。これに対し、木村三浩は阿形充規、犬塚哲爾、蜷川正大、市村清彦と共に、「対『週刊新潮』」抗議団を結成し、正面から徹底的に抗議活動を展開した。結果、『週刊新潮』は虚報を認め、関係者に対し全面的に謝罪した。
【サッダーム・フセイン大統領の追悼会】
ブッシュのイラク攻撃、大量破壊兵器とやらが全くの捏造と分かり、彼は単なる愛国者だった可能性も出て来た。つまり米国の諜報機関によって造られた悪役だった訳だ。フセイン自身は完全な世俗主義(普通の政治家)で、イスラムのテロ支援組織とは全く無関係だった。今ではイラクの英雄だろう。対米従属一辺倒の多くの右翼系の者には理解不能なことだろうが。
2010年(平成22年)8月11日には国民戦線のジャン=マリー・ル・ペン党首ら欧州諸国の政党・活動家を東京に招き、14日にはル・ペンらとともに靖国神社参拝を敢行してニュースになった。 2014年に「韓国を嫌って日本だけを愛するというのは本当の愛国心とは言えない。そんな愛国心は嘘。」と主張。「日本人の品位を貶める」ものと批判し、鈴木邦男、木村三浩が排外主義・レイシズム反対集会に参加。2013年4月号の機関紙レコンキスタ内でも在特会等のデモをヘイトスピーチとし、批判している。
2015年には「右翼団体」という名で組織を呼称することを止めることを宣言している。結構な話だ。「対米自立」が三島の本意なら対米従属の憲法改正、核武装は全くの欺瞞だ。対米従属一辺倒を重んじるなら憲法改正は不要だし、自衛隊は今のままで何ら支障もない。戦後はまだまだ終わっていない。「対米自立」なんて多くの日本人は考えていない。核の傘は必要だ。自分で持つなんて? 三島由紀夫氏にとって、今の日本の現状どう見るかな。
**今の国際世論は、核兵器の使用は絶対に不可である。つまり核の傘はあってはならないもの。核を戦争の抑止力に使ってはならない。核の傘は無用の長物だ。つまりもし、日本が近隣国から武力攻撃を受けてもそれが核攻撃でない限り米国は何も助けてくれないということが明確になって来た。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
伝説の街—枚方市
枚方市と言えば大阪市の衛星都市、人は多いけど特にこれと言った個性は乏しい。関東にも似たような市は沢山ある。しかし子細に見ればどこの町にもそれなりの歴史があり、それが自然と残っているものだけど。
 枚方市の市長さん達
枚方市の市長さん達
「自治体も都市間競争の時代に入り、市民が永住を望み、また、新しく枚方市へ住みたいという人たちを呼び寄せるためには、まちの魅力や個性の向上が求められています。
枚方市には様々な魅力と個性がありますが、江戸時代から京・大阪を結ぶ淀川三十石船の中継港として栄えた舟運の歴史もその一つであり(中略)そのほかにも、天の川七夕伝説や古代蝦夷の英雄アテルイ終焉の地伝説、日本に漢字を伝えた王仁博士の墓など、豊かな伝承もあります。今後、そうした歴史や伝承などをまちづくりに生かし、新たな観光ルートの開発や市民参加で取り組む新たな「まつり」の創出など、まちの魅力と個性の向上に取り組みます」
ただこの構想、市民達からのクレームもあるようだ。伝説は伝説で良いが、歴史を捏造してまで観光開発を推し進める姿勢はいかがなものか。
その中の一人の発言
今を生きる街、神話に生きる街
ジョン・レノンは「イマジン」で「想像するのだ、すべての人が今日のために生きていることを」と歌っている。
ザ・ブルーハーツは「トレイントレイン」で「世界中に建てられてるどんな記念碑なんかより、あなたが生きている今日はどんなに意味があるだろう」と歌った。
人は自らの今ここに自信と安心を得られないとき、歴史に集団としての権威を求めようとする。その心の動きがナショナリズムの根底にあるのではないかと私は考えてきた。
しかし、中司元市長のマニフェストには次のような宣言があった。
ジョン・レノンやザ・ブルーハーツが歌うのとは逆に「住みたいまちとしての都市間競争に勝つためには歴史や伝承によって魅力と個性を向上させる」と言うのである。
私は現在の市民が今を充実して生きているまちであればそんなことは考えないと思うのだが、どうか?
いや、歴史を学問的に探求するのは、いっこうにかまわないのである。
しかし、根拠のない伝承をもって、なりふりかまわず史跡を捏造し、「まつり」を「創出」していく様子を見ていると、なぜそこまでするのか?と首をかしげずにはいられない。
今の生活や政治の実態から目をそらし、偽りの誇りを集団で持とうとする草の根ナショナリズムの心理を私はそこに見るのである。王仁塚が捏造されたものであることは別稿に譲るとして、ここでは牧野公園のアテルイ塚について検証してみよう。

**確かにこれらの遺跡は科学的に実証されたものでなくあくまでも伝説の域を出るものではない。しかも今を生きる市民生活とはまったく関係が無い。でも、半分ジョークとして観光の目玉にするのならまあ許される気もする。しかし、これ等を歴史的事実と強弁して市民や観光客に押し売りするのでは頂けないね。一般の市民や観光客も「なんかわからないけど、とにかくそれは専門家によると嘘(ジョーク)なんだなあ」ということさえ、わかればいい。でも、枚方市は関東の街に比べると、恵まれてはいる。大和朝廷と絡んだ伝説が多いから。
枚方市が、ここまで歴史的事実だと拘る根底には「椿井文書」の存在があるという。聞いたこと無い名前だけと。「椿井の思想の根底には、近代皇国史観に繋がるものがあり、故に「椿井文書」が大いに利用された。
「椿井文書」なんてそもそも正式な歴史書として認められてないのでは?しかも未だ機能していることに鑑みれば、今後畿内国境地域史を構築するためには、単に「椿井文書」を排除するだけではなく、「椿井文書」が引き起こした諸問題を精算していくことが不可欠である。→これ本当のこと?
【椿井文書(つばいもんじょ)】
旧山城国相楽郡椿井村や明治時代の木津町のある旧家で、あるいは、江戸時代後期に椿井政隆(1770-1837)によって作成、販売されたとされる神社仏閣の縁起書、由緒書や境内図である。椿井文書は悪意で作られたものであるという。Wikipediaでは以下長々解説があるがこれ以上読む気にもなれない。
伝説があることは、それなりに尊重する必要はある。しかし、そこに構造物を立てて正当化しようとする行為は確かに歴史の捏造だね。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
からゆきさん
からゆきさんと女衒の歴史:日本の近代化に必要だった彼らの今
名を変え形を変えて今も存在する人買い稼業
2022.2.1(火)市川 蛇蔵 連載:少子化ニッポンに必要な本物の「性」の知識
江戸時代後期の成人向け絵解き本「七七四草(ななしぐさ)」には「女見の女を衒(う)るところより、女衒(ぜげん)と書き、音読み転訛してゼゲンと呼ばれるに至れるならん」とある。つまり、娼婦としての価値を見定める目利きを女見と呼んだとのこと。
女衒は、凶作で生活に窮した貧農の親から娘を買いとり遊廓などに売り、売春労働に斡旋することを業とした人買い稼業で、嬪夫(ぴんぷ)とも呼ばれる。風来山人こと平賀源内の滑稽序文集『細見嗚呼御江戸序』の序跋には、目鼻から爪の先、指のそりよう、歩みぶりまで注意して、その後価格が定まる、とある。
娘を買い取る査定として極上、上玉、並玉、下玉という格付けがあり、それを瞬時に見極める、女性を見る術の秘伝があった。遊女・瀬川と客・五郷との悲恋を描いた戯作に『契情買虎之巻(田螺金魚 著:安永7年(1778)刊)』がある。
その中で、親が病いに伏せっているからと、兄と称する女衒が娘を吉原の妓楼に売りとばすシーンでは、楼主は女を見てはすぐに気に入り、奉公人に命じて目先の利く女衒の権二を呼ぶと、権二は次のようにその娘を即座に鑑定している。
「この娘でございますが、まず、なたまめ、からたちの気遣いもなしと。そして小前で、足の大指も反るし、言い分なしの玉だ」
娘の身売り額の1~2割が、斡旋仲介手数料として徴収される。その際、女衒は文字の読み書きが達者で、証文を認めるなど文書構成能力があり、遊廓や岡場所、貸座敷業には欠くべからざる存在であった。
日本の戦場では古くから勝った方が負けた国の男女を戦利品として拉致する「乱妨取り」が行われていた。
ポルトガル人が1514年、日本に上陸し、マラッカ、中国、日本の間で貿易が始まると、ポルトガル人は捕獲になった日本人を奴隷として買った。そのほとんどが女性で、船員の妻や妾、もしくは売春婦として東南アジアなどに売られていった。南蛮貿易で売られた娘たちは知性や勤勉な気質が尊ばれアフリカからの奴隷よりも人気があった。
江戸幕府が、キリスト教圏の人の来航と日本人の海外渡航を禁止した1639年(寛永16年)、長崎に丸山遊廓が誕生する。丸山遊郭の遊女は日本人男性相手の「日本行」の遊女のほかに、出島に出向きポルトガル人やオランダ人を相手にする遊女たちもいて、「紅毛行」と呼ばれた。唐人屋敷へ中国人を相手にする遊女たちは「唐人行(からひとゆき)」と呼ばれた。唐人屋敷の近隣・島原のあたりでは「からゆき」という言葉が生まれ、それは「唐人行」または「唐(からん)ん国行(くにゆき)」という言葉がつづまり「からゆきさん」となる。
遊郭内では少女の人身売買が行われ、ポルトガル人の貿易業者により万単位の数の少女が東南アジアなどに売られていった。春を鬻ぐ(ひさぐ)女性は、人間の最も秘匿性の高い性的行為によって、カネを稼がなければならない。それは理不尽ともいえる低賃金で労働する生活より、もっと苛虐なものといえよう。
そんな・からゆきさんとなった女性の多くは農村、漁村など飢餓に喘ぐ貧困家庭の娘たちだった。貧窮した村の多くが間引きや捨て子などの悪習が蔓延したが、そうした窮乏した村落の娘たちを海外の娼館へと女衒は橋渡しをしたのである。女衒は全国の貧しい農村や漁村を周って年頃の娘を探し「海外で奉公させると、お金が儲かる」などと言葉巧みに親子を説得し、親に現金を手渡した。娘を売り飛ばした両親はわが子を売らなければならないほど貧しかったのである。
女衒は娘たちを下関や門司、長崎、神戸、横浜、清水の港から密航させた。学校に行くことができず、ひらがなも数字も書けない・読めない少女らは、当然ながら彼女らが自らペンを執ってその生活の実情と苦悩とを訴えるということはできなかった。娘たちは女衒により斡旋手数料や経費といった名目で多額の借金を負わされて、それが返済されるまでは日本に帰れないようにカネで、その身体を縛られたのである。
開国したばかりの明治4年、シンガポールには既に日本人の・からゆきさんの姿があった。そして、アジア太平洋戦争の敗戦まで、シベリア、中国、香港、朝鮮から台湾、シンガポール、フィリピン、ボルネオ、タイ、インドネシアなどの東南アジア、オーストラリアなど太平洋の各地、ハワイ、北米(カリフォルニアなど)、南アフリカやザンジバルなどの至る処に約30万人以上の娘たちが売られた。彼女らは現地で稼いだカネを日本に送金したのである。
南洋の地域に売られていった・からゆきさんたちは、日本よりももっと文明が遅れ、それゆえに西欧列強の植民地とされてしまった東南アジアの国々で客を取らされた。客は主として中国人や原住民。彼女らは南国の夜ごと、様々な肌の色をした異国の男たちが入れ替わり、立ち替わりやって来てカネを払い彼女らの身体を弄び、蔑ろにする。インドシナ半島では早くから日本女性売春婦の市場が形成され、日本人の人口の大半を売春婦が占めるようになった。
身体だけでなく心も蹂躙された彼女たちの遣る瀬無い思いを、はかり知ることはできそうにない。1910年の「福岡日日新聞」には、現地を訪れた記者は、当時の・からゆきさんの様子を次のように記している。
「異類異形の姿せる妙齢の吾(わ)が不幸なる姉妹、之(これ)に倚(よ)りて数百人とも知らず居並び、恥しげもなく往来する行路の人を観て、喃喃(なんなん)として談笑する様、あさましくも憐(あわ)れなり」
また、当時、シンガポールあたりに立ち寄った夏目漱石や森鴎外は手記にシンガポールの・からゆきさんのことを書いている。「彼女たちには微塵の暗さがない。愚痴、泣き言をこぼさない、どうしてあんなに朗らかで明るく突き抜けたように気分でおれるのか不思議でしょうがない」 酸鼻を極めた状況に置かれた少女たちが、晴れ晴れとしている様子に面食らっていたことが覗える。シンガポールのマレー街と呼ばれる通りには日本人娼館が連なり633人の娼婦が働いていたとの記録がある。
愛情のない不特定多数の男性に金銭と引き換えに自らの肉体を自由にさせる生業は、その肉体のみならず精神まで蝕むことが多いとされる。一夫一婦制の婚姻方式が一般的となりつつあった当時の日本で、売春はモラルに反することであり、それに従事せざるを得なかった女性たちは、世間から無慈悲な差別を受けるのが普通だった。
ましてや、借金でがんじがらめにされ、いつまでたっても貧窮とは縁が切れないとなれば、精神的に絶望して投げ遣りとなって挙措を失う人も多いだろう。
しかし、彼女らは心が潔く、清らかに澄み切ったかのように、暗鬱がなく、明るく朗らかに振る舞えたのは、現実に置かれた状況にまごつくことなく、深刻な物事も忽(ゆるが)せにとらえて、気丈夫に、それを受け入れてしまう。
それは真俗二諦の境地という絶対的真理に到達したかのようにも思えてくる。人は、ありとあらゆる汚濁に染まりながらも、様々な醜悪に出会えば出会うほどに、他人に対して寛容となり、円熟していくことも、稀にあるのだろう。女衒の顔役・村岡伊平治は、少女たちが海外に売り飛ばされることは日本のためであり、現地にも大きな利益と発展をもたらすと主張している。「からゆきさんたちが海外に送られると、国元にも手紙を出して、毎月送金する」「女の家も裕福になると税金が村に入る」「どんな南洋の田舎でも、そこに女郎屋ができるとすぐに雑貨屋ができ、日本から店員が来る」「その店員が独立して開業する」「商社など会社の現地出張所ができる」
「女郎屋の店主も嬪夫(ぴんぷ)と呼ばれるのが嫌で商店を経営する」「1ケ年内外でその土地の開発者が増えてくる。そのうち日本の船が着くようになる。次第にその土地が繁盛するようになる」
明治33年(1900年)当時、『海外邦人発展史(入江寅次 著 井田書店 昭和17年刊 )』によれば、ウラジオストクを中心としたシベリアの日本人出稼者が日本へ送金したのは約100万円(現代に換算すると約50億円)。そのうちの6割、約30億円以上が・からゆきさんからの送金だった。そうした女性たちからの日本への送金は世界各地で行われていた。 明治政府は、当初・からゆきさんたちの送金が経済に貢献しているとして、海外で少女たちを外貨獲得のために働かせることを奨励していた。
日本人女性の海外渡航は海外進出の先兵と位置付けられ「娘子軍」と賞されたのである。 西欧諸国に政治、経済、軍事に対抗するため近代国家を目指した日本にとって、彼女たちの送金は欠けてはならないものだった。貨幣価値の高かった明治・からゆきさんたちの働きにより、それが外貨獲得につながる。彼女たちは国家の富国強兵の一翼を担っていたのだ。
『サンダカン八番娼館(山崎朋子 著 筑摩書房 1972年刊)』によれば大正から昭和のボルネオでは、娼婦の取り分は50%、その中で借金返済分が25%、客の1人あたりの時間は、3分か5分、それよりかかるときは割り増し料金がかかる。娼婦たちは現地人を相手にすることは好まず、かなりの接客拒否ができたという。また、日露戦争時、海外日本人娼婦が明治政府に、軍事に関する情報の提供もしていた。その役割は勝敗を決する上でも大きかったといえよう。
衛星やレーダーのなかった当時、ヨーロッパのバルト海に展開するロシア海軍のバルチック艦隊が、バルト海を出てアフリカ大陸の南を通って日本に向かっていた時、マダガスカルからは、「バルチック艦隊が、いまマダガスカルに入りました」 そして、シンガポールを通過した時には、「マラッカ海峡をバルチック艦隊が四十数隻黒い煙を吐いて日本に向けて出航しました」
と世界各地の・からゆきさんから日本に向けての電報が相次いだ。明治末期になると・からゆきさんは最盛期を迎えるが、国際的に人身売買への批判が高まり、国内でも彼女らは「国家の恥」と非難されるようになった。彼女らは平均で4、5年くらい海外で稼ぎ、借金の返済を終えて日本に帰ったが、残留した人、亡くなった人も数多くいる。その死因はマラリア、風土病、性病、肺病、阿片などで平均すると20歳前後で命を散らしていった。亡くなっても現地に墓を建ててもらうことは極めて稀で、ほとんどはどこかに埋められるか、海や密林に放り投げられたようだ。家族にはいつどこで亡くなったか命日を知らされることもなかったという。
昭和恐慌期(昭和5~6年)になると、食うこともままならない貧窮した人たちが追いつめられて、裕福な家に妻子や、自分自身を売る人が相次ぎ、女衒による人買いは高度成長期初頭まで続いた。斡旋仲介業者は上野と青森を結ぶ列車を買い取った娘たちの輸送に使っていた。1950年、18歳未満の未成年者を人身売買した容疑で、警察に検挙された仲介者は377人。未成年者の送り先の55%は売春婦として計上されている。
人類最古の職業といわれる女性が春を鬻ぐ(ひさぐ)という商売はなくなることはないだろう。 昨今では、女衒は消滅したかに見える。しかし、それは「スカウト」という言葉に代り、いまも活発に蠢いている。スカウトとは街中で女の子に声をかけるプロの落とし屋である。彼らは女性を口説く技術に磨きを重ね、女を落とすための独自の指南書もあるらしい。 そこに仕事に金銭、恋人など身近な問題に悩んでいる女性を落とし込むための、人間心理を巧みに突いた高度な口説きの技が記されているという。
かつて、女衒は少女たちを海外に売り飛ばし、娘に多額の借金を負わせて日本に帰れないようにした。しかし、似たような流れで、今度は逆に多額の借金を背負いながら海外から日本に働きに来る人たちがいる。
それは日本の少子高齢化社会の労働力不足が深刻な問題を解決するために国家が考えた技能実習制度により来日する人たちである。日本政府は技能実習制度は途上国に技術を教えるという国際貢献の看板を掲げている。だが、技能習得というのは名ばかりで、本国に帰っても役には立たない内容というのが実態と囁かれている。東南アジアから来日する技能実習生の働き先の多くは、日本人の若者が嫌がる労働力不足が極めて深刻な産業や職種への就業、そして低賃金労働者の確保として技能実習制度は機能している。
ベトナムでは、実習生が日本に働きに出ることを「労働力輸出」と称して奨励する。来日する実習生は親類縁者に平均100万円以上の借金を重ねて渡航費用を工面することになる。それを返すまでは故郷には帰ることができない。
実習生の来日は現地外国の送り出し機関と日本の監理団体を通して行われるのだが、送り出し機関に過大な手数料を取られる悪質なケースが後を絶たない。また、悪徳仲介斡旋業者が賃金の半額程度をピンハネしているケースや、受け取る給料が時給に換算すると300~400円程度といった働き先もある。こうした過酷で非人道的ともいえる扱いは、かつての・からゆきさんが置かれた状況と同じようなものといえよう。
1816年(文化13)頃に書かれた江戸時代後期に書かれた「世事見聞録」に、拐かし(かどわかし)について記されている。「かどわかしというものありて、群集の場所、または黄昏の頃、遊び迷い居る子を奪いとりて、遠方などへ連れ行きてついに売るなり」
「かどわかす」は騙して取る、欺き誘うという意味の古語の「かどふ」が、その語源である。それは強引に何かをするという意味の接続詞「かす」が付き「かどわかす」となる。人を騙し、欺き、借金で強引に縛って売り飛ばす稼業は名を変え、形を変えて、いまも暗躍しているようだ。
売春婦という世間からは蔑視されている人達に歴史の光を宛てて見直しを迫る。良くできた作品ですね。下記はそのプロフィール。ただし、ネットからのコピーなので真偽は保証しませんが。
【市川 蛇蔵(いちかわ・へびぞう)さん:作家・編集者のプロフィール】
市川海老蔵さんではありません。昭和40年生まれ。小学校の頃、精通し人体の神秘に興味を持つ。高校時代「遊びをせんとや生まれけん(『梁塵秘抄』)」と、この世に生まれてきた理由を覚る。大学時代、タイ・バンコクやインド・バラナシなどで長期間沈没。日々快楽に耽る。その後、出版社を転々とする。春をひさぐ女性から元首相まで数くの著作を手がける。「快楽こそが人生」を高唱する巨匠、団鬼六師の薫陶を受け、さらなる堕落に拍車がかかる。出版業界の斜陽により低迷していた会社を退職。新天地を求めて日本語教師として教壇に立つもコロナの影響で集団解雇の憂き目に遭う。現在、失業者や退職者の憩いの場である防波堤(通称、年金波止場)にて釣り糸を垂れながら、ただぼんやりと時間を消化する日々を過ごしている。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
グアンタナモ湾収容キャンプ
 グアンタナモ湾収容キャンプ(Guantanamo Bay detention camp, Guantánamo, G-Bay, Gitmo, GTMO)は、キューバのグアンタナモ湾のグァンタナモ米軍基地に設置されているアメリカ南方軍グアンタナモ共同機動部隊運営の収容キャンプ。 2002年にジョージ・W・ブッシュ政権時に設立されアフガニスタン紛争およびイラク戦争の過程でアメリカ軍によってテロに関与しているか何らかの情報を持っていると疑われて強制連行ないし逮捕された数多くの人物が収容、監禁、拘禁されているが、法の適正プロセスを規定したアメリカ合衆国憲法修正第5条や修正第14条に違反する違法な拘束であると批判を受けており、キューバ政府は同基地の返還を求めている。
グアンタナモ湾収容キャンプ(Guantanamo Bay detention camp, Guantánamo, G-Bay, Gitmo, GTMO)は、キューバのグアンタナモ湾のグァンタナモ米軍基地に設置されているアメリカ南方軍グアンタナモ共同機動部隊運営の収容キャンプ。 2002年にジョージ・W・ブッシュ政権時に設立されアフガニスタン紛争およびイラク戦争の過程でアメリカ軍によってテロに関与しているか何らかの情報を持っていると疑われて強制連行ないし逮捕された数多くの人物が収容、監禁、拘禁されているが、法の適正プロセスを規定したアメリカ合衆国憲法修正第5条や修正第14条に違反する違法な拘束であると批判を受けており、キューバ政府は同基地の返還を求めている。
【解放された収容者の動向】
2013年にまとめられたアメリカの報告書では、グアンタナモから解放された収容者のうち16.6%が再びテロ活動に戻ったとのデータがある。2007年に解放されたアブドゥル・カユム・ザキールは、ターリバーンに復帰後に組織内で頭角を現し、2021年のカブール陥落で司令官として活動した。また、2018年に解放されたアブドゥル・ガニ・バラダルはターリバーンのナンバー2となった。反政府組織などで活躍する人物が存在する一方、ロシアや中華人共和国ではグアンタナモ出身者に少なからずCIAに取り込まれた人物がいるとの推測もされている。なお、バラダルについてはCIAとの関与の有無は別にして、アフガニスタンの政権崩壊前後にアメリカとの交渉窓口役を担った実績がある。
アメリカ合衆国の暗部といって良い。この中でどのようなことが行われて来たのかはほとんどの米国人すら知らないはずだ。解放された収容者の動向では、この施設内はテロ指導者の養成機構としての役割すら果たしていた可能性が伺われる。となると、今各地で散発しているテロ活動は米国覇権を維持するための諜報機関の別動隊として活動しているのかも。アルカイダとかISとか。そのように考えた方が世界の動きがよく分かる面もある。
当初は施設の存在が秘密扱いになっていた上に、アメリカ国内でもキューバ国内でもない治外法権区域になっているため、収容者に対する非人道的な扱いや拷問による自白の強要などが横行していました。このことが人権団体の手で明るみに出ると一気に批判が高まり、これを受けて2009年1月にはオバマ大統領がグァンタナモ基地の収容施設を含む秘密収容施設の閉鎖を命令、収容者は他の施設に移されることが決定されている。その後、それが実施されたかどうか?
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
DNA鑑定
DNA鑑定
Wikipediaで調べて見た。
DNA型鑑定とは、デオキシリボ核酸 (DNA) の多型部位を検査することで個人を識別するために行う鑑定である。犯罪捜査や、親子鑑定など血縁の鑑定に利用される。また、作物や家畜の品種鑑定にも応用されていた。
**これが定義だろう。知りたいのはどのような方法でかだ。当然PCR法も含まれていそうだが。
DNAは「デオキシリボ核酸」の略称で、遺伝子の本体として生物の核内に存在する物質である。DNAを主成分とした物質は1869年に発見され、「ヌクレイン」と名づけられた。しかし、遺伝子の本体は長い間タンパク質であると考えられていたこともあって、DNAの初期の研究は遅々として進まなかった。
遺伝子の本体はDNAであるということが初めてはっきり示されたのは1944年であり、それが学会で公認されたのは1952年である。二重らせんで知られるDNAの立体構造、いわゆるジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックのモデルが発表されたのは1953年である。この発見は分子生物学史最大の発見の一つと称えられ、以後DNAの研究は急速に進展する。この発見により、2人は1962年にノーベル生理学・医学賞を受賞している。ただし、科学史を紐解けば、二重らせん構造はともかく基本的の機能は多くの科学者達によって解明されており、大発見と言うより集大成と言う方が適切ではないか。
1984年にはレスター大学の遺伝学者アレック・ジェフリーズが、科学雑誌「ネイチャー」に論文を発表した。彼は多くの研究者が関心をもった“遺伝子の働き”でなく、“DNAによって個人を区別できるか否か”の観点に着目したといわれる。その結果「ヒトのDNA型は十分に個性があり不同性がある。そして、終生不変である」こと、したがってDNAで「個人の特定ができる」ことを説いた。この発表により、DNA型鑑定は個人特定の切り札として飛躍的に発展していく。
【DNAの構造】
DNAはRNAとともに核酸と呼ばれ、その構成要素は次の3つ。①糖、②リン酸、塩基。
DNAでは糖がデオキシリボースであり、塩基がアデニン (A)、チミン (T)、グアニン (G)、シトシン (C)の4種。RNAではチミン(T)がウラシル(U)に代わるだけ。
DNAはデオキシリボースとリン酸が交互に長くつながった鎖が2本、螺旋状にねじれた二重らせん構造になっている。糖であるデオキシリボースの部分にはA,T,G,Cの4種類の塩基が1つずつ結合している。そして、この塩基がもう1本の鎖の塩基と結び合うことで、DNAの本鎖は結合している。この塩基の結合規則は、AとTと、GとCのペア(塩基対)。したがって、二重らせんの一方の鎖の塩基の並び方(塩基配列)が決まると、もう1本の鎖の塩基配列も自動的に決まる。塩基配列は互いに相補的。AとT、GとCの数が同数であることからそのように推測されていた。
ヒトの細胞は1個の受精卵から出発して、誕生までに約3兆、成体になると約60兆にも及ぶ。そしてヒトの細胞1個に入っているDNAは60億塩基対くらいとされている。総ての細胞がこの同じ塩基対を持っていることはある意味驚きだ。なんて無駄なことなんだろう。だって、約60兆×60億もの塩基対がなぜ必要なんだ。
ヒト細胞は2倍体なので、ゲノム(配偶子または生物体を構成する細胞に含まれる染色体の組・またはその中のDNAの総体)あたりは約30億塩基対である。
DNAの塩基配列のうち、同じ塩基配列が繰り返して存在する特殊な「縦列反復配列」と呼ばれる部分を検査し、その繰り返し回数が人によって異なることを利用して個人識別を行う手法が最も一般的であり、世界的に共通した検査法が確立している。2009年現在、同じ型の別人が現れる確率は4兆7000億人に1人とされている。2019年2月28日、警察庁は、新たな検査試薬を導入することを決め、同じDNA型の出現頻度が「4兆7千億人に1人」から「565京人に1人」となり、より精密な個人識別が可能になると発表した。
**DNAの仕組みはこの説明で分かる。全塩基対総てが一致すれば個人識別はまず問題無かろう(100%かどうかは別にして)。約30億塩基対もあるので実際に不可能かあるいはスーパーコンピュータでも使えばたちどころに検査できるのかは分からないが。
となると、「縦列反復配列」と呼ばれる部分が何を意味していて、繰り返し回数が何故人によって異なるのか。そもそも繰り返しとは、ある塩基配列が重複して存在することで、ある意味無駄な配列だ。無駄を調べることが個人識別に繋がる。その無駄が個人識別に使える程大きな数ということだから。警察庁の発表では余りにも心もとないね。やはり、ノーベル賞級の学者達のお墨付きが無いと。
【反復配列】
反復配列(repetitive sequence)とは、生物ゲノムのDNA配列で、同じ配列が反復して(特に数回以上)見られるものの総称である。真核生物、特に進化した動植物に多く見られる。一部を除いて機能はよくわかっていないため、従来は無駄な「ジャンクDNA」あるいは「利己的遺伝子」の例とされる一方、遺伝的組換えを通じて進化に大きく関わったとも考えられてきた。最近になって、一部のものについては遺伝子の発現調節に関わっている可能性も指摘されている。要は何も分かっていない。
反復配列は、更にいくつかに分類されており、大別すると
A.縦列(単純)反復配列(タンデムリピート):同じ配列が同じ向きに隣り合って存在
B.散在反復配列:隣り合わず散在する配列。レトロトランスポゾンに由来すると考えられている。長さによりLINEおよびSINEに分けられる
遺伝子鑑定にはAの縦列(単純)反復配列のうちのサテライトDNAが良く使われているらしい。
サテライトDNA:他の部分のDNAと密度が異なる。染色体の動原体にあるα-サテライトなどが知られる。配列ユニットの比較的短いものは特にミニサテライトおよびマイクロサテライトとして区別され、個体による反復回数の違いが多いのでDNA型鑑定によく利用される。
**どうも、反復配列の部分を調べれば精密な個人識別が可能になるとの説明はあやふやだ。Wikiの説明はDNA科学の進歩についての概論だけだ。DNA型鑑定についての説明はほとんどされていない。DNA型の出現頻度が「4兆7千億人に1人」から「565京人に1人」なんていう計算が可能ということは、どういう方法で推定したかが明確にされないと信頼性が無い。単なる当て推量ということか。DNA型鑑定はPCR法を使っているから正確だという説明もあるが、DNA型鑑定にPCR法が入り込む余地はなさそうだ。PCR法は遺伝子断片をコピーできても鑑定は出来ない。マリス博士の言う通りだ。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
世界特許戦争
世界特許戦争
国産ワクチンが何故簡単には出来ないか。それは先発企業が総ての関連特許を押さえているから。特許は当然、公開はされるがそのためには高額の特許料を請求される。それまではほとんどの情報は機密情報だ。ファイザー社のワクチンに関しても政府の言っているデータは皆、ファイザー社から提供されたものなので、利用者はデータの精度や信頼性を知ることは全く不可能。
ノーベル賞学者のPCR法発明者マリス博士は、シータス社に就職しており、PCR法に関連する特許は総てシータス社に売却されているとされる。シータス社は、ジェネンテクやビオジェンより先に立ち上がったバイオのベンチャーであり、基礎から応用への旗印を掲げる、希望のバイオベンチャーである。 ちなみに、シータス(Cetus)は“くじら座”を意味し、怪獣も意味する。
シータス社が今どのような状態かは分からないが、PCR検査機器が世界中に売れていることから、もう特許の効力は無くなっているようだ。
特許制度は、先願主義。一秒でも早い方が勝ちだ。でも、特許の要件は発明であって発見ではない。だから、人為的に合成した化学化合物。例えばアンモニアは化合物で特許にはならないが製造技術(例えばハーバー・ボッシュ法)等は特許に出来る。
ところが、米国製薬業界などの強い要求で、人為的に合成した化学化合物にも特許が取得できる仕組みに変えられている。例えばDNA組換え製品などだ。DNAは4つの塩基で構成される化学物質だ。DNA→アミノ酸→タンパク質。つまり無限の組合せが可能になる。バイオ産業の育成が目的とされているが。その結果はどういう未来が出来るかよく考えて欲しい。
化学化合物製品にも特許は、明かに不合理な仕組みだ。アマゾンの原住民達に新しい遺伝子が発見される。これが発見者の特許? これ単なる人権侵害だね。
遺伝子改良のトウモロコシの遺伝子が近隣の農家で見つかる。さあ、特許侵害賠償金払えだ。花粉は風で飛ばされて何処へでも飛んでいく。つまり、農家は単なる被害者。でもこんなことが弁護士を使えば勝訴できるのが米国の今の現状らしい。
化学化合物製品にも特許で、膨大な利益を貪ることが出来るのは製薬業界だけ? いや、メディアでこれを宣伝するメディア業界も美味しいご利益にあずかれるようだ。つまり化学化合物製品にも特許は、米国の重要な経済戦略の一環らしい。工業やエネルギーで世界経済を支配する時代は終わった。これからはバイオとITということだ。
HIVウィルスの発見でノーベル賞が決まると、製薬各社は一斉に新薬開発競争に突入する。HIVウィルスが本当に感染症の原因。そんなことはどうでもよい。何よりも他社に先駆け可能性のある特許を出願してしまわないと。製品が出来ればマスメディアを利用してスター商品に仕立て、後は国の認証を貰うだけだ。国の認証を貰うにはメディアが後押しする。
ノーベル賞は、特許のお墨付き。製薬の本当の効果は使ってみないと分からない。臨床試験何てマスメディアを利用すればいくらでも作れる。90%効果あり。どんな試験したのか。薬害の発生リスクは極めて高い。でも、責任の大半は認証を与えた国の責任だ。
新薬の儲けの大半は特許収入らしい。つまり開発費。薬九層倍何て言われるように薬価に製造費の占める割合はわずか。だからゼネリック薬品の出現は出来れば押さえたい。
シータス社にいたマリス博士は、ゼネリック薬品開発の名人でもあったらしい。大手製薬会社が高価な新薬を開発しても、すぐに特許の中身を見破り、超廉価な同等品を作り上げてしまう。マリス博士が、薬品開発の現状に極めて批判的であったことの現われかも知れないね。
HIVウィルスが感染症の犯人かどうか疑問を持つ者は、科学者の態度しては立派でも製薬会社にとっては迷惑な存在だったようだ。HIVウィルスが感染症の原因でなければ大変なことに。将来得られる特許料を失うだけでなく、薬害等の責任を取らされる可能性もある。
同様に新型コロナで感染症を増やした真の犯人がPCR検査だと分かると、人類一般に対しては極めて重要な知見ではあるが、世界中の製薬会社や厚生省及び政治家にとっては迷惑な話なのかも。では、皆がワクチン打てば新型コロナは解消できるかな。PCR検査を止めない限り不可能でしょうね。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
単一民族国家
 この写真見て、どこかに差別を感じる人いる。北京オリンピックのパレードの一部。中国が多民族国家で色々な少数民族も平和の暮らしていることをアピールする目的があるんでしょう。でも悪意は感じないでしょう。大きな大陸の国、中国は歴史的に見ても多くの民族が集まって一つの文化を共有して出来た国。遺伝子解析によっても欧州よりも遥かに多くの遺伝情報があることが判明している。勿論、日本だって同じで南方北方から移り住んだ人々の混血だ。それはお隣の韓国も同じはず。
韓国人はどう考えているのか?韓国のライターの説。
この写真見て、どこかに差別を感じる人いる。北京オリンピックのパレードの一部。中国が多民族国家で色々な少数民族も平和の暮らしていることをアピールする目的があるんでしょう。でも悪意は感じないでしょう。大きな大陸の国、中国は歴史的に見ても多くの民族が集まって一つの文化を共有して出来た国。遺伝子解析によっても欧州よりも遥かに多くの遺伝情報があることが判明している。勿論、日本だって同じで南方北方から移り住んだ人々の混血だ。それはお隣の韓国も同じはず。
韓国人はどう考えているのか?韓国のライターの説。
判定を巡り様々な議論を巻き起こしている北京冬季五輪。韓国市民の間でも、反中感情が沸き上がっている。若者たちを中心にして反中感情が激しいが、とりわけ30代、40代の中国に対する反感は根が深い。
彼等は、あからさまに、中国が「反則国家」だと認識している。スポーツだけでなく、政治的、社会的、文化的な交流において、韓国と不公正なゲームを繰り広げてきたのが、まさに中国だという認識だ。
中国人が、韓国の固有衣装である韓服を中国の衣装だと言い張ることに対して、「中国に住む朝鮮族が嫌悪を感じる?」になるとし、「共に民主党」所属の国会議員は「野党が、意図的に反中感情を煽っている」「中国を嫌悪するよう仕向けている」と中国を擁護している。
ただ、競技の判定を巡る不満は日本視聴者も同じだが、このような反応にはならない。だって競技のルールは、IOCの管轄だろうし、冬季オリンピックでは中国選手が特に優遇されているとも思えない。
しかし、この写真の女性を見て差別?そこそこ美人では。どこに不満があるのだろう。残念ながら和服の人は出てない。実際に朝鮮族は世界各地に散らばっており独自の文化を保存しつつ少数民族として暮らしている人達も多い。カザフスタンにも朝鮮族稲作民が暮らしていた(実はソ連国境にいた朝鮮族をスターリンが強制移住させたのが原因らしい)。
でも、中国の朝鮮族が同じ韓服を着ているなら中国の衣装だと言っても間違いで無いし。朝鮮族の服装が実際は写真と異なり、写真は今の韓服なのかも知れない。でも、それが韓国を蔑視する目的があったとも思われない。
このような韓中の論争は歴史学者達の間でも。朝鮮半島の古代国家、高句麗も多分百済も中国の学者達は、中国国家の一部としか見なさない。周辺に起こった契丹と女真族と一緒の扱いだ。多分科学的に調べるとそうかもしれない。渤海国も韓国学者は朝鮮民族が建てた国。勿論中国は?? 高句麗国を支配した民族は勿論歴史の謎だ。日本だって、大化の改新何て言っているけど、出来たのは百済王朝の分家だったり。だから白村江の大敗があった。
単一民族国家を主張する学者達は、過去もそうであったと信じたい。もし、日本の朝廷が百済の移民が造った組織、或いは遠くからやって来たユダヤ民族の子孫。意外とそんなことが事実となって判明するかも知れない。だからと言って、皇室を廃止すべし何て言う議論にはならないことは明白だ。
単一民族国家を主張する意味は何だ。単一民族国家だからと言って何もいいことは無いはずだ。百害あって一利無し。人類はホモサピエンス一種しかいない。だからこそ多様性を大事にしないといけないんだろう。
歴史学の認識としては、中国が正しい。中国は南北、東西が別の国であった時期も中国だ。つまり、東アジアと言う括りの中で。アフリカの人達は、実際北京と東京の区別すらつかないのが一般の市民だ。そう考えれば、あまり騒ぎ立てる問題ではなさそうだ。
勿論、日本も韓国も中国の一部ではない。それと同じく、米国の一部でもない。対中従属派はあってはならないのと同様、対米従属もそれ以上にあってはならない。対米独立、対中独立が国是でないと今後の世界を乗り切ることは不可能でしょう。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
ドーピング違反
世界アンチ・ドーピング機関(World Anti-Doping Agency, WADA)は、反ドーピング(薬物使用)活動を世界的規模で推進するために設立された、独立した国際的機関。世界アンチ・ドーピング機構、世界反ドーピング機関とも書かれる。
概要
WADAは、禁止薬物リスト・検査・分析などの国際的なドーピング検査基準やドーピング違反の罰則規定の統一化、アンチ・ドーピング活動に関する教育・啓発活動等を目的として設立された。現在は、スポーツ界だけでなく、各国政府や公的機関とも協力しながら、アンチ・ドーピング活動を行っている。
1968年のメキシコオリンピック及びグルノーブルオリンピックで初めてドーピング検査が実施されて以降、アンチ・ドーピング活動は国際オリンピック委員会 (IOC)の主導で行われてきた。しかし1998年のツール・ド・フランスにおいて、チーム主導による組織的なドーピング違反が複数発覚し、選手・チームスタッフ10名以上がフランス警察に逮捕されたことをきっかけに、翌1999年に、国際オリンピック委員会 (IOC)の主催で行われた「スポーツにおけるドーピングに関する世界会議」において採択された「ローザンヌ宣言」に基づき、1999年11月にWADAが設立された。
それまでIOCが主幹として取り締まっていたドーピング検査はWADAが行うようになり、2003年3月にはIOC医事規程からWADA規程(WADA Code)が正式なルールとして採用されるようになっている。WADAに反発していた国際サッカー連盟 (FIFA) も、2006年6月に、条件付ながらWADAの統一基準受け入れに合意した。
競技者から採取され検体の分析は、WADAが各国において公認する機関(現在は33機関)に委託されており、日本ではLSIメディエンスが唯一の公認機関となっている。なお、公認機関の検査精度などに問題がある場合は、WADAが公認を取り消す場合もある。ドーピング検査は、競技の場で行われるものの他に時間や場所の通告なしで行われる抜き打ち検査がある。プライベートな場で検査を要求される選手側にとっては、不快を感じることやトラブルに発展することもある。
実際にWADA規程に準拠する国際自転車競技連盟 (UCI) の管轄下のレースで抗議行動が起こる事態に発展した。2008年にロードレース選手のケビン・ヴァンインプに対して通常の抜き打ち検査が行われた。しかし、検査が自身の息子の死と重なったことが波紋を呼び、チームメイトと他チームの選手が団結しての抗議行動となった。
2014年12月、ロシアの陸上選手のドーピング疑惑をドイツの放送局が報じたことを受け、WADAは独立委員会を設置した。2015年11月9日、独立委員会は国家ぐるみでロシアがドーピングを行っているという報告書を発表した。報告書には、検査の際前もってコーチや選手に検査が通告されていた、1400件以上の検体が廃棄されていたなど、ドーピング検査の実態が浮き彫りになっていた。この報告書は、モスクワ反ドーピング研究所の公認取り消し、WADAのロシア反ドーピング機関への不適格認定、さらに、世界陸連のロシアへの出場資格停止処分、2018年平昌オリンピックへの参加禁止など波紋を呼んだ。
そもそもドーピングとは何か。阿片などの麻薬が禁止される理由は。ドーピングと言う行為は反社会的な行為なのか。
【ドーピング(doping)】
肉体を使うスポーツおよびモータースポーツの競技で成績を良くするため、運動能力・筋力の向上や神経の大きな興奮などを目的として、薬物を使用したり、物理的方法を採ったりすること、及びそれらを隠蔽する行為を指す。
**そもそも成績を良くするため、ドーピングをやっていて、それで成績が良くなれば何も問題無いはずだ。それが問題なら薬物の入手が出来なくする以外にない→製薬会社が困る。
**試合前にコーヒーやお茶を飲んでカフェインを体に取り入れる行為は、明かにドーピングになるか。眠気覚ましに自分の顔を叩いたり、擦ったりもドーピングだね。隠蔽する必要もないが。
そもそも違法薬物でない限り、誰でも何処でも簡単に入手できる薬剤がほとんど。多くのアスリート達は、その薬の成分も知らずに、製薬会社が書いている効能だけを信じて使っているのだから、選手やコーチ達には防ぎようがない。
**dopeという英語。本来の意味は①マリフアナ、麻薬、②〔スポーツや競馬での違法な〕興奮剤、禁止薬物となっている。ここでは②の意味。①は、スポーツ以外でも別の法律で禁止されているので対象外。禁止薬物とされるには禁止しないと問題が生じることが明確になっているはずで、総ての禁止薬物リストと問題事例が公表されているはずである。一方、大手製薬会社はこのリストから外れるように、化学成分を変えたり、遺伝子組換えの新薬をどんどん開発しているのも現状だろう。
ゲノム編集などによる肉体改造(遺伝子ドーピング)、興奮とは逆に交感神経を抑制して、あがりなど精神的動揺を防ぐ薬物の使用も含まれる。競技力向上を意図しない服薬や飲食物、サプリメントの摂取による「うっかりドーピング」を含めて、オリンピックや競馬など多くの競技で禁止されている。現代では世界反ドーピング機関(WADA)などにより規制と厳重な検査が行われており、発覚すれば違反行為として制裁を科される。
しかし、ドーピング自体の性質からもし、発覚してもアスリートだけに制裁を科されるとすれば、アスリート達にとってはあまりにも不条理な仕打ちであろう。制度自体の見直しが必要な様だ。
ドーピングとはどこまでが許されるか。そもそも論が明確でない状態で検査だけ厳重に行えば不条理な判定が増加するばかり。WADAと言う機構が、特定の国だけを困らせる陰謀団体と化している可能性は無いだろうか。WADAと言う機構に存在意義があるのだろうか。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
孤立主義傾向の進む米国
ロシア軍がウクライナに侵攻した。今後の対応が注目されるバイデン米政権だが、米国の積極的な関与を求める世論は必ずしも高まっていない。大規模な対ロ制裁がガソリン価格の上昇を招き、国内世論の不満につながりかねない恐れもある。中間選挙を控えながら支持率が低迷するバイデン政権にとって、ウクライナ情勢は国内でもリスク要因になりつつある。
「米国民の多くは米国の主要な役割に反対」。AP通信は23日、こう題した記事を配信し、ウクライナ情勢で「米国が主要な役割を果たすべきだ」という回答が26%にとどまったという自社の世論調査結果を報じた。一方、「小さな役割を果たすべき」は52%、「役割を果たすべきではない」との回答は20%だったとか。
そもそも、英国から独立を果たした頃の米国は旧大陸の列強諸国からの干渉を極力排除する孤立主義が本来の姿勢であった。いわゆる「モンロー主義」。ところがこの傾向は、第二次世界大戦を契機に転換。積極外交か。特に英国の覇権を踏襲し、世界に警察官としてやたらと世界情勢に口出しするように。いわゆる単独覇権主義。
以降、世界は大きな戦争は無くなったものの米国が作り出した多くの戦争の被害を受けるようなった。ベトナム戦争、イラク戦争、パレスチナ紛争、アフガン戦争。どれも多くの犠牲を払った割に得たものは何もない。残されたの混乱と破壊だけだった。一体米国の正義は何だったのか。こんな戦争に駆り出されるのは真っ平ごめんだね。国民の多くがアメリカ・ファースト。本来の建国理念に戻ろう。
東西冷戦の時代も終わった。共産主義革命の恐れなくなった。今さらイスラム原理主義とか領土拡張主義とか、わざわざ新たな敵を造る必要はあるの。そんな妄想捨てて自国民の平和と安全に力を集中すべき時だね。本来の米国に戻ろう。大きな流れになればいいね。(2022.2.25)
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
ゼレンスキー
 人気コメディアンから祖国防衛の指導者に、
人気コメディアンから祖国防衛の指導者に、
注目集まるゼレンスキー大統領 ウクライナ 2022年2月27日
スティーヴン・マルヴィー、BBCニュース
2019年4月にウクライナの大統領に当選したウォロディミル・ゼレンスキー氏は、それまで政治経験ゼロの人気コメディー俳優だった。コメディアンとしても人気があったかどうか。あれから3年近くたった今、ゼレンスキー氏は突如、戦時下のリーダーとして説得力のある姿を世界に示している。
ウクライナ出身のフルシチョフやトロキーの名前は知らない人も、ゼレンスキー大統領がウクライナ人ということは知っているだろう。
まさしく造られた英雄だね。誰が作ったか。マスメディア+米国諜報機関。説得力があるとは思えないが、つまりマスメディアの作った虚像。ウクライナ国民を盾にして自己保身に明け暮れしているようにしか見えないけど。祖国防衛の指導者なんて誰が証明できる。これぞマスメディアの作った虚像でしかない。3年前までは国民の融和を唱えていたのが、ロシア国境二州の自治権を剥奪し、二州の政治家達や民衆へのテロ攻撃。民族浄化政策なんか始めてロシアを挑発。明らかに人権侵害を先にしたのはゼレンスキーだった。確かに意図したとおりロシアは挑発に乗ってしまった。メディアのおかげでそこは巧みに隠蔽できた。計画が狂ったのはNATO諸国が派兵してくれなかったことか。
今、テレビやネットの映像はウクライナ発の画像で満杯だ。建物の爆破風景なんかも、どうも空爆ではなく、小型携帯テロ組織用のミサイル兵器でやられたようだ。つまり、ロシア軍ではなくウクライナ民兵(ゼレン子飼いの)の仕業らしい。つまり、映像のかなりの部分は自作自演。ただ、こんな情報発して世界の同情引いても何の足しにもならない。ロシア軍は人民への被害を最小限に食い止めながら、少しずつ包囲の輪を狭めて行く。
原子力発電を攻撃したのは、ゼレンが原発爆破を脅しにして立てこもることを防いだものだろう。相当たくさんの核燃料が保存されているらしい。当然の措置だ。
ゼレンスキーが降伏すれば、ウクライナ国民は解放される。確かに日本だって、なかなか敗戦を認めなかった。昭和天皇の英断は立派なことだ。ゼレンスキーの抵抗は祖国防衛どころか祖国の破壊しかあり得ない。全くの無駄な抵抗だ。メディアは、こういう人を英雄にするのが好きなようだ。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
国際科学技術財団
公益財団法人国際科学技術財団は、科学技術の分野における権威ある国際的な賞「日本国際賞(JAPAN PRIZE)」の顕彰などを実施する公益法人。元内閣府所管の財団法人だったが、公益法人制度改革に伴い、2010年10月1日に公益財団法人に移行。
事業内容
① 日本国際賞による顕彰事業
② ストックホルム国際青年科学セミナーへの学生の派遣や、若手科学者への研究助成などの若手科学者育成事業
③ 一般人を対象としたやさしい科学技術セミナーの開催
何故、ここに注目したか。日本国際賞と言うものの存在だ。PCR法の発明者とされるキャリー・マリス博士の研究に一早く着目し、1992年に彼に日本国際賞を授与したとのことである。つまり、翌年ノーベル賞をもらう直接最大のキッカケを作ったと言う意味が大変大きい。賞金額も相当巨額であったマリス博士も書いている。日本政府は世界に先駆けてマリス博士の偉業を発見したのか?
マリス博士は、その後天皇皇后両陛下(平成天皇)にご進講をする機会を与えられ、その際のざっくばらんな会話が出来たことを楽しいげに自叙伝に記している。
**「マリス博士の奇想天外な人生」キャリー・マリス、福岡伸一訳、早川書房
公益財団法人国際科学技術財団(理事長 小宮山宏)は、本日2022年1月25日(火)、2022年Japan Prizeの受賞者を発表しました。本年の対象2分野について、「物質・材料、生産」分野はカタリン・カリコー博士(ハンガリーと米国)とドリュー・ワイスマン博士(米国)が共同で、「生物生産、生態・環境」分野はクリストファー・フィールド博士(米国)が単独でJapan Prizeを受賞します。
受賞業績は、カリコー博士とワイスマン博士が「mRNAワクチン開発への先駆的研究」、フィールド博士が「観測に基づく先進的な定式化によるグローバルな生物圏の生産力推計と気候変動科学への目覚ましい貢献」です。
科学立国を目指す日本としては、日本国際賞というノーベル賞に匹敵する賞を持つことの意義は大きい。歴史的に凌駕出来ないまでも賞金額で競争は出来る。ただ、日本国際賞の知名度はどう見ても低い。そもそも日本のマスコミがあまり取り上げない。受賞者の選定の過程があまり明確でない。日本独自の視点はどこにあるのか。欧米の権力筋の下請けになっていなことを希望するが。
キャリー・マリス博士は、本人も自叙伝で述べているように、日本国際賞もノーベル賞も晴天の霹靂のようだ。本人もノーベル賞級の研究であることは自負しているものの実際の受賞は不可能と信じていた節もある。つまり国際的な学会の要人たちの支持を得られない。サーファーとしての他、通常の行動が品格不足とのことらしい。
どうやら、キャリー・マリス博士の受賞は、権力側(どうも米国CDC等)の意向のようだ。それは米国流の特許制度が大いに関係している。ノーベル賞は、ポリメラーゼ連鎖反応を実現したこと、つまりDNA断片のコピーの大量生産の方法までだが、特許の方は「感染者ウィルスや感染者の発見が出来る」となっているはずだ。さもないと売れる特許にならない。だからマリス博士の特許はある意味ペテンである。では、マリス博士は犯罪者か? そんなことは無い。特許は科学的に可能であることの証明は問わない。永久運動機間のように科学的に不可能でない限り反証は出来ない。しかし、権力側は「感染者ウィルスや感染者の発見が出来る」ことを既成事実(ノーベル賞の権威)としたいということだろう。医療関係機関の大きな儲け代となるから。更に特許を理由に肝心なところを非公開に出来る。
マリス博士は「感染者ウィルスや感染者の発見に使ってはならない」と言いだした。HIVウィルスがPCR検査で発見されたとニュースに対応してだ。彼は2019年に謎の死を遂げる。翌2020年から、PCR検査は世界の標準として使い回されている。PCR検査陽性者=感染者ということで、検査の拡大が感染の拡大に寄与していることも公然の事実。
カリコー博士の研究も、外部のRNA断片を人体に騙して入れ込むための重要な科学的発見で当然ノーベル賞候補である。しかし、この発見を基にして作られた特許、mRNAワクチンは果たして科学的に妥当かどうか。特許は科学的に積極的な反証が無い限り認められる。彼女にノーベル賞を授与して、mRNAワクチンを正当化しようという意図が丸見えである。
【1993 Japan Prize受賞者】国際科学技術財団
医学における細胞・分子生物技術分野
ポリメラーゼチェイン反応(Polymerase Chain Reaction PCR)の開発
キャリィ・B・マリス博士(米国)(1944年生まれ)アトミック・タッグズ社創立者・研究担当副社長
授賞理由
マリス博士の開発したポリメラーゼチェイン反応(Polymerase Chain Reaction PCR)はその開発以来、分子生物学、医学、また、これらに関連した様々な分野に革命的変革をもたらしてきている。遺伝子解析における最大の問題点は、標的DNA領域がゲノム全体からみるとあまりにも小さいことである。哺乳動物は約10万個の遺伝子を持つと考えられているが、このうちの一遺伝子の動向を理解するためには、遺伝子のクローン化、クローン化したDNAの塩基配列の決定、これらを可能にするための様々な技術の利用など時間的にまた労力的に莫大な努力が必要であった。PCR技術はクローニング技術にたよることなしに、直接ゲノムDNAの解析を可能にすることにより、このような状況を一変してしまったのである。PCRは小量のゲノムDNAから、特定のDNA塩基配列を大量に増幅する技術である。二本鎖DNAを加熱することにより一本鎖とし、得られた各一本鎖DNAに化学合成したデオキシオリゴヌクレオチドをハイブリッド結合させる。熱耐性DNAポリメラーゼの存在でDNAを鋳型としたオリゴヌクレオチドプライマーの鎖の伸長が起こる。この加熱、ハイブリッド結合、プライマー鎖の伸長の過程を繰り返すごとに、DNAコピーが二倍に増えてゆき、30サイクルほどの反応を繰り返すと、二つのプライマーに挟まれた領域のDNA断片が大量に得られる。
PCR技術は、最初にゲノムDNAからβ-グロビン遺伝子の塩基配列を増幅し、制限酵素による切断の有無で鎌状赤血球貧血の診断に応用された。これからもわかるように、PCR技術の医学における波及効果は絶大である。たとえば、遺伝病やがんの原因遺伝子の同定やこれら疾病の診断を可能とし、マイコバクテリアやHIVなど病因となりうる微生物やウイルスあるいは、白血病における残存がん細胞の検出やHLA型の迅速で高感度な検出を可能にするなど計り知れないものがある。この技術は、また進化の研究などにも応用され、例えば、様々な人種のDNA解析からヒトの起源にさかのぼる系統樹の作成を可能にしたり、絶滅した動物の化石や博物館の標本などからのDNAの塩基配列決定を可能にしている。このように極く微量のしかもかなり短くなったDNAも解析可能なことから、犯罪捜査における証拠の提供といった利用もされている。
マリス博士は1966年ジョージア工科大学を卒業後、1972年カリフォルニア大学バークレイ校において生化学の分野での研究で学位を取得している。カンサス大学医学部、カリフォルニア大学サンフランシスコ校でポストドクトラルフェローとして医学生化学の研究に従事した後、1979年、シータス社に移り、そこでPCR技術を開発した。1986年、ジトロニクス社の分子生物学部門の長として転出したが、現在は、アトミック・タッグズ社創立者・研究担当副社長である。
以上のようにポリメラーゼチェイン反応(PCR)の開発に貢献したマリス博士の功績は「医学における細胞・分子生物技術」の分野において、遺伝子解析技術に革新的な進歩をもたらしたものであり、本年度の日本国際賞を受けるのにふさわしいものである。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
台湾独立を支持する?
対中政策を「民主主義対専制主義」と位置づけ、台湾の蔡英文政権を強く支援してきたアメリカのバイデン政権のスタンスを、「冷戦思考」と批判する声があがっている。確かに総ての国を二分して、Aか非A。非Aは敵だとする短絡的な思考は極めて危険な考えだろう。これがファシズムと非難される所以だ。
でも、ロシアを一方的に敵視し、経済戦争を回避して対話による和解を主張する中国まで敵に回してしまったら、台湾の独立をはっきりと表明しないわけにはいかなくなる。米国の世論もそうならざるを得ないし、既にそういう動きもあるようだ。台湾人も7割以上自分達は中国人では無いとはっきりと認識している。
もし、米国が台湾の独立を支持したら日本の人達はどうする。もちろん大歓迎でしょうね。当然中国は怒って、何らかの報復を試みるでしょう。手っ取り早く対象として脅かされるのは日本かも知れない。
でも、現実問題として台湾が独立を宣言すれば、中国は台湾に武力侵攻する? これが「冷戦思考」にとらわれた考えだ。現実問題として台湾は米国寄りとなっているが貿易や人的交流では中国とは既に共存共栄の友好的関係を既に築いている。台湾が独立国となれば米国の関与する余地は寧ろ軽減するはずだ。台湾進攻は中国に何ら経済的な利益をもたらさないし、損失ばかりが目立つ。台湾独立は結果的には、中国も日本も台湾も米国もハッピーとなる最適な選択となるはずである。
つまり、中国が何らかの報復を主張するのは一時的な形づくりということになる。しかし「冷戦思考」、つまり敵を意図的に造り出すための政策としては逆効果。中国も本音は米国が台湾の独立を認めて欲しいというのが本音ではないのか。台湾だっていつまでも中国領でかつ米国の核の傘の下という二重の支配から脱却したい。だから台湾に武力侵攻の警告は、米国に台湾独立を認めさせるための意図的なものだろう。日本のリーダーシップが必要なところだ。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
テキサス州の独立
【アメリカの話題】テキサス州の独立気運が加速する!?
最近の日本の国内ニュースは、いつも同じ内容の繰返しばかりでとてもつまらない。たまには海外からの生の声も聴きたいですね。これは米国発の話。
。:+* ゚ ゜゚ *+:。:+* ゚ ゜゚ *+:。:+* ゚ ゜゚ *+:。:+* ゚ ゜゚ *+:。:+* ゚ ゜゚ *+:。
いつもニューヨーク支店のブログをご覧いただきありがとうございます。ニューヨークは徐々に観光スポットも再開してきております。
皆様が安心してニューヨークにお越しいただけるようになった際に参考になる観光情報や
スタッフの日常生活などの記載を引き続き努めてまいります。
みなさま、こんにちわ。
お元気でお過ごしでしょうか。
今日は「近い将来、ひょっとして独立するかも」と言われているテキサス州のお話をしたいと思います。
 ご存知の通り、アメリカ合衆国は50の州で形成されています。
ご存知の通り、アメリカ合衆国は50の州で形成されています。
各州は、それぞれ独自の州憲法と州政府を中心に運営されており、個々の州が国家に近い形態で、USAという連邦政府に加盟しています。
今、話題となっているテキサス州ですが、もともと独立国家だったという歴史的経緯があります。
メキシコ領からテキサス共和国として独立宣言したのは、1835年。当時のテキサスにはメキシコ人の5倍以上のアメリカ移民が居住しており牧畜業(牛肉となるロングホーン種の育成)で自立していました。
テキサスの独立宣言に対し、メキシコ側は独立を阻止すべく軍隊を派遣。歴史上有名な〈アラモの戦い〉が1836年2月に勃発します。アラモの砦に立てこもった187人の義勇軍は全滅しますが、その後、戦力を整えたサム・ヒューストン将軍率いるテキサス軍が勝利し、
1836年4月、テキサス共和国の独立が実現します。
その後、1845年にアメリカ合衆国の28番目州として併合されますが、合衆国の加入に至るまでに長い議論がありました。最終的には、共和国議会の決議によって承認されますが独立国家継続を主張する勢力も、根強いものがありました。
テキサスに旅行すればわかりますが、テキサス人は今でも独立心が旺盛です。アメリカ国旗に負けないくらい、テキサス州旗が目立ちます。現職の共和党アボット州知事は、民主党新政権が憲法に違反する動き(ワクチンの義務化や言論統制)を見せた場合「保守の砦」として異議を唱える姿勢を明らかにしています。
正義感の強いテキサス気質を考えると連邦政府からの独立も辞さない態度を取ることも十分に考えられます。テキサスが独立すれば、世界の10強に入るほどの国力になると言われています。
あくまで今後の情勢次第なので、どうなるかわかりませんが、アメリカ合衆国とテキサスの将来を見守っていきたいと思います。
Posted by Firebird '21
話題のオンラインツアー!在米30年のスタッフが解説するアメリカ西部開拓史
確かに、今の米国は中国・ロシア顔負けの民主党の超独裁的強権政治が続いているので、独立を盾にした反対運動が起こりうる可能性は零では無いですね。米メディアは完全に民主党翼賛会みたいでこんな情報はなかなか日本のメディアには伝わってこないかもしれませんが。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
核抑止力
核抑止とは、核兵器の保有が、対立する二国間関係において互いに核兵器の使用が躊躇される状況を作り出し、結果として重大な核戦争と核戦争につながる全面戦争が回避される、という考え方で、核戦略のひとつである。核抑止理論や、比喩的に「核の傘」などとも呼ばれる。
核抑止は2つの意味を持つ。元々の意味としては国家間(核保有国と非核保有国)の戦争を核保有国からの核攻撃を避けようとするため戦争が抑止されるもの。もう一つは1960年代以降に確立した、核保有国同士で核兵器の使用による収拾し難い壊滅的な状態を避けようと、互いに核兵器を圧倒的多数保持することで抑止するというものである。
戦争抑止については核兵器保有国と非保有国との間で成り立つと考えられた。これは冷戦初期のアメリカ合衆国のみが核保有国だったころに強い支持を受け、事実、核戦力一辺倒に傾倒し、朝鮮戦争においては兵力に不自由するほどの通常戦力の減勢を行った。
しかし、ソビエト連邦が原爆実験に成功して以降、米ソは核戦争に打ち勝つ(国家を破滅させうるだけの)核戦力を構成することに努力が払われたが、米ソ双方の核戦力が相互の国家を破壊できるだけの質量を整えた1960年代以降は、いかに国家の破滅に至る核の使用をためらわせる軍事的経済的状況を維持するかにシフトした。この状況においては必ずしも戦争の抑止は目的とされず、また戦術分野にカテゴライズされた核兵器の使用を否定することにもならない。
1960年代、早期警戒衛星の配備で、米ソは相手の核ミサイル発射をより早く的確に察知できるようになった。これにより敵の核ミサイルが着弾する前に報復核攻撃を決断することが可能になった。
相互確証破壊(Mutual Assured Destruction、MAD、1965年)は最も知られた核抑止理論で、ロバート・マクナマラによって発表された。元は確証破壊戦略(Assured Destruction Strategy、1954年)に遡るが、先制奇襲による核攻撃を意図しても、生残核戦力による報復攻撃で国家存続が不可能な損害を与える事で核戦争を抑止するというドクトリンである。
核兵器も通常兵器も、軍事力による戦争抑止と言う意味では手段に過ぎないため、手持ちの戦力をいかに有効に抑止力に転化させるかという観点から、核抑止理論も大量報復戦略(ニュールック戦略、1954年)、柔軟対応戦略(Flexible Responce Strategy、1961年)、損害限定(Damage Limitation、1964年)、相殺戦略(Countervailing Strategy、1980年)、戦略防衛構想(Strategic Defense Initiative, SDI、1983年)など、時代や技術の変化を受ける。
ソビエト連邦崩壊の直後からロシア連邦の政治的経済的安定が図られた21世紀までの間に、旧ソビエト連邦の核関連技術の流出があり、さらには米国の一極化への対抗から中華人民共和国が支援した事もあり、北朝鮮、パキスタン、イランにおける核拡散が発生した。これらは従来の米ソ二極対立における核抑止とは別の核保有・核兵器使用の動機となるため、別種の対策が必要となる。
現在、米国で非常に重要視されている問題。国家と違ってテロリストには報復核攻撃されて困る都市がないので、世界最強の米国の核戦力を持ってしても、弱小国家以下の存在であるテロリストが米国や同盟国の都市で核兵器を爆発させることを抑止できないというパラドックスである。核抑止は喪失の脅迫で効果を得るので、喪失するものがない非対称な相手には効きにくいともいわれる。しかし、テロリストといえど帰属する国家や奪還すべき土地が明確に存在する場合、報復核攻撃での放射能汚染は懸念すべき事態であると言える。
核保有国同士が武力衝突を起こした場合、戦況が劣勢となった国が局面の打開を目的として核兵器を使用する可能性は否定できない。しかし問題の核心は軍事的劣勢と自国都市がすでに瓦礫になって失うものがないことにあるため、国家体制そのものが保証されるのであれば使用する可能性は低い。また軍事的に優勢になった国も、核を使用されることを恐れて国家体制を転覆するまでの攻勢は思いとどめる可能性が高い。核保有国同士での全面戦争は現在のところ無く、核抑止が通常兵器による戦争をも抑止している、との考えもあるが、核兵器を含む大量破壊兵器を所有しているのではないかという、アメリカの思い込みを一因としたイラク戦争のような件もあるので、一概に核抑止が通常兵器による戦争をも抑止しているとは言い難い。
ノーベル賞を作ったノーベルは強力な兵器が開発されれば、世界は戦争を諦め平和になるとの考えもあったようだ。ただ核兵器の威力は進化し、例えば北朝鮮やイラン一国が米国に報復攻撃を加えた場合、例え核保有の全体は明かに劣勢でも、ニューヨークやロスなどの大都市を一瞬に破壊できる能力を開発するに至った。また、核保有国の数も大変増えた。その内に小型の核兵器はテロリスト達も保有する可能性すらある。
これは核大国も許容できない事態であり、これ以上核に頼る世界戦略は全く無効ということになる。つまり、どこの国も戦争には核兵器を使えないと証明されたことになり、核廃絶運動への追い風となってはいるようだ。
しかし、圧倒的な核保有を誇っていた米国にとっては由々しき事態とも言えよう。たとえば、対米従属一辺倒の日本は、安全保障は米国の核の傘だより一辺倒。欧州のNATO加盟国も同じだ。しかし、日本が近隣国と紛争を起こして武力衝突になっても、米国は何も支援してくれないということだ。核兵器は使ってはならない。大量破壊兵器は国際法で禁止だ。日本も通常兵器で防戦しないといけない。通常兵器での戦争では米国の優位性は一機に喪失してしまう。つまり、日本を含めG7国は、対米従属一辺倒からロシア、中国、インド、台湾と全方位に友好関係を構築し、バランスのとれた外交を自ら考えて行く必要に迫られる。特に日本は、台湾の帰属問題を抱えている。台湾を中国固有の領土と認める限り、国際法上中国の台湾進攻は合法化され、米国が侵略者となってしまう。つまり、米中対立を続ける限りどこかで米国は台湾の独立を承認せざるを得ないはずだ。これを中国が飲むとしたら、台湾が米国の傀儡政権でないと何らかの形で示さないといけない。さもないと、今のウクライナの様な状態になってしまう。例えば、台湾や沖縄の米軍基地を撤去するなど。日本が対米従属一辺倒の姿勢を変えたことを目に見える形で世界に発信しないといけない。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
人質司法
人質司法:冤罪を生む日本の「人質司法」―村木厚子「改革はまだ道半ば」
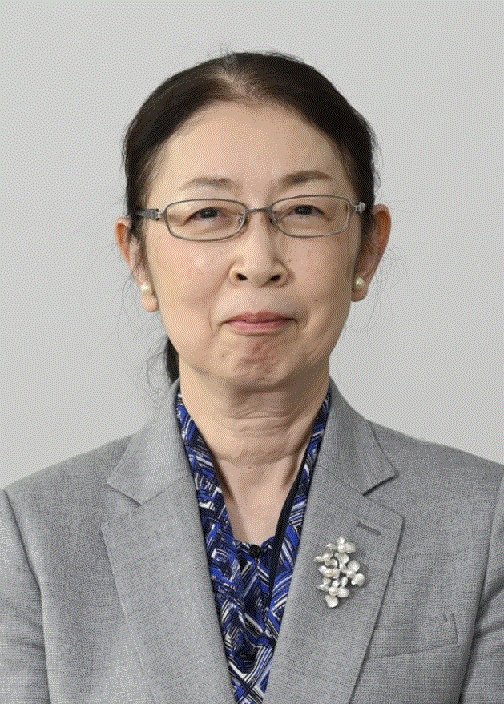 日本の刑事司法は容疑を否認すると保釈が認められない「人質司法」だといわれる。10年前に無実の罪で半年近く勾留された経験を持つ元厚生労働事務次官・村木厚子さんが冤罪(えんざい)事件を振り返り、司法制度改革に残された課題を指摘する。
日本の刑事司法は容疑を否認すると保釈が認められない「人質司法」だといわれる。10年前に無実の罪で半年近く勾留された経験を持つ元厚生労働事務次官・村木厚子さんが冤罪(えんざい)事件を振り返り、司法制度改革に残された課題を指摘する。
カルロス・ゴーン日産自動車前会長の逮捕、長期勾留で、海外から日本の刑事司法制度に対する注目、批判が高まっている。密室での取り調べが連日続き、罪を否認すれば保釈がなかなか認めらない「人質司法」だと、以前から国内外で問題視されてきた。起訴後の有罪率「99.9」%は、冤罪(えんざい)をテーマにしたドラマのタイトルになるほど極端に高い数字だ。
2019年6月には、刑事司法改革の一環として「取り調べの可視化」(=録音・録画)が一部で義務付けられる。一連の改革を生むきっかけとなったのは、10年前、厚生労働省の局長だった村木厚子さんが巻き込まれた「郵便不正事件」だった。近著『日本型組織の病を考える』(角川新書)で事件を振り返り、「改革はまだ不十分」と言う村木さんに話を聞いた。
 無実の証明を阻む3つの障害
無実の証明を阻む3つの障害
2009年6月、村木さん(当時は厚労省雇用均等・児童家庭局長)は、身に覚えのない容疑で大阪地検特捜部に突然逮捕された。04年当時、障害保険福祉部企画課長だった時に、障害者団体をかたる「凛(りん)の会」に対し郵便料金が格安になる障害者用の郵便割引制度を利用できる偽の証明書発行を部下の係長に命じたとするものだ。「凛の会」は制度を悪用して、家電量販店などの商品広告をダイレクトメールで送り利益を得ていた。
取り調べでは、検察官が突きつけてくる調書の筋書きを一貫して否認したが、起訴されて4回目の保釈申請が認められるまで大阪拘置所に164日間拘束された。裁判では取り調べメモを全て廃棄したという検察のずさんな捜査が露呈した。元部下の係長は証人尋問で、村木さんに命じられたとする自分の供述調書は「でっち上げ」で、自分の独断でやったことだと証言、その他の証人のほとんど全てが供述調書の内容を覆した。村木さんは無罪判決を勝ち取り、間もなく取り調べ主任検事による証拠改ざんも発覚し、国を揺るがす大スキャンダルとなった。
「一般市民にとって刑事司法はそれほど関心のない領域かもしれません。私も関心がなかった。何かの事件で容疑者が逮捕されたというニュースを聞けば、悪い人が捕まって良かった、程度の認識でした」と村木さんは言う。「いざ逮捕されて自分の無実を証明しなければならなくなった時、公平な裁判を阻む大きな問題が三つあると実感しました」
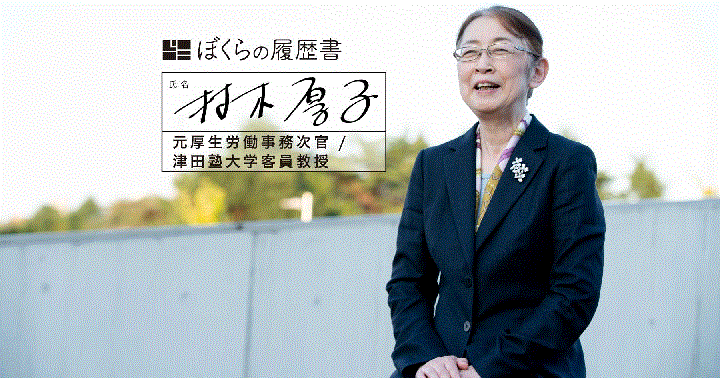 「第一に、取り調べが密室で行われること。そこで私が話したことよりも、その中から検事が取捨選択して紙に記すことが供述調書になり、一番重要な証拠になっていくことです」
「第一に、取り調べが密室で行われること。そこで私が話したことよりも、その中から検事が取捨選択して紙に記すことが供述調書になり、一番重要な証拠になっていくことです」
「第二に、否認をしていると勾留が長引く問題です。罪証隠滅と逃亡の恐れが勾留理由によく挙げられますが、自由を拘束する根拠を厳密に検討するのではなく、罪を否認するとほぼ自動的に勾留が続き、そのこと自体が検察の武器になってしまう。いわゆる『人質司法』です」
「『泊まっていきますか』と聞かれるわけですよ」と言って村木さんは微苦笑を浮かべた。「結局検事の判断で勾留が決まる。それが一種の武器になる。長く拘束されるのが怖くて、検事が望んでいる方向で話してしまえばいい、という誘惑になるのです」
「第三に証拠開示の問題です。家宅捜査ができるのは警察・検察だけなので、重要な証拠は全て検察側が手にしている。その中からどうやって弁護側に必要な証拠を探し出して検察に開示を求めるか、まさに手探りの作業です」
取り調べで許せなかった検事の一言
検察側は、村木さんが2004年当時準備していた「障害者自立支援法案」を国会ですんなり通したいと思っていたことが背景にあるというストーリーを描いていた。自称障害者団体から口利きを頼まれた国会議員からの依頼(=議員案件)で、その議員に気を遣って証明書発行を命じたというものだ。
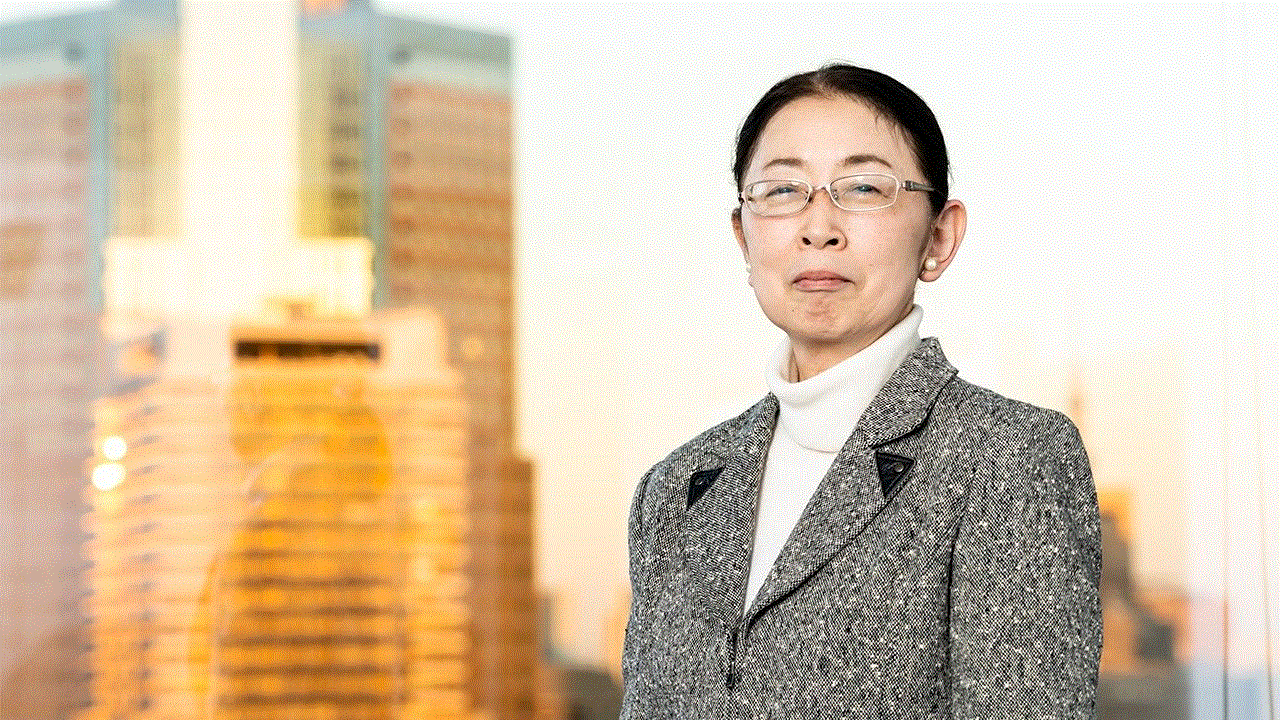 検事の取り調べ中、村木さんがどうしても聞き流すことのできない言葉があった―「執行猶予が付けば大した罪じゃない」
検事の取り調べ中、村木さんがどうしても聞き流すことのできない言葉があった―「執行猶予が付けば大した罪じゃない」
「『大した罪』って何ですかと聞くと「殺人や傷害」と言われたので、思わず『偽の障害者団体の金もうけのために証明書を偽造するような情けない罪を認めるぐらいなら、恋に狂って男を刺し、罪に問われた方がまだましです』と抗議しました」
目の前の小柄で穏やかな村木さんから、そんな激しい表現が飛び出すのは意外に感じるが、心底怒っていたのだと言う。「殺人や傷害はもちろん罪です。ただ、人間だから激情に駆られることもある。個人的には、まだそちらの方が同情できる犯罪だと思ったんです。執行猶予がついても黒は黒。大したことはないという検察の感覚は、普通の人からだいぶずれていると感じました」
検察による証拠隠ぺいと改ざん
「無罪を勝ち取ったのは幸運だった」と村木さんは言う。「弁護団の女性弁護士から、『村木さん、一番暇なのはあなたよ。役所の証明書を出す仕組みは私たちにはよく分からない。自分で調べて、どんなに小さなことでも不自然なことがあれば、全部リストアップして知らせて。裁判に使えるかは私たちが決めるから』と言われました」
大阪拘置所では「本当に暇だった」ので、検察から弁護側に開示された膨大な証拠資料のコピーを必死で読み続けた。その中にあった一通の捜査報告書に目を留める。そこには、証明書が作成された時のフロッピーディスクのプロパティー(文書の作成・更新日時などの属性情報)が記載されていたが、その作成日時は、検察の筋書きと矛盾するものだった。そもそも、検察はフロッピーディスクがあることを隠しており、裁判に使う予定ではなかったにもかかわらず、うっかり報告書を開示してしまったのだ。この発見は、裁判で検察の見立てを崩すのに役立った。後日、フロッピーディスクのプロパティーが、検察の筋書きに合うように書き換えられていたことも明らかになった。
「偽の証明書を作成したフロッピー自体の証拠開示がないことが不自然でした」と村木さんは言う。「取り調べの検事に、証明書を作った時の電子データがあるはずだと何度も尋ねましたが、ないという返事でした」。裁判で検察の立証を阻む証拠としてフロッピーディスクが持ち出されることを恐れ、改ざんした上で、その存在自体も隠蔽(いんぺい)したのだった。
課題を残す刑事司法改革
検事総長が引責辞任をするに至ったこの事件では、最高検察庁が検証結果を公表するが、なぜ無理な供述調書を作り続け、間違いに気付いても軌道修正しなかったのかについての検証はなかった。真相究明のために、村木さんは国家賠償裁判も起こしたが、国はあっさりと原告の賠償請求を認め、裁判を終わらせる。一方で2011年、法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」が設けられ、村木さんは委員の一人として議論に加わることになった。委員の大半は刑事司法の専門家たちだった。
「法制審の議論ですごく違和感を覚えた発言の一つは、『取り調べの録音・録画は治安維持に悪影響が出る』でした。間違った人を捕らえて、真犯人を取り逃がしたとすれば、それこそ治安維持の上で最悪ではないですか」
法制審で決まった刑事司法改革では、取り調べの録音・録画や検察側が証拠の目録を弁護側に開示しなければならないなど、いくつか改善された点はある。だが、「いろいろな意味で課題は残ります。録音・録画も裁判員裁判と検察独自捜査の案件に限られ、参考人の事情聴取も対象になっていません」
弁護士が取り調べに立ち会えないことも、被疑者に不利だ。「取り調べは、プロである検事のリングにアマチュアが上げられて、レフェリーもセコンドもいない状態で戦うようなものです。弁護士の同席が無理なら、せめて調書にサインする時に弁護士に相談できる仕組みを作るべきでしょう」
証拠開示では、検察側に不都合な証拠は開示されにくいのではという懸念は払しょくされず、「人質司法」といわれる身柄拘束に関しても、進展はなかった。村木さんのケースでそうだったように、「逃亡の恐れ」「罪証隠滅の恐れ」があると言えば、裁判所はほとんどのケースでそれを受け入れて勾留を認めている。「身柄拘束には透明性のあるルール作りと、適切に運用する仕組みが必要です」
無理な取り調べをして、過ちに気付いても軌道修正できない検察の「病理」は、日本の組織に相通じるものがあると、村木さんは言う。2018年の財務省による公文書の隠ぺい、改ざんをはじめ、官僚の不祥事が相次いでいる。失敗や間違いが起きたときに「なかったことにする」という組織的な隠ぺい行為は、「建前は守らなければならない」「失敗や間違いは許されない」という意識が生む不祥事だと言う。
「取り調べの録音録画と同じで、外から見える仕組みを作ることが大事です。明確なルールやシステムを作り、情報開示をすること。隠せない仕組みを作ってしまえば、政治家への『忖度(そんたく)』もできないので、役人は精神的に楽になるはずです」
164日の勾留経験を社会活動に生かす
冤罪事件で村木さんを支えたのは、強い家族の絆や無罪を信じる多くの支援者、優秀な弁護団、そして村木さん自身の強い好奇心だ。半年近く大阪拘置所で「未決因13番」として過ごす間、食事のメニューも含めて、ノートに細かく記録した。
逮捕前は仕事で多忙を極めていたが、「あんなに自由時間があったのは初めて。仕事しなくていいし、家事もない、食事は3度出てくるし、洗濯もやってくれる。3畳程度の部屋の掃除はすぐに終わってしまいますし」
裁判に備えながら、推理小説など差し入れられる本を読みまくり、その数は150冊におよんだ。もちろん、拘束され、管理される生活はつらいことも多かった。好きな時間に横になれないし、真夏の堪えがたい暑さの中でも、体を拭くことは決められた時間内でしかできない。
だが、ルールはルールと割り切って従い、周囲を観察し続けた。一番気になったのは、刑務作業として食事や洗濯物を運ぶ女性受刑者が、みんなあどけなさの残る若い女性たちだったことだ。取り調べを受けていた時、検事に「あの子たちはどうしたの?」と聞くと、「薬物が多いですね。売春もいます」という返事だった。
復職後に担当した自殺対策や生活困窮者支援の仕事を通じて、貧困、虐待、性的暴力など、厳しい家庭環境に置かれた少女たちの多くが居場所を失い、性産業に取り込まれてしまう実態を知った。厚生労働事務次官を経て2015年に退官、翌年、作家で尼僧の瀬戸内寂聴さんらと共に「若草プロジェクト」を立ち上げ、「生きづらさ」を抱える少女たちの支援活動を行っている。自分たちが悪いと思い込み、人に助けを求めることもできず、公的支援の手が届かないところにいる少女たちだ。LINE相談やシェルターの運営、研修の実施のほか、支援企業の開拓などを行っている。
164日間の勾留経験を社会活動に見事に昇華しましたねと言うと、軽やかな笑い声を挙げた。「公務員だった時は、役所として何ができるか、どういう制度を作れるかを検討することが仕事でした。役人を辞めたので、制度作りとは離れたところで、いろいろな活動が自由にできる。もちろん、いつか制度につなげられればいいと思っています。今の私は少しずつ、頭が自由になっていくプロセスにいます」
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
サッコ・ヴァンゼッティ事件
サッコ・ヴァンゼッティ事件(Sacco and Vanzetti)は、1920年にアメリカ合衆国のマサチューセッツ州で発生した強盗殺人事件。
 概要
概要
1920年4月15日にアメリカのマサチューセッツ州で強盗殺人事件が発生した。その後イタリア移民でアナーキストのサッコとヴァンゼッティ2名が逮捕され、その後の裁判で死刑宣告されたが、当初から偏見による冤罪との疑惑があり、アメリカ国内のみならずイタリアをはじめとするヨーロッパなど各地でデモが行われるほどの大きな問題となった。
しかし1927年に死刑執行された。後に調査をおこなった行政側は1977年に冤罪であったと認定したが、司法側は冤罪を認めていない。事件は、アメリカ合衆国の歴史上の汚点とも呼ばれている。
強盗発生と逮捕
1919年に1件目の強盗事件。製靴工場の現金輸送車が襲撃されたが失敗に終わっている。翌年の1920年4月15日に2件目の強盗事件が発生。マサチューセッツ州ブレインツリー市で別の製靴工場が5人組のギャングに襲撃され、会計部長とその護衛が射殺されたほか、16,000ドルが強奪された。
翌月の5月5日、この強盗殺人事件の容疑者として共にアナーキストのイタリア移民の製靴工ニコラ・サッコ(Nicola Sacco、1891年4月22日 - 1927年8月23日)と魚行商人バルトロメオ・ヴァンゼッティ(Bartolomeo Vanzetti、1888年6月11日 - 1927年8月23日)が逮捕された。
 裁判
裁判
1921年7月14日、マサチューセッツ州ボストン郊外のデッダム裁判所はこの容疑者二名に死刑判決を下した。有罪判決から3ヵ月後、公正さに欠ける審理に抗議する動きがボストンに留まらず、ニューヨークをはじめ暴動がアメリカ国内各地で起きた。
更に共産主義者やアナーキストがイエロージャーナリズムを使い巻き起こした暴動は、ヨーロッパや南アメリカをはじめ各地で起こった。そのため死刑は確定していたものの執行は長く延期となっていた。しかし、弁護側の裁判やり直しの申し立てはことごとく却下され、マサチューセッツ州知事も特赦を拒否した。
処刑
1927年4月9日、州知事は特別委員会を設置したが、国際的な助命嘆願を棄却。委員会は判決を支持し死刑判決が再度確定した。8月23日、マサチューセッツ州ボストン郊外の刑務所で0時19分にサッコが、続いて0時27分にヴァンゼッティが電気椅子で処刑された。
この日、2人が収容されていた刑務所は彼らの処刑に抗議する群集の襲撃を恐れてサーチライトが輝き、機関銃と共に警官隊が警備に就いた。同じ頃、ボストン市内の留置場には処刑に抗議した作家のドス・パソス、ドロシー・パーカー、女流詩人のE・V・パーカーが留置されていた。有罪判決に対する抗議行動には多くの知識人が参加し、アナトール・フランス、アルバート・アインシュタイン、ジョン・デューイなどが支援した。
裁判詳細と時代背景
サッコとヴァンゼッティの2人は、共にイタリア移民のアナーキストで、第一次世界大戦中はそろってアメリカの徴兵を拒否している。実際には、警察は明確な物的証拠がないまま2人を検挙し、2人を有罪とする明確な物的証拠はほぼ無い。事件当時の検事は偽の目撃者を雇って法廷で証言させたといわれる。
さらに強盗事件の真犯人は誰だかわかっていないし、誰も再捜査をしようとしなかった。また5人のうちほかの3人のギャングメンバーも誰だか不明のまま裁判は終了した。
第一次世界大戦後の不景気で労働紛争が熾烈化していたアメリカでは、社会不安の原因を過激分子になすりつけ、共産主義に対する憎悪を募らせていた。ボストンでは特にその傾向が強く、裁判では2人の前歴とアナーキストという点が、2人の思想を嫌う裁判長と陪審員に誤った予断を抱かせ、死刑判決が出されたといわれる。
冤罪確定
死刑執行の50年後にあたる1977年7月19日、マサチューセッツ州知事のマイケル・デュカキスは、この裁判は偏見と敵意に基づいた誤認逮捕並びに冤罪であるとして2人の無実を公表、処刑日にあたる8月23日を「サッコとヴァンゼッティの日」と宣言した。なおアメリカの世論が右傾化するたびに歴史修正主義者から、2人は本当に冤罪だったのか、などの異論が出されてきた。
**********************************************************
 サッコ・ヴァンゼッティ事件
サッコ・ヴァンゼッティ事件
この事件の話は昔、大学の何かの講義で聞いたことがある。大変有名な事件らしい。「明確な証拠無き者は無罪、古代バビロニアでも秦の始皇帝の法家思想にもきちんと含まれている」はずなのに。遅きに失したとはいえ冤罪は確定したと思いきや、未だに異論があるらしい。しかし裁判官に偏見と敵意があれば誰でも有罪に出来るというのは困りものでは?
日本でも、毒入りカレー事件の林眞須美さん。どう見ても冤罪っぽいね。確たる証拠が無いようだ。
それと、今はやりのDNA鑑定、PCR検査の生みの親マリス博士によるとかなりの確率で冤罪を生み出してしまう可能性があるとか。そもそもPCR検査で犯人を特定することは不可能なことらしい。
しかし、三権分立が確定しており政治家の判断に拘る必要のない裁判官が何故有罪判決に拘る必要があるのだろう。この件も行政サイドは冤罪を認めているのに司法サイドは未だ納得していないらしい。つまり、事件は終わっていない。
***死刑台のメロディ:
死刑台のメロディ(原題:Sacco e Vanzetti、米国ではSacco and Vanzetti)は1971年のイタリア・フランス合作映画。なるほど、映画にもなっていた有名な事件だったんだ。
1920年のアメリカ合衆国・マサチューセッツ州で実際にあったサッコ・ヴァンゼッティ事件を正面から描いた史実的社会派ドラマである。アメリカ史の汚点的冤罪事件として語られる事件をジュリアーノ・モンタルド(イタリア語版)監督が映画化。イタリア移民のサッコとバンゼッティがいわれなき死刑を受けるまでを描いている。主題歌『勝利への讃歌』(エンニオ・モリコーネ作曲)を社会派の歌手であるジョーン・バエズが担当したことも話題となった。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
アゾフ大隊
 アゾフ大隊
アゾフ大隊
アゾフ特殊作戦分遣隊、アゾフ分遣隊、アゾフ連隊(ウクライナ語: Полк Азов)、アゾフ大隊(2014年9月まで)、または単にアゾフは、アゾフ海沿岸のマリウポリを拠点とする元準軍事組織、現在はウクライナ内務省管轄の国内軍組織である国家親衛隊に所属している組織。数年前まで極右・右翼やネオナチ、ナショナリストとして報じられていた。
**組織自体は今でも全く何も変割らず健在のようだ。
 2014年3月に制定された国家親衛隊法によりウクライナ国内軍を改編して創設された。現在は、ウクライナ国家親衛隊の東部作戦地域司令部第12特務旅団所属のアゾフ特殊作戦分遣隊(通称: アゾフ連隊)となっている。アゾフ海沿岸地域のマリウポリを拠点とする。
2014年3月に制定された国家親衛隊法によりウクライナ国内軍を改編して創設された。現在は、ウクライナ国家親衛隊の東部作戦地域司令部第12特務旅団所属のアゾフ特殊作戦分遣隊(通称: アゾフ連隊)となっている。アゾフ海沿岸地域のマリウポリを拠点とする。
国家親衛隊の任務は、国民の生命と財産の保護、治安維持、対テロ、重要施設防護等を主な任務とし、ウクライナ軍と協力しての軍事作戦による武力侵略の撃退、領土防衛等も実施する事となっている。
 2014年5月の創設当初は義勇兵部隊であったものの、ドンバス戦争で対親露派・分離主義者の戦闘で名をあげ、ドンバス危機以降の11月からは国家警備隊として機能するようになり、2014年11月11日のウクライナ内務大臣アルセン・アバコフの署名によってアゾフ大隊は正式にウクライナ国家親衛隊に編入された。義勇兵は黒い制服を着用することがあり、それ故「メン・イン・ブラック」(ロシア連邦側の武装集団「リトル・グリーンメン」に対抗したもの)という異名を持つ。
2014年5月の創設当初は義勇兵部隊であったものの、ドンバス戦争で対親露派・分離主義者の戦闘で名をあげ、ドンバス危機以降の11月からは国家警備隊として機能するようになり、2014年11月11日のウクライナ内務大臣アルセン・アバコフの署名によってアゾフ大隊は正式にウクライナ国家親衛隊に編入された。義勇兵は黒い制服を着用することがあり、それ故「メン・イン・ブラック」(ロシア連邦側の武装集団「リトル・グリーンメン」に対抗したもの)という異名を持つ。
初代司令官は当時、以前、社会民族会議に参加し、当時「ウクライナの愛国者党」を率いていたアンドリー・ビレツキー(2014年5月から10月)。2022年3月現在の司令官はデニス・プロコペンコ少佐である。
 --------------------------------------------
--------------------------------------------
どうやら、この軍組織がゼレンスキーを支持するウクライナ最大の部隊のようだ。だから、ロシア軍がキエフから東部に戦線を移した理由だろう。
ウクライナが極右・右翼やネオナチに支配されていると言ったプーチン氏の主張の根拠がこれか。当初対露宥和を公約していたゼレンスキーが、突如ロシアと全面対決の姿勢に転換したのもアゾフ連隊との対話以降とのこと。
 どうやら、この写真を見る限り、彼等の理想がナチスの再興を目指している可能性は否定できそうもない。この鍵十字の旗。ウクライナの大富豪オルガルヒや米国からも多大な援助を受けているようだ。
どうやら、この写真を見る限り、彼等の理想がナチスの再興を目指している可能性は否定できそうもない。この鍵十字の旗。ウクライナの大富豪オルガルヒや米国からも多大な援助を受けているようだ。
西欧では、独仏の指導でナチズムは悪として否定されているが、ソ連圏に属していた東欧諸国では、共産主義に変わる集団主義として未だに根強い人気があるかのようだ。
ゼレンスキー大統領は、自らがユダヤ人であることを理由に、ナチスとの関係を懸命に否定しているが、オルガルヒ達の中も米諜報機関の中にもユダヤ人は多数いる。つまり、世俗的ユダヤ人と言われる人々。ユダヤ教の信者でなければナチスと組むことはいとも容易だ。ヒットラー自身ユダヤ系の血を引いている。このあたりが日本人は騙される。
**これで、ロシアがキエフを一旦退いて、東部戦線に矛先を転化した理由も明確だ。アゾフ大隊を殲滅しない限りウクライナの解放は無い。アゾフ大隊がなくなればゼレンスキーは停戦に応じるしかなくなる。逆にG7側にとっても東部戦線は生命線だ。喉から手が出るほど軍事進攻したいはず。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
過激派の巣窟
国際政治学者の六辻彰二氏がウクライナ民兵組織アゾフ連隊に欧米各国からネオナチや極右参加を指摘! 捕虜虐殺しながら国防軍に編入、現在、民間人訓練で「総力戦推し進める主体」! 記事公開日:2022.3.18 テキスト(文・IWJ編集部 文責・岩上安身)
特集 ロシア、ウクライナ侵攻!!
2013年1月28日に岩上安身がインタビューを行った国際政治学者の六辻彰二氏が、2022年3月5日記事で、ウクライナが呼びかけた国際義勇兵が「過激派の巣窟」になるという欧米各国の懸念を指摘した。
岩上安身によるインタビュー 第266回 ゲスト 六辻彰二氏 2013.1.28
2014年のクリミア危機から、ウクライナでは「アゾフ連隊」などの極右ネオナチ民兵組織に、欧米各国から極右の活動家などが続々加わった。六辻氏は、彼ら民兵の捕虜虐殺等の戦争犯罪や、ウクライナ国防軍編入後もナチスを賞賛するなどの問題を指摘する。
彼ら民兵組織は、海外の白人至上主義者が献金で支え、ウクライナ政府は黙認状態である。しかもロシアの侵攻後、彼らは民間人に訓練を行い、「総力戦を推し進める主体」になっているという。こうしたことは、日本の大手記者クラブメディアはまったく報じようとしない。
ウクライナの「義勇兵」の問題を検証せずに、「この戦いはネオナチとの戦いである」などのロシアの主張を「偽情報」と決めつけるわけにはいかないだろう。
確かに、ゼレンから送られてくるSNSのキエフ民間人殺害に記事を見れば、殺人犯はイスラミック・ステートと同じような過激な思想の持ち主としか考えられないだろう。つまり、画像から判断して、自分達の主義に従わないものは無差別に殺害して良い。
明かに、ロシアの正規軍ではなくゼレンスキーを支援する過激派民兵の仕業としか言いようがなさそうだ。米国の諜報機関は、この事実を知りつつ米政府には隠蔽している。
民兵に海外活動家が続々参加! 捕虜虐殺や、国防軍編入後にナチス賞讃! 白人至上主義者が献金し、ウクライナ政府は黙認!
岩上安身が2013年に、アルジェリアの人質事件についてインタビューを行った国際政治学者の六辻彰二氏が、2022年3月5日付けヤフーニュースに、ウクライナが呼びかけた国際義勇兵に対して、各国政府が「過激派の巣窟」になると警戒している、という個人記事を掲載した。
「『義勇兵』はすでにいた」! 国際政治学者の六辻彰二氏がウクライナ民兵組織アゾフ連隊に欧米各国からネオナチや極右参加を指摘! 捕虜虐殺しながら国防軍に編入、現在、民間人訓練で「総力戦推し進める主体」! 2022.3.18
2013年1月28日に岩上安身がインタビューを行った国際政治学者の六辻彰二氏が、2022年3月5日記事で、ウクライナが呼びかけた国際義勇兵が「過激派の巣窟」になるという欧米各国の懸念を指摘した。
岩上安身によるインタビュー 第266回 ゲスト 六辻彰二氏 2013.1.28
2014年のクリミア危機から、ウクライナでは「アゾフ連隊」などの極右ネオナチ民兵組織に、欧米各国から極右の活動家などが続々加わった。六辻氏は、彼ら民兵の捕虜虐殺等の戦争犯罪や、ウクライナ国防軍編入後もナチスを賞賛するなどの問題を指摘する。
彼ら民兵組織は、海外の白人至上主義者が献金で支え、ウクライナ政府は黙認状態である。しかもロシアの侵攻後、彼らは民間人に訓練を行い、「総力戦を推し進める主体」になっているという。こうしたことは、日本の大手記者クラブメディアはまったく報じようとしない。
ウクライナの「義勇兵」の問題を検証せずに、「この戦いはネオナチとの戦いである」などのロシアの主張を「偽情報」と決めつけるわけにはいかないだろう。
民兵に海外活動家が続々参加! 捕虜虐殺や、国防軍編入後にナチス賞讃! 白人至上主義者が献金し、ウクライナ政府は黙認!
米国務省がアゾフ連隊を「ナショナリストのヘイトグループ」と呼び、NATOも外国人戦闘員のリスクを調査! にもかかわらずロシアの主張を「偽情報」と決めつける危険!つまり、米国はこの事実を知りつつ関係国には「偽情報」として否定し続けて来た。
「2014年のクリミア危機をきっかけに、ウクライナでは祖国防衛を掲げる民兵がロシア軍と戦闘を重ねた」「その代表格であるアゾフ連隊には、欧米各国から活動家が次々と加わり、その数は2015年段階で総勢1400人にも及んだ」「クリミア危機の後も、東部ドンバス地方ではロシアに支援される分離主義者とウクライナ側の戦闘が断続的に続き、アゾフなどはその最前線に立ってきた」「そのなかでアゾフなどの民兵には、捕虜の虐殺といった戦争犯罪が指摘されてきた」。
「クリミア危機後、アゾフなど民兵はウクライナ国防軍に編入された」「ところが、国防軍の一部となりながら、アゾフはナチスを賞賛する一方、人員のリクルートや訓練を独自に行なってきた」「資金面でも、アゾフには仮想通貨などを用いた海外の白人至上主義者などからの献金が集まってきた」「歴代のウクライナ政府は、ドンバスの分離主義者やロシアに対抗する必要から、アゾフの民兵組織を積極的に活用して来たようだ。
このほかにも、アゾフがヘイトメッセージや陰謀論を振り撒き、白人極右を惹きつけてきたことや、テロ組織との関わり、米国務省からも「ナショナリストのヘイトグループ」と名指されていることなどを指摘している。
また、現在ウクライナ国内で民間人に訓練を行っているのもアゾフで、六辻氏は「総力戦を推し進める主体となっている」と分析している。
一方、六辻氏は、「今回の当事者の一角を占めるNATOも2017年の時点で、シリアとウクライナに共通する現象として外国人戦闘員を取り上げ、その安全保障上のリスクに関する調査・研究を行なってきた」ことも明らかにしている。
こうした指摘があるにもかかわらず、西側のメインストリームメディアは「ウクライナ東部の住民虐殺は事実ではない」というウクライナの主張だけをもとに、「東部のロシア系住民を保護する」「ウクライナは住民を『人間の盾』にしている」「この戦いはネオナチとの戦いである」「ウクライナを非ナチ化する」といったロシアの主張を検証することもなく、一方的に「偽情報」「フェイクニュース」と決めつけている。
しかし、世の中声を大にして「偽情報」「フェイクニュース」と決めつけて、SNSを流し続ける側が大体は大嘘つきであることが常例となっているだ。ニュースは裏を取って読めだ。
こうした事実を無視する状況は、非常に危険である。結果はいつも予想を裏切る。
→でも、西側諸国は何故そうするか? それが、米国政府の意図で対米従属を維持するために必要と思っているから?でも、本当にこれが米国の意図か?
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
膨大な量の嘘
ウクライナのゼレンスキー大統領がロシアの軍事侵攻後、国連の安全保障理事会で初めて演説し「ロシア軍と彼らに命令した人物はウクライナでの戦争犯罪について、直ちに裁判にかけられなければならない」と訴えた。(4/6)
今、米英がロシア制裁を声高に主張するのはこのゼレンスキーがSNSで流す情報のみで、ロシア軍がウクライナ民間人を虐殺したとされる証拠は全くない。証拠も全くない段階にて制裁を声高に主張する英米の主張は全くの虚偽で、これでは世界の人達の信用を得ることは全く無理だ。少なくとも現時点でのこの犯罪にロシアが関与しているという証拠は全くない。
① そもそも、殺害された民間人は総てが親ロシアか中立の人達ばかりで、ゼレンスキーのシンパが含まれていないのは何故か。ロシア軍兵士の多くの者は、ウクライナ解放を目指したウクライナ人のはずなのに、このような暴挙を企てる動機は全くない。だから、プーチン氏の支持率は異常に高い。
② 一方の、ゼレンスキー陣営では、周囲をロシア派や中立の市民達に囲まれており、自己保身の為、ウクライナ市民を平気で虐殺する動機は十分すぎるほど存在する。
③ ゼレンスキーを守る国軍の主体は、アゾフ連隊という海外からの義勇兵の部隊で、ゼレンスキー氏自身が既にかれらの傀儡化しているようだ。
④ ゼレンスキーが流す情報は、総てSNSからのもので、その真偽は著しく疑わしい。つまり、送られて来た情報は総て自作自演で画像を子細に見ればどう見ても怪しげなものばかりである。
⑤ ウクライナ政府(アゾフ政府)は、ウクライナ市民達にゼレンの味方を示す青の腕章をつけることを義務付けていたとか。ロシア軍が来たらその腕章をロシア側であることを示すために白の腕章に付け替えるように指示していたらしい。
ロシア軍が引き上げた途端に多くの虐殺事件が発生した。死体には白い腕章がまかれていたとか。(あるSNS画像分析者の証言)
⑥ 虐殺死体は検死も行われず、ウクライナ政府の手によって埋葬されている。つまり、証拠隠滅。ロシア軍の仕業とする冤罪は永遠に解決されない。つまりゼレンスキーが主張するように裁判にかけたくても全く証拠が無いことに。SNSの画像はフェイクかも知れないが本当の部分もあるかも。
⑦ なぜ、ロシア軍は何故、一旦キエフから退いたか。その際、市民に食料を配給していたとか。その配給袋(緑色)を受け取った市民は虐殺の対象となったらしい。つまり、プーチンさんは騙された。多分、ゼレンスキーは既にキエフにはいないのではないか。
英米の諜報機関に匿われていて安全な場所からSNS発信をしている可能性もある。
⑧ ゼレンスキーを失えば、ウクライナには正当な権力は不在となってしまう。つまり、国民の総選挙で大統領を選び直すことに。それでは、親ロ政権になってしまう。これ以上の戦争の長期化はごめんだ。
だから、米英諜報機関にとっては、ゼレンスキーを死守する必要がある。戦争の長期化を試みる必要があるようだ。
米英諜報機関がやっていることは、ある意味諜報機関としては定石的な手法だ。
① イラクに大量破壊兵器の所持の濡れ衣を発信し、無理やり戦争を起こした。
② 満州鉄道を自ら爆破して、中国側の責任にして戦争を仕掛けた。
③ 広島、長崎は純粋の軍事施設だとの報告を上げ、トルーマン大統領に原爆を落とさせた。
④ 国会議事堂に火をつけて共産党の責任とした。
ロシア軍によるウクライナ民間人を虐殺は、明かに虚構の産物だ。G7以外の国は当然もう気がついている。虚構の産物と知りつつ騙された振りをして行う外交と、騙された馬鹿が行う外交は一見似ていても全く異なったものになるね。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
ピザゲート
ピザゲート(Pizzagate):
2016年アメリカ合衆国大統領選挙の期間中に広まったフェイクニュースで陰謀論の代表例とされている。民主党のヒラリー・クリントン候補陣営の関係者が人身売買や児童性的虐待に関与しているというフェイク情報。
 2016年秋、ヒラリー・クリントン候補陣営の選挙責任者であったジョン・ポデスタの私的なメールアカウントがフィッシングの被害に遭いハッキングされ、メールがウィキリークスに公開された。このメールに、アメリカ国内の複数のレストランや民主党の上級関係者が、ワシントンD.C.にあるコメット・ピンポンというピザ店を拠点とした人身売買や児童買春に関わっていることを示唆した内容が含まれている主張が流布した。
2016年秋、ヒラリー・クリントン候補陣営の選挙責任者であったジョン・ポデスタの私的なメールアカウントがフィッシングの被害に遭いハッキングされ、メールがウィキリークスに公開された。このメールに、アメリカ国内の複数のレストランや民主党の上級関係者が、ワシントンD.C.にあるコメット・ピンポンというピザ店を拠点とした人身売買や児童買春に関わっていることを示唆した内容が含まれている主張が流布した。
児童虐待に絡めた偽物語は求心力が強く、オルタナ右翼やクリントン陣営を疎ましく感じる者によって疑惑は4chanや8chan、Twitterなどインターネット上で拡散され、疑惑をまともに信じた男が実際にピザ店にライフルを持って押し入り発砲する(「子供達を解放せよ!」)という事態に発展した。ピザ店の地下に子供達が監禁されている当時実はなく、そもそもその店には地下室さえなかったという極めてお粗末な結論に。
****************************************************
これだけでは、単にフェイクニュースを信じた大馬鹿が裏も取らずに単細胞的に行動したという超愚劣な事件で「お終い」のはずだが。今の米国が自己の政策をアピールするより相手候補のネガティブキャンペーンばかりに熱心。でも、こんなことを真に受ける米国人のメディアリテラシーもかなりお粗末な気もするが。
ピザゲートは一般的に、Qアノン陰謀論の前身と見なされている(誰がそんな勝手な推測を)。ピザゲートは主にQアノンによって、偶然選挙の年である2020年に再び流行した。
2016年に、大統領選挙でヒラリー・クリントン陣営の選挙責任者であったジョン・ポデスタの私的な電子メールがウィキリークスに流出すると、そのメールを読んだ一部のインターネットの利用者は、メールの中に小児性愛や人身売買を示唆する暗号が含まれていると推測した。
その後こうした仮説は Godlike Productions という掲示板に投稿され、翌日には4chanの書き込みを典拠としてYour News Wireというニュースサイトに取り上げられた。Your News Wire の記事はドナルド・トランプ候補を支持するウェブサイトによって拡散された。そのうち、 Conservative Daily Post というサイトでは、FBIがこの陰謀論を正しいと認めたという虚偽の見出しがつけられた。
あくまでも推測と言う前提で発信している点では、表現の自由かも知れないが、特定の個人を誹謗中傷することになるので損害賠償の対象となる明かな違法行為だろう。ただネット社会では発信者の特定が難しい点が問題だ。
 コメット・ピンポン
コメット・ピンポン
コメット・ピンポン(Comet Ping Pong)は、ワシントンD.C.のコネチカット通りにあるピザレストラン(ピッツェリア)がある。店主のジェームズ・アレファンティスは熱心な民主党支持者であり、バラク・オバマやヒラリー・クリントンの選挙資金集めに協力していた。ポデスタの流出したメールの中にコメット・ピンポンやアレファンティスの名前が挙がっていたために、疑惑の標的になったとされる。全く迷惑な話だ。
ソーシャルメディアでの拡散
Twitterと4chanの利用者は、性的な人身売買を示唆する言葉を食べ物関連の言葉に言い換えた「暗号」がポデスタのメールに含まれていることを見つけ出したと主張した。例えば、ある4chanの投稿者は、"cheese pizza" という言葉は "child pornography"(児童ポルノ)とイニシャルが同じであるため、児童ポルノを示す暗号であると主張。また彼らは、大統領選挙の直前に「インターネットの主流」でこの疑惑はすでに広まっており、Redditで疑惑の「証拠」となるものが投稿されていたとしている。そのRedditの投稿は11月4日から21日の間に削除されたが、ワシントンD.C.にあるコメット・ピンポンというピザ屋の関与を疑う内容のものであった。
11月7日にTwitterで初めて #pizzagate というハッシュタグのついたツイートが投稿され、その数週間後には毎日膨大な数のピザゲートに関連するツイートやリツイートがされるようになった。しかし、エロン大学のジョナサン・オルブライトによれば、ピザゲート疑惑を支持するツイートは異様にチェコやキプロス、ベトナムからの書き込みが占める割合が高く、頻繁にリツイートするアカウントの中にはボットのものもあるという。
**フェイク投稿に対していちいち発信源を特定する意味あるのかね。
"/r/The_Donald" というトランプを支持するRedditのコミュニティのメンバーは "/r/pizzagate" という陰謀論を拡大するためのコミュニティを作成したとの推測も。このコミュニティは、疑惑に関連する人物の個人情報が投稿されていたことから、Redditの規約違反のため2016年11月23日に削除された。その後、VoatというRedditに似たサービス上で議論が続行された。
疑惑の支持者の一部(デイヴィッド・シーマンや後述するマイケル・フリン・ジュニア)は、ピザゲートをさらに拡大して "Pedogate" なる疑惑を提唱した。彼らの説によれば、新世界秩序の「悪魔的なエリート集団」が世界的に性搾取目的での人身売買を行っているという。
トルコでは、新暁新聞などレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領を支持する政府寄りの新聞によって疑惑が取り上げられた。疑惑はエクシ・ソズリュックや HaberSelf といった誰もが書き込めるウェブサイト上で拡散され、政府寄りの報道機関によって転載された。政府寄りの報道機関がピザゲートの疑惑を強調するのは、2016年3月にトルコで実際に起こった児童虐待スキャンダルから話題をそらすためではないかと、The Daily Dotのコラムニスト Efe Sozeri は推測している。
それで、米国政府はトルコ政府にきちんと疑惑解明について抗議したのか?まさか、SNSでトルコ政府を攻撃させた?
ピザ店への嫌がらせ
Comet Ping Pong sign
コメット・ピンポンは、陰謀論を信じる者からの多数の脅迫にさらされた。疑惑が広まるにつれて、人身売買の拠点となっていると見なされたコメット・ピンポンは、疑惑を信じる者から多数の脅迫を受けるようになった。店主のジェームズ・アレファンティスは「とんでもない、でっち上げの陰謀論のせいで、我々は常に攻撃にさらされることになった。私は何日間も何もできていないが、早くこの状況を片付けて、恐怖にさらされている店のスタッフや友人を守りたい。」とニューヨーク・タイムズの取材に答えた。
一部の支持者はアレファンティスのInstagramのアカウントを特定し、そこに投稿されていた写真のいくつかをピザゲートの証拠であるとした。店の従業員や店主はソーシャルメディアから嫌がらせと脅迫を受け、特に店主は死の脅迫を受けた。ピザ店のYelpのページは、陰謀論関連のニュースに影響されたレビューが多数書き込まれたため、書き込みができなくなった。
ピザ店では幾つかのバンドがよく演奏を行っていたが、そのバンドも嫌がらせを受けた。Heavy Breathing というバンドの Amanda Kleinman は、Twitterに疑惑と彼女を結びつけるリプライを送られた後、アカウントを閉鎖した。Sex Stains という別のバンドはYouTubeに投稿した動画のコメント欄を閉鎖した。店に壁画を展示していた芸術家の Arrington de Dionyso は、自らが受けた嫌がらせについて詳細に語り、「これは意図的な攻撃だと思う。それもあらゆる表現の自由に対する仕組まれた攻撃だと思う」と主張した。
Storefront of bookstore Politics and Prose
嫌がらせは、コメット・ピンポンのみならず、その周辺にある別のレストランや商店にも及んだ。コメット・ピンポンの3軒隣にある Besta PizzaやLittle Red Fox、著名な書店である Politics and Prose 、ビストロの Terasol などが被害に遭った。これらのレストランや商店は、脅迫や威嚇の電話を大量に受け、またネット上でも嫌がらせを受けた。
ワシントンD.C.市内の商店だけでなく、ニューヨーク市ブルックリン区のレストラン Roberta's も、従業員に危害を加えるという脅迫を含んだ嫌がらせの電話を受けた。このレストランが疑惑に巻き込まれたのは、ソーシャルメディアでの疑惑を伝える書き込みを使用したYouTubeの動画が拡散され、Roberta'sはクリントン一家のお気に入りで、クリントンに関連した性的搾取にかかわっていると主張されたためである。
テキサス州オースティンの East Side Pies も、CIAやイルミナティと関係があると疑惑を持たれ、ネット上でピザゲートに関与しているとされて嫌がらせを受け、配送トラックに落書きされる被害を受けた。
FBIは2017年3月、ピザゲートに関連した脅迫について、大統領選挙におけるロシア疑惑の捜査の一環として調査した。→これも陰謀論みたいだ。
銃撃事件
2016年12月4日、ノースカロライナ州ソールズベリー出身の28歳の男が、コメット・ピンポンにライフル銃を持って押入り、店内の壁や机、ドアに3発発砲した。けが人はいなかった。男は警察に店を囲まれると投降した。男は警察の取り調べに対し、ピザゲートを取り調べようと思っていたと供述した。彼は、自分が買春の被害にあっている子供達を救う英雄になれるかもしれないと考えた。
男は、ピザ店が子供達を性的売買のために匿っているという話をウェブサイトで読み、実際に子供達がいるかどうか確かめたいと思ったと供述した。ニューヨーク・タイムズの取材に対して語ったところによれば、彼は犯行を反省してはいるものの、ピザゲートがフェイクニュースであることは否定している。また、一部の陰謀論者は、銃撃事件そのものがピザゲートの捜査を妨害するために仕組まれた陰謀であると推測した。
2016年12月13日、男は攻撃目的で州をまたいで火器を持ち込んだ容疑で起訴された。裁判所の文書によれば、男は事件の3日前、友人に陰謀論についてのYouTubeの動画を見せ、協力を募ったという。その後男は、大陪審によって2件の別の容疑で起訴された。
2017年3月24日、司法取引により、男は火器持ち込みと武器による攻撃の容疑を認め、コメット・ピンポンに対し賠償金として5,744ドル33セントを支払うことに同意した。7月22日、地方裁判所は男に懲役4年の判決を下した。審問において男は犯行を謝罪し、自身を「愚かで無謀だった」と述べた。
一方、2017年1月12日には、銃撃事件が起きる3日前に、コメット・ピンポンと同じブロックにある別のピザ店に脅迫の電話をしたとして、ルイジアナ州在住の男が逮捕され、容疑を認めた。
2019年1月25日、店の裏側が放火される被害に遭ったが、従業員が素早く火を消し止め、怪我人は出なかった。
真相
ニューヨーク・タイムズやファクトチェックを行うウェブサイトSnopes.comの詳細な調査により、ピザゲートは誤報であると判断された。また、ニューヨーク・オブザーバーやワシントン・ポスト、インデペンデント、ハフポスト、ワシントン・タイムズ、ロサンゼルス・タイムズ、FOXニュース、CNNなど多くのメディアによってピザゲートは陰謀論であるとされている。コロンビア特別区首都警察(MPDC、DC警察)も、ピザゲートは虚偽であるとみなしている。
陰謀論の支持者によって挙げられた根拠のほとんどは、陰謀論を補強しているかのように偽装されたものであった。例えば、児童虐待の被害者の写真であるとされたものは、実際にはInstagramなどのSNSに投稿されたピザ店の店員の家族や友人の写真であった。
2016年12月10日、ニューヨーク・タイムズはピザゲートを検証する記事を発表した。記事は以下の点を強調している。
コメット・ピンポンのロゴマークが悪魔主義者や小児性愛者が使うシンボルに類似したデザインになっているという主張があったが、AOLやタイム・ワーナー、MSNなど無関係の企業のロゴにも同じようなデザインが見られる。
コメット・ピンポンの地下に秘密のネットワークがあるという主張があったが、コメット・ピンポンにはそもそも地下がない。店の地下であるとして挙げられていた写真は全く無関係のものである。
コメット・ピンポンの店主アレファンティスが小児性愛を支持するようなデザインのTシャツを着ていたという主張があったが、証拠としてあげられた写真は全く別人のものであり、またTシャツはワシントンDCにある他のレストランの店名を書いているだけのものであった。
ジョン・ポデスタとトニー・ポデスタ(ジョンの兄)が、2007年にポルトガルで起きたマデリン・マクカーン失踪事件に関与しているという主張があったが、証拠として挙げられた犯人2人のものとされる似顔絵は、異なる目撃情報を元に別々に描かれた犯人一人の似顔絵であった。
**陰謀論と言う言葉を使うことがかえって陰謀論と言われているフェィクニュースを大きくする原因となっているね。大手のメディアが「それは陰謀論だ」と断定すれば彼等はかえって聖戦を行っている気持ちにさせてします。まっとうな話し合いを続ける道を遮断してしまうことになるから。きちんと理路整然と反論しないとかえって逆効果だ。そもそも陰謀論の出発点は、政府がキチンと情報公開を行っていないとの不信感からでているものともいえるから。
反応
2016年11月27日、コメット・ピンポンの店主ジェームズ・アレファンティスはナショナル・パブリック・ラジオのインタビューに応じ、ピザゲートは「ひどく複雑にでっち上げられた虚構の物語」であり「仕組まれた政治的攻撃」であると述べた。コラムニストの Daniel Ruth は、陰謀論者の主張は「繰り返し虚偽であると証明され、否定されている」「危険で有害な主張」であるとした。
ピザゲートは陰謀論として否定されたにもかかわらず、ソーシャルメディアで拡散され続け、2016年11月にはTwitterで #Pizzagate のハッシュタグ付きでつぶやかれたツイートが100万以上にのぼった。
12月8日、ヒラリー・クリントンはピザゲートについて言及し、フェイクニュースの危険性について語った。「悪意あるフェイクニュースの流行と嘘のプロパガンダがここ数年ソーシャルメディアに広がっている。いわゆるフェイクニュースが実社会で起きたことの帰結であることは今や明らかだ」と彼女は述べた。
世論
Public Policy Polling が2016年12月6日から7日にかけて、1,224人の有権者に対して世論調査を行った。「ヒラリー・クリントンがワシントンのピザ店の児童性的虐待に関わっていると思うか?」という質問に対し、9%の有権者が「関与していると思う」と回答し、72%が「関与していないと思う」と回答した。
**ヒラリー・クリントンさんがそんなことに関与しているはずはない。健全な常識だ。しかし、このフェィクニュースはもっと早く消し止められなったのか。意図的に放置した可能性は?
同様の世論調査が、12月17日から20日にエコノミストとYouGovによって行われた。この調査で、クリントンに投票した有権者のうちピザゲートは真実であると回答したのはわずか17%であった。一方、トランプに投票した有権者は46%がピザゲートは真実であると回答した。
**今度はトランプ氏が関与している?SNS情報はとんでもないデマを造り出す。
マイケル・フリン親子
2016年11月、大統領選に当選したドナルド・トランプの政権移行チームの一員であり、トランプから国家安全保障問題担当大統領補佐官に指名されていたマイケル・T・フリンが、ヒラリー・クリントンと選挙責任者のジョン・ポデスタが悪魔崇拝的な儀式で人の血液と体液を飲んでいたという陰謀論的な言説をツイートした。政治系ニュースサイトのポリティコは、このツイートについて、ピザゲートの陰謀論に類似したものであると報じている。11月2日、フリンはピザゲートの疑惑について根拠のない非難をした文章へのリンクをツイートした。ツイートは9,000人以上にリツイートされたが、12月12日から13日の間に削除された。
**こんなツイートが役に立つ政治とは? 米国の民主主義は今や幻想?これでは戦争だね。
陰謀論としての最大のものは、今ウクライナ問題で、米国が発している情報だろう。米国政府自体が陰謀論の妄想にはまっている。ゼレンスキーが作った自作自演の一方的なSNS情報だけを毎日世界中に流しまっくっている。
まるで、ウクライナ進攻はロシアのプーチンさんの個人的な感情で行われているかのようなフェイク情報ばかりだ。ロシアは領土拡張主義者?プーチンはナチスの信奉者?
プーチンさんの個人資産の凍結。こんなこと好きでやっている政治家なんている訳がない。ロシア軍人の中に何%のウクライナ人がいるのか。殺害されたウクライナ人の何%の民間人がロシアの保護を求めていたのか、全く考慮されていない。
SNS情報の拡散ということに問題が含まれている。SNSへの過度の依存は脳の機能を著しく退化させ、自己の判断能力を失うという脳科学者達の提言を取り入れる必要がありそうだ。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
ジェノサイド
ジェノサイド(英: genocide、露: геноцид):
国家あるいは民族・人種集団を計画的に破壊すること。ジェノサイド条約第2条によれば、国民的、人種的、民族的、宗教的な集団の全部または一部を破壊する意図をもって行われる行為のこと。集団殺害、大量虐殺。
genocide はギリシャ語の γένος(種族)とラテン語 -caedes(殺戮)の合成語であり、ユダヤ系ポーランド人の法律家ラファエル・レムキンにより『占領下のヨーロッパにおける枢軸国の統治』(1944年)の中で使用された造語である。つまり、未だはっきりと定義されていない用語。
 米国のバイデン氏がロシアに対してこの言葉を使ったことが、世界の国々に大きな波紋をもたらしている。ウクライナで生じている民間人へのリンチ虐殺が、ロシアのプーチン氏の意図的計画的な犯行と断定していることが正義かどうかだ。ブッシュ大統領の「十字軍」発言以上の失言であろう。
米国のバイデン氏がロシアに対してこの言葉を使ったことが、世界の国々に大きな波紋をもたらしている。ウクライナで生じている民間人へのリンチ虐殺が、ロシアのプーチン氏の意図的計画的な犯行と断定していることが正義かどうかだ。ブッシュ大統領の「十字軍」発言以上の失言であろう。
ジェノサイドのもっとも典型的な例が、ナチスドイツのユダヤ人の虐殺とされているが、これがヒットラーの元に計画的の行われたものか、現場の空気が多くのドイツ人達にそのような行為を正当化するように働いたのかは不明である。虐殺の実行者と言われるアイヒマン氏に死刑判決を出したことは、アイヒマン氏に責任があることを認めたことに。
意図的計画的な犯行と最適な事例は、広島・長崎に落とされた原爆で20万以上の民間人が殺害された事件であろう。米国は広島・長崎は純軍事施設で戦争を終結させるためには止むを得ない行為だったと強弁しているが。しかし、純軍事施設ということは米諜報機関の捏造で、しかも当時の日本は降伏間近であった。
ジェノサイド条約第2条によれば、国民的、人種的、民族的、宗教的な集団の全部または一部を破壊する意図をもって行われる行為のこと。集団殺害、大量虐殺。さらに、原爆投下時には事前の避難勧告すら一切出されていない。明らかなジェノサイドである。
何度も出されている避難勧告を無視して無駄な抵抗を続けるウクライナの傭兵集団とは全く条件が異なる。
では、事前に侵攻を警告してあれば、戦争による民間人の犠牲は正当化できるか。国際法上はそれが正しいようだ。民間人を盾にした籠城作戦は、防御側がジェノサイドになってしまう。だから日本の昭和天皇が降伏を宣言してくれた。
バイデン氏のジェノサイド発言は、早く攻撃を仕掛けろという合図だね。では、何故圧倒的に有利に見えるロシア軍は、攻撃を警告するだけで実際には動かないのか。ゼレンスキー・サイドが民間人を盾にゲリラ戦をしているからだ。犠牲になるのはほとんどが親ロ派か中立のウクライナ市民。いわゆる人質だね。キエフでの虐殺はウクライナ民兵が親ロ的な市民を感情に任せて殺害したのが本当のようだ。攻撃する多くのロシア兵の中にも多くのウクライナ人が含まれている。だから膠着状態が続いている。基本的にゼレンスキーが降伏する以外に終戦にはならない。ところが、何故か米英の諜報機関は、ゼレンスキー軍が未だ挽回できるとメディアに流し、長期化を企んでいる。これがウクライナの人々が望むことでないのは明かだ。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
ウクライナ軍は本当に強い?
ウクライナ軍は本当に強い?
日本のメディアは、ウクライナ軍の善戦を伝えており、ロシア国内には厭戦気分がみなぎっているとの論調がやたらと多い。しかし、事態は一向にウクライナにとっては改善の兆しは全くなく、単なるジリ貧の悪あがき。
ウクライナ軍の唯一の勝利とされるものはロシア戦艦「モスクワ」沈没ぐらい。原因は不明であるが。ウクライナの国軍とロシア軍が会戦した形跡はどこにもない。ゼレンスキー親衛隊が都市部でゲリラ戦をやっているだけのようだ。
ロシア軍が兵力を小出しにしているのは、そもそも発端がこれはウクライナ人同士の内戦であるからだろう。つまり、ロシアの被害は実際には極めて過少であり、民間人の犠牲を減らすため、非難の余裕を与え最小限の予告攻撃しかしていなようだ。一見激戦があったように見えるのはSNSによる自作自演のようだ。ロシア国内には厭戦気分がみなぎっているというのはNATO諸国の意図的妄想ということのようだ。実際にはロシア軍はほとんど健在のようだ。プーチン大統領の人気は鰻登りが本当らしい。
NATOは、そもそも軍事同盟で上部の指揮官は総て米国人だから、米国の意図ということだが。
日露戦争の際には英国がロシアの敗戦を誇張し、ロシア国内には厭戦気分がみなぎっているとの論調を盛んに発信し、日本を実際に勝利へと導いてくれた。つまり、日本は英国に助けられた。しかし、同じ情報戦略がウクライナ人達にとって良い結果をもたらすのか?
ウクライナ軍が本気で抵抗したのは、今続いているマウリポリ周辺だけ。ここには多くの民間人(中立か親ロシア派と見られる)人間の盾をして監禁されている。軍需工場の地下のシェルターに子供達が大勢いる? 要するに人質では。しかも、マウリポリ周辺はアゾフ連隊とかいう、義勇兵とか傭兵集団が主役らしい。要はテロリスト集団で人質を殺害することには何の罪の意識も無い人達らしい。
攻めるロシア軍の主力がウクライナ人で、人間の盾としてのウクライナ人を攻撃に犠牲になる所に配置しているので、侵攻が著しくスローでロシア軍が攻めあぐねているように見えるだけのようだ。
ゼレンスキー氏にとっては、マウリポリ周辺は最後の砦らしい。本気で海外からの武器支援を求めている。マウリポリが陥落すれば、親米反露勢力は一掃されてしまう。ウクライナ軍人はロシア兵の中にも身内の中にもいる。ロシアは、ゼレンスキー氏の大統領の地位を保証するから降伏せよと説得を続けているらしい。ゼレンスキー氏は喉から手が出るほど乗りたい話。でも、ゼレンスキー氏の側近(米諜報機関)が許すはずはない。ウクライナ難民の人達も早く戦争が終わって帰りたいと望んでいる。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
外国人義勇兵
ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は2月27日、外国人兵士の部隊を編成すると発表した。名称は「ウクライナ領土防衛部隊外国人軍団」。既にロシア軍と戦うために入国している義勇兵に加え、ネット上で新規入隊を募るという趣旨だった。10日後、52カ国から約2万人の応募があったと発表された。
しかし自らの意思で戦いに参加した外国人が犠牲になったり捕虜にされたら、いったい彼らはどうなるのか。ウクライナが外国人義勇兵を正規軍の一部として採用するのなら、ジュネーブ条約で兵士に認められている権利を全て持つべきだということになる。実際にウクライナは2010年代、親ロシア派勢力と戦う民兵隊に参加した外国人をそのように扱っていた。人数も少ないうちはそれで済んだかも。でも、ウクライナ戦争は基本的にはウクライナ人同士の内戦だ。親ロシア派や中立の民間人は総て敵だ。外国人義勇兵は誰が的で誰が味方か全く不明の状態で参加していることに。
国際法の下では、兵士が負傷したり捕虜にされるなどして戦闘外に置かれたときには、報復や拷問、屈辱的な扱いから保護されることが求められている。また母国の行為について連座して罰を受けないよう、法的な保護が提供されなければならない。
だが、傭兵は正規の戦闘員と同等の保護を受けられない。戦争捕虜に与えられる権利も認められず、その扱いは各国政府の判断に任される。
 誰が傭兵であるかを見極める基準も定まっていない。国際法の下での傭兵は、主に個人的な利益を動機として紛争に加担する外国人を意味する。しかし、この動機の真偽を証明することは難しい。既にウクライナ入りしている外国人兵士には傭兵も多いが、その区別は曖昧だ。傭兵を雇うことが悪いとは言えない。常備軍を持たずに必要に応じでリクルートできるのは戦争を避ける上では寧ろ良いことかも。
誰が傭兵であるかを見極める基準も定まっていない。国際法の下での傭兵は、主に個人的な利益を動機として紛争に加担する外国人を意味する。しかし、この動機の真偽を証明することは難しい。既にウクライナ入りしている外国人兵士には傭兵も多いが、その区別は曖昧だ。傭兵を雇うことが悪いとは言えない。常備軍を持たずに必要に応じでリクルートできるのは戦争を避ける上では寧ろ良いことかも。
弱小な軍しか持たないゼレンスキーが戦闘を続けるには、大量の外国人義勇兵を投入する以外に手は無い。ロシア軍なら親ロシア派ウクライナ人から兵をリクルートできる。でも、大量の外国人義勇兵を送り込んだ国の責任はどうなる。バイデンさんも戦争目的で出国するものにはビザを出さないと明言。つまり今までは無尽蔵に出していた。
欧州の国も他人ごとではない。厳しいコロナ対策で私権を剥奪し国家の為に奉仕せよでは、感染症よりも高尚な国家の運命を左右する問題には強権発動は当然と見なされる。つまり、極右ナチス的思想の過激派が台頭。ウクライナに自らの理想とする政権樹立を目指して続々と義勇兵に志願して来る。マリウポリに巣食う有名なアゾフ軍団もその代表らしい。義勇兵として参加したいものの数が増えてきているらしい。欧州の国々も初めはロシアを懲らしめるためと黙認して来たようだが、母国の不作為の罪として連座させられる恐れが出て来る。
彼等は捕虜になっても国際法で認めれる権利を保障される可能性はないので、民間人を盾に立てこもりゲリラ戦を継続し決して降伏しない。しかも、彼等の出国地が、例えばフランスだったらどうなる。明かにフランスによる戦闘行為と見なされてしまう。
第一次大戦前ならば、傭兵や外国人義勇兵は極めて当たり前の存在で、その代わり自己の生命は自己で責任を持つ。でも、それは同じ国民でも志願兵なら同じではないか。でも、多くの国は徴兵制を採用している。徴兵された段階で既に犠牲者だね。
兵隊がいなければ戦争は継続できない。徴兵制や傭兵と言う制度を禁止すれば戦争はボランティア活動になってしまうのか。でも、外国にまで義勇兵として出かけて戦いたいという動機の正当性はどう説明するのでしょうか。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【ウクライナ義勇軍に日本人は参加できる? 法的問題は?横粂弁護士が解説】
2022年03月01日 11時12分
ウクライナへの侵攻でロシアに対する国際的な非難が日に日に増す中、ウクライナは海外から志願兵を募っている。在日ウクライナ大使館も募集のツイートをし、日本人から問い合わせが殺到しているという。この「国際義勇軍」に日本人が参加することは可能なのか。
在日ウクライナ大使館は「ゼレンスキー大統領は27日、ボランティアとしてウクライナ兵と共にロシア軍に対して戦いたい各国の方々へ、新しく設置されるウクライナ領土防衛部隊外国人軍団への動員を呼び掛けた。お問い合わせは在日ウクライナ大使館まで」と27日にツイートしていた。
在日ウクライナ大使館は「ゼレンスキー大統領は27日、ボランティアとしてウクライナ兵と共にロシア軍に対して戦いたい各国の方々へ、新しく設置されるウクライナ領土防衛部隊外国人軍団への動員を呼び掛けた。お問い合わせは在日ウクライナ大使館まで」と27日にツイートしていた。
この書き込みには「応募資格が気になります」「戦闘経験0で言語もしゃべれないけど一緒に戦いたいな」「兵役経験なし、難病持ちですが可能でしょうか」「ニートでも大丈夫ですか」「就活で役立つかな」などと前向きなコメントが寄せられていた。
問い合わせが多かったのか、同大使館は28日になって「日本の皆様から多くのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございます。候補に対する大事な条件の一つは、自衛隊経験など、専門的な訓練の経験です。ご了承をお願い致します」とツイートしている。
過去、義勇兵の存在が注目されたことがあった。有名なのはスペイン内戦で、「国際旅団」という義勇兵団には作家のアーネスト・ヘミングウェーやジョージ・オーウェル、アンドレ・マルローら文化人が参加したことで知られる。関心が高いのも当然だろう。
果たして日本人から国際義勇軍に参加する人はいるのか気になるところだが、その前にこんな指摘もある。参加は日本の法律である「私戦予備罪・私戦陰謀罪」にあたるのではないかというのだ。
この法律は刑法93条で「外国に対して私的に戦闘行為する目的で、その予備又は陰謀をした者」を処罰するというもの。聞き慣れない罪名だが、2014年に「イスラム国」に参加しようとした大学生らに適用された(不起訴処分)。
元衆院議員で弁護士の横粂勝仁氏は「私戦予備罪にあたる恐れがあります」とキッパリ。確かに、「赤軍派」と「盾の会」とかの極左極右とか国内での活動を制限された団体が大量の応募してくる危険性は極めて大だ。
ただ、欧米各国はどのように対策しているのか、ゼレンスキー・ウクライナ兵の大半は外国人義勇兵で支えられているとも言われているし、国策としてしてコッソリと支援している疑いは拭えないね。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
本当のこと
 本当のこと
本当のこと
元ウクライナ大使の馬淵さんがはっきりと語ったらしい。「毎日毎日、プーチンの悪口ばかり。最近はプチャで虐殺したと。あれ、虐殺したのはウクライナの軍、警察当局、治安当局ですよ」「ロシア軍が掌握していた間、暴力行為にあった住民は一人もいない。」
朝日新聞に5月3日付に出ている。朝日に記者は元大使の自説としているが、ゼレンスキーから送られてくる写真情報からも確かに読み取れる。自説ではなく公開情報だけでもこれが本当の事と分かる。世界を闇から支配しているディープステートがコントロールしている虚偽情報の世界は翻弄されているという。
日本でも沖縄戦の時には、住民に自決を強要したり、降伏を許さないなんて言う軍人は沢山いた。もちろん自決する前に住民を先に避難させたまともな軍人も沢山いたことは事実だろうが。殺害する前に手を縛ったり、目隠しをしたり虐待を加える兵士何ている訳がない。明かに国際法違反だし、正規の兵士のする業ではない。
マウリポリの製鉄所地下に監禁されている民間人のケースもそうだ。アゾフ連隊にとっては、大切なのは人質。降伏を希望する民間人は敵とみなし平気で射殺する。アゾフ連隊の兵士自体が海外からの義勇兵(傭兵)の集まりで、ウクライナの民間人は単なる盾でしかない。
 一方の、ロシア軍の兵士の大半はウクライナ人で、ウクライナ人の解放のために戦う正義の戦いと信じている人達だ(つまり、SNSゼレン情報は意図的なフェィク情報)。こんなこと過去の歴史を調べて見れば一目瞭然のことだ。東ヨーロッパの人達は、父がウクライナ人で母がロシア人、おじいさんにはユダヤ人の血が流れている何て普通のことだ。ロシア対ウクライナ何ていう発想は全くのトンデモ論でしかない。
一方の、ロシア軍の兵士の大半はウクライナ人で、ウクライナ人の解放のために戦う正義の戦いと信じている人達だ(つまり、SNSゼレン情報は意図的なフェィク情報)。こんなこと過去の歴史を調べて見れば一目瞭然のことだ。東ヨーロッパの人達は、父がウクライナ人で母がロシア人、おじいさんにはユダヤ人の血が流れている何て普通のことだ。ロシア対ウクライナ何ていう発想は全くのトンデモ論でしかない。
元ウクライナ大使の馬淵さん、よくぞ本当のこと。これからもどんどん発言して欲しいね。今の日本、いや欧米では本当のことをいう人は陰謀論者としてネット社会で批判されることが当たり前になっている。新型コロナ騒動でも同じで、PCR検査で本当に感染者分かるの? なんて科学的観点から疑問を発しただけで陰謀論者。温暖化は嘘じゃない?なんていう科学論文を書いただけで陰謀論者。可笑しいと思ったことをはっきり可笑しいと言えない社会は崩壊寸前だ。
ディープステートに翻弄されているのは、欧米各国の首脳達も同じだ。崩壊寸前のゾンビ・ゼレンスキーがまだ、ロシアに対して反撃してロシアを打ち負かすことが可能。だから軍事支援? 経済制裁を続ければ、ロシアはウクライナから撤退する? だから制裁を続けろ。
ゼレンスキーははっきり言っているでは、「同情するなら武器をくれ。」
逆に、ロシアは軍事侵攻失敗で、兵力を損耗しているからその内崩壊する?
そんな絵空事、信用できる。ウクライナ軍は外国人傭兵がゲリラ的応戦しているだけで、一度も全面対決していない。つまり、まだロシアはほとんど本気で闘ってはいない。民間人の犠牲を避けつつ、極めてゆっくりと攻撃しているだけが。「ロシアは負けている」の情報は、日露戦争の時は功を奏したかもしてないが、今回は明かに逆効果。弱いロシアを宣伝することでNATO諸国の士気を煽るつもりかもしれないが。ロシア軍は本当は強いし、周辺国のとってはある意味脅威であることは変わりない。なんせ、米国が成敗できなかったイスラム国を退治しているのはロシアだから。
米国は大幅に軍事予算を。本当に軍事侵攻する。核兵器を使わない全面対決は米国にとっては余りにリスクが大きすぎる。米国人自身戦争は嫌だ。だから、何とかNATO加盟国に戦わせたい。まずは、隣国ポーランドあたりが候補に選ばれる。ウクライナの西部、昔は確かにポーランド領だったらしい。ロシアが東半分を取るならポーランドはドサクサに紛れて西側を領有したい。そのために多数の難民を受け入れた。更に米国からは多大な武器供与。さあ、武器を取って立ち上がる? NATOは当然支援してくれる? ロシアの軍隊はとても弱く張子の虎らしい。ドイツもエネルギー問題があるから支援して軍を出してくれる?
でも、梯子を外されたら? ウクライナと同じ運命だ。わざわざ国内の親ロシア派を排除するため東ウクライナに軍隊を派遣してロシアの支援を要請させた。ロシアをわざわざ戦争に巻き込んだ。NATOが軍を派遣することを期待したからだろう。でも、やってくれたの経済制裁だけ。「同情するなら武器をくれ。」→武器なんか貰っても使えない。兵を送れということだね。つまり、もう事実上敗北している。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
京大霊長類研解体
チンパンジーの研究などで知られる京都大霊長類研究所(愛知県犬山市)が、3月末で解体、組織再編される。きっかけは、研究費の不正経理問題が発覚したことだ。京大は、ガバナンス(組織統治)強化や研究活動の進展につながると説明するが、半世紀以上の歴史に幕が下りることに、OBらからは惜しむ声が上がる。
住宅街が広がる丘陵地。甲子園球場60個分の敷地の一角に、木立に囲まれた巨大なケージがある。チンパンジー12頭が暮らす霊長研の飼育施設だ。時折、仲間を呼び合う鳴き声が響く。12頭でよく知られているのは、メスの「アイ」だ。コンピューター画面に表示された0~9の数字を見た後、数字を隠した状態で5個までなら小さい順番に指し示したという2000年の研究は、世界を驚かせた。アイは今、45歳。人間で言えば高齢者だが、組織再編後も物体の認識などに関する実験に参加するという。
霊長研が開設されたのは1967年6月。旗振り役を務めたのが、日本の霊長類学の創始者とされる今西錦司・元京大理学部教授(1902~1992年)だ。終戦後、宮崎県の 幸島こうじま で野生ニホンザルの調査に着手。1匹ずつ名前をつけて集団を観察する「個体識別法」を編み出したことで知られる。今西氏らの働きかけを受けて、日本学術会議が政府に霊長研の開設を勧告した。
研究棟が犬山市に建てられたのは、渋沢栄一の孫にあたる実業家・渋沢敬三の仲介で、名古屋鉄道が敷地を提供したことに由来する。霊長研はアフリカでの野外調査を長年続けており、2020年度末時点で、教員や大学院生ら約200人が所属している。
京大が霊長研の解体を発表したのは、昨年10月26日だった。脳や遺伝子、人類の進化について研究する5部門を、現在の場所に新設する「ヒト行動進化研究センター」(仮称)に引き継ぎ、サルの生態などを野外で調査する4部門は、大学院理学研究科や野生動物研究センター(京都市)に振り分ける。不正経理にかかわった松沢哲郎・元特別教授(懲戒解雇)が主宰していた「思考言語分野」など3部門は廃止か休止とする。今、最も注目されている分野ではないか。
湊長博学長は記者会見で、「不正経理がかなりの期間にわたって続いていたにもかかわらず、所内で注意喚起がされなかった。組織体制や運営に問題があった」と指摘。再編により学内の他部局との連携が期待できるとし、「霊長研の機能を十分維持しつつ、霊長類学の一層の展開を推進する」と説明した。学者間のいがみ合いの結果としか見えない。
新組織では、チンパンジーやニホンザルなど約1100頭の飼育は続けるが、年間9億円近くあった運営費は、規模縮小に伴い大幅に削減される見通しだ。研究者らからは、京大に再考を求める声も上がる。霊長研OBら29人でつくる有志の会(代表=杉山幸丸・京大名誉教授)は昨年12月16日、インターネットで集めた約3万1500人の反対署名を京大に提出した。
1996~99年に所長を務めた杉山名誉教授は「霊長研は分野の垣根を越えた交流の場だった。野外で調査する研究者と、実験が主の研究者が活発に議論を重ねることで、世界をリードする成果を上げてきた」と惜しみ、「組織がバラバラになれば、どうやって研究を推進していくのか」と疑問を口にする。日本霊長類学会と日本人類学会も「多大な損失。再考を促す」との文書を京大に提出した。
研究費の不正経理問題:チンパンジー研究の第一人者で、霊長研の所長も務めた松沢氏らが2011~14年度の飼育施設工事で、業者に代金を二重払いするなどの方法で、研究資金計約5億円を不正支出。京大が20年6月に調査結果を公表した。会計検査院は同11月、複数の業者に入札の内部情報を伝えて参加させるなど、不適切な支出は計約11億円に上ると指摘した。
研究費の不正経理問題を理由に組織を解体するでは納得がいかない。松沢哲郎氏は学者であり、経理の専門家ではない。そもそも初代今西錦司博士は、金集めの名人。民間企業からの寄付金を基に組織を運営して来た伝統がある。新しいことを次々と行うには、文部省などのルートでは理解を得ることは困難。不正経理問題と見なされるグレーな経理が最初からあったのかも知れない。
しかし、世界的な研究成果を出し続けている組織で海外でも評価が高い。野外調査が不可欠なため研究費が不足することは当然予想される。運営費は、規模縮小に伴い大幅に削減では、ロクな活動が期待出来ないだろう。
一方、哲学や倫理的反対の意見は予測できる。京都大霊長類研究所の研究成果は、どんどん人と霊長類との境目を不明確にしていく。チンパンジーは人と同じ、すなわち人権を持つ。心も知恵も持った生き物。では人とは何だ。キリスト教徒がダーウィンの進化論を忌み嫌ったの同じ構図か。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
キヨシ・クロミヤ
 彼の名を知ったのは、Google検索の入力画面のイラストから。つまりGoogle社一押しの検索項目。
彼の名を知ったのは、Google検索の入力画面のイラストから。つまりGoogle社一押しの検索項目。
**Google Doodle celebrates Kiyoshi Kuromiya, a Japanese American auther and civil rights, anti-war, gay liberation, and HIV/AID acitivist, in the honor of the organization's celebration of LGBTQ Pride Month on June 4, 2022.
Who was Kiyoshi Kurimiya?
キヨシ・クロミヤ(Kiyoshi Kuromiya, 1943年5月9日~ 2000年5月10日):
日系アメリカ人の作家、公民権、反戦、ゲイ解放、 HIV/AIDS活動家。
第二次世界大戦中、ワイオミング州ハートマウンテンにあった日系アメリカ人強制収容所に生まれる。1960年代には、マーティンルーサーキングジュニアの右腕となり、ベトナム戦争の反対者として著名になった。
クロミヤは、フィラデルフィアゲイ解放戦線を創設し、「クリティカルパス」プロジェクトを設立した。また、HIV/AIDSと共に生きる人々によって、HIVと共に生きる人々のために作成された最初の医療・文化的能力ガイドラインであるACT UP注意基準の作成にも加わった。
1943年5月9日、ワイオミング州のハートマウンテン移住センター日系人移住キャンプにて、日系アメリカ人の3世として生まれる。第二次世界大戦中、他の日系アメリカ人と共に家族で収容されていた。戦争終了後、一家は1年間オハイオ州に移り住み、その後カリフォルニア州モンロビアに落ち着くことになる。
カリフォルニアに住んでいた8〜9歳の頃には、男性に惹かれていることに気がついたと告白している。しかし当時、彼はゲイという言葉を聞いたことがなく、ホモセクシャルが何であるかを知らなかった。10歳のとき、公園で16歳の少年と一緒にいるところを警察に見つかり、「淫らで不道徳な生活を送る危険性がある」と警告されたことをきっかけに、クロミヤは両親に同性愛者であることをカミングアウトした。その罰として、少年院に3日間収監され、さらに裁判所から腺病質専門医によるホルモン治療を受けるようにとの命令が出された。しかし、クロミヤは「何をされているのかよくわからないということもあって、トラウマになった」という。
黒宮は、この治療で性欲が増すと警告されていたことから、この「男性」ホルモンの注入は、転換療法の初期の試みであったと推測される。性欲が高まり、声が出なくなっただけでなく、羞恥心と倒錯感が残る事件だった。このときの逮捕によって、自分が一種の犯罪者であると無意識に自覚するとともに、性的な羞恥心も感じはじめ、性的行為について公言を避けるようになったと述懐している。
1961年9月にベンジャミンフランクリン国費奨学金を受けて、フィラデルフィア州ペンシルベニア大学に進学する。奨学金は、在学に必要なほとんどの費用のカバーできるほどの充実したもので、1500人の新入生の中で6人しか選抜されない狭き門だった。フィラデルフィアに移住した動機については、「兄弟愛の都市」という名前のみに基づいていると述べている。
大学ではデザイン学部の建築学の教授であったルイス・カーンに影響を受け、建築が人文科学の諸分野を包括する分野であると感じ、建築を学ぶことを決意した。しかし授業にはほとんど出席せず、「時間の無駄」「高校時代の教養に劣る」と考えていた。その代わり、フィラデルフィアのレストランを紹介するガイドブックを制作・出版し、その売り上げでかなりの収入を得ることができた。
在学中に、クロミヤは人権活動への関わりを深めるようになる。それは彼の性的指向に加え、ペンシルバニア大学が非常に閉鎖的であると感じたことが大きな要因であった。
クロミヤが本格的に積極行動主義の運動を開始したのは、大学1年生時に、人種平等会議のメリーランドの食堂での座り込みに参加したのがきっかけだった。
 クロミヤはマーティン・ルーサー・キング・ジュニアの「 I Have a Dream 」の演説に立ち会ったその夜、ラルフ・アバナシー牧師やジェームズ・ボールドウィンらとともにキング牧師に会った。1963年のワシントンD.C.への20万人デモであるワシントン大行進後、再びキング博士と会ったクロミヤは、公民権運動を通じて牧師と密接に協力していくことになる。
クロミヤはマーティン・ルーサー・キング・ジュニアの「 I Have a Dream 」の演説に立ち会ったその夜、ラルフ・アバナシー牧師やジェームズ・ボールドウィンらとともにキング牧師に会った。1963年のワシントンD.C.への20万人デモであるワシントン大行進後、再びキング博士と会ったクロミヤは、公民権運動を通じて牧師と密接に協力していくことになる。
1965年3月7日、クロミヤをはじめとする活動家たちは、アラバマ州セルマからモンゴメリーへの公民権運動「血の日曜日事件」にて、セルマのペタス橋で負傷した人々を支援するため、ペンシルバニア州フィラデルフィアの独立記念館を、フリーダムホテルと名づけて占拠する行動に出た。
翌週の3月13日、アラバマ州のセルマからモンゴメリーへの行進を前に、クロミヤ、キング牧師、フレッド・シャトルスワース師、ジェームズ・フォルマンは、モンゴメリーの州議事堂まで黒人高校生の有権者登録行進を先導している最中に保安官代理とそのボランティアに襲撃された。この事件でクロミヤは血まみれになり、頭の傷を20針縫う大けがを負った。警察の情報遮断で当初は死亡したと思われたが、ゲイの病院関係者の助けでマスコミに連絡することができた。
クロミヤは入院し、警察は封鎖される事態となったが、翌日、この事件について郡庁長から謝罪を受けたキング牧師は「南部の警官が公民権活動家を負傷させたことを謝罪したのは初めてだ」と述べた。
また、クロミヤに暴行を加えた保安官ボランティア部隊(白人市民会議またはKKKと同じ)を解散させるという、保安官からの署名入り声明文も受け取った。クロミヤはキング牧師のみならず、さらに家族とも親しく交際するようになり、キング牧師が暗殺された際には、アトランタの葬儀の期間中、牧師の子供たちの世話をした。
クロミヤは、1967年頃から反戦運動にも深く関わるようになる。 1967年10月20日から21日、クロミヤはアビー・ホフマンが主催したペンタゴン・ビルを浮揚させようとする大規模なデモに参加し、ビルを囲んで手をつないでパフォーマンス・アートで抗議した。
パフォーマンスには失敗したが、代わりに他のデモ参加者とともに周辺の警察のバリケードを集めて火をつけ、国防総省の長さ全体に及ぶ焚き火の列を作った。翌年には、ダーティ・リネンというペンネームで、ビル・グリーンシールズがにやけながら徴兵証を燃やしている写真の下に「FUCK THE DRAFT(徴兵制なんてクソ食らえ)」という文字を大きく配置した郵便配布用のポスターを制作した。
その年の後半、クロミヤはアメリカの郵便制度を利用して犯罪を誘発したこと、および公序良俗に違反するポスターを作ったという名目で、FBIに逮捕されることになる。
クロミヤはそれでも、1968年のシカゴのコンラッド・ヒルトン・ホテルでの民主党全国大会で、デモを警戒してマシンガンを持つ警官たちに囲まれる中、2000部のポスターを配り続けこのポスターの普及に努めた。クロミヤは暴力は受けなかったものの、その後3年間、「FUCK THE DRAFT」の裁判で闘うことになった。1971年6月7日、最高裁のコーエン対カリフォルニア裁判において、このフレーズは言論の自由の下で保護されると判断され、最終的に棄却された。
1968年4月26日、ペンシルバニア大学においてクロミヤが発起人となり、2000人を集めたペンシルバニア史上最大の反戦デモを行う。架空の団体「Americong」が、ベトナム戦争でのナパーム弾使用に抗議して、大学図書館の前で罪のない犬をナパーム弾で焼く予定であるというビラを印刷し貼るという内容であった。
デモに先立つ数日間、市長と警察署長は、デモを実行した者は相当の間刑務所に入ることになるだろうと警告を発していたが、それが却ってデモを過激化させた。抗議の日、クロミヤは「おめでとう、君は罪のない犬の命を救ったんだ。では、生きたまま燃やされた何十万人ものベトナム人はどうだ?」と書かれたビラを配った。
ゲイ解放闘争
 First Annual Reminder protest at Independence Hall on Independence Day 1965
1965年7月4日、ペンシルベニア州フィラデルフィアの独立記念館での最初のアニューアル・リマインダー抗議集会→写真
First Annual Reminder protest at Independence Hall on Independence Day 1965
1965年7月4日、ペンシルベニア州フィラデルフィアの独立記念館での最初のアニューアル・リマインダー抗議集会→写真
公民権と反戦運動への関与に加えて、クロミヤはゲイ解放運動に非常に積極的に参加した。1965年7月4日、独立記念館で行われた最初のアニュアルリマインダー抗議集会で、彼は正式にゲイであることをカミングアウトした。ワシントンDCとニューヨーク市でも同様のデモが行われ、フィラデルフィアのデモには12人の活動家が参加した。このイベントは1969年まで5年間にわたって行われ、人々が公に集まって同性愛者の平等な権利を要求した、有史以来初めての出来事であった。
クロミヤは、1969年、ストーンウォールにおける暴動に続き、フィラデルフィアで開催されたホモファイル・ムーブメントの会合に参加していたバジル・オブライエンとともに、ゲイ解放戦線(Gay Liberation Front, GLF)を設立した。
クロミヤは、ゲイ開放の背景には、性的アイデンティティに起因する孤独に対処するための、一種の男性意識の向上があったと述べている。
当時のGLFは、アフリカ系、ラテン系、アジア系の多様なアメリカ人を含んではいたものの、10人少々の小さな集団にすぎなかった。
しかし、GLFは、ストーンウォールの後に結成されたいくつかの同種グループよりも過激だった。クロミヤの指導の下、GLFは多様な人々を採用し、ブラックパンサー党やヤングローズといったグループとも連帯した。1970年にテンプル大学で開催されたブラックパンサー党大会にGLFを代表してオープンリー・ゲイの代表として参加し、ゲイ解放を訴えて支持を得た。1970年にテキサス州オースティンで開催された全米ゲイ解放会議「Rebirth of Dionysian Spirit」への参加はクロミヤにとって、ゲイ解放闘争に対する考え方を変化させる出来事であった。
1972年、クロミヤはペンシルバニア大学キャンパス内で最初のゲイ組織「ゲイ・コーヒー・アワー」を創設。この活動は毎週キャンパスで開催されながらも学生以外にも開放され、あらゆる年齢のゲイにとってゲイバーに代わる空間として機能した。
1980年代初頭にアメリカでエイズの流行が始まると、クロミヤは、ACT UPフィラデルフィア支部の創設メンバーとして、多くのグループでエイズ活動家、研究者として幅広く活動するようになる。 1989年にクロミヤ自身がエイズと診断された後、擁護活動はさらに激化した。クロミヤは「情報は力である」をモットーに、病気と向き合いながら知識を深め、後述のエイズ患者に対する医療用大麻の利用に関して国立衛生研究所の代替療法パネルに招待されるまでになった。
ACTUP 注意基の作成にも関与作成。これは、HIVの人々のために、AIDSの人々によって作成された基準としては初めてのものになった。
クロミヤはまた、ニュースレター「クリティカルパス」を創刊し、世界中の何千人もの人々や、AIDS情報にアクセスできない何百人もの収監者たちに郵送しました。彼はさらに、「クリティカルパス」をインターネットの創成期のWebサイトの1つに発展、誰でもAIDSの最新情報が得られるHIV治療についての最初のリソースの1つとなった。
後にこのサイトを通じて、クロミヤは24時間ホットラインを運営し、フィラデルフィアの数百人のHIV感染者に無料でインターネットを提供する「クリティカルパス・エイズ・プロジェクト」を設立した。
1990年代後半、クロミヤはいくつかの社会的にインパクトを与える訴訟(影響訴訟、impact litigation)に参加し、成功を収めた。1997年には、インターネット上でのエイズに関する性的な情報の流通を保護するために、言論の自由を拡大するために最高裁に提訴し、通信品位法を破棄させることに成功。
1999年には、連邦政府による医療用大麻の禁止に反対する集団訴訟(Kiyoshi Kuromiya v. The United States of America)の原告として、エイズ患者への医療用大麻の合法化を求めた。彼は医療用大麻のバイヤーズクラブを運営し、フィラデルフィア地域の数十人のエイズ患者に公然と無料で大麻を提供していた経験から、大麻が初期のHIV治療薬の副作用を緩和し人によっては既存の薬よりも効果的な治療法であることを訴えたのである。ただし、裁判所の判決はクロミヤに不利なものであった。
1970年代半ばに肺がんを克服したクロミヤは、バックミンスター・フラーとも親交を深め、1983年に亡くなるまでの約5年間、世界中を旅するとともに、フラーの最後期の著書6冊に共同執筆などで協力した。特に1981年に出版された『クリティカル・パス』は、科学技術が世界をより良くする可能性を説き、大きな反響を呼んだ。
1983年、クロミヤは母親と一緒に自身が生まれた日系人収容所ハートマウンテンを訪れている。その経緯や経験が、政府、戦争、人種問題に対する考え方を育み、活動家となる基礎となったと回想している。クロミヤは全米ランクレベルのスクラブル選手でもあった。
クロミヤは2000年に57歳でこの世を去った。当初はエイズによる合併症であると報告されていたが、実際はガンによる合併症によるものであった。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
ナチスをだました男
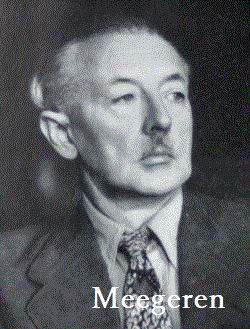 オランダが誇る17世紀の画家、フェルメールの作品を敵国ナチス・ドイツに売ったとして1945年、オランダ人の男が国家反逆罪の疑いで逮捕された。その名前は、ハン・ファン・メーヘレン。戦時中にフェルメールの作品として「姦通の女」をナチス高官のヘルマン・ゲーリングに売却していた。
オランダが誇る17世紀の画家、フェルメールの作品を敵国ナチス・ドイツに売ったとして1945年、オランダ人の男が国家反逆罪の疑いで逮捕された。その名前は、ハン・ファン・メーヘレン。戦時中にフェルメールの作品として「姦通の女」をナチス高官のヘルマン・ゲーリングに売却していた。
しかし、メーヘレンは「あれは自分の描いた贋作だ」と主張。法廷で実際にフェルメールのタッチを真似した「寺院で教えを受ける幼いキリスト」を描いたことで、裁判所も認めざるを得なかった。「ナチスをだました男」として一躍英雄となったメーヘレン。詐欺罪だけの、たった1年の実刑判決で済んだが、収監中に心臓麻痺で死んだ。
 当時の美術界では、メーヘレンの写実的な絵は全く評価されなかった。そこで彼はフェルメールを初めとした過去の人気画家の作風を真似して贋作を作り、評論家を騙して高値で売りつけていたという。彼の絵は本物のフェルメールよりも遥かに高値で買い取られた訳。本物よりも価値の高い贋作は世界の絵画においていくらでもあり得るということかも知れない。
当時の美術界では、メーヘレンの写実的な絵は全く評価されなかった。そこで彼はフェルメールを初めとした過去の人気画家の作風を真似して贋作を作り、評論家を騙して高値で売りつけていたという。彼の絵は本物のフェルメールよりも遥かに高値で買い取られた訳。本物よりも価値の高い贋作は世界の絵画においていくらでもあり得るということかも知れない。
第二次大戦中、ナチスドイツはメーヘレンの住むオランダを含むヨーロッパを侵略していました。そして各地で美術品の略奪を行っていました。戦後に連合国軍によって発見された略奪品の数は約25万点に及ぶと言います。
 **ハン・ファン・メーヘレン(Han van Meegeren、1889~1947年):
**ハン・ファン・メーヘレン(Han van Meegeren、1889~1947年):
オランダの画家、画商。本名はヘンリクス・アントニウス・ファン・メーヘレン(Henricus Antonius van Meegeren)。20世紀で最も独創的・巧妙な贋作者の一人であると考えられている。特に、ヨハネス・フェルメールの贋作を制作したことで有名。
国家反逆罪として告訴された人物が一躍、ナチスを欺いた英雄に変身。騙された人間が馬鹿ということか。では贋作とバレた時点で絵画の価値はどうなったんでしょう。
**ヘルマン・ゲーリング:
ヘルマン・ヴィルヘルム・ゲーリング(Hermann Wilhelm Göring De-HermannWGoering.ogg 発音[ヘルプ/ファイル]、1893年1月12日 ‐ 1946年10月15日)は、ナチス・ドイツの政治家、軍人[1]。ナチ党の最高幹部で総統アドルフ・ヒトラーの後継者であった。ドイツ空軍総司令官であり、軍における最終階級は全ドイツ軍で最高位の国家元帥 (Reichsmarschall)。
第一次世界大戦でエース・パイロットとして名声を得る。戦後の1922年にアドルフ・ヒトラーに惹かれて国家社会主義ドイツ労働者党(ナチ党)に入党。ミュンヘン一揆の失敗で一時亡命生活を送るも、1928年に国会議員に当選し、1932年の選挙でナチ党が第一党となると国会議長に選出された。ナチ党と上流階級の橋渡し役を務めてナチ党の党勢拡大と政権獲得に貢献した。1933年のナチ党政権誕生後にはプロイセン州首相、航空相、ドイツ空軍総司令官、四ヵ年計画全権責任者、ドイツ経済相、森林長官、狩猟長官など要職を歴任し、ヒトラーの後継者に指名されるなど高い政治的地位を占めた。しかし政権内では対外穏健派だったため、対外強硬派のヒトラーと徐々に距離ができ、1930年代終わり頃から政治的影響力を低下させはじめた。第二次世界大戦中にドイツ空軍の劣勢が目立つようになると一層存在感を落とした。しかし戦後のニュルンベルク裁判では最も主要な被告人としてヒトラーとナチ党を弁護し、検察と徹底対決して注目を浴びた。死刑判決を受けた後、執行方法を絞首刑から銃殺刑に変更するよう嘆願したが拒否されたため、それを不服として刑執行前に独房内で服毒自殺した。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
中東の覇者トルコ
ウクライナ危機で注目度が上がる「トルコ」
ロシアのウクライナ侵攻とこれに対する西側諸国の制裁で、国際社会、特に対米従属諸国は経済的に大混乱に陥っている。そんな中、国際社会からの注目度が上がっているのがトルコ。
ロシアやウクライナと同様、黒海沿岸国であるトルコは侵攻当初から、両国の仲介を積極的に行ってきた。当然と言えば当然で黒海沿岸国はまさに古代からトルコの庭みたいなものだから、欧米諸国にゴチャゴチャ言われる筋合全くないね。もちろんオスマン大帝国の時代を持ち出しても欧米は納得しないが。
最近ではウクライナの穀物輸出の問題の解決に向けて尽力。この問題はトルコの経済的利益に直結する。トルコ自身も小麦の大生産国だが、ロシアやウクライナからも多くの小麦を輸入し、パスタなどに加工して世界各国に輸出している。トルコの昨年のパスタ輸出量は130万トンと世界有数の規模を誇っており、ウクライナからの小麦輸出が滞る事態を回避して、「虎の子」産業に悪影響が及ぶことを阻止しなければならない。
トルコは北大西洋条約機構(NATO)加盟国であり、欧州連合(EU)と関税同盟を結んでいるにもかかわらず、中立的な態度をとることで巧みに立ち回っているわけだ。そもそもNATO諸国は旧十字軍勢力で、イスラム敵視の最大勢力だ。わざわざNATOに加盟するのはそれなりの下心があって当然だろう。
トルコに「ロシア系企業」が急増している
トルコメディアは6月9日に「国営ガス大手ガスプロムなど43のロシア系企業が今年7月からトルコの首都イスタンブールに欧州の拠点を移転する」と報じた。EUは米国とともにロシアに厳しい制裁を科しており、域内企業も相次いでロシア企業との取引を停止している。
これに対してトルコは西側諸国の制裁に当然ことだが参加していない。トルコを拠点に国際的な調達や販売を続けようとするロシア企業が増加。イスタンブールはモスクワと時差がなく、地域の拠点となる空港(ハブ空港)を有している。ロシアとの直行便の運航が続いている利点も加味して、多くのロシア企業が「移転先として好都合だ」と判断している。
トルコ商工会議所連合会によれば、昨年1年間のトルコに設立されたロシア系企業は177社だったが、今年3月は64社、4月は136社となっており、ウクライナ侵攻後に急増していることが見てとれる。
「ウクライナ危機の最大の勝者」と報じられた国
トルコのように外交の舞台で目立った動きをしていないが、実利面で大きな利益を上げているのはインドだろう。6月13日付サウスチャイナモーニングポストが「ウクライナ危機の最大の勝者はインドだ」と評しているほどだ。新型コロナのワクチンでもインドは世界最大の独占的供給者となっており、G7諸国を除けばほとんどがインド製だね。
インドはウクライナ危機以降、ロシアと米国両大国との間で絶妙なバランスを取り、ほとんど譲歩することなく、多大な利益を引き出している。インドもトルコと同様、ウクライナ危機について中立的な立場をとっており、この方針のおかげでロシアから原油や肥料など幅広い商品を格安価格で購入できている。
とりわけ目立つのは原油取引の分野だ。西側諸国がロシア産原油の購入を手控えるのを尻目に、バレル当たり約30ドルのデイスカウント価格でロシア産原油を「爆買い」している。中国もそうだろう。つまり、原油価格は愚劣な経済制裁に加担しなければ寧ろ以前よりも低価格で買うことも可能ということのようだ。トルコもインドもまともで常識的な判断をしているだけで特に何かを企んだわけでもなさそうだ。
侵攻前のロシア産原油の輸入量は日量3万8000バレルだったが、5月には日量81万9000バレルにまで急拡大している。
インドは国内需要(日量約500万バレル)の8割を輸入に頼っているが、5月のロシア産原油の輸入シェアは18%、輸入国のランキングでもイラクに次いで第2位に躍り出ている(第3位はサウジアラビア)。格安のロシア産原油を輸入したインドの石油企業は石油製品を欧米諸国に高値で売っている。欧米諸国にとっては残念なことだが、OPEC諸国は原油値上げ大歓迎だから、ロシア産原油の輸入制限も歓迎だろう。つまり欧米側にとって原油はますます値上がりしてしまう。
ロシアへの制裁を骨抜きにしかねないインドの行動について、米国は「行き過ぎであり、抑制してほしい」と再三懇願しているが、インドは聞き耳を持たない。当然のことだ。「行き過ぎ」を強制しているのは明かに米国側だから。
米国からの二次制裁(制裁の取引相手に対する制裁)を恐れている中国とは異なり、インドは米国が主導する対中包囲網(クアッド)に参加している自国の強みを存分に利用している。「制裁したらクアッドから抜けるぞ」と脅かせるというわけだ。二次制裁発動への圧力はバイデン政権にも強いようだ。でも、これをやったら本当に欧米経済は破綻だ。
ウクライナ危機が中国との国境紛争でもインド側に有利に働く可能性がある。中国との対抗上、ロシアとの軍事協力を長年大切にしてきたインドに対して、米国政府はロシアとの離間を図るための軍事支援に前向きになっている。装備面で中国に遅れをとるインドにとって願ってもないチャンスが到来している。人口世界一のインドが、世界の大国として躍り出る日も近いか。
「インドに続け」とばかりに動き始めたのはインドネシアだ。
途絶えていたロシア産原油の輸入を再開し、ロシアが主導するユーラシア経済同盟(EAEU)との間で自由貿易協定締結に向けた交渉も開始した。西側諸国の制裁にもかかわらず、ロシアとの関係を強化しようとする国が相次いでいるのは、歴史的なパワーバランスの変化が生じていることが背景にある。
米シテイは13日に「商品価格の上昇により世界の商品購入者が生産者に支払う金額は2019年に比べて5兆2000億ドル以上増加する。増額分は世界のGDPの5%以上に相当するが、この比率は1970年代初頭の石油危機の際に生じた所得移転の規模に匹敵する」との分析結果を公表した。
ロシア抜きでは成り立たないのか…
1970年代のOPECは「泣く子も黙る」恐るべき組織であり、国際社会、特に西側諸国の生殺与奪の権を握っていたと言っても過言ではない。現在のロシアもエネルギーや食料などコモデイテイーを世界市場に供給する大国だ。
ロシア経済は1991年のソ連崩壊以降、最大の危機に直面しているが、プーチン大統領が述べたように、現下の世界経済はロシア抜きでは成り立たない。→戦争と言う意味では危機だろうが、経済が危機だという分析はどうも正しくない。ウクライナ戦争自体も実際はメディアで云々されるほどの大戦争ではない可能性もある。キエフの街は人通りが多く、戦闘は東部の限られた地域だけ。都市施設に立てこもっているウクライナ兵はほとんどが外国人傭兵。SNSの写真は戦車や破壊された都市の残骸だけ。ロシアがかけた戦費は? バイデンさんの追加軍事予算の方が遥かに大きいようだが?
西側諸国はこの厳しい現実を直視すべき時期に来ているのではないだろうか。
でも、ここに描かれた状況は、米国の諜報機関やシンクタンクは当然予測済みのことではないか。過去の歴史を振り返れば当然このような動きになることは頭のいい人達なら予測しているはずだ。
そもそも、経済制裁は明かな戦闘行為の一部と見なされている。経済制裁に加担することはロシアを敵国と断定したことになる。経済支援も軍事支援武器支援でなくとも戦闘行為の一部と見なされて当然の行為だ。だから自国の経済発展と世界平和を求めるG20諸国を含む普通の国は、経済制裁網からは次々と離脱し、最後にはG7諸国だけが孤立して逆制裁(自分の首を自分で絞める)を受ける形となってしまようだ。
だとすれば、米国の諜報機関の連中は何故、ロシアの非道(ある意味捏造)を煽り世界中の国に経済制裁の呼びかけを行うのだろうか。つまり意図的経済崩壊、覇権国家を止めたいということのようだ。G7諸国も早く気づいて対米従属を止めてくれ。もう経済支援も出来ないし、核の傘を頼るのも止めろ! 自分で自衛しろ!
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
志願兵のリクルート
志願兵のリクルート(recruit)
キーウで外国人志願兵のリクルーターを直撃「日本人3人を前線に送り込んだ」「私の仕事は志願兵を10万人集めて戦わせること。5000人では勝てない」(2022.6.20(月)木村)
 [キエフ発]2014年、親露派のヤヌコーヴィッチ大統領を失脚させた「マイダン革命」の舞台になったキエフの独立広場。そこに立つウクライナ独立記念碑のそばには現在、世界52カ国の国旗と「世界には50億人の成人がいるのにウクライナでロシア軍と戦う外国人兵士はわずか5000人だ」と書かれたビラが貼られている。「ウラジーミル・プーチン露大統領に殺された外国人は287人」という立て札もある。
[キエフ発]2014年、親露派のヤヌコーヴィッチ大統領を失脚させた「マイダン革命」の舞台になったキエフの独立広場。そこに立つウクライナ独立記念碑のそばには現在、世界52カ国の国旗と「世界には50億人の成人がいるのにウクライナでロシア軍と戦う外国人兵士はわずか5000人だ」と書かれたビラが貼られている。「ウラジーミル・プーチン露大統領に殺された外国人は287人」という立て札もある。
**たったこれだけ? いやウクライナ人でなくて外国人だ。しかも日本人も? でもニュースにはならない。
各国の国旗には志願者と戦死者が書かれている。ジョージア(旧グルジア)1000~1500人(11~50人死亡)、エストニア500人(10人死亡)、ラトビア500人、米国400人(1人死亡)、ギリシャ300人(12人死亡)、リトアニア200人、ドイツ120人(2人死亡)、英国100人(10人死亡)、フランス100人(1人死亡)。日本は5人と記されている。
「本当だろうか」。ビラに書かれていた連絡先の米国人ライアン・ルース氏にテレグラムアプリでメッセージを送った。約束の6月17日昼過ぎ、ウクライナ独立記念碑に行くと52カ国の国旗の前にルース氏が座っていた。
「国旗の数字はどこから来たの」と尋ねると「各国政府機関、民間人、ニュースいろいろなところからだよ」と話した。まあ、情報自体はそんなに正確なものではなさそうだ。
ルース氏は外国からウクライナにやって来る志願者のリクルーターだ。時と場合、場所によって任務は戦闘、食料や水の搬送など戦闘地域での人道支援に分かれる。ルース氏はこれまでに外国人志願兵として50人から60人ぐらいをリクルートしたという。「日の丸に5人と書かれているが、本当なの」と確かめると、「3人をリクルートした」とだけ答えた。
**日本でもウクライナ大使館が募集していたらしいが。多くの若者が押し掛けたが戦闘経験無しで、特技無しで門前払いらしいが。ではもし合格ならば志願兵として合法的に出国できるのだろうか。
日本人1人はジョージアからの志願兵で構成される部隊に加わった。現在の居場所については「分からない」としながらも「最前線ではない。第二戦線にいる。おそらく北東部ハルキウだろう→つまり最前線ではないか?」と語った。
ルース氏は仲間と写った日本人の写真を示し、1人の名前と連絡先を教えてくれた。その日本人は筆者の問い合わせに「ジョージアの部隊ではなく、キーウ郷土防衛隊の所属だ」と答えた(木村氏は会った訳だ)。ルース氏によれば、日本人志願兵の1人は74歳、残りの2人は35歳前後だという。
「各国政府は自国民がウクライナで戦うのを望まない。プーチンはウクライナのために戦う外国人志願兵に4万ユーロの懸賞金をかけている。私のような民間人は2万ユーロだ。だから自分のことを話さないし、人目に触れるのを嫌うんだ。秘密を保っている。みんな殺されたくないからね。私も米国に帰ればロシアマフィアに殺されるかもしれない」
**米国に帰ればロシアマフィアに殺されるかもしれない人間がキエフの街中で非合法なrecruit活動を続けている? キエフの街中はたまにミサイル警報が出て避難が必要でそれ以外はかなり普段と変わらない生活が続いているようだ。
半信半疑でルース氏の話に耳を傾けた。
「私の仕事は世界中の国から10万人を集めて戦わせることだ。この戦争に勝つためには10万人、いや20万人、30万人が必要だ。5000~6000人ではこの戦争に勝つことはできない。世界の指導者たちは馬鹿げた理由でウクライナに軍隊を送らない。プーチンが核兵器を持っているから恐れているんだ」
「これは白か黒か、善か悪かだ。地球上で最も単純なテロのケースだ。善の側に立つのか、それとも悪の側に立つのか。みんなソファに座ってテレビを見て、普段通りの生活を送っている。この厄災に対して、ほんの一握りの人たちだけが自分のお金でここに来て戦っているのに、他の人たちはガソリン代に文句を言いながら座っているなんておかしいと思わないか」
ルース氏はこの後、6人の男をバンに乗せて2つの基地を回るという。待ち合わせ場所は近くのカフェだ。「同行していいか」と尋ねると「話をするのはいいけど、写真は絶対にダメだよ。みんなの命と安全がかかっているからな。それよりお前も行ってみないか」と誘われた。「いや年を取りすぎているのでとても無理だ」と断ると「まだまだ行けるぞ」とからかわれた。
内心、大変なことになってきたなと思った。56歳のルース氏自身、最初は前線で戦うつもりで2カ月半前にウクライナにやって来た。しかし軍は未経験で年齢を理由に断られ、キーウでリクルートを始めた。ズブの素人で60歳の筆者にはもともと無理な話だ。カフェには屈強な男たちが待っていた。最終的に米国、英国、ドイツ、スイスからの4人が集まった。
ルース氏はカフェの外で5~6人のグループとも話し込んでいた。ウクライナで捕虜になった英国人2人とモロッコ人1人がロシアの「代理法廷」で「雇い兵」であることを理由に死刑宣告を受けたことを心配しているのか、英国人男性はほとんど口を開かなかった。「軍事オタク」というドイツ人男性はハルキウの戦闘地域での支援活動について語り始めた。
「ロシア軍の大砲はウクライナ軍の10倍はある。しかし射程40キロメートルのGPS(全地球測位システム)誘導弾も発射できる米国製『M777』155ミリメートル榴弾砲だけでなく、英国やフランス、ドイツからも誘導弾が撃てる大砲が前線に届き始めた。ドイツのPzH2000自走榴弾砲は位置を変えながら砲弾を連射できるから大いに期待できる」と胸を張った。
**軍事オタク→まず彼らは最先端の兵器を使ってみたくてうずうずしている。最先端の兵器の操縦なら彼等に出番があると言うものだ。
ドイツ人男性は支援活動に使うバンの写真をスマホで見せながら「キーウで赤十字のバンを3台、国連のバンを2台見かけただけで、ハルキウや東部ドンバスで見かけたことはないよ。まだ砲弾が飛んでくるからね」と話す。動けなくなった高齢者を抱えた世帯は逃げたくても祖父母を残して安全な場所に避難できない。自宅には砲撃から身を守る地下壕もない。
米国人男性の“チェリーマックス(愛称)”は元米軍兵士で昨年7月までアフガニスタンに駐留していた。「混乱に陥る前にアフガンを離れた。自宅でゆっくりくつろいでいるのが性に合わないんだ。戦闘地域でバンを走らせている時、砲弾が落ちてくると、ワオッという気持ちになる。怖さなんか少しも感じないよ」とアッケラカンとして語った。しかし戦闘地域に取り残された住民の話になると表情が沈んだ。
**戦闘してないと心の平穏が保てない。長期に軍にいるとこんな人間が出来てしまうのか。
「水や食料を配って回っても、絶望して生きる希望をなくしているんだ。アルコールばかり飲んでいる。戦争が何かを理解できない子供たちは外で遊んでいる。戦争孤児もいる。そんな様子を目の当たりにするとやり切れなくなる」
みんな貯金をはたいてウクライナにやって来たボランティアだ。チェリーマックスはルース氏と会ってから同郷であることを知ったという。この3週間で7000キロメートルもバンで走行したとのことだった。
スイス人男性は「プロの兵士」で、1カ月と期限を切ってウクライナ入りした。これまで戦闘任務に参加した。所属した国際部隊の司令官は最初、外国人だったが「とにかく前進」というタイプ。次はウクライナ人で外国人志願兵に十分な情報や支給品を与えず、自費で食料を買うことすらあった。
今回はルース氏が仕切る任務に加わった。このスイス人男性だけが「戦闘任務か、支援活動かは時と場合による。行ってみないと分からない」と打ち明けた。
徒歩で移動する途中、軍隊経験のあるカナダ人男性が待っていた。カナダ人男性は元スナイパーで、戦場での医療にも精通しているとスイス人男性が教えてくれた。カナダ人男性はしばらくの間、自分が仲介する部隊の任務を説明したが、ルース氏と4人は先を急いだ。そこには欧州連合(EU)加盟国のナンバープレートがついた支援活動用のバンが止まっていた。
チェリーマックスとドイツ人男性が交代でバンを運転するという。ルース氏と残りの2人は座席も窓もないバンの荷台に乗り込んだ。「一緒に荷台に乗っていくか」と誘われたが、断った。これからどこに行くのかは教えてもらえなかった。ロシア軍が携帯電話を追跡しているので、戦闘地域に入る時は電源を切っている。
4人は荒くれ男というより、向こう見ずで、気のいい人たちだった。顔が見えないように後方から撮ることを約束して写真を撮影させてもらった。戦場には「戦闘」以外に「後方支援」などいろいろな任務がある。戦争は大砲戦に移行し、戦闘地域に住民が取り残されている状況では、水や食料を住民に配る支援活動にも大きな危険が伴う。
ロシア国防省によると、2月24日以降、ウクライナのために戦う外国人志願兵6956人がウクライナに入り、1956人が戦闘で死亡、1779人が出国した。現在、少なくとも3221人が戦闘を行っている。欧州の中ではポーランドが1831人と最も多く、378人が死亡、272人が帰国した。日本人1人が現地に滞在中というが、真偽のほどは分からない。
ルース氏は、ウクライナ政府は外国人がここに来て戦いに参加することを簡単には認めないと説明した。「しかし、私はウクライナ軍の司令官を知っている。彼らは人手不足で必死なんだ。毎日電話がかかってくる。“ライアン、誰かに来てもらえないか”ってね。私に会いに来てくれれば、大使館で煩雑な手続きをしなくても10分で部隊に入れてあげるよ」
所属した部隊が給与をくれることもあるが、基本的に「外国人志願兵はウクライナに来る飛行機代も、自分たちの装備も自費で買い、食べ物も自分で持って来なければならない。全部、個人のお金だ。車を売り、家を売り、すべてを売って資金を作ってくる。私もここに来るためにすべてを売り払った。政府のお金はないんだよ」とルース氏は強調した。
軍隊の未経験者を訓練するため米軍や英軍のトレーナーはウクライナ国内にたくさんいるという。しかしルース氏の話だけでは、現役なのか、退役軍人なのかはっきりとは分からなかった。「志願兵」のことを英語では「ボランティア」という。戦闘地域では「志願兵」と「ボランティア」の区別はつきにくくなるだろう。
暗いバンの荷台に乗り込み、扉を閉めれば、死と背中合わせの戦闘地域の手前まで連れて行ってくれる。
「善のために戦いたければウクライナ独立記念碑のそばに座っているライアンを尋ねてくるだけでいい。すぐに前線に連れていってあげるよ」しかし、そこには命の保証も何もない、危険な任務が待ち受けている。
**************
これと似た報道がNHKでもあった。志願兵は確かに手弁当でウクライナ政府からは費用は出ない。軍の指導を希望した退役軍人は最も戦闘の激しい戦いに送られる。帰りたくても費用も尽きた。
ひょっとして? ウクライナ東部で闘っているウクライナ兵はほとんどが外国人傭兵または志願兵ではないのか。降伏して捕虜にでもなろうものなら誰が身元を保証してくれるのか。しかも東部地域は親ロシア・ウクライナの地盤で、住民たちは彼等の味方か敵かも分からない。住民に手を出し殺害した証拠でも掴まれれば死刑宣告やむなし。言葉も通じないだろう。どんなに不利でも戦い続ける以外になさそうだ。
そう考えれば、ゼレンスキーのSNS発信の意味も分かってくる。ロシアが既に実質的に手に入れた東ロシアでの戦いは、外国人傭兵たちに任せておけば良い。ウクライナ人同士を東西で闘わせるのは愚の骨頂だね。外国人傭兵達への支援は当然、彼等の出身国が担うべきだ。そもそも、米国製の超高性能の最新兵器等一般人から徴兵したウクライナ人が使いこなせる道理もない。武器支援する欧米側だってそんなこと百も承知だろう。外国人志願兵のリクルーターたちが世界中で暗躍する土壌が出来ている。武器支援する以上、兵も送らないといけないはずだ。また、人生を戦争にかけて志願する者の数も世界中で増えているようだ。
米国人英国人の捕虜が死刑の判決を受けたことで、志願兵達の間で激震が走っていると言うが、そんなことは初めから百も承知のつわものしか参加するはずも無かろう。
しかし、では一体誰がウクライナ戦争を行っているだろう。そもそも戦争の落としどころが見えない。ロシアの実質の敵は海外からリクルートされてくる傭兵部隊ならなかなか殲滅は難しそう。一つ潰せは新しく基地を一つ作る。しかし傭兵部隊も本当はウクライナの市民の望まない邪魔者で勝利する可能性は零だ。でも、キエフを見れば分かるようにウクライナ全体が戦争に巻き込まれている状態ではなさそうだ。
では、正義のために戦っている傭兵たちの立場はどうなるか。単に欧米の諜報機関の陰謀に巻き込まれただけ? やはり、国際的に傭兵の使用を禁止するか? でも、戦争とは元々傭兵が主力で行うものかも。徴兵制は、戦争をするべきでないという個人の自由を著しく阻害する弊害もある。国が志願兵を募集できるなら、他国から志願兵を募集することも一概に不法とも言えないかも。
しかし、事態は更に複雑化する。傭兵を使っているのが欧米側だけなら、いずれリクルートのコストが増大しいずれ破綻する可能性もあるが、実際にはロシア側も傭兵を使う可能性も。実際のかなりの外国人傭兵部隊が使われているらしい。当然こんな代理戦争ではロシア兵の間にも厭戦気分が出てきて反戦デモもボチボチ。戦争当事国が安易に陽へに頼ることは戦争を拡大する原因になっているようだ。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
エチオピア内戦
エチオピア内戦は1974年9月から1991年6月にかけてエチオピアとエリトリアでの共産主義を掲げるエチオピア人民民主共和国政府と国内の反政府勢力の対立による内戦。
エチオピア暫定軍事行政評議会(通称デルグ (エチオピア))は1974年9月12日のクーデターでハイレ・セラシエ1世皇帝とエチオピア帝国を廃し、マルクス・レーニン主義を掲げる軍事暫定政府を樹立した(エチオピア革命)。
日本の皇室とも親密で、世界的にも慕われていたハイレ・セラシエ1世皇帝が退位させられたのはそんなに古い話でもないのか。バングラデシュがインドから独立したのと同じ年?なんせ、国のシンボルとしてのライオンを宮廷内で飼っていたとか。国民が貧困にあえいでいる時に許すべからず贅沢三昧の生活をしていたとか。
この内戦では以前より国内で起こっていたエリトリア独立戦争でのエリトリア分離主義者に加え、共産主義者から反共主義者といった様々な政治組織や各民族の解放戦線など民族組織が、ソ連の支援を受けたデルグに対し、武力によって抵抗した。デルグはこれらの反乱軍を軍事的な作戦や赤色テロによって制圧していた。 1980年代中頃までにはエチオピア飢饉や経済の衰退、デルグ政権の失策による国内の荒廃によって、反乱軍を支持する民衆が増加した。デルグは1987年に解散し、エチオピア労働者党によるエチオピア人民民主共和国を建国する。しかし、同国を支援していたソ連が支援を打ち切りはじめ、1980年代後半には政府軍が反乱軍に敗北を重ねるようになった。1991年5月にエチオピア人民民主共和国がエリトリア独立戦争で敗北し、メンギスツ・ハイレ・マリアム大統領は国外逃亡する。そして、1991年6月4日にエチオピア人民革命民主戦線が首都アディスアベバに進駐して内戦は終結した。 エチオピア人民民主共和国は解散し、ティグレ人民解放戦線主導のエチオピア暫定政府が樹立されることとなった。
エチオピア内戦では少なくとも140万人が死亡したが、戦闘や暴力で死亡したのは40万人にとどまり、100万人以上が戦争に伴う飢饉によって餓死した。
Wikiによるとエチオピアの現状は以上のようですが。
日本に取っては、ウクライナよりも遥かに重要な国だね。もっとニュースでどんどん取り上げて欲しいね。ソ連の支持を受けていたメンギツスは敗北して国外逃亡。
誤った社会主義、スターリンや毛沢東主義が経済を滅茶苦茶にしたことも原因だろう。同じ社会主義国でもキューバ何かは独自路線で上手くやっている。今では、ロシアでも中国でも内々否定されている思想だ。
エチオピア暫定政府は日本も含め、世界の多くの国の支持を受けているという理解でいいのかな。
エリトリア独立は確定。メンツギスはロシアの支援は得られない。では、内戦は何故続くのか? 誰は反政府勢力に武器援助しているのか? 終結に向けて動いているとの理解でいいのだろうか。そもそも内戦の原因は?原因がはっきりしないと解決の道は見つからない。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
ウクライナ戦争の落としどころ
ウクライナ軍の東部2か所の要衝での敗北が決定的になったようだ。ゼレンスキーさんは100%失地を回復するまで戦うと言うが、その可能性は?
元々ウクライナの東半分は全くの親露派の支配地域。旧ウクライナ国軍の多くの者が離脱して民兵として頑張っている。そんな地域を武力でウクライナ国軍が攻め込み親米化できる道理もない。それこそウクライナ人同士の戦闘になってしまう。
だから、米諜報機関が代わりに海外から傭兵をリクルートとして、親露派地域の武力制圧をやらせた。傭兵だからナチス系のならず者もいるだろうし、言葉も通じない危険な存在になっている。つまり、親露派民兵たちが危険に晒されるようになったことがロシア侵攻のキッカケであったことは間違いない。
でも、ロシアは意図的に過激な侵攻を行い、キエフ周辺まで攻め込みウクライナ全土を掌握する姿勢を示し、あえて悪玉を演じて見せた。わざとG7諸国を怒らせるためか。
ゼレンスキーさん初めから米国頼りだから、当然米国の支援をあてにしている。米国の支援がなくなればゼレンスキー政権は崩壊し、ウクライナ全土はロシアのものになってしまうぞ。実際、多くのウクライナ人が人的犠牲まで伴って親米を守る必然性は無いね。つまり、ゼレンスキーさんは負けても困らないけど、支援している米国側だけが困る構図だ。つまり、ロシア側はゼレンスキーを戦犯とはせずに大統領の地位も保全してもらえる。
傭兵集団は、欧米諸国から義勇兵として黒海を経由してウクライナに入っていた。マウリポリやゼベロドネツク等の拠点が占拠され、多くの傭兵を失ったウクライナは今後どうやって戦士を募集するつもりだろう。何と首都キエフ市内でもリクルート活動が行われているようだ。でも武器担いでやってくることは困難だ。つまり身一つで入隊する。また、欧米各国大量の武器を送ってもそれで戦う人材が著しく不足する事態が生じる。そもそもこれらの傭兵を積極的に認めて支援する国は限られている。確かに米国製の最新鋭の武器を使ってみたいという軍事オタクも大在押しかけて来るかも。しかし、多くの義勇兵たちは適切な給料も支払われず、手弁当で参加。しかも入隊すれば直ちに最前線の最も危険な地域へ。つまり使い捨てだ。マウリポリでロシア軍の捕虜となった米英人司令官はウクライナ民兵達に手渡され死刑の判決が出されるものと予想されている。
一方の、ロシアは近隣諸国の兵を高額で募集することはいくらでも可能だ。一方のウクライナは志願して来た傭兵達には給与など優遇することはしない。所詮米国の為の戦争だから。また支援した武器も傭兵達には渡らずにどこかの兵器市場で転売され世界のテロリスト達の手に渡るのが落ちらしい。所詮ウクライナの善良な市民達の使いこなせる武器ではない。
つまり、この戦争は長引けば長引くほどG7諸国だけが困る仕組みになっている。
軍事支援しなければ、ウクライナ軍は後退し続け、いずれ首都キエフ陥落は目前。
軍事支援しても、武器を使うのは海外から傭兵で、海外からリクルートしないといけない。武器支援しても実際に戦闘の現場までどうやって運ぶか。米国が自らリスクを冒して直接軍事介入できないのに、NATO加盟国、例えばポーランドなどが単独軍事介入できるかと言えば、チョット大義名分も無くリスクも大きすぎて無理。そもそも米国民自体がこの戦争は続けるべきでないと考えている。
経済制裁は残された唯一の手段だったけど、一体全体これが何の意味があったのか。G7諸国がインフレ加速で経済崩壊の危険があるのよそ目に、G20の資源国や発展途上国にとっては寧ろ経済的に有利に働いている。世界の多極化が一機に進む。つまり、続ければ続けるほど経済的にG7諸国だけが困窮する超愚策に変わっている。
つまり、G7諸国は何とかウクライナ紛争を収めないことには大変なことに。政権が崩壊し経済がもたない。現状は、明かだろう。ウクライナは親ロシア派に変わる。現状の変更は認められない(カラー革命はインチキだった)。しかし、ゼレンスキーが敗北を認めない限り米国は支援を止められない泥沼状態だ。さらに、ゼレンスキーさんアメリカの手前、自分から敗北を認めることなどできないでしょう。キエフが陥落するまでゼレンスキーは同じことをSNSで発信し続けるようだ。プーチンさんもそれを楽しんで見ているのかも。そう言う意味ではゼレンスキーさんは英雄と言うのにふさわしいかも。さすがコメディアンだ。ヒトの心を掴むのが上手い。
日本もそろそろ、ポストウクライナを考えて行動しないといけない。11月の中間選挙で米国の流れも大きく変わる。ゼレンスキーが敗北を認めてしまうと、ロシアは悪玉から善玉に変わってしまう。英米帝国主義をはねのけた世界の英雄。ゼレンスキーもうまくするとそれに乗っかることが出来るかも。今、軍拡競争なんかのプロバガンダに踊らされて軍事費を増大することよりも身近な経済対策をどうするかの遥かに大事だ。それとソロソロ経済制裁の解除見直しも必要だ。ロシアや中国を悪玉として欧米だけが民主主義国とする偏見外交を見直さないといけないね。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
戦況地図1
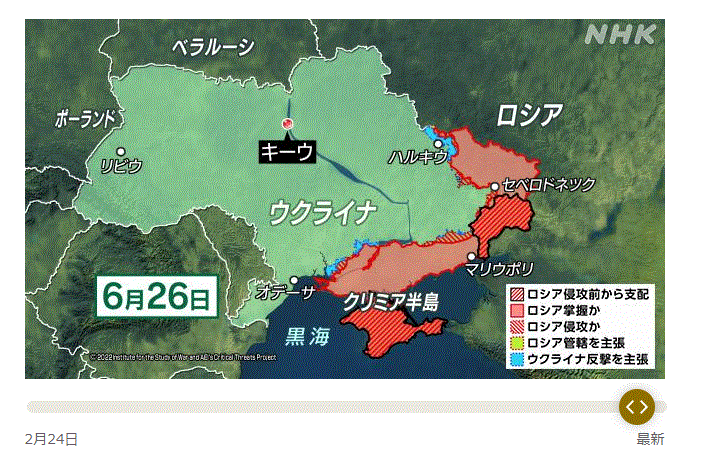 NHKがウクライナ戦争の経過を戦況地図としてまとめてくれている。テレビのニュースとの整合性から、この線引きが著しく偏ったものと考える根拠は無い。
NHKがウクライナ戦争の経過を戦況地図としてまとめてくれている。テレビのニュースとの整合性から、この線引きが著しく偏ったものと考える根拠は無い。
戦闘の現場は当初から東部地域の限定されており、ロシアがウクライナ全土を掌握しよう意図があるとは思われない。だとすれば、ロシアが要求する東部州の独立を認め、講和が成立しそうなものなのだが。どうせ元々住民はロシア側への帰属を求めているところだから。でもこの条件を拒否しているのがゼレンスキー側である。
ウクライナのほとんどの地域が緑の非戦闘地域。広大な農地では正常に農作業が行われており、首都キエフでも時折ミサイル攻撃があるだけ、正常な都市活動が続いている。この状況は、終戦前の日本の状況とは全く異なる。多くの都市が破壊され、広島・長崎にまで原爆が投下された。無条件降伏以外に選択肢はなかった。
ロシア軍の攻撃は、どうもウクライナ軍の反撃を待って拠点だけに絞って攻撃しているようだ。マウリポリは明かに海外からの傭兵隊の拠点で、彼等は黒海を渡って東部地域占領を試みていた。ロシアがクリミア半島に拘っていた理由もこれだ。
マウリポリを取られた傭兵集団は、セベロドネツクやハルキウ等の拠点を移して戦闘を継続しているが、抵抗の期間がだんだんと短縮。ウクライナ人なら当然東部戦線へ行くことを拒否するはず(ウクライナ人同士の戦いになる)なので、東部戦線のウクライナ兵は傭兵集団で構成する以外にない。では、東部戦線の終結がウクライナ問題の解決になるのか。
ウクライナ側が攻勢に転じるためには、いかに海外から傭兵をリクルートできるかだ。目標は20万人規模とかの話もあるが(あるリクルータ)。G7のいくつかの国は多大な武器供与支援を表明している。でも、如何にして傭兵を入国させることが出来るか。
この地図をもう一度見て見る。ロシアと戦っているのがほとんどが外国人傭兵集団なら今の戦いの現場はブルーの場所だけに限られる。グリーンの地域には、ロシア軍は何時でも侵攻可能だろう。しかし、抵抗勢力を温存すれば背後からテロ活動を行われる。だから今徹底した殲滅作戦が行われているのだろう。
ゼレンスキーの訴えは正鵠を得ている。今、米国が支援を止めれば外国人傭兵集団は壊滅してしまう。キエフも侵攻され、ウクライナ全土掌握されてしまう。でも、それでウクライナがロシア領となる可能性は零だろうが。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
知床遊覧船沈没事故
知床遊覧船沈没事故は、2022年(令和4年)4月23日に北海道斜里郡斜里町で発生した海難事故。連日ニュースで報道されたので記憶に新しいだろうが。
遊覧船「KAZU I」(カズ ワン)が斜里町の知床半島西海岸沖、オホーツク海域で消息を絶ち、船内浸水後に沈没した。5月29日現在、「知床観光船沈没事故」「北海道知床遊覧船事故」などとも呼称されている。
なお、「知床観光船」を登録商標としている道東観光開発、並びに同社が運行する「知床観光船おーろら」と本件事故は一切無関係である。
遊覧船「KAZU I」は、有限会社知床遊覧船(しれとこゆうらんせん)が所有・運行する小型観光船で、斜里町ウトロのウトロ漁港から知床岬へ向かい、折り返してウトロへ帰港する予定だった。このコースは「知床岬コース」と呼ばれており、所要時間は3時間程度だった。
事故当日は有限会社知床遊覧船が当季の運航を始めた初日だった。ウトロ港を発着する観光船は同社を含め5社が運航していたが、同業他社はゴールデンウィーク初日の4月29日ごろから運航を開始する予定だったため、当日は同社の遊覧船だけが運航していた。
当日の気象状況
事故当日、斜里町には3時9分に強風注意報(海上で6時から24時まで風速15.0m/s以上)、9時42分に波浪注意報(海上で9時から12時まで波高2.0m、12時から15時まで波高2.5m)が発令されていた。発航以前の時点で運航基準に基づく発航を中止すべき条件(風速8m/s以上、波高1m以上)に達するおそれがあった。
ウトロ漁港沖合の波高は10時に32センチメートルと穏やかだったが、11時40分ごろから上昇を開始、12時20分に1メートルを超え、13時18分には2メートルになった。14時には3.07メートルに達した。
また、事故当日の朝KAZU Iの船長は別の観光船運行会社の従業員から「今日は海に出るのをやめておいたほうがいい」と忠告されていた。ウトロ漁業協同組合によると、昼頃から現場海域の視界が悪くて波も高く、漁船は午前中に引き返していた。
遊覧船の出航
KAZU Iはウトロ漁港を10時に出港。子ども2人を含む乗客24人と、船長・甲板員の合計26人が乗船していた。10時10分ごろ、ウトロ漁港から北東に3キロメートル余り離れた付近で、トレッキングツアーの客がKAZU Iを目撃、撮影している。ツアーに同行していたガイドによると、この時点で船の様子は普通通りだった。
10時20分ごろ、僚船のKAZU IIIが臨時船長の操船で乗客12名を乗せ、カムイワッカの滝で折り返す70分のコースに出航、11時ごろから若干の波風を感じたが、11時40分ごろ、予定通り帰港している。
12時10分ごろ、波が強まったため、知床遊覧船事務所は14時に出港する便の運航を中止することを決定した。
事故発生
13時ごろ、KAZU Iが帰港していない事に気付いた別の観光船運行会社の従業員が、知床遊覧船事務所を訪れると「船長の携帯電話がつながらない」と告げられた。知床遊覧船事務所の無線用アンテナは同年1月ごろに破損して以降、修理しておらず無線交信ができなかったため、従業員は自社の事務所から無線交信にあたることになった。
13時10分ごろ、従業員が無線で現在地を尋ねると、船長Aは「カシュニの滝にいる。戻るのに時間がかかる」と応答した。この時点で切迫した様子はなかったが、通常通りの運行をしていた場合、現場付近は1時間ほど前に通過していたはずであり、減速して航行せざるを得ない事態に見舞われていた可能性がある。従業員が知床遊覧船事務所に状況を伝え自社に戻ると、わずか数分で状況が一変しており、無線で問いかける前から「救命胴衣を着せろ」と誰かに指示する声が聞こえた。船長Aに呼びかけると「大変なことになった」「エンジンが止まって前の方から沈んでいる」と応答があった。
13時13分、この交信をした従業員が海上保安庁へ救助要請の118番通報をした。「アマチュア無線で(沈みそうだ)と言ってきた。知床遊覧船のカズワン。乗客はいる。カシュニの滝あたり」。これが事故第一報となった。従業員は海上保安庁への通報後、船長Aにも携帯で118番通報するよう伝えた。それ以後、無線を呼んでも会話はできなくなり、これが無線機での最後の通信になった。
13時18分、船長Aは乗客から借りた携帯電話で、「カシュニの滝の近く。船首 浸水、沈んでいる。バッテリーダメ。エンジン使えない。乗客 10人くらい」と118番通報した。通報の位置情報はカシュニの滝の沖に約1キロメートルの地点で、のちに判明する船体発見地点から南西におよそ200メートル離れている。付近の潮の流れから、通報後まもなく沈没したとみられている。
また、沈没前に携帯電話が通じた乗客もおり、乗船していた佐賀県在住の70代男性は、「船が沈没しよるけん、今までありがとうね」と妻に電話で別れを告げていた。
14時ごろ、KAZU Iから知床遊覧船の事務所に、乗客から借りた携帯電話で「船が30度ほど傾いている」と連絡。以後、KAZU Iと事務所との連絡は途絶えた。
この事件の奇妙な点は、事故発生の現場が北方領土国後島の目と鼻の先で起こったことだ。ところが今回事件の奇妙な点は、自国の庭先で起こった事件についてロシア側は何も把握していない点だ。海難事故である以上、もし連絡を受けていればロシア側はそれなりの対策を取ってくれていたはずである。何故ロシア側にSOSを発信しなかったのか。船長Aが乗客から携帯電話を借りなければならない事態が不思議だ。つまり、事前にロシア側と連絡できないように仕組まれていた? 対ロシア政策を積極的に進めたい外務省・国土交通省がロシア側に恩を受けたくない? つまり、日露関係が正常ならばこんな事故は発生しなかった。知床観光船がある意味、現地での日ロ友好促進の事業として行われていた訳だろうから。どちらの住民もある程度の好意は互いに持っている。
日本からの救助活動の拠点が釧路では、何かあっても間に合う距離ではない。連絡を受けた時点ではもう手遅れだ。何はともあれロシアに依頼する、これが海難事故防止の最重要項目だろう。海難事故に関しては敵も味方も無い。人命救助のためには交戦中の相手国の船でも民間人なら救助するのは国際常識だ。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
統一教会
そういえば今は昔、そんな名前の宗教団体があったね。今は、世界平和統一家庭連合(Family Federation for World Peace and Unification)という。統一教会に関わるニュースもあったような気がする。韓国発のキリスト教を母体の新興宗教ぐらいにしか考えていない人が大多数ではないだろうか。
 朝鮮半島のキリスト教の土壌から発生した宗教法人。教祖文鮮明(1920年~2012年)によって、1954年に韓国で創設された。旧名称は、世界基督教統一神霊協会(Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity)。1994年5月に名称が変更され、日本では遅れて、2015年8月に宗教法人名を管轄している文化庁から改称を認証された。
朝鮮半島のキリスト教の土壌から発生した宗教法人。教祖文鮮明(1920年~2012年)によって、1954年に韓国で創設された。旧名称は、世界基督教統一神霊協会(Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity)。1994年5月に名称が変更され、日本では遅れて、2015年8月に宗教法人名を管轄している文化庁から改称を認証された。
宗教学ではキリスト教系の新宗教とされ、文化庁が発行している宗教年鑑ではキリスト教系の単立に分類されている。
朝鮮半島の平安北道定州出身の教祖・文鮮明(1920年~ 2012年)によって、1945年に布教活動が始まる。その後1950年に朝鮮戦争が勃発。1952年に経典の「原理原本」の草稿が完成。
1954年5月に韓国ソウルで、世界基督教統一神霊協会が創設。1965年に文鮮明一家と幹部たちは、アメリカに宗教・政治的情宣活動の拠点を移し、世界宣教・経済活動を拡大し巨大な統一運動傘下の組織を創設。韓国の多くの少数派宗教団体とは異なり、朝鮮半島を超えて世界中に普及したという特異性を持つ。世界193か国に支部がある。
日本では、1958年6月に崔奉春(チェ・ボンチュン。日本名西川勝。)が来日し、統一教会を伝えた。1959年から1965年まで宣教が行われ、同年にアメリカ、イギリスでも布教が行われた。近年は東ヨーロッパと南アメリカで拡大中。
1964年7月16日、日本で宗教法人の認可を受ける。初代会長になったのは元立正佼成会信者の久保木修己。同年、「原理研究会」が設立され全国の大学で学生伝道を開始。世界平和統一家庭連合の総裁は、文鮮明の妻である韓鶴子が就任している(2008年時点)。
**そういえば、昔大学のサークルとして「原理研究会」と言うのがあった。
1968年4月、文鮮明が岸信介らの協力を得て反共産主義政治団体「国際勝共連合」を日本に設立。「合同結婚式」(信者は「祝福」と呼ぶ)と呼ばれる教団内婚制をとり、教祖のインスピレーションに従って信者同士で結婚する。小規模な閉鎖的コミュニティを除き、教団内婚制をとる巨大教団はほかには見られない。1990年代の前半に霊感商法や合同結婚式で話題になったが、この時代でさえもあまり信者を獲得できていなかったはず。この合同結婚式によって家庭を持った日本人の信者数は一万組を超え、2004年時点で統一教会による合同結婚式で韓国人男性と結婚して韓国で暮らす日本人女性信者数も7千人ほどいるとか。
**こんな統計あるんですね。国としては総務庁の管轄かしら。
2010年代には信者の高齢化が進み、若い信者が入ってこない状態で衰退傾倒になっている。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス名誉教授であるアイリーン・バーカーは論文によると、1970年代に入信した信者たちは教団に残っているが、その後に入信者を増やすことには成功していないため、教団の高齢化が進んでいる。
2012年には開祖の文鮮明が死去し、妻の韓鶴子が組織全体の責任者となったが、「家庭連合幹部と母親韓鶴子女史が、後継権を奪い、韓鶴子女史が自ら教主となり、相続権を奪われた」と主張する七男の文亨進派と分裂。文亨進によって、サンクチュアリ教会が設立された。文亨進が家族連合(韓鶴子率いる統一教会)との『統一マーク使用権訴訟』で勝訴している。サンクチュアリ教会の掲げる主張は統一教会とは異なり、「全能の神が与えた権利によって武器を持ち、民が互いと人類の繁栄を守ることのできる平和の警官、平和の兵士の王国」と銃賛美の宗教となっている。
歴史
文鮮明は戦闘的な反共産主義者であり、共産主義は神の摂理に基づく民主主義に対抗する悪魔によるものと主張していた。韓国主導の南北統一を望む西側諸国、特に西側諸国の反共派から相互支持を獲得することで統一教会は規模を拡大した。
**確かに当時の米国は、反共さえ唱えればどんな独裁政権でも支持を与えていた。
ソ連には共産主義が失速した後、西側から様々な新興宗教が進出していたが、文鮮明もソ連人を援助し、1990年4月にモスクワで開かれた統一教会の世界メディア会議の後、ゴルバチョフと個人的に面会し、日本の経済界に働きかけて対ソ投資について調査させることを約束した。
アメリカでは1970年代以降、共同的な組織から権力を分散した家庭的な構造に移行し、「ホームチャーチ(家庭教会)」として知られる一つの家族の家庭で暮らすことが奨励されるようになった。ホームチャーチは地域の家族に仕え、責任を持つよう期待される。1980年代に祝福を受けた会員のほとんどは、この落ち着いた生活スタイルになり、統一教会の正会員をやめ賛助会員として、個人的な家庭と仕事を持って暮らしている。
しかし、文鮮明の子息で末っ子の文亨進が2015年頃にアメリカ合衆国でワールド・ピース・アンド・ユニフィケーション・サンクチュアリー教会(通称:サンクチュアリー教会を分派的に設立している。クーリエ・ジャポンによると、教会の信念はキリスト教と聖書に根ざしてはいるが、「武器信仰」が特徴であり、経典は独自のものとなっているらしい。
冷戦崩壊後の北朝鮮に対する融和路線への転換
統一教会は北朝鮮とは、「宗教の自由を認めず、弾圧している」として長年敵対関係にあった。政治団体である国際勝共連合という「反共組織」を通じて、反共の先頭に立って「共産主義撲滅」「打倒金日成政権」の運動・活動を展開していた。北朝鮮の金日成主席を「共産主義の悪魔」と攻撃し、北朝鮮もまた世界基督教統一神霊協会(統一教会)の創始者・文鮮明教祖を「反共の頭目」と痛烈に批判していたように統一教会と北朝鮮はまさに不俱戴天の間柄だった。
しかし、ベルリンの壁の崩壊と東欧社会主義諸国の瓦解後である1990年11月30日に、文は金日成による招聘を受けて北朝鮮を電撃訪問し、金日成主席と会談している。金日成は「連邦制による祖国統一実現のためには反共主義者とも手を握る必要がある」として、文をVIP待遇で「統一の使者」として受け入れるよう指示していた。これは、北朝鮮の党国際局・対韓担当の祖国平和統一委員会などの反対を押し切った判断であった。
文鮮明は1950年12月以降から韓国へ移住まで北朝鮮部分に住んでいて拷問を受けたこと、3年近くの興南監獄で多くの罪なき囚人たちが死んでいくのを見たことで反共思想になったと述べている。満40年10か月ぶりの北朝鮮訪問後の1991年12月7日に北京での声明文「北朝鮮から帰って」において、「北朝鮮に恨(ハン・恨み)が多いと言えば誰よりも多い人間です。」「過去40年の東西冷戦時代に誰よりも徹底した反共指導者であり、国際勝共連合の創始者として一生を勝共闘争に捧げてきたことは、世界がみな知っております」「冷戦時代の終焉とともに招来した平和の運勢を世界的に拡散させるために、私は「世界平和連合」を創設し、国際的平和運動を主導しています。」「統一祖国の明るい新世紀を迎える準備を急ぎましょう。」と冷戦崩壊後に対北朝鮮方針を転換した理由を述べている。
2012年9月3日に世界基督教統一神霊協会(統一教会)の創始者の文鮮明が死亡した際には、北朝鮮の金正恩第1書記は遺族に弔電を送り、「文鮮明先生は逝去したが、民族の和解と団結、国の統一と世界平和のために傾けた先生の努力と功績は末永く伝えられるだろう」との哀悼の意を表している。
2013年1月22日には北朝鮮と世界基督教統一神霊協会(統一教会)の合弁会社「平和自動車(Pyeonghwa Motors)」の最高経営責任者(CEO)で、米国市民権を持つ朴相権へ追加投資を引き出すために、北朝鮮から平壌市の名誉市民証を授与されている。
1954年の設立当時の名称である世界基督教統一神霊協会は「全キリスト教会を霊的に統合させる協会」を意味する。英語名の「神霊」の部分には Holy Spirit が充てられ、Holy Spirit Association for the Unification of World Christianityとなっているが、これは命名当時に他に適切な訳語が思いつかなかったためであるという。
統一教会は、社会における家族の重要性を強調しており、それを反映して1994年5月に名称が世界平和統一家庭連合に変更され、日本では遅れて2015年8月に改称された。
韓国では統一教、日本では旧称の略称の統一教会、またキリスト教会側からはキリスト教の教会と混同されないよう統一協会と記載され、英語ではUnification Church(統一教会)、Unificationism(統一主義)、開祖の姓から俗にMoonies(ムーニーズ)の名で知られる。ただし、信者はムーニーズを蔑称と考えており、自らそう名乗ることはない。文鮮明が率いる組織の集合体は統一運動と呼ばれる。今は、「天の父母様聖会」と、呼ばれている。
**まてよ! 文鮮明の子息で末っ子の文亨進があらたに分派を形成したのでは? こちらの方は武器を用いた積極的戦闘行為も賛美している。サンクチュアリー教会とか言ったか。全く異なった組織が世界を股にかけて血みどろの戦いを繰り広げているのだろうか。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
サンクチュアリ教会
2022年7月8日、「山上徹也(やまがみ てつや)年齢:41歳」が奈良県の奈良市で街頭演説中の安倍晋三元首相を銃撃という非常にショッキングな事件が発生。
銃撃した銃は手製の銃だとも言われています。
そして山上容疑者は、「ある特定の宗教団体に恨みを持っていて、その宗教団体の幹部を狙うつもりだった」と言っています。
そしての恨みとは、母親が特定の宗教団体を信仰しており、そこにお金を注ぎ込み幼い頃家庭が崩壊したとか。
宗教信仰に関連がある山上家ですが、容疑者本人は「サンクチュアリ教会」に所属していたという情報が入ってきました。
そこで今回は「サンクチュアリ教会」について調べると銃の所持やヤバイ評判について表立っていましたので調査結果をまとめました。→どんな結果だったんでしょう?
ある特定の宗教団体とは、いわゆる統一教会のことであるが、教祖が死んだ後、その後継者とめぐって激しい闘争が行われているらしい。つまり、山上容疑者は母の属していた宗派と対立する宗派に属していた。
 【文 亨進】
文 亨進(ぶん ひょんじん、 문형진、Moon Hyung-jin、1979年9月26日~ );
【文 亨進】
文 亨進(ぶん ひょんじん、 문형진、Moon Hyung-jin、1979年9月26日~ );
韓国系アメリカ人宗教家。世界基督教統一神霊協会(統一教会)の教祖文鮮明(문선명)と韓鶴子(한학자)の7男。
統一教会の文鮮明と韓鶴子は14人の子供を持ったが、息子の中では文 亨進は末っ子である。事業など様々な面に携わる他の兄弟とは異なり、父親の後を引き継ぎ、唯一信徒を指導する牧会者として活動してきた。 ハーバード大学で哲学と神学を学ぶ、とされていたが後に学歴詐称が発覚。在学していたと自称していた学生時代には仏教に傾倒し、髪を剃り僧服を着用していた。超宗教的な活動にも積極的で、チベット仏教の最高指導者、ダライラマ、韓国最大の仏教宗派、曹渓宗(チョゲチョン)の前総務院長である法藏(ポブジャン)など面会している。 18歳で結婚し、5人の子供がいる。
2008年4月、統一教会の公式発表により宗教分野の後継者とされた。文鮮明の死後、統一教会とは活動を別にして、サンクチュアリ教会を率いた。
AR-15(普通の銃よりも威力があるようだ)を重要視する“Rod of Iron Ministries”を率いている事でも知られ、2021年アメリカ合衆国議会議事堂襲撃事件にも参加した。サンクチュアリ協会の儀式参加には銃所持が求められる。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
アジア歴史資料センター
アジア歴史資料センター(Japan Center for Asian Historical Records):
日本国政府の機関が保管するアジア近隣諸国との関係に関わる歴史資料を提供する電子資料センター。インターネットを通じ明治期から第二次世界大戦終結までの期間に関する情報提供を行っており、日本の国立公文書館によって運営されている。略称は「アジ歴」。アジア諸国との相互理解と相互信頼の構築、および他国と比べて遅れている歴史記録保存・公開を進める、といった目的を有す。これらの歴史記録は、例えば日本の近現代史に関する研究資料、近隣諸国との対話材料などに利用することが可能。
2006年10月時点の公開画像は約1,270万画像、目録85万3,000件のデータベースが公開。アジア歴史資料センターによれば、毎年約15万件から20万件、画像数にして200万~300万画像ほどの資料が毎年追加公開されており、2011年4月の時点では、約2,246万画像、162万件の目録データを提供。2016年3月末時点では、2,985万画像、206万件のデータを公開。またデータ更新は四半期ごとを目処としている。
収録対象となっているのは、それぞれ日本の国立公文書館、外務省外交史料館、防衛省防衛研究所戦史研究センターが保管するアジア歴史資料であり、デジタル化に応じて順次公開されている。センターでは、これらの公的機関が所蔵する資料は2,800万画像を越えると予測している。
アジア歴史資料センターの公開資料へのアクセスは、インターネットを利用して誰でも可能。旧センター内では閲覧室で端末を用いた閲覧も可能だったが、事務所移転にともない、インターネット公開という特殊性から閲覧室は廃止された。画像はDjVu、JPEG 2000の2形式により保存・公開されていたが、PDF・JPEG方式へと移行。
歴史
1994年に村山内閣が発表した平和友好交流計画の一つとして、計画がスタート。1999年11月、日本政府が所有するアジア歴史資料を一般公開することを目的として、国立公文書館の一組織として設立することが閣議決定された。アジア歴史資料とは、「近現代における我が国とアジア近隣諸国等との関係に関わる歴史資料として重要な我が国の公文書その他の記録」とされた。2001年11月30日に開設。
資料の引用
2011年4月に施行された公文書管理法に基づき、アジア歴史資料センターの資料を出版物などで使用するにあたっては、利用申請が不要となった。ただし資料の出典は明示しなければならないとされる。また論文などへの使用に際してはアジ歴の略称と11桁のレファレンスコードを表記することが求められた。
所在地:
当初は「東京都千代田区平河町二丁目1番2号」に事務所が置かれていたが、2011年9月12日より移転された。現所在地は以下のとおり。
東京都文京区本郷三丁目22番5号 住友不動産本郷ビル10階
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
村山談話と安倍談話
「村山談話」どう投げ捨てたか
2015年8月16日(日);「しんぶん赤旗」日本共産党
**日本と周辺国の間での歴史認識の相違が問題とされている。これには色々な意見があるだろうから、色々なソースの言い分を見て見ることもいいだろう。以下は日本共産党の主張といって良いのか?
*******
「安倍談話」を検証すると
安倍晋三首相が14日に発表した戦後70年談話。村山富市首相の戦後50年談話をいかに実質的に投げ捨てたのか、いくつかのテーマに即して見てみました。
侵略
日本の行為と言わず
「安倍談話」は「侵略」について、「事変、侵略、戦争。いかなる武力の威嚇や行使も…」と一般論としていっています。侵略が日本自身によるアジア侵略だったという肝心のことを語らず、「安倍談話」の戦前の歴史部分にはでてきません。これは村山談話にある「国策を誤り」「植民地支配と侵略によって…アジアの諸国の人々に対し多大な損害と苦痛を与え」たとの認識とは異質で、事実上これを否定するものです。
**第一次、第二次世界大戦は帝国主義国同士の戦いであり、敗戦国のドイツや日本だけが国策を誤り、アジアの諸国の人々に対し多大な損害と苦痛を与えと言う認識は既に過去のものと言えるだろう。当然勝ち組、米国の原爆投下による民間人のジェノサイド等も反省の中に含まれていても良いだろう。
「安倍談話」は、戦前の日本が、欧米列強の「経済のブロック化を進めると、日本経済は大きな打撃を受け」その「行き詰まりを、力の行使によって解決」しようとしたと描いています。昭和史に詳しい作家の保阪正康氏は「経済ブロックが戦争の原因だという言い方は、1930年代の日本が太平洋戦争を起こすときの論理と通底している」と指摘します。(14日テレビ朝日「報道ステーション」)
**経済ブロック化が戦争の原因だと言う点は、世界史の共通認識の上で特に安倍さん独自の視点ではあるまい。大きな要素としてはロシア革命による共産主義の出現がある。英米は共産主義を潰す為、意図的にナチスドイツや日本の軍国化を支援して経済発展を促してきた面もある。だから米国の大恐慌のあと、独日は突然経済的な打撃を受け、その行き詰まりを、力の行使によって解決せざるを得ない羽目になったとも。
さらに日本が日露戦争で「植民地支配のもとにあった、多くのアジアやアフリカの人々を勇気づけた」とのべています。しかし、日露戦争は、朝鮮や中国東北部(満州)の支配権をめぐってはじめた、日露双方からの、いわば“強盗”同士の戦争でした。
**現実的には、ロシアの南下を押さえたい英米に背中を押されて日露戦争をさせられた(日英同盟)のが現実だ。少なくとも当時に日本人達にとっては、ロシアは強敵で負けたら植民地にされてしまうぐらいの恐怖心があったようだけど。
日露戦争に勝ったことにされたのが後の日本の悲劇の伏線となっている。「植民地支配のもとにあった、多くのアジアやアフリカの人々を勇気づけた」のは事実で、実例を挙げるのも容易だ。これもある意味、英米のプロパガンダに載せられたものでもある。
植民地支配
主体がだれか、語らず
「安倍談話」は、植民地支配について、「植民地支配から永遠に訣別(けつべつ)」すると、戦後の誓いのなかでいっています。しかし、日本が戦前、朝鮮半島と台湾を長く植民地支配したという、支配した主体がだれなのか、肝心のことが語られていません。日露戦争にふれながら、その戦争の目的だった韓国併合(1910年)=朝鮮半島の植民地化にも言及なしです。
朝鮮半島は併合から敗戦までの35年間、日本の軍事強権下で独立・自由を完全に奪われ、日本の侵略戦争に動員されて多くの命を奪われました。「韓国への誠意が感じられない」(マイク・モチヅキ・ジョージワシントン大教授、「東京」15日付)といわれて当然の内容です。
**これは、大英帝国下のインドの場合と全く同じだ。英国がインドのどのような誠意を見せたのかを大いに参考にすれば良い。インドも大戦で多くの命が奪われた。違いは?
イギリスは民主主義を守るための戦いだから善で、日本は侵略の為の戦争だから悪?
これは、今のウクライナ戦争と同じ構図か? ロシアは侵略の目的?だから悪で、NATOは共産主義から民主主義を守る戦いだから善? それが歴史認識の一つのポイントだ。
「慰安婦」問題
談話で一言も触れず
談話は、「二十世紀において、多くの女性たちの尊厳や名誉が深く傷つけられた」といいますが、人ごとのような言い方です。肝心の日本軍「慰安婦」問題にまったくふれていません。
女性の問題をとりあげるのなら、当然「慰安婦」問題にふれて、「当時の軍の関与」を認めた河野談話(1993年)にも言及すべきでした。それがいま日本の謝罪を求める、高齢になった被害者の声に応える道です。そうしなかったことに安倍首相の「慰安婦」問題への態度があらわれています。
**韓国との慰安婦問題は、実際には決着済み。当時の韓国政府には賠償金も支払っている。それが、被害者の手に渡らなかったのは韓国政府が渡してないだけだろう。だから韓国以外の国では慰安婦問題は生じていない。理由もなく謝罪だけ繰返す日本政府の態度にも問題があるが。
「お詫び」
首相自身の意思表明なし
「安倍談話」は、「我が国は、先の大戦における行いについて、繰り返し、痛切な反省と心からのお詫(わ)びの気持ちを表明してきました」としました。「お詫び」が首相自身の意思と責任によるものではなく、まさに人ごとで欺瞞(ぎまん)に満ちたものであることを露呈させました。
戦後50年の村山談話は、「私は…心からのお詫びの気持ちを表明いたします」と明言していました。これと比べても、「安倍談話」の主体性なき「お詫び」ぶりは一目瞭然です。「安倍談話」を「内閣総理大臣談話」としている以上、安倍首相本人の意思表明のない「お詫び」は意味を持たないはずです。
**主体性ある「お詫び」ぶりは、誰もやっていないでは。英語ならI am sorry for …..
で、当然for以下が大切だ。
「安倍談話」は「私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません」と強調しました。自ら謝罪しないことに加えて、その必要は今後も一切ないといっているに等しい異常な姿勢です。
**でも、国際的にそんなに非常識な話でもない。寧ろ最もな考えだろう。人類の歴史など所詮戦争は繰返し、勝者が敗者を裁いてきたものだ。過去の話は相互に歴史的科学的に調査を行って個別の案件毎に話し合いで解決していく以外に解決法は無い。
という訳で、共産党の主張にも歴史問題を解決すべき新しい視点はなさそうだ。談話の言葉尻だけの揚げ足取りでは無意味だ。少なくとも村山談話→安倍談話で特に、周辺諸国に対して悪影響を与えた形跡は無いようだ。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
核拡散防止条約
核兵器の不拡散に関する条約(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons、略称:NPT)は、核軍縮を目的にアメリカ・フランス・イギリス・中国・ロシアの5ヶ国以外の核兵器の保有を禁止する条約である。略称は核拡散防止条約または核不拡散条約とも呼ばれる。
**つまり、当初は5カ国以外の国への拡散を防止するだけが目的。つまり核兵器の寡占化。5カ国内での開発競争は否定してないし、第3国が極秘で核を所有してしまった場合も何も制裁を加えられない。
この条約は核兵器廃絶を主張する政府及び核兵器廃絶運動団体によって核兵器廃絶を目的として制定された。核保有国は核兵器の削減に加え、非保有国に対する保有国の軍事的優位の維持の思惑も含めて核保有国の増加すなわち核拡散を抑止することを目的として、1963年に国連で採択された。
**軍事的優位の維持の思惑が条約の進展の大きな阻害要因になっていた訳だね。非保有国はどうしても保有国側に立場を転じたい。現実に今は5カ国以外に多くの国が核保有国に転じている。
関連諸国による交渉・議論を経て1968年に最初の62ヶ国による調印が行われ、1970年3月に発効した。通称でNPT体制とも言う。25年間の期限付きで導入されたため、発効から25年目に当たる1995年にNPTの再検討・延長会議が開催され、条約の無条件・無期限延長が決定された。なお採択・発効後も条約加盟国は増加し、2015年2月現在の締結国は191ヶ国。
**ここまで、条約締結国が増えた以上、後は非締結国をいかに仲間に加えられるが勝負だね。
条約の内容
条約では全加盟国を1967年1月1日の時点で核兵器を保有する国(=1966年12月31日までに核兵器保有を果たし、保持を許された核保有国)であると定められたアメリカ・イギリス・ロシア、1992年批准のフランスと中国の5ヶ国と、それ以外の加盟国(保持しておらず、また許されない非核保有国)とに分けられる(第9条第3項)。旧ソ連構成共和国であったウクライナ・ベラルーシ・カザフスタンは核兵器をロシアに移転し、非核保有国として加盟。核保有国では無かったが核兵器を保有していた南アフリカは条約加盟前に核兵器を放棄し、1991年に非核保有国として加盟。
**他にはっきりと核実験を行って保有宣言をした国、或いは他国から核兵器の保有を確認された国、或いは疑いのある国も合わせると、実際に核兵器を保有する国、或いは開発中の国は相当数ありそうだ。
→インド、パキスタン、イスラエル / イラン、イラク、北朝鮮
或いは、原子力発電所を多数運転し、核燃料を大量に保有し、近い将来核兵器保有国になる可能性のある国まで加えると核兵器保有ポテンシャルのある国の数は更に増加する。
日本やドイツだって、韓国だって核兵器保有ポテンシャルは小さいとは言えないでしょう。
そもそも、1945年に最初の原子爆弾が落とされてから、80年近くが経過しており、核兵器の製造ということ自体が、そんなに極秘にしなくても簡単に入手できる時代になっていることも考慮に入れないといけない。
核保有国については核兵器の他国への譲渡を禁止し(第1条)、核軍縮のために「誠実に核軍縮交渉を行う義務」が規定されている(第6条)。しかしアメリカとソ連は核開発競争により「誠実に核軍縮交渉を行う義務」の実行どころか核兵器の保有数を大幅に増加させた。
非核保有国については核兵器の製造・取得を禁止し(第2条)、IAEAによる保障措置を受け入れることが義務付けられ、平和のための原子力については条約締結国の権利として認めること(第4条)、などを定めている。また5年ごとに会議を開き、条約の運営状況を検討すること(第8条第3項)を定めている。
再検討会議
5年に1回加盟国がNPTによって定められた核軍縮や不拡散が履行されているか確認する会議が開かれる。
2000年には「核廃絶の明確な約束」を盛り込んだ最終文書を採択し、2010年には核廃絶への具体的措置を含む行動計画を盛り込んだ最終文書を採択した一方で、1980年・1990年・1995年・2005年には最終文書は採択できなかった。
1995年には25年の期限付きだった条約を無期限で延長し、運用会議の5年ごとの開催を決定し、核廃絶を「究極的な目標」として掲げ、中東の非核地帯創設を目指す決議を採択し、2005年にはイランや北朝鮮の核開発疑惑に具体的な対策を示せず、2015年には中東非核地帯構想をめぐって意見が対立した。
2020年の再検討会議はアメリカのニューヨークで4月27日から5月22日までの日程で予定されていたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、2020年3月27日に再検討会議の開催を1年延期することを決定した。しかし、その後も感染状況が改善せず、2021年末には4度目の延期が決定し、2022年8月の開催が検討されている。
当条約上の「核保有国」以外の核保有国または疑惑国
加盟国であるイラクは国際社会より核開発疑惑を受け、1991年に起きた湾岸戦争に敗北し、核を含む大量破壊兵器の廃棄と将来に渡っても開発しないことなどを条件に和平する国連安保理決議687を受け入れた。しかし核開発計画の存在が明らかになった他、生物・化学兵器の廃棄が確認できない等の問題がある。
またNPTに1970年より加盟しているイランも核兵器を開発しているとみられている。
未加盟国はインド・パキスタン・イスラエル・南スーダンの4ヶ国である。なおインドとパキスタンは条約が制定時の5ヶ国の核保有国にのみ保有の特権を認め、それ以外の国々には保有を禁止する不平等条約であると主張し、批准を拒否している。
イスラエル政府は核兵器の保有を肯定も否定もせず、疑惑への指摘に沈黙を続けている。2010年9月3日にIAEA事務局長の天野之弥が、条約に加盟し全ての核施設についてIAEAの査察を受けるようイスラエルに対し求めたことを報告書で明らかにした。イスラエルはこの要請を拒否している。
脱退国
北朝鮮は加盟国(特にアメリカ)とIAEAからの核開発疑惑の指摘と査察要求に反発して1993年3月12日に脱退を表明。翌1994年にIAEAからの脱退を表明したことで国連安保理が北朝鮮への制裁を検討する事態となった。その後、北朝鮮がNPTにとどまることで米朝が合意し、日米韓3ヶ国の署名によりKEDOが発足した。しかし北朝鮮が協定を履行しなかったためKEDOが重油供与を停止。これに対し北朝鮮は2003年1月、再度NPT脱退を表明した。
**北朝鮮脱退にも一理ある。先発組だけが有利な条件では加盟しても利益が無いか。イスラエルも同様だね。そもそも米国の核の脅威が無ければ北朝鮮は核を持つ必要もない。
核軍縮交渉義務
第6条は締約国に「誠実に核軍縮交渉を行う」ことを義務付けている。しかし、締約国のうち5ヶ国の核保有国の核軍縮交渉や実行・実績は1987年に締結され、その後2019年2月にアメリカによって破棄され失効したINF(1991年に廃棄完了を確認)、1991年に締結されたSTART I(2001年に廃棄完了を確認)に限定され、現在に至るまで核兵器の全廃は実現していない。
核保有国の目的はコスト削減と核保有の寡占の固定永続化が目的であることから、核兵器の数量削減や、核実験をコンピューターシミュレーションに置き換えることを進めている。
「リーチング・クリティカル・ウィル」のレイ・アチソン代表は、核兵器の近代化や投資を終わらせる第6条の義務に反し、全核保有国が自国の核兵器及び関連施設を今後数十年で近代化する計画に着手するか、あるいはそうした計画を持っていると主張。また核拡散を抑制しようとする一方で、自らの核兵器は強化しようとする核保有国の姿勢はダブルスタンダードであり、「核兵器なき世界」を追求するという約束が裏切られている、と述べた。
2014年4月にマーシャル諸島共和国は、核拡散防止条約に違反しているとして9ヶ国の核保有国を国際司法裁判所に提訴した。加盟する5ヶ国(アメリカ・フランス・イギリス・中国・ロシア)は核軍縮交渉の義務を履行しておらず、加盟していない3ヶ国(インド・パキスタン・イスラエル)と条約脱退を表明した北朝鮮についても、慣習的な国際法により同じ義務があるべきところ、それを果たしていないというのがマーシャル諸島の主張である。6月には、国際司法裁判所の強制管轄を受け入れているイギリスとインドについて、審理に入ることが決まった。
日本
日本は1970年2月にNPTを署名し、1976年6月に批准した。NPTを国際的な核軍縮・不拡散を実現するための最も重要な基礎であると位置付け、また、IAEA保障措置(「平和のための原子力」実現のための協定)や包括的核実験禁止条約をNPT体制を支える主要な柱としている。署名にあたり政府は、条約第10条が自国の利益を危うくする事態と認めた時は脱退する権利を有するとしていることに留意するとし、「条約が二十五年間わが国に核兵器を保有しないことを義務づけるものである以上,この間日米安全保障条約が存続することがわが国の条約加入の前提」「日米安全保障条約が廃棄されるなどわが国の安全が危うくなつた場合には条約第十条により脱退し得ることは当然」との声明を発表していた。
なお、NPTを批准するまでの過程には様々な葛藤があり、1974年11月20日に通商産業大臣の中曽根康弘(当時)は来日中のアメリカ国務長官のヘンリー・キッシンジャーに対し、アメリカとソ連の自制に関連して「米ソは非核国に核兵器を使ったり、核兵器で脅迫したりしないと確約できますか」と問うと、キッシンジャーは、「ソ連は欧州の国々を上回る兵力を、中国も隣国を上回る兵力を持っている。核兵器がなければ、ソ連は通常兵力で欧州を蹂躙できます。中国も同様です」という見解を示しながら、もしもアメリカが非核国への核使用を放棄すれば、ソ連の東欧の同盟国にも使用できなくなるとの懸念を示して、中曽根の要求を拒否した。
**米国の言い分は簡明な事実に基づいている。ロシアも中国も通常兵力では欧米を上回る兵力を有しており(内陸国で人口も多い)、もし核兵器を使う権利を放棄してしまえば、ロシアや中国が周辺諸国を蹂躙してしまうことは明白だ。だから、核兵器の所有に関して絶対的優位性を手放すわけにはいかない。ただし、今のロシアや中国が帝国主義時代のように拡張主義を旗印にしているという証拠は乏しい。
2009年5月5日、国連本部ビルで開かれたNPT再検討会議の準備委員会に広島市長の秋葉忠利と長崎市長の田上富久が出席。秋葉は2020年までの核兵器廃絶を強く訴え、各国政府が核兵器廃絶への行動を直ちに起こすよう呼びかけた。また田上は、アメリカ大統領のバラク・オバマが提唱した世界核安全サミットを長崎で開くよう要請した(しかしこの願いは果たされなかった)。
2022年、ロシアがウクライナに侵攻したことを機に、自民党参院幹事長の世耕弘成が「核共有についての議論をし、核共有をしないのであれば、他にどんな手段で厳しい周辺状況に対応していくかを議論すべきだ」と発言し、日本維新の会も同調した。
**核共有とは、日本を防衛するためには、日本側の意向だけで米国の核兵器が使えるということらしい。現実的ではなさそうだ。つまり、核共有は不可能であるから、日本も核開発を行い核保有国になるべきだということらしい。
今、米国を始め核保有国は、戦術的核兵器として小型で個人でも携帯出来る核兵器の開発に余念がない。現にウクライナでも米国は小型の携帯用ミサイルを多数供与している。これに小型化した核弾頭を搭載すれば良く、戦術的核兵器は既に実用化された段階と言える。
戦術的核兵器の怖さは、核のボタンを押す権限は現場の戦闘員個人の判断に任されてしまう可能性だ。テロリストにとっては夢の兵器かも知れないが、この兵器に対応することは大変なコストが伴いそうだ。ウクライナでは、核を搭載しない通常の爆弾でも相当の戦禍を上げているとネット上で喧伝されている。少人数のウクライナ兵(実際はプロの傭兵)で、多数のロシア兵やインフラ施設の破壊に成功しているようであるが、相手方にも同様な報復を許してしまう。残されるのは瓦礫の山だけだろう。
核拡散の問題は、国家間の問題から、核兵器そのものの拡散防止を図らねばならない時代に突入したようだ。小型の携帯用ミサイルの禁止等も含め核兵器の使用を全面禁止する方向へと舵を切らないと条約そのものが効果が無くなってしまう。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
自民党の党内派閥
派閥の力学→この話はマスコミの政治系の記者たちにとっては、とても面白い話題のようだ。肝心の政策論をほっぽり出して、誰がどっちにつくかなんて言う分析を延々と論議したいらしい。
「現職の自民党の国家議員は衆参あわせて379人。参院選で初当選した新人議員を、それぞれの派閥が大学のサークルのようにリクルーティングをしているところだ。
まず主流派は岸田さんが率いる『岸田派』(宏池会)、もともとは同じ宏池会だった「麻生派」、そして兄弟派閥だった『茂木派』(経世会)だ。これに対し、いわば“反主流”だと言えるのが『二階派』と『森山派』だ。
そしていずれにも属していない、“中間派”に、安倍元総理が率いていた、90人を超える最大派閥の『安倍派』がある。これがどっちにつくかで決まるが、安倍さんは岸田さんとも菅さんとも仲が良かったので、党内のバランスが取れていた。
ただ、安倍派の中にも岸田さんに近い議員もいれば、菅さんに近い議員もいる。さらに派閥というのは所属議員が100人を超えてくると割れていくもの。なんとかバラバラにならずに安倍元総理の名前を残してやっていこうと頑張っている。
そしてもう一つ、いわば“帰宅部”のような議員80人の中に菅さんがいて、『菅派』とも言うべき『菅グループ』も20人ほどいる。これが“反主流派”の中でもシンボリックな存在になっていると言っていい」。
そもそも新人議員が派閥を選ばねばならない理由は何か。それ以前に派閥は必要なものか?
戦後ズット、自民党の単独政権が続いている日本の政治土壌では、各議員は自己の政策を実現するには、どこかの派閥に入る以外の入るしかない? つまり、派閥とは一種の政党の変形の様なもの? 確かに、今の野党、すべて派閥として自民党内で活躍していても同じことのようにも見える。逆に言えば、どの派閥も政策の違いを明確にしていない。
安倍氏がテロで倒された今、自民党は派閥抗争をしている余裕は無くなった。テロの結果を容認したい派閥。つまり統一教会が自民党と密接な関係があったとし、テロの犯人は正義感に駆られて安倍氏を殺害したというストーリーにしたいグループと、いや安倍氏殺害は台湾独立を阻止したい米国諜報機関の陰謀だと考える人達だ。
安倍氏の国葬を進める人達は勿論後者で、国葬に反対の人達は台湾独立を阻止したい一派と色分けがなされてしまったようだ。自民党議員の各々に統一教会に何らかの関係を持った人の入閣を辞退させようという勢力は当然前者だろう。安倍氏の二の舞になりたくない岸田さんは当然後者だね。何時暗殺されるが分からない。つまり、自民党は2分される。
「一つの中国」に拘る連中には当然、台湾独立を支援して来た安倍さんは、殺されて当然と思っている人達だろう。当然自民党からは真っ先に排除されるべき人物だ。
つまり、派閥の構想だけ見ているマスコミには、今後の進展が全く理解できないだろう。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
警察の隠蔽工作
山上容疑者が撃ったと推定される弾丸は未だ見つかっていない?
いや、実は医師が安倍さんの体から取り出し、担当の警察官が受け取って保管していたが紛失した?
まずありえないことだけど、それが今の処のストーリーらしい。
この辺はマスメディアでは本当のことは隠蔽されている。
担当した医師の証言、担当した警察官の証言、失われた経緯。
山上容疑者は、どうも犯人としては特定できそうもない。
弾丸が山上容疑者のものなら紛失させる必要もない。どちらにしても紛失は意図的だ。
では、真の実行犯は? 明らかに米国の諜報機関の関与が疑われる。もちろんこれがそのまま米国民の意図という訳ではない。「一つの中国」政策に固執する連中にとっては確かに「台湾独立」を理念にしていた安倍氏は邪魔な存在かも。米国の諜報機関が関与しているのでマスコミも「一つの中国」論に著しく協力的。
安倍氏の国葬は、テロで倒れた安倍氏を悼む声は国際的なものだから。テロに屈しないことを世界に示すのは大切な機会でもある。
山上容疑者を殺人犯人と無理くり特定し、個人的な恨みだなんていう言い訳はに日本国内でしか通用しない。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
国葬法とは
岸田内閣が安倍元首相の国葬を国民の総意で実施する希望を出しているのに対し、一部の野党やマスメディアが国葬反対を訴えている。その最大の論拠が国葬には法的根拠が無く、これを実施することは憲法違反だということらしい。「国葬法」が廃止されたのは1947年、進駐軍指令下のもとのこと。天皇が国民の象徴となったため皇族や天皇の臣下の国葬が廃止されたと解するべきだろう。国葬が憲法に抵触するかの議論とは関係が無いようだ。
国葬(こくそう)とは、国家にとって特別な功労があった人物の死去に際し、国費で執り行われる葬儀のこと。
古来、天皇の崩御などの場合、大喪が発せられる慣習があったが、特に国葬の名は明治以降正式に使用された。明治以降、国葬をすべき必要が生じた場合に応じて「特ニ国葬ヲ行フ」とする勅令が個別に発せられていた。国家に功績ある臣下が死去した場合にも天皇の特旨により国葬が行われるほか、皇族においても特に国家に功労があった者が薨去した場合には、通常の皇族の葬儀ではなく特別に臣下同様の国葬が行われた。
第二次世界大戦後、国葬令が失効したことにより、それによって規定された国葬はなくなった。また、新しい皇室典範の葬儀に関する規定は、第25条の「天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う」という記述のみとなった。また、2019年の皇位継承に際して制定された皇室典範特例法では、上皇の崩御に際しても大喪の礼が行われることが規定されている。「大喪の礼」は国家儀式として行われ、その費用が国庫から支出される国葬として扱われている。一方で伝統的な宗教儀礼を含む儀式は、「大喪儀」として皇室が主宰する儀式として行われている。皇族については、その葬儀の呼称にかかわらず、皇室の主宰する儀式となっており、いわゆる国葬としては扱われていない。これは第二次世界大戦前ならば大喪が行われる皇太后の身位にあった香淳皇后の2000年の葬儀でも同様である。ただし、1951年(昭和26年)に貞明皇后が崩御した際には、国葬と明確にしないまま「事実上の国葬」(準国葬)として一連の葬儀が行われた。
第二次世界大戦後、天皇・皇后以外で国葬が行われた初めての例は、1967年(昭和42年)10月20日に死去した元内閣総理大臣の吉田茂である。閣議決定による「国葬儀」形式での国葬とし、かつ政教分離に基づき宗教色を排して同年10月31日に日本武道館で開催。勅使・皇后宮使拝礼や皇太子明仁親王・同妃美智子以下皇族による供花の他、三権の長、外国使臣ら5700人が参列し、一般会葬者3万5000人が献花に訪れた。葬儀委員長は内閣総理大臣の佐藤栄作、葬儀副委員長は総理府総務長官の塚原俊郎が務めた。同夜、内閣総理大臣官邸(現公邸)で海外賓客を招いたレセプションが開催された。国葬の国費負担額は1810万円。
少なくとも、国葬は前例があった。安倍晋三の国葬が憲法違反なら、当然吉田茂氏の国葬も同じだ。しかも、戦後のドサクサの内閣であったので、当然国民の間には賛否両論があったことは間違いない。済んでしまったこととは言え、吉田茂氏の国葬も憲法違反であったと併記しないと筋が通らない。
2022年(令和4年)7月8日に銃撃を受け死亡した元内閣総理大臣の安倍晋三も、国の儀式開催を規定した内閣府設置法第4条第3項第33号を法的根拠として、閣議決定により同年9月27日に日本武道館で「国葬儀」が開催されることとなった。葬儀委員長は内閣総理大臣の岸田文雄が、葬儀副委員長は内閣官房長官の松野博一が務める。国庫負担額は2億4940万円。
現在、内閣総理大臣経験者をはじめとした有力政治家の葬儀は、内閣、所属政党、所属議院、遺族のいずれかの組み合わせによる合同葬として行うことが多い。1975年(昭和50年)に死去した佐藤栄作は、戦後において存命中に大勲位を受勲した三人(吉田・佐藤・中曽根康弘)のうちの一人で、その葬儀は「自民党、国民有志による国民葬」として行われ、経費の一部を国庫から支出する旨閣議決定が行われた。国庫負担額は2004万円。「国民葬」の名で呼ばれた先例には大隈重信のものがあるが、大隈の葬儀に国家は関与しておらず、佐藤の国民葬は公葬と民葬の中間的なものとなった。1980年(昭和55年)に現職首相のまま急死した大平正芳は「内閣・自由民主党合同葬」で行われた。国庫負担額は3643万円。1980年の大平以降は、首相経験者の葬儀が行われる際に内閣が関与する葬儀が慣例化していった。ただし、元首相が最後に所属していた政党が野党であり政権に参画していない場合は葬儀に内閣が関与していない(例として1993年に死去した田中角栄、2017年に死去した羽田孜は内閣が関与しない葬儀となった)。また、元首相が最後に所属していた政党が与党として政権に参画している場合でも葬儀に内閣が関与しないこともある(例として1998年に死去した宇野宗佑、2000年に死去した竹下登、2022年に死去した海部俊樹は内閣が関与しない葬儀となった)。第二次世界大戦前後を通じて、国葬は普通東京で行われる。例外的に島津久光は鹿児島で、元大韓帝国皇帝で朝鮮王族であった高宗と純宗は京城府(現在のソウル特別市)で行われた。
ただ、今回の場合は、政治家として道半ばのテロによる死であり、国民相違による哀悼の意を示すことは日本国憲法には抵触しないのではないか。前例を上げれば韓国で殺害された伊藤博文さんなんかと同じか。でも、韓国ではそのテロリスト(安重根さん)が今でも国民的英雄とされている。日本でも一部のマスコミが、山上容疑者を統一教会の被害者を代弁した英雄と祭り上げようと模索している。でも、残念なことに容疑者が狙撃したとしている銃弾が発見されていない。つまり、彼は「本当は犯人でない」なりすましの更に卑劣なテロリストなのかも知れない。つまり、野党やマスメディアが国葬反対を主張する最大の根拠は全く理由が無いようだ。
安倍氏の政治実績は、後世から見れば決して褒められたものではないかもしれない。アベノミックスも感染症対策もどうも失敗続きだったのかもしれない。でも、日本人の精神は死者は皆神様になる。今後も彼の政治実績の功罪を詳細に検証し続ける意味では、国葬も一概に悪い者でもないかもしれない。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
チャットボットとは?
チャットボット(Chatbot)とは、「チャット(Chat)」をする「ボット(bot)=ロボット」を指します。ここでいうロボットとはドラえもんのような「人や動物型のコンピュータ」の意味ではなく「自動で(何かを)行うプログラム」という意味です。簡単にいうと、チャットボットとは「自動でおしゃべり(チャット)するプログラム(ボット)」と言い換えることができるようだ。
近年チャットボットは、問い合わせ対応やマーケティング支援に利用されることが多く、顧客や従業員の疑問を解決したりコミュニケーションをとったりするなど、様々な用途で使われているという。これは消費者側から見ると大変迷惑な技術だ。情報の発信者と受け手に巨大な格差が生じてしまう。丁寧な対応かと思いきや実はボットだった?
ロボットは初めから組み込まれた答えしか返さない。逆に、ロボットが思考力を持ち、勝手な判断を行うように進化すればそれはそれで大問題だ。
こういう技術は、犯罪にも多用されそうな危険な技術でもある。情報の受け手は、話し相手がロボットであることに気がつかない場合がそうだ。実は、ボットはすでに、ウクライナ戦争に関する英国発のニュースに多用されているとか。ウクライナ戦争の情報は大部分がゼレンスキーの自撮りによる一方的なSNS情報で、それがボットを使って大量にばら撒かれている。なら、人々は一体何を信用したらいいのでしょうか。どうも現実はどうも英国情報とは異なった方向に進んでいるようですが。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
ウクライナ戦争は初めから茶番だった
2022.9月になっても、ウクライナの戦争は一向に終戦の気配はない。そもそもロシアはこの戦争?に対して宣戦布告すら発していない。侵略何て初めからしていない。親ロシア住民が多数住んでいる東部ウクライナ地域の民兵団に武器支援をした程度だったのか。東部の反乱(先に攻撃を仕掛けたのはゼレン側?)に手を焼いたゼレン政権がロシアの侵略をでっち上げたというのが本当のことらしい。つまり、ゼレン氏の自作自演が本当のことらしい。
西側諸国に送られてくる情報は、すべてゼレンの発するSNS情報で、映像は総て自撮りで戦闘の風景は無くインフラが破壊された風景のみ。英国情報機関がこれをチャットボットのようなAIでストーリーを作ってばら撒いているだけのようだ。
そもそも、戦死者の数が他の国際紛争と比べてみても著しく少ない。そもそも、首都キエフの状況は全く戦時下と思えない平穏そのものでホテルもマーケットも正常に稼働しており観光客すら訪れることも可能らしい。
ウクライナが反撃成功を主張する地域は、映像は最新ミサイル兵器の攻撃のためか、瓦礫の山の廃墟しか映っておらず、とても重要な拠点とは思えない。しかも反撃と言うにはあまりにも戦果が小さすぎる。
一方、サポリージャ原発への攻撃は、この原発が既にロシア管理下にある以上、攻撃を仕掛けているのは明かにゼレン側であり、しかも未だ稼働中の原発へのミサイル攻撃は極めて危険なもの。さすがに、国際原子力機関(IAEA)も黙ってはいられなくなり、双方の攻撃中止を。その結果、サポリージャ原発は稼働中止を決断せざるを得なくなる。サポリージャ原発は、ロシア管轄下でウクライナ国内に電力を供給(戦時下で需要低下の為70%程度)していた貴重なインフラ。更にロシアがドイツに供給していたガスも止まれば、ウクライナはそのガスのピンハネも不可能になる。
ゼレンスキーが言う通り、ウクライナ紛争は今年の冬までは続けることは不可能だろう。だから、今回のウクライナ反撃?は最後の賭け? どうすればNATO諸国の同情を勝ち取れるか? ドイツが軍隊を派遣してくれるのか?
サポリージャ原発は欧州で最大の原子力発電所とか。この原子炉が破壊されれば未曽有の大災害が生じる。原子炉への攻撃は確かにNATO諸国の同情を得られる。しかし、誰もゼレンに原子炉の管理を任せようとは思わないだろう。
ロシア国民は、プーチン氏が本気で闘っているとは誰も信じない。ウクライナの主要都市は、キエフもリビウもどこも健在でミサイルの攻撃も極めて限定的。今まで電源もガスもきちんと供給していた。宣戦布告すらこれから行おうと? ロシアが戦争しているならこんな弱いはずはない。こんな不真面目な戦争は止めろ。
ごく最近、プーチン氏と習近平氏が直接対決。ウクライナ問題は大方目途が付いたようだ。今後の両国は、協力して極東問題に対処しましょう。まずは、中国の固有の領土台湾を不法に占拠して軍事支援している米国を東太平洋から追放することだ。そもそも「一つの中国」は米国が言いだしたもの。台湾を軍事支援することなど絶対あってはならない。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
戦況地図2
 ウクライナ内戦については、NHKが経時的に戦況地図を公開している。この地図は多数のニュース記事よりも遥かに、内戦の状況を明確に表している。ウクライナゼレンスキー軍が猛反撃をしているとの報道とは裏腹にゼレンスキー軍が奪還したとされる地域は水色の周辺部に限定されている。映像は荒廃したインフラが移っているだけで、解放された人民の喜びの顔も見られない。ロシア軍が引き上げたところに侵入して勝った勝ったと騒いでいるだけのようだ。もし、ロシア軍が反撃に転じたらひとたまりもない防御には極めて不利な地勢だ。
ウクライナ内戦については、NHKが経時的に戦況地図を公開している。この地図は多数のニュース記事よりも遥かに、内戦の状況を明確に表している。ウクライナゼレンスキー軍が猛反撃をしているとの報道とは裏腹にゼレンスキー軍が奪還したとされる地域は水色の周辺部に限定されている。映像は荒廃したインフラが移っているだけで、解放された人民の喜びの顔も見られない。ロシア軍が引き上げたところに侵入して勝った勝ったと騒いでいるだけのようだ。もし、ロシア軍が反撃に転じたらひとたまりもない防御には極めて不利な地勢だ。
ウクライナ軍による原子力発電所攻撃も聞かれなくなった。IAEAの査察も行われたようだ。原子力発電所は、戦争中は稼働を止め、一切の外部からの攻撃から守られなければならない。実際に発電所は電力供給は停止する。そう言う意味では初めから原子力発電所は有害無益な産物で、将来は廃炉にすべきだろう。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
戦争は個人がするものではない
 こんな極めて当然の理屈がメディアを通すと忘れられてしまう。誰かを悪者にしないと心が休まらない大衆の性(さが)。
こんな極めて当然の理屈がメディアを通すと忘れられてしまう。誰かを悪者にしないと心が休まらない大衆の性(さが)。
例えば、ナチスドイツのヒットラー。最初は国民の多大な支持を得て政権に上り詰めた。英国なども当初は陰ながら指示を与えていた事実を忘れてはいけない。とても頼もしいリーダが徐々に凶悪な独裁者に変身。でも、それを助長して来たのは誰か?
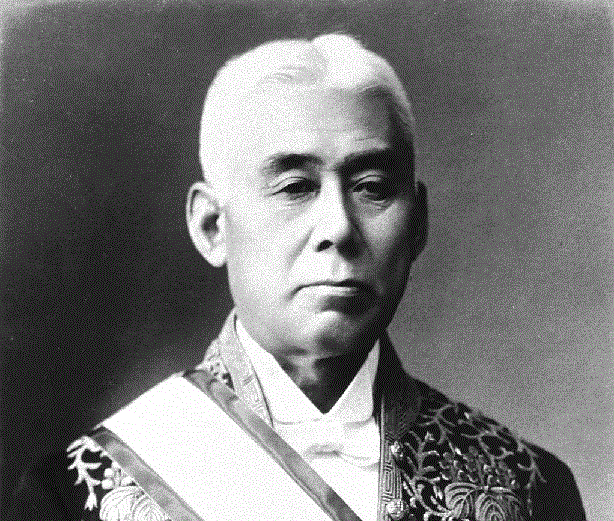 日本では、誰が戦争への道を選ばせたのか。陸軍中堅層の暴走(昭和天皇はこれを下剋上と呼んでいた)。でも、当時の日本も日本初の平民宰相・原敬をリーダとして大正デモクラシーという世界で最も民主的な政治体制への移行を進めていたところだった。一方のドイツだってワイマール憲法下で世界でも最も民主的な体制下にあったはずだ。陸軍中堅層の幹部たちは、自分達の行いが国益に沿っており、国民の支持を得ているという信念で動いている。一般大衆から徴兵された自分達の考えが国民の考えだと。当時普通選挙は実現していた。事実当時のマスメディアはクーデターを起こそうとした若手軍人達に一定の理解を示し英雄視し先導していた面は否めない。
日本では、誰が戦争への道を選ばせたのか。陸軍中堅層の暴走(昭和天皇はこれを下剋上と呼んでいた)。でも、当時の日本も日本初の平民宰相・原敬をリーダとして大正デモクラシーという世界で最も民主的な政治体制への移行を進めていたところだった。一方のドイツだってワイマール憲法下で世界でも最も民主的な体制下にあったはずだ。陸軍中堅層の幹部たちは、自分達の行いが国益に沿っており、国民の支持を得ているという信念で動いている。一般大衆から徴兵された自分達の考えが国民の考えだと。当時普通選挙は実現していた。事実当時のマスメディアはクーデターを起こそうとした若手軍人達に一定の理解を示し英雄視し先導していた面は否めない。
一方、熱い戦争は、経済戦争の延長でもある。つまり、経済的対立の無い場合、戦争は起こりえない。熱い戦争は勝っても負けても多大の損失があり、経済的な対立なら話し合いで解決は可能と言うの国際連合の理念が。双方が納得できる和解案を示すことが肝要。国際連合が多数決原理で一方のサイドに肩入れすればこれは国連の機能喪失だ。今テレビでやっている、鎌倉幕府の成立も同じだ。関東武士団間の戦いを調停するのが幕府の重要な役割だった。
日本が戦争に走る直接的な原因は石油資源の確保である。米英は経済制裁として石油の輸出を禁止した。ドイツも同じだろう。更にドイツは前大戦の多額の賠償金の支払いを課せれている。同時のこの時世界の大不況が起こる。このような国民の不安の元に過激な改革を唱え、他国を非無し戦争への道を煽るリーダの出現は、大衆が寧ろ待ち望んでいたものだろう。
経済制裁は、戦争行為の一環であり相手を挑発して戦争を引き起こすための起爆剤。つまり世界大戦へボタンは既に押されている。
今日本のマスメディアで平気で流されている「プーチン氏は凶悪な独裁者」「習近平氏は独裁体制を確立させている」との情報の真偽。明らかに悪質なデマ。プーチン氏はソビエト連邦崩壊後のロシア社会の立て直しをした国民の恩人だ。ゴルバチョフ、エリツィンと続いた社会経済崩壊を何とか立て直し、ロシア国民に自尊心を回復させた英雄でもある。つまり国民の支持率は欧米社会のリーダと比べると著しく高い。
また、プーチン氏が帝国的侵略主義者という観点も明らかに怪しい。本当は平和を愛する優しい人なのかも。やりたくもない戦争につき合わされているのかも。ウクライナ発の情報は全く一方的でゼレンスキーの自作自演の可能性が高い。ロシアの攻撃は極めて限定的。東ウクライナの親ロシアの住民達は、ロシアの併合してもらうことで初めて身の安全が確保できるのかも。
習近平さんも、安倍さんとの会談で、安倍さんは首相になるために自民党に入った。習さんはやはり主席になるために共産党に入った。しかも最初は下積みから始め周りの信頼を獲得しながら今の立場に。人民あっての主席だ。強権的独裁者は外交上の外向けの顔かも。
熱い戦争は経済戦争の延長である。中国やロシアとどのような経済上の確執があるのかを理解した上で、脅威論を展開すべきだ。いま、日本が軍事予算を拡大。適地攻撃能力? 一体全体何のため。まさか、中国が台湾の上陸作戦を強硬? ロシアが北海道に侵略?
どう考えても誇大妄想だね。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
何故今、防衛費増額の話
岸田内閣が説明に四苦八苦。何故防衛費増額が必要かの話をすっ飛ばして国会は財源の話に終始している。この点は野党も同じで増額ありきで議論している。これでは、まとまるわけがない。消費税値上げ→これ以上景気悪くしてどうするんだ。復興税からピンハネ→ダメダネまだ復興終わってないぞ。法人税値上げ→当然経済界の反対。借金超大国の日本が今増税してまで防衛費あげる根拠は全くない。
財政破綻・経済破綻に近い日本で防衛費減額の話は合ってもこの時期増額何てとんでもない話のはずだ。GDPの2%が目標。G7並み? 何故経済凋落のG7と同じにしないといけないんでしょうか。G7とは要は米英仏それに加えて先の大戦で敗戦国の独伊日。それとアングロサクソンのカナダだけだ。戦勝国米英仏は海外にもかなりの植民地的利権を保有しているからその財産防衛のための軍事力は必要かも。でも敗戦国・日独伊は軍事力何て増強しても何のご利益も無いはず。戦後の高度成長は戦争放棄の第九条憲法のおかげた。朝鮮戦争とベトナム戦争の特需もあった。つまり熱い戦争は大抵、経済戦争の成れの果て。例えば先の大戦は日本もドイツも経済封鎖で石油を止められたことが最大の原因だ。
GDPの2%と言えば人口の多い日本では金額ベースでは世界第三の軍事大国となるらしい。独仏英は人口では日本の半分以下。しかも今戦闘態勢に入っている国々だ。ウクライナ危機では兵器支援で多大の支出を強いられており、多くの志願兵や傭兵を送り込んでいる。その点日本には適地攻撃能力となるべき、仮想敵国が存在していない。GDPの2%と言うのがいかに非現実的な話か分かる。
という訳で、今防衛の要である適地攻撃能力とは一体何なのか。ウクライナ内戦を見ればお判りのように、通常のミサイル兵器は何の役にも立たないことは明々白々。ズバリ言えば核兵器。核の抑止力。しかし、核兵器は世界に拡散しており、核大国の抑止力は過去の話。
もし、北朝鮮が日本に核ミサイルを発射したらどうする。適地攻撃能力とは一体何なのか。
そもそもなぜ北朝鮮が日本を。確かに米国と韓国は国境で共同軍事演習をして何時でも北へ攻め込む能力をアピールしている。未だに朝鮮戦争は停戦交渉が出来ていない。米国の北朝鮮の攻略基地が沖縄なら確かに沖縄は北朝鮮や中国の先制攻撃の目標かも。これに対して米国が反撃してくれるかも。これが抑止力の根拠。でもこれが抑止力? 単に戦争を拡大するだけの意味しかない。
でも、もし北朝鮮を攻撃する基地が例えば沖縄なら、日本は米国に協力しているので当然攻撃の対象となっても文句は言えまい。同様に経済制裁に参加している国は当然戦争当事国と同等の待遇を受けるだろう。現在はそれに偽情報(不都合な情報)を流すことも同様だろう。
G7諸国は、既に経済封鎖に積極的に参加しており、大量の武器支援行っている。チョットしたきっかけで本格的な戦争になりかねない。因みにウクライナの隣国ポーランドにはミサイルが着地し、ロシアの攻撃とポーランド政府が発表。しかし、米国の監視システムがウクライナの自作自演(誤射)と訂正し事なきを得た。つまり、NATO諸国は能動的に何時でも戦争を仕掛ける権利を有していると言えそうだ。
日本のロシアへの経済制裁は日本側からの一方的行為であり、ロシア側へダメージも著しく少ない。更に北海道の北方4島付近の住民達にとっては歴史的に続いてきた民間の交流まで失われダメージは計り知れない。例の観光船「カズワン」の沈没事故もロシアの警備船の協力を仰いでおればあのような惨事は防げたはずだ。
ロシアへの経済制裁は100害あって一利無しの愚策。同様に日本と同じ敗戦国のドイツはもっと悲惨なようだ。ドイツ国民は頼みの綱のロシアからのガス供給を断たれこの冬は暖房無しで我慢しろ。しかもドイツは大量の武器供与までやらされている。
つまり、日本とロシアは戦争の火種になる経済的な衝突は考えにくい。寧ろロシアの方は経済交流を盛んにすることを望んでいる具合。つまり、仮想敵国となる可能性は零だ。
一方の、GNPでもうじき米国を凌駕する中国が日本を攻撃する可能性は更に少ない。日本メディアが想定するのは、もし日本が台湾の独立を支持すれば、中国が怒って戦争を仕掛ける。こんな妄想は台湾では100%否定されている。つまり台湾有事なんて存在しない。台湾は中国の友好国と非友好国の貿易を取り持つ重要な存在。日本に取っては米国以上に重要なパートナー。と言うより昔は台湾は日本の一部だったことを忘れてはならない。
軍事費増額は多くの国民が反対している案件だ。ところが対米従属を重視したい野党は軍事費増額を言わないと顔が立たない。でも愚策だ。結局、財源の話から当面はこの話はお預け、コロナや温暖化やウクライナの件が一段落してから慎重に議論だね。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
英国の陰謀
ウクライナ内戦でロシア側が苦戦している? 専ら、英国発の情報だ。歴史を良く学べば何故こんな報道を発信しているのか理解できる。日露戦争を思い出せばよい。英国は戦争の間中、ロシアは負け続けているとの報道を流し続けた。確かに帝国海軍の働きは見事だった。しかし、陸戦ではロシアは負けてはいなかった。戦いの被害は明かに日本が不利だった。戦死者数は圧倒的に日本が多い。しかし、情報戦ではロシアが負けていることが既成事実で、ロシア国内世論すら反戦へ傾く、遂には革命で政権崩壊。英国は結局、手を汚さずにロシアを負かすことに成功。
ウクライナ内戦でロシア側が苦戦している?こちらはどうか。ゼレンスキー側(ウクライナ人の半分は親ロシア派)が反撃に転じた。あちこちで勝利しつつある。
ゼレンスキー側の兵器は米国が事前に供与していたものらしい。最新兵器を揃えているという情報はそのことを示している。つまり、今回の戦争は、ゼレンスキー側が周到に準備して仕掛けたものらしい。つまり、米国が支援するのことが大前提だったはずだ。
しかも、ゼレンスキー側の兵は、外国人の傭兵や志願兵で、後は無理やり徴兵したものばかり、従来の国軍は機能していない(プロの軍人の指示は得られない)。つまり、都市の建物に市民を盾にして立てこもり、ゲリラ戦で応じているだけのようだ。
経済制裁を続けて、メディアでロシアの苦戦を発信し続ければ、ロシア(プーチン)は音を上げ降参するはずと宣伝しまくっている。でも、現実の戦いは完全に封鎖された状態での兵糧攻めだ。つまり、ロシア軍は余り兵力を消耗していない。住民を盾にしているので、ある程度反撃に動いてくれないと戦いにもならない。勢力を温存して反撃を待っているだけだ。
ロシア側が苦戦しているとの情報に、ゼレンスキー側が反撃を試みてくれれば渡りに船。つまり、苦戦しているふりを意図的にやっている。
果たして、英国はゼレンスキーの味方? ゼレンスキーのSOSに本気で対応している。英国の努力で、ロシア包囲網は完成したようだけど。経済制裁も本格化。それでロシアは困っている? 実際困るの制裁した側のようだ。武器を送ると約束しても兵まで出す国どこにある。エネルギーなどの資源輸出能力はいまやほとんど非米諸国側。
武器を搬入するにも兵はいる。つまり、ゼレンスキーはどこかで降参せざるを得ない。米国は許すはずはないが。少なくとも英国は手を汚す気は全く無いはずだ。
このまま続けば、G7諸国は経済的に疲弊し分裂するだけだ。物価は急上昇。株価もどんどん低迷。英国の安全のためにはNATOやEUが崩壊して、米国の覇権が極力小さくなることが最も望ましい。いずれ、ウクライナは中立の国になる。東ヨーロッパも中立の国に。米国の大富裕層達の考えと同じ。ロシア、中国、インドも一緒になったグローバルな社会の建設が資本主義経済のさらなる発展のためには絶対必要だから。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
パトリオットミサイル
 パトリオットミサイル(MIM-104 Patriot、MIM-104 パトリオット)は、アメリカ合衆国のレイセオン社がMIM-14 ナイキ・ハーキュリーズの後継としてアメリカ陸軍向けに開発した広域防空用の地対空ミサイルシステム。ミサイル防衛では終末航程**に対応し、20 - 30 kmの範囲を防御。
パトリオットミサイル(MIM-104 Patriot、MIM-104 パトリオット)は、アメリカ合衆国のレイセオン社がMIM-14 ナイキ・ハーキュリーズの後継としてアメリカ陸軍向けに開発した広域防空用の地対空ミサイルシステム。ミサイル防衛では終末航程**に対応し、20 - 30 kmの範囲を防御。
**ミサイル防衛(Missile Defense, MD)または弾道ミサイル防衛(Ballistic Missile Defense, BMD)は、主に弾道ミサイルからある特定の区域を防衛すること及びその構想。敵のミサイルを迎撃するミサイル防衛は時代と共にその名称が変遷。
湾岸戦争時に、イラク軍が発射したスカッドミサイルを撃墜したことにより有名になった。米国のほか、日本を含む同盟国など世界10か国以上で運用されている。パトリオットミサイルは厳密にはミサイルそのものを指すが、付帯するミサイル発射システムを含めてパトリオットミサイルと呼ぶ場合もある。「MIM-104」はミサイルの形式名称、「Patriot」はその愛称で、「Phased array Tracking Radar to Intercept on Target」(直訳:目標物迎撃用追跡位相配列レーダー)のバクロニムであるとされる。
発射システム概要
パトリオットミサイル発射システムはトレーラー移動式のシステムであり、1つの射撃単位はパトリオット発射中隊によって運用される射撃管制車輌、レーダー車輌、アンテナ車輌、情報調整車輌、無線中継車輌、最大で8輌のミサイル発射機トレーラー、電源車輌、再装填装置付運搬車輌、整備車輌という10台以上の車両により構成される。これらの車両が自走して野外に発射サイトを設営後、射撃体勢が整う。一個大隊は指揮所運用中隊、整備補給中隊および最大で6個の射撃中隊から編成される。
ナイキの発射システム**よりも省力化が図られている。交戦時に人員が配置されるのは射撃管制車だけで、無人となったレーダーや発射機等は射撃管制車からの遠隔操作によって制御される。
**ナイキの発射システム
ナイキミサイルとは、アメリカ製の地対空ミサイル。日本でも、航空自衛隊が地対空誘導弾ナイキJとして採用。ギリシャ神話の勝利の女神「ニケ(Nike)」より。“ナイキ”は英語読み。1953年からアメリカ合衆国のウエスタン・エレクトリック・カンパニーなどで開発された高高度迎撃用地対空ミサイル。高々度から飛来するソビエト連邦の爆撃機に対する拠点防空を主目的とする2段式のミサイルであり、発射台から発射される。地上からのレーダーによって誘導される、セミ・アクティブ・レーダー・ホーミング方式。
どうも、軍事費増大の裏で日本の自衛隊が最も導入をしたいとする兵器の一つのようだ。ゼレンスキーも米国に頼み込んで上手く入手に成功したらしい。ミサイル防衛システムは適地攻撃能力が無いような説明だが、本当にそうなのか。
ミサイル戦では、攻撃よりも防御の方が遥かに難しいし値段も遥かに高額。更にこのシステムが有効に機能するかどうかは、実戦で使って見て実証する以外にない。
湾岸戦争の時のように、超一方的な戦争で効果があったというのはまだ試行実験レベルと言うことだ。イラク側がこのシステム使って米軍の攻撃を止めたなら絶大な効果だ。効果の確認は大成功。ゼレンスキーはウクライナにおいて実証実験を行う予定なのか。
この盾は、本当にどんな矛でも通さない? でも、そんな盾も難なく通す矛はすぐに開発されてしまうのが現実の世界のようだが。こんなシステム開発するより、互いにミサイルなんか発射しなくて良いように、相互の話し合いで軍縮を進めて行く方が遥かに経済的で安全なはずだが。
パトリオットミサイル(MIM-104 Patriot、MIM-104 パトリオット)は、アメリカ合衆国のレイセオン社がMIM-14 ナイキ・ハーキュリーズの後継としてアメリカ陸軍向けに開発した広域防空用の地対空ミサイルシステム。ミサイル防衛では終末航程**に対応し、20 - 30 kmの範囲を防御。
**ミサイル防衛(Missile Defense, MD)または弾道ミサイル防衛(Ballistic Missile Defense, BMD)は、主に弾道ミサイルからある特定の区域を防衛すること及びその構想。敵のミサイルを迎撃するミサイル防衛は時代と共にその名称が変遷。
湾岸戦争時に、イラク軍が発射したスカッドミサイルを撃墜したことにより有名になった。米国のほか、日本を含む同盟国など世界10か国以上で運用されている。パトリオットミサイルは厳密にはミサイルそのものを指すが、付帯するミサイル発射システムを含めてパトリオットミサイルと呼ぶ場合もある。「MIM-104」はミサイルの形式名称、「Patriot」はその愛称で、「Phased array Tracking Radar to Intercept on Target」(直訳:目標物迎撃用追跡位相配列レーダー)のバクロニムであるとされる。
発射システム概要
パトリオットミサイル発射システムはトレーラー移動式のシステムであり、1つの射撃単位はパトリオット発射中隊によって運用される射撃管制車輌、レーダー車輌、アンテナ車輌、情報調整車輌、無線中継車輌、最大で8輌のミサイル発射機トレーラー、電源車輌、再装填装置付運搬車輌、整備車輌という10台以上の車両により構成される。これらの車両が自走して野外に発射サイトを設営後、射撃体勢が整う。一個大隊は指揮所運用中隊、整備補給中隊および最大で6個の射撃中隊から編成される。
ナイキの発射システム**よりも省力化が図られている。交戦時に人員が配置されるのは射撃管制車だけで、無人となったレーダーや発射機等は射撃管制車からの遠隔操作によって制御される。
**ナイキの発射システム
ナイキミサイルとは、アメリカ製の地対空ミサイル。日本でも、航空自衛隊が地対空誘導弾ナイキJとして採用。ギリシャ神話の勝利の女神「ニケ(Nike)」より。“ナイキ”は英語読み。1953年からアメリカ合衆国のウエスタン・エレクトリック・カンパニーなどで開発された高高度迎撃用地対空ミサイル。高々度から飛来するソビエト連邦の爆撃機に対する拠点防空を主目的とする2段式のミサイルであり、発射台から発射される。地上からのレーダーによって誘導される、セミ・アクティブ・レーダー・ホーミング方式。
どうも、軍事費増大の裏で日本の自衛隊が最も導入をしたいとする兵器の一つのようだ。ゼレンスキーも米国に頼み込んで上手く入手に成功したらしい。ミサイル防衛システムは適地攻撃能力が無いような説明だが、本当にそうなのか。
ミサイル戦では、攻撃よりも防御の方が遥かに難しいし値段も遥かに高額。更にこのシステムが有効に機能するかどうかは、実戦で使って見て実証する以外にない。
湾岸戦争の時のように、一方的な戦争で効果があったというのはまだ試行実験レベルと言うことだ。イラク側がこのシステム使って米軍の攻撃を止めたなら絶大な効果だ。効果の確認は大成功。ゼレンスキーはウクライナにおいて実証実験を行う予定なのか。
この盾は、本当にどんな矛でも通さない? でも、そんな盾も難なく通す矛はすぐに開発されてしまうのが現実の世界のようだが。こんなシステム開発するより、互いにミサイルなんか発射しなくて良いように、相互の話し合いで軍縮を進めて行く方が遥かに経済的で安全なはずだが。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
パトリオット続2
 ウクライナのゼレンスキーがわざわざ米国まで出かけてパトリオットミサイル発射システムの米国からの供与に成功したらしい。本当にこんなもの使って勝てると信じているのかしら。米国の武器では鳴り物入りの虎の子だ。サウジに配置しているのを引き上げてウクライナに移動するらしい。
ウクライナのゼレンスキーがわざわざ米国まで出かけてパトリオットミサイル発射システムの米国からの供与に成功したらしい。本当にこんなもの使って勝てると信じているのかしら。米国の武器では鳴り物入りの虎の子だ。サウジに配置しているのを引き上げてウクライナに移動するらしい。
サウジが原油増産に同意しなかったからの制裁らしい。サウジにとっては原油は虎の子だ。脱炭素何て原油を使わないように言っている欧米に増産して安売り何て出来るはずが無い。ウクライナに持っていくのが最初からの意図だろう。
パトリオットが本当に虎の子なのか単なる張り子の虎なのか、使って見ないと分からない。ロシアなどはやって見ろと寧ろけしかけている感がある。もし、パトリオットが張子の虎ならウクライナは今さら攻撃を止めてくれとは言えない。極めて危険な賭けだ。
日本に取っては張子の虎であることが明らかになれば、無駄で高額な兵器を購入しなくても良いけど。(2022.12.26)
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
ゼレンスキーはファシスト?2
ウクライナの裁判所は1日、キーウにあるキリスト教東方正教会の「キーウ・ペチェルシク大修道院」トップが、ロシアのウクライナ侵略を正当化し、宗教間の憎悪を扇動した疑いがあるとするウクライナ情報機関の主張を支持し、60日間の自宅軟禁を命じた。
日本のマスメディアではロシア正教会と表記されるが、実際は正教会が一つあるだけらしい。つまりウクライナ正教会もロシア正教会も対等で支配関係は無いとか。そもそもはローマ帝国が認めた唯一の正統のキリスト教と言うことらしい。因みにカトリックは西ローマ帝国滅亡後に新たに造られたもの。つまり捏造された教会だ。
正教会は、そもそもソビエト連邦時代は、「宗教は阿片」で弾圧されて来た歴史がある。正教会のスタンスは、世俗的な政治的判断をしないようで、ロシアの侵略も非難しない代わり、ゼレンスキーの判断も支持しないと予測される。
因みにゼレン自身は、ユダヤ教を信じないユダヤ人。ヒットラーにもユダヤ人の地は流れているらしい。でも、彼はユダヤ教を信じないユダヤ人。どんな思想にも気軽に変身できる。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
戦争の当事者
ウクライナ内紛はどうも、現実には経済成長するロシアを米国が何とか制裁しようというのが意図だったようだ。現実にゼレンスキーは、米国+NATOの支援した大量の兵器でNATO諸国が派遣した傭兵達の助けで戦争しているだけらしい。
そもそも、AIで自動操作され多くの戦士が不要な現代の戦争は兵士の数は問題では無いようだ。「同情するなら武器をくれ」。そう今の戦争は正義とか兵士の数ではなくお金で成果を買う時代なのだ。
 米国が虎の子のパトリオットを供与したことで、この戦争の主役はウクライナではなく、米国であることが自明となった。ウクライナでの戦果は米国の国益に直結するというのが米議会の大勢の意見。
米国が虎の子のパトリオットを供与したことで、この戦争の主役はウクライナではなく、米国であることが自明となった。ウクライナでの戦果は米国の国益に直結するというのが米議会の大勢の意見。
英国の得意の情報作戦。ロシアは戦費が枯渇している。経済困窮で内部崩壊?でもこの戦争で米国とロシアのどちらが多額の戦費を出資しているか。ロシアは東ウクライナのいくらかの既に自国の自治州として確保し住民投票まで実施して、戦闘過激な地域の住民を安全な地域の避難させ、もっぱら専守防衛策。ウクライナ軍はミサイル攻撃で廃墟となった街に大量のミサイル攻撃をかけ旗を上げて勝った勝ったと旗を振っている。しかし、一向にゼレンスキーの支配地は広がる気配もない。戦闘はゼレンスキーの自作自演のようだ。どうせ費用は米国持ちだ。思い切り派手に行きたい。
つまり、ロシアの徹底したケチケチ作戦に対して、米国の大量の資金力。戦争は兵士がするのは時代遅れ。決定打は武器? 勝利はお金で買うものだ。ロシアは資源外交があるが、米国は基軸通貨のドルがある。足らなくなればいくらでも印刷すれば出て来る。米国の資金力は無尽蔵のようである。
ゼレンスキーは降参しない。何故なら武器は無尽蔵に供給されるから。米国はゼレンスキーに負けを許さない。ウクライナは来年もミサイルの飛びかう国になるのかしら。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
ロシアは負けない
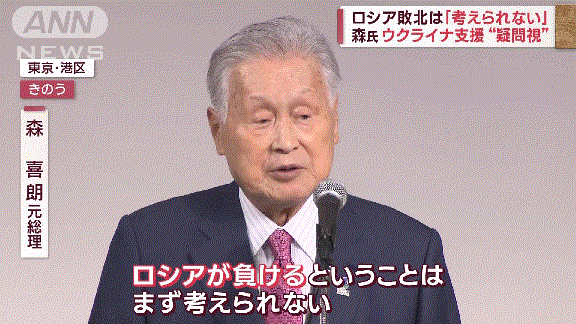 「ロシアが負けることは、まず考えられない」──これが、かつて日本のトップだった人物の発言だ。森喜朗・元首相(85)は1月25日、日印協会の創立120周年記念レセプションであいさつし、ウクライナへの侵略を続けるロシアを擁護した。
「ロシアが負けることは、まず考えられない」──これが、かつて日本のトップだった人物の発言だ。森喜朗・元首相(85)は1月25日、日印協会の創立120周年記念レセプションであいさつし、ウクライナへの侵略を続けるロシアを擁護した。
マスメディアの極論ここに極まりだね。森喜朗さんは日本の総理も務めた重鎮が現状を分析した結果だろう。別にロシアの肩を持っている訳でもない。世論(せろん)の9割以上が欧米のプロパガンダ情報を鵜呑みにしている現状。もっと現実を見つめなさい。
戦前の日本だって敗戦直前まで勝った勝ったのオンパレードだったことを忘れているのか。
「ロシアがウクライナに侵入した」で始まり、最初は皆で経済制裁をかけましょう。2~3カ月でロシアは経済崩壊に陥り降参する。でも、降参しない。次は、プーチンさんは気違いだから戦争を止めない。経済支援が必要だ。まだ、懲りないどんどん軍事兵器支援しろ。今度はドイツが最新鋭の戦車を供与? 既にゼレンスキーは旗振り役。実際に戦争しているのは米国とNATOの最新兵器だけだね。ウクライナ国民にとっては全く迷惑な話。ゼレンスキーの独裁政権は早く崩壊して貰わないと本当に国中が廃墟と化してしまうぞ。
毎日ニュースを見ていて、本当にウクライナが勝利してロシアの自治州と化した東ウクライナの解放に成功する見込み多少でもあると思う人があるだろうか。「米国が負けることは、まず考えられない」。全くの神話だ。ベトナム戦争。イラク戦争。アフガン戦争。どれも米国が支援した傀儡政府は腐敗崩壊。結局、米国は引き下がる以外にない。
ドイツが参戦すれば、独ソ戦の再来となってしまう。ナチスドイツの敗北は独ソ戦での敗北が決定打だった。ドイツが最新鋭の戦車を供与するということは宣戦布告と同じ意味。ドイツ陸軍は何時そんなに強くなったんだ。NOTO全軍が協力しても通常兵器を使っている限り難しい。極めてリスキーな話だ。
「ロシアが負けることは、まず考えられない」「そう、全くその通りだろう。」米国が欧州大陸で勝利するためには核兵器を使う以外に考えられない。ドイツが最新鋭の戦車を供与するためには米国がそれ以上の兵器を供することが大前提。でも、米国は戦場にはならないからやるかね。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
ウクライナは核保有国?
核兵器による東西冷戦時代の一方の雄、ソ連邦は崩壊し、共産主義の恐怖からは欧米諸国は解放されたはずだ。それでは、それまでソ連邦が所有していた核兵器は総てロシアが引き継いだのか。当然、ソ連邦を構成する他の主要国、ウクライナや白ロシアにはかなりの核兵器が移転されていると見た方が妥当だろう。もちろん公式にはこんなことが公表されている筈もない。イスラエルだって、最近は核兵器所有を隠さないけど従来ズット核兵器保有を隠蔽していた。ウクライナが核兵器を持っているはずが無い。全くお人好しの議論だね。ウクライナは欧州で最大の原子力発電保有国だ。当然核技術者も大勢連れてきているはず。しかも、戦時下にもかかわらず通常に稼働している。ロシアは止めるべきと言っているが。
マスコミでは、ウクライナはソ連邦の植民地でウクライナ人はロシア人に虐待を受けていたような説明がなされている。これは明かに史実と異なる。ウクライナで多くの農民が略奪虐殺を受けたとあるが、これはボルシェビキ政権が、都市労働者の飢餓を解決するため農民たちを悪者に仕立て国民の憎悪を煽ったため。都市労働者は革命の主役だけど、農民達はプチブルで資本主義の敵だ。この思想を宣伝したのはやはりウクライナ出身の思想家や革命家。もちろん白ロシア(ベラルーシ)やロシアの人達も一緒だけど。つまり、ロシア3兄弟たちの仕業。
だから、当然のことではあるがウクライナは独立時にはロシア3兄弟たちで仲良くやって来れたはずだ。いわゆるカラー革命が起こるまでは。欧米では民主化と称されている暴力革命。
もとコメディアンのゼレンスキーは欧米の諜報機関や民主化NGOの支援なしにはとても一国の大統領になれる可能性は無い。ウクライナ国民にとってはロシアも米国も敵ではない。戦争なんて全く不要だ。ゼレンスキー内閣の存立基盤は欧米の軍事支援だけだ。しかし、ゼレンスキーは最後の切札を持っている。核兵器のボタンを持っていること。
もし、ゼレンスキーがこのボタンを押せば、ロシアは対抗して米国へ核ミサイルを発射することは必然。どちらかが降参するまで核兵器のやり取りが続く最悪の事態。もし、ゼレンスキーが核ミサイルを米国や欧米諸国に直接打ち込んでも、彼らはゼレンスキーを責めることもできずロシアとの戦争になってしまう。
欧米諸国が、もとコメディアンのゼレンスキーの一言一句に迎合し、平伏して服従せざるを得ないのはゼレンスキーがソ連由来の核兵器を押さえているからだろう。NATO諸国が最新鋭戦車や戦闘機まで供与しなければならない事態は明かに異常だ。次は核兵器の使用となることは目に見えている。
開戦開始後1年たって、今回の米バイデン大統領のお忍びウクライナ訪問はやはり異常な事態だ。支援しているはずの米国のリーダが、土下座してゼレンスキーに懇願。この訪問にはロシアの諜報機関の多大の協力があったとか。核戦争の危険は米ロ協力して阻止しないといけない。命を賭してのウクライナ入りだ。キューバ危機以上の遥かに危険な水域に入ってきたようだ。
日本の自民党内には岸田首相もウクライナ訪問すべきとの愚論もあるようだが、危険でもあるし不可能なこと。事態は話し合いで解決する段階をとっくに越えている。安倍氏の二の舞になるのが目に見えている。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
バイデンの電撃キエフ訪問
岸田内閣内で総理も早くキエフを訪問すべきだ等とトンチンカンな議論が出でいるらしい。バイデンさんの今回の訪問はとても苛酷な旅だったらしい。ポーランドから列車で10時間、他のEUのリーダも実は皆列車でキエフに入っているらしい。つまり、制空権は既にロシア(あるいはウクライナの旧国軍民兵達)に制覇されている。ロシアの協力無しではキエフ訪問は不可能な話。でも列車の旅は更に危険なはず。つまり、バイデンさんの訪問は教祖ゼレンへのお目通りが叶ったということらしい。また、欧米主要国とロシアは一見戦争状態だが、実は裏では微妙な取引が続けられていることに。日本は当然蚊帳の外。
実は、先に述べたようにウクライナはロシアやベラルーシ(白ロシア)と同じく旧ソ連を支配していた官僚達が作り上げた国。当然ロシアがもっているように核弾頭を多数保有しているはずである。カラー革命で民主化したとされているがその強権的体質は全く変わっていない。バイデンさんはウクライナに核弾頭を使わないように説得しているはずであるが、そんなことを簡単に聞く相手ではなさそうだ。初めは経済制裁やればロシアは数カ月で降伏すると豪語していた米国が、実際は大規模な軍事支援しても全く効果無し。後は核を使う以外にない。ゼレンスキーもしびれを切らして怒っている。何故欧米諸国(米、英、仏、独)のリーダ達がかくも簡単にゼレンの要求に平身低頭して従わざるを得ないか。ゼレンスキーが負けたら困るからだろう。日本は今のところ蚊帳の外、余計なチョッカイを出しては核のターゲットにされることに。
ロシアが繰返し、核報復を辞さないと言っているのは、ウクライナが先制攻撃を仕掛けることを警戒しているためだろう。ウクライナの戦争はメディアで報道されているような激しいものではなさそうだ。ロシアもウクライナもまだまだ余力がありそう。少なくとも当面はロシア側が折れることはなさそうだ。
更に危険なことは、戦闘中にもかかわらずウクライナには未だ稼働している原子力発電所が15か所以上ある。これらの原子力発電所がミサイル攻撃でメルトダウンしたら、欧州もロシアも中国も日本も放射能に汚染される。これも欧米各国への大きな脅しになっている。ロシアは原発の稼働を止めるべきだとして原発周辺のインフラを壊しており、サポリージャの原発、チェルノブィリの原発は一応管理下に収めたが、未だ多数の原発が稼働中。ロシアも核兵器だけは使わないようにしたいのは米国と同様だろう。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
バフムート陥落
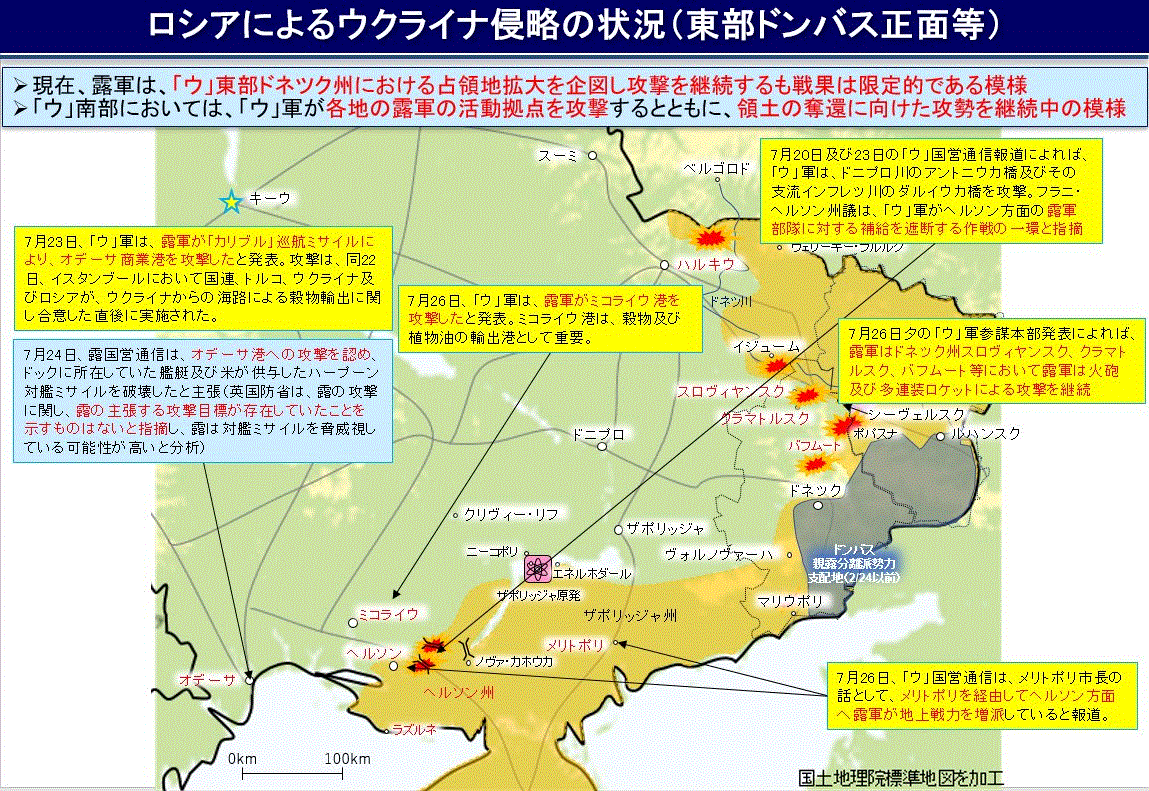 ロシアは2つ目の激戦を勝利しそうな状況になっている。バフムート市は人口7万程度の街だけど何故この地が重要なのか。ここがNATO軍の事実上の基地と言うことらしい。映像ではこの地は既に廃墟と化しており住民の影は無い。大量の兵器がこの地に投下されているらしい。欧米諸国が供与した兵器の墓場状況らしい。
ロシアは2つ目の激戦を勝利しそうな状況になっている。バフムート市は人口7万程度の街だけど何故この地が重要なのか。ここがNATO軍の事実上の基地と言うことらしい。映像ではこの地は既に廃墟と化しており住民の影は無い。大量の兵器がこの地に投下されているらしい。欧米諸国が供与した兵器の墓場状況らしい。
一つ目のマウリポリは、元地下核シェルターがあって、ここに欧米からの義勇兵や傭兵達が割拠しており、事実上ゼレンスキー軍を統括していた本拠地だったらしい。幹部は米国や英国の諜報機関からの志願兵だったようだ(ただしこれはロシア側の調査)。
ロシアの世論調査では、ウクライナ人は敵だと思っている人は数%で、真の敵は米国とNATO とはっきりと割り切っている。だから欧米の期待に反してプーチン氏の支持率は下がらない。逆にウクライナでこの調査を行えば? 勿論こんな調査が可能なはずはないが、ウクライナの人口の20~30%程度はロシア人とか。では真の敵は?多くの人達は早く戦争が終わって平和になればいいと思っている。勝利するまで戦うべきなんて思っている人がいるはずも無かろう。敗戦直前の日本と同じ状況だ。
 現代の戦争は、国民皆兵の徴兵令で兵士を確保しても勝てるものではない。近代兵器の購入には膨大な費用が必要だ。ウクライナの人々はこの戦争においては完全に蚊帳の外、単なる犠牲者でしかない。
現代の戦争は、国民皆兵の徴兵令で兵士を確保しても勝てるものではない。近代兵器の購入には膨大な費用が必要だ。ウクライナの人々はこの戦争においては完全に蚊帳の外、単なる犠牲者でしかない。
NATO諸国は膨大な兵器を導入してロシア軍を破ろうとしているが、ウクライナ自身は全く蚊帳の外。ロシアは既に東部地区の一部を押さえており、あえて攻撃を仕掛けてこない。バフムートは全くの例外。ここはNATO軍の要所だから。バフムートが落ちれば、ゼレンスキーも容赦なく停戦に応じざるを得ない。或いは既にそれを望んでいる。NATO諸国は何とかゼレンスキー政権を維持したいのだろうが、残る手段は、核兵器を使う以外にないだろう。
ドイツ軍の自慢の戦車隊をどうやって使うつもりだろうか。西部ポーランド国境から東のロシアとの国境地帯のバフムートあたりまで陸路で進軍?こんな行動はウクライナの人達が歓迎してくれるとは思えない。ナチス軍の再来としか映らないだろう。 或いは航空機で運び込む? 或いは戦闘機を供与。航空圏はどうもロシア側にとっくに握られている。バイデンさんが10時間かけて鉄道でキエフに入ったこと記憶しているでしょう。NATOが軍事支援を止めればゼレンスキーは容赦なくロシアと仲直りしてロシア側についてしまうかもしれない。そもそもウクライナ国民が本当に総てのロシア人を国から追い出すまで戦いを続けたいと願っているとは誰も信じない。いま、関係国は皆停戦の模索をしているはずだ。林外務大臣がG20の参加を見送ったことは多分正しい判断だったんでしょう。
バフムートは、上の地図では反ゼレンのウクライナ民兵達の拠点(地図の灰色部分)の近傍ではないか。当然NATO軍への反発は大きいところだ。欧米からの義勇兵たちで構成されるウクライナ軍が苦戦することは当然予想される。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
ウクライナファシズム
 地図はウクライナの民族分布とでもいえよう。これを見ればウクライナ東部はロシア語を母語とするウクライナ人で、概ねカラー革命で追放されたヤヌコビッチ大統領に投票した地域だ。当然今のゼレンスキー政権には不満のはずだ。ゼレンスキーが無理やりウクライナ語を強制したロシア敵視政策をすれば、ロシアに支援を要請せざるを得ない。
どうもロシア人は無根拠に悪者にされており、市民も財産没収やテロ攻撃を受けていると。これがプーチンがゼレンスキーをナチズムと呼ぶ所以らしい。
地図はウクライナの民族分布とでもいえよう。これを見ればウクライナ東部はロシア語を母語とするウクライナ人で、概ねカラー革命で追放されたヤヌコビッチ大統領に投票した地域だ。当然今のゼレンスキー政権には不満のはずだ。ゼレンスキーが無理やりウクライナ語を強制したロシア敵視政策をすれば、ロシアに支援を要請せざるを得ない。
どうもロシア人は無根拠に悪者にされており、市民も財産没収やテロ攻撃を受けていると。これがプーチンがゼレンスキーをナチズムと呼ぶ所以らしい。
どうも、ロシアの侵入も実際はウクライナ側の自作自演が本当らしい。勢いに乗ってキエフまで攻め入ったがこれが罠と知って、後退。しかし、時すでに遅し、いつの間にか侵入のニュースだけが拡大解釈されて広まってしまったようだ。
ソ連邦=ロシア、ウクライナはソ連の植民地。とんでもない歴史の歪曲である。
同じような歴史を歪曲したナチズムはバルト三国、ロシア人の人口が20%を越えている。ロシア人経営の会社を没収したり、ロシア系市民に弾圧を加えてNATO諸国にいい顔をしていると、それこそ痛い目にあう可能性もある。
【追記】
米国でも、ルーズベルト大統領の時代に多くの日本人が財産を不法に没収され強制収容所に強制連行された事実がある。多くの日系人は米国に忠誠を誓って愛国心を持っていた。ナチス化のドイツも多くのユダヤ人達は他のドイツ市民と同様な愛国心のある善良な人達だった。ホロスコープはヒットラー一人が悪者で実施した訳ではなく、多くのドイツ人や周辺の国の人達も積極的に加勢した共犯者だったことを忘れてはならない。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
WBC
ワールド・ベースボール・クラシック(World Baseball Classic、略称:WBC)。今年(2023年)は日本中が沸いたね。メジャーリーグベースボール(MLB)機構とMLB選手会により立ち上げられたワールド・ベースボール・クラシック・インク(WBCI)が主催。世界野球ソフトボール連盟(WBSC)公認の野球の国・地域別対抗戦で、かつ、世界一決定戦。
2023年日本は3年ぶりの優勝とか。3月21日の準決勝のメキシコ戦。翌22日の決勝の米国戦。ともに最後まで勝敗の行方の分からない大接戦を制しての勝利だ。
 1990年代後半頃からメジャーリーグベースボール(MLB)では、東アジアや北中米カリブ海諸国の選手を中心にMLBの国際化が進み、彼らの様なアメリカ合衆国以外の国籍を持つMLB選手による活躍が著しくなる。また、2000年代初頭から日本やメキシコ等のアメリカ合衆国外でMLB開幕戦を開催するなどして、本格的なMLBの世界進出(グローバル化戦略)によるMLB拡大と野球マーケットの拡大、それに伴う収益の拡大を目指していたMLB機構のバド・セリグコミッショナーは「野球の世界一決定戦」の開催を提唱。関係各所で国際野球連盟(IBAF)主催の大会に出場していないメジャーリーグ選手を中心とした各国のプロ・アマ野球リーグ選手による国別世界一を決める国際大会の開催へ向けて協議がなされてきた。
1990年代後半頃からメジャーリーグベースボール(MLB)では、東アジアや北中米カリブ海諸国の選手を中心にMLBの国際化が進み、彼らの様なアメリカ合衆国以外の国籍を持つMLB選手による活躍が著しくなる。また、2000年代初頭から日本やメキシコ等のアメリカ合衆国外でMLB開幕戦を開催するなどして、本格的なMLBの世界進出(グローバル化戦略)によるMLB拡大と野球マーケットの拡大、それに伴う収益の拡大を目指していたMLB機構のバド・セリグコミッショナーは「野球の世界一決定戦」の開催を提唱。関係各所で国際野球連盟(IBAF)主催の大会に出場していないメジャーリーグ選手を中心とした各国のプロ・アマ野球リーグ選手による国別世界一を決める国際大会の開催へ向けて協議がなされてきた。
** MLB;メジャーリーグベースボール(Major League Baseball)は、アメリカ合衆国、及びカナダ所在の合計30球団により編成されるプロ野球リーグ。北米4大プロスポーツリーグの1つ。厳密には、1903年に発足したナショナルリーグとアメリカンリーグの2つのリーグ(日本のセリーグとパリーグのような)の共同事業機構で、両リーグの統一的運営をしている。日本では「メジャーリーグ」「大リーグ」とも呼ばれる。「大リーグ」の呼称は、メジャーリーグの別名「ビッグリーグ (Big League)」の訳語である。
 2005年5月にMLB機構が翌年3月に野球の世界大会を開催する事を発表。7月12日にMLBオールスターゲーム開催地のデトロイトで、参加が確定していなかった日本とキューバを除く14カ国の代表が出席して、開催発表記者会見が行われ、大会の正式名称が“World Baseball Classic”と発表された。
2005年5月にMLB機構が翌年3月に野球の世界大会を開催する事を発表。7月12日にMLBオールスターゲーム開催地のデトロイトで、参加が確定していなかった日本とキューバを除く14カ国の代表が出席して、開催発表記者会見が行われ、大会の正式名称が“World Baseball Classic”と発表された。
当初、日本(NPB)はMLB側の一方的な開催通告やMLB中心の利益配分に反発し、参加を保留。日本プロ野球選手会も開催時期の問題から参加に反対し、2005年7月22日の選手会総会で不参加を決議した。しかし、MLB機構は参加を保留するNPBに対し、改めて参加を要求し、もし日本の不参加によりWBCが失敗に終わった場合、日本に経済的補償を要求することを通達。更に、WBCへの不参加は「日本の国際的な孤立を招くだろう」と警告した。これを受けて、日本プロ野球選手会は不参加の方針を撤回。最終的に同年9月16日に選手会の古田敦也会長がNPB機構に参加の意向を伝え、日本の参加が決まった。その結果、2006年3月にMLB機構が選抜した16か国・地域が参加する第1回大会が開催された。なお、MLB機構はこの大会を夏季オリンピックの野球競技に代わる国際大会として育てたい意向である。
**NPB機構:Nippon Professional Baseball (日本野球機構, Nippon Yakyū Kikō) or NPB is the highest level of baseball in Japan. Locally, it is often called Puro Yakyū (プロ野球), meaning Professional Baseball. Outside of Japan, it is often just referred to as "Japanese baseball".
The roots of the league can be traced back to the formation of the "Greater Japan Tokyo Baseball Club" (大日本東京野球倶楽部, Dai-Nippon Tōkyō Yakyū Kurabu) in Tokyo, founded in 1934, and the original circuit for the sport in the Empire founded two years later, the Japanese Baseball League (JBL), which continued to play even through the final years of World War II. The organization that is today's NPB was formed when the JBL reorganized in 1950, creating two leagues with six teams each in the Central League and the Pacific League with an annual season-ending Japan Series championship play-off series of games starting that year.
The NPB also oversees the Western League and the Eastern League, NPB's affiliated minor leagues.
Since the first Japan Series in 1950, the Yomiuri Giants have the most championships with 22, and the most appearances with 37. Entering the 2023 season, the Orix Buffaloes, who defeated the Tokyo Yakult Swallows 4–2–1 in the 2022 Japan Series, are the reigning champions. The Japan Series has been contested 73 times as of 2022, with the Pacific League winning 37 and the Central League winning 36.
たかが野球、しかしこの裏には日米の経済戦争の一面が隠されてもいる。多分日本が勝利したための経済的波及効果は相当大きいのでしょう。しかし、実際にそういう思惑を離れて選手たちの勝利への情熱。大いに楽しませてもらいましたね。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
国際刑事裁判所
我が国の裁判所の機能実態は明白だろう。最高裁判所を頂点に高裁→地裁→家裁等の組織がピラミッド組織となっており、三権分立の憲法の基盤石?の基盤を有している。
では、国際刑事裁判所(International Criminal Court; ICC)とは一体全体何者なのか。国連の下部機関? 何でも個人の国際犯罪を裁く常設の国際裁判所となっている。本部はオランダのハーグ。
ICCは1998年7月17日に、国際連合全権外交使節会議において採択された国際刑事裁判所ローマ規程(ローマ規程または、ICC規程)に基づき2003年3月11日、オランダのハーグに設置された国際裁判所。国際関心事である重大な犯罪について責任ある「個人」を訴追・処罰することで、将来において同様の犯罪が繰り返されることを防止することを目的としている。国際関心事である重大な犯罪に個人が係わっている何て言うことがあり得るのでしょうか。
判事・検察官などは、締約国会議(ASP: Assembly of States Parties)によって選出される。判事・検察官として選ばれるためにはどのような条件が必要か。覇権国の恣意的な意向で選ばれるとしたら、そもそもこんな機関は不必要だろう。
その管轄は当初、個人の刑事責任に限られて「集団殺害犯罪」、「人道に対する犯罪」、「戦争犯罪」、そして、「侵略犯罪」(いずれも国際刑事裁判所ローマ規程固有の名称)など、国際人道法に対する重大な違反のみを対象としていた。侵略犯罪についてはその定義が明確に定められていなかったが、2010年の再検討会議 (Review Conference) にて協議が行われ、その定義とICCによる管轄権の行使を認める改正条項が採択された。同改正は30か国の批准により発効する規定となっている。
国際司法裁判所(ICJ)と混同されることがあるが、国連の常設司法機関であるICJは、領土の範囲など「国家間の法的紛争(係争案件)」の解決を役割としているのに対し、ICCはあくまで「個人」の戦争犯罪などに関する刑事責任を明らかにして処罰を科し、将来の同種犯罪抑止を目的としており、全く別の裁判所である。また、ICCは国連からも独立し、その協力関係は別途、「国連と国際刑事裁判所の地位に関する合意」(国連地位協定)を締結することによって成り立っている。国連との協定は2004年7月24日に発効している。
世界123か国が締約している一方、批准していない国も多くある。アメリカ合衆国、中華人民共和国、ロシア連邦の三か国は未加盟であり且つ国連安保理常任理事国であることから、有効性を疑問視する見方もある。
日本は2007年7月17日には加入書を国連に寄託し、同年10月1日、正式に105か国目の締約国となっている。ローマ規程およびその協力法は、国内法において2007年10月1日に発効した。日本がそれまで批准できなかった理由については、様々な複合的な要素が絡んでいたと考えられているが、2007年11月30日に行われた補欠判事選挙では、初めての日本のICC裁判官候補として指名された齋賀富美子がトップ当選を果たすなど、加盟以後は積極的な参加姿勢を示している。齋賀は2009年4月、在任中に急病で死去した。同年、11月の補欠選挙で尾崎久仁子が当選し、同裁判官は第一審裁判部門に配属された。2018年3月には、日本人として3人目の判事に最高検察庁検事・国際司法協力担当大使の赤根智子が就任した。
**齋賀 富美子(さいが ふみこ、1943年11月30日 - 2009年4月24日)
日本の元外交官、特命全権大使(人権問題に関する各種協議、調整等担当=いわゆる人権担当大使)で国際刑事裁判所の初代日本人裁判官。女性初の国連大使(日本で?)も務めた。
日本がICCに対して人材面・財政面で様々な貢献を行う理由について、日本政府は、「日本は外交政策の柱の一つとして、国際社会における法の支配の強化を掲げ、紛争の平和的解決等を促進」するという外交上の理由を挙げており、いわゆる価値観外交、人権外交の一環として位置付けられる。2020年時点で、日本は最も分担金を拠出している(約2400万ユーロ、16.3%)。
主な具体案件
・2005年7月8日にジョゼフ・コニーらテロ組織神の抵抗軍幹部に初のICC逮捕状が発行され、同年10月13日には逮捕状が公開され、2006年6月1日にICCから要請を受けた国際刑事警察機構(ICPO)は国際手配を行った。
**ジョゼフ・コニー (Joseph Kony, 1962年 - ) はウガンダの反政府勢力神の抵抗軍 (LRA) の指導者。霊媒であると主張し、聖書と十戒に基づく神政政権の樹立を掲げ、ウガンダ北部を中心として1987年以降残虐行為を伴い、また少年兵を使ってゲリラ闘争を続けている。
・ICCが初めて国際連合憲章第7章に基づく案件の付託を受けたスーダン・ダルフール案件については、2007年5月に、現職の政府閣僚を含む容疑者2名に対して初めて逮捕状が発行されている。同案件について2008年7月、ICC検察局はさらに同国のオマル・バシール大統領の逮捕状も請求し逮捕状は2009年3月4日に発行された。
**ダルフール紛争は、イスラム原理主義を重視した強権的なバシル前政権が、土地の利用を巡って黒人住民と対立したアラブ系住民に肩入れしたことから、黒人住民が2003年に武装決起して勃発した。推定30万人が死亡するなど世界最悪の人道危機と呼ばれたが、国連などの調停による和平交渉は大きな進展を見せなかった。
・2008年8月には、北オセチアをめぐるグルジア事態について、グルジア・ロシア連邦両国政府の協力を得て調査を開始している。
・2009年1月26日にコンゴ民主共和国の案件について公判が開始された。
・2011年2月26日にICCへの付託では初めて全会一致で採択された安保理決議1970に基づいてICC検察官によるリビアに対する捜査が開始され、6月27日に当時の指導者ムアンマル・アル=カッザーフィーの逮捕状を請求、ICC検察官の要請に従ってICPOは国際指名手配を行った。
・2011年11月30日に2010年コートジボワール危機のさなか人道に対する罪を犯したとしてローラン・バグボ前大統領を逮捕・収監。元首経験者に対しはじめて逮捕状を執行した。
・2012年4月26日にリベリア内戦で人道に対する罪などを犯したとしてリベリアの元大統領チャールズ・テーラーがオランダのハーグで開かれたシエラレオネ特別法廷で国家元首経験者に対する国連設置法廷史上初の有罪判決を受けた。なお、シエラレオネ特別法廷は、この裁判をリベリア国内で開廷した場合には治安・警備上の懸念があったことから、公判はオランダのハーグで実施したため、国際刑事裁判所で裁判があったとする報道があるが、この法廷は、国連が設置したものであり国際刑事裁判所で裁判されたものではない。
・2007年からアフガニスタンにおける予備調査が開始され、2013年11月には「アフガニスタンで、戦争犯罪及び人道に対する罪が過去そして今も犯されている」と結論づける報告書が発表された。しかし、カルザイ政権が人権委員会による報告書の公表を阻止し、米国ほか諸外国政府も了承するように非協力姿勢で、ICCも「正義にかなう」ものにならないと調査は進まず、予備調査は最長の13年間も続いた。それでも、2020年3月にアフガニスタン紛争における米国などの戦争犯罪の疑惑について、捜査を進める判断を出した。これに反発する米トランプ政権はICC職員を制裁するなど圧力をかけ、ICCも一時は捜査開始を却下するなど屈した。その後再開するも、優先対象をISILなどの過激派組織に変え、米軍犯罪は後回しにするとした。
・2022年3月2日には、ロシアによるウクライナ侵攻に伴う戦争犯罪、人道に対する犯罪について、検察官による捜査開始の申立てを受け、日本の赤根智子判事を含む3名の裁判官による検討に入り、2023年3月17日にウラジーミル・プーチン大統領とマリア・リボワ・ベロワ大統領全権代表(子供の権利担当)に対し、ウクライナ占領地域からの子供たちの違法連行に関与した容疑で逮捕状を発行した。更にロシアは条約締結国でない。つまりこんな判決は全く意味がない。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
ワグナー・グループ
ワグナー・グループ(ロシア語: Группа Вагнера、英語: Wagner Group)? 最近ニュースでもチョコチョコ名前がでてくる。ロシアの民間軍事会社(PMC)?。と言うより国際的に活躍する多国籍軍事会社。ソビエト連邦崩壊に伴ってリストラされた元軍人たちの営利会社と言うことか。
複数の紛争にて、ロシア連邦政府の対外政策に沿う形で傭兵として派遣され、親ロシア系武装勢力や外国軍と共に戦うことが多い準軍事組織だと(NATO 諸国によって)推定されている。2014年クリミア危機やシリア内戦、リビア内戦で活動したとか。
ただし、ロシア連邦大統領報道官ドミトリー・ペスコフは記者団に対して、「ロシアには民間警備会社はあるが、民間軍事会社はない」と説明している。確かに今のロシアや中国ではこんな会社は存在すら許されないだろう。
ワグナーと言う名作曲家の名も、意味ありげだ。ワグナーはたまたまナチスドイツのヒットラーに曲が愛されたため、ワグナー好き→ヒットラー好き→プーチン氏もワグナー好き(それ会社名だろ)→プーチンはヒットラー好き→プーチン氏はヒットラーと同じだ。
香港に拠点を置いていたスラヴ軍団に所属していたドミトリー・ウトキン(GRU麾下の元スペツナズ中佐)により創設されたと言われている。組織名はアドルフ・ヒトラーが好んだ作曲家ワグナーを意味し、これをウトキンがコールサインとして使っていたことが由来である。5000人以上いる社員のうち2000人ほどが戦闘要員であり、ロシア連邦軍および警察の出身者以外にもチェチェンやイングーシなどの親露派元民兵なども所属している。
グローバル経済の元では軍事も資本主義も元では金儲けの手段になり得る。自国で軍隊を持つよりも外注した方が遥かに安上がり?
 経営者はウラジーミル・プーチン大統領と懇意なオリガルヒのエブゲニー・プリゴジンという説が一般的であり、主にロシア連邦軍が公式には介入していない状況において、特殊部隊や民兵、サイバー戦争、プロパガンダ工作などを組み合わせて展開されるハイブリッド戦争に従事しているとみなされている。2013年にはウクライナ内戦でロシア軍がウクライナ領内で活動していない状況を作るため投入され、シリア内戦において、ロシア連邦軍が直接介入する前に要員を派遣していた。また、これらの海外での活動において、ワグナー社はGRUより支援・調整を受けているといわれている。逆にウクライナではロシアの侵攻を誘発するためゼレンスキーが先に東ウクライナ民兵を攻撃させたアゾフ連隊の形成にも民間軍事会社の大規模な参加が推定されているようだ。
経営者はウラジーミル・プーチン大統領と懇意なオリガルヒのエブゲニー・プリゴジンという説が一般的であり、主にロシア連邦軍が公式には介入していない状況において、特殊部隊や民兵、サイバー戦争、プロパガンダ工作などを組み合わせて展開されるハイブリッド戦争に従事しているとみなされている。2013年にはウクライナ内戦でロシア軍がウクライナ領内で活動していない状況を作るため投入され、シリア内戦において、ロシア連邦軍が直接介入する前に要員を派遣していた。また、これらの海外での活動において、ワグナー社はGRUより支援・調整を受けているといわれている。逆にウクライナではロシアの侵攻を誘発するためゼレンスキーが先に東ウクライナ民兵を攻撃させたアゾフ連隊の形成にも民間軍事会社の大規模な参加が推定されているようだ。
2021年12月13日、欧州連合(EU)はワグナーなど3社と創業メンバーである元GRU将校らへの経済制裁を発動した。プリゴジンの活動にはロシア企業だけでなく、香港の企業も支援しているとされ、アメリカ合衆国財務省は香港の企業にも経済制裁を行っている。
また、中央アフリカ共和国での内戦でワグナー社を取材しようとしたジャーナリストが死亡しており、彼らが暗殺に関与した疑いが推定されている。
2020年以降、ワグナー社が軍事クーデターとイスラム勢力の攻勢に揺れるマリ共和国で活動していることが判明。マリ政府とロシア政府は否定しているもののアメリカアフリカ軍(AFRICOM)の司令官は、インタビューにて「ワグナーはロシア軍の支援を受けている。ロシア空軍機が彼らを現地へ移送している」とロシア政府が関与していると示唆。また、フランスの外相は、ワグナーの傭兵がイスラム過激派との闘いを口実にマリ暫定政権を支援していると非難するとともに、「ロシア機で移送されてくる傭兵について、ロシア当局が知らないとしたら驚くべきことだ」と言及している。
当然のことだろう。戦争請負人は請負金額にみあう戦闘の成果だけが製品だ。詳細は当然企業秘密であるから、ロシア当局にも何も知らされるはずはない。しかも、状況次第で戦闘のどちらサイドにも寝返るのは当然の資本の論理だろう。
自分は直接武力介入しないで、こっそり大量に武器支援だけをして誤魔化す欧米流の身勝手な行動が、戦争請負人や軍事専門会社の巨大化を原因となっている可能性がある。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
プリゴジン氏の死
軍事民間会社のプリゴジン氏が飛行機事故で無くなったらしい。欧米諸国にとっては朗報だろうが真相は闇の中。プーチンさんの関与が取りざたされているが、ただロシア国内ではプリゴジン氏の人気は異常なほどだ。モスクワへの進軍はまるで凱旋将軍で多くの旗とサイン攻め。死して英雄となる。ゼレンスキー配下の外国人傭兵部隊に対して、東ウクライナ民兵をまとめ、マウリポリ、バフムトの大勝利を収めたのも彼らの功績だったのかも。しかし、プリゴジン氏を支援したプーチン氏はまるでウクライナ侵略の主犯とされてしまった。と言うことはプリゴジン氏は欧米の意図を組んで行動していた可能性も零ではない。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
年金問題は嘘ばかり
*年金問題は嘘ばかり(高橋洋一著:PHP新書)
タイトルは一見過激だけど、著者は年金数理の専門家、年金制度の仕組みについての彼の説明は事実として良さそうだ。「この本に書かれていることは総て嘘だ」とその本の中に書かれていれば、あなたはその本の内容をどう思うでしょうか。
しかし、この本には多分一般の読者には、目を開かせるものがある。
まず議論を始めるにあたって、この本が挙げている大前提がある。数学でいえば定理みたいなもの。大前提が間違っていれば後の議論は机上の空論にしかならない。だからこの部分は大いに検証が必要だ。
1. 年金は保険である。
2. 「40年で支払った保険料」と「20年で受け取る年金」が等しい
3. 「年金定期便」は国からのレシート
4. 保険料は税金である。
5. 日本の年金は賦課方式である。
上の3つは著者が冒頭にあげているもので、4、5は筆者がこの本の内容から判断して付け加えたものです。この5つ前提が守られていれば、「年金は危ない」というデマは払拭されることになる。
§1.年金は保険である
これについては「年金は老後の生活を保障するもの」と言う考えが一般に普及している。だが、保険料を支払わないものは一銭も年金は払われない。つまり自助努力が必要で備えあれば憂いなし。確かに今の年金では生活できないかもしれない。でも、無いよりましでしょうということ。
保険と言えば、何かリスクに備えるもの。生命保険なら死亡するリスクに対応するもの。年金は長生きして仕事もできない収入も無くなる状態になるリスクと考えれば良い。だから定年後の高齢者でも再就職できれば年金は要らないでしょうとなるわけです。そもそも自由業の人には定年なんてないしね。だったら、お金持ちには年金は要らない? 収入も無くなる状態がリスクなら貧富の差は関係ない。リスクへの対応は故人の権利だ。保険料を支払っていればもちろん年金を貰う権利はある。決して若い世代からの所得移転でも施しでもない。
§2.「40年で支払った保険料」と「20年で受け取る年金」
これには少し議論が必要だろう。そもそも40年だの20年だのとの数字が何処から出て来るのか。保険と言うのは複雑で大きな独立した社会システムだ。このシステムが持続可能であるためには、
「国民全体が支払う保険料」≧「国が支払う年金額」
不等号にしたのは、保険料の徴収や支払いに関する人件費等の支払いがあるためで、これ等も年金額の一部(手数料)と考えれば、
「国民全体が支払う保険料」=「国が支払う年金額」
この議論は、国民年金なら総人口約1億人全体を考えたマクロな話。60歳で定年になって年金をもらい始めて100歳まで生きれば積み立てた金額の倍の年金を受け取ることが出来る。でも、60歳で亡くなった方は年金を一銭も貰えない。これを不公平と考え、保険料の支払いなど馬鹿げていると思われる人もいるかもしれない。でも、残念ながら保険料の支払いは、税金であって国民の義務なのだ。上の等式が成り立つように年金数理官達は大量のデータを処理して、保険料や年金額を決めているようだ。年金システムは維持するのにも膨大な労力のかかる社会システムである。みだりにルール変更してはならないものだ。
§3. 「年金定期便」は国からのレシート
この点に関しては、筆者はコメントできない。あまり関心を持って眺めたことがないからだ。 でも、支払った保険料のデータは大切だ。年金の保険料には、国民年金と厚生年金がある。国民年金は定額で問題はなさそうだが、厚生年金の場合は危ない。転職やら姓が変更したり、海外勤務があったりした場合に、正確に転記されていない場合があったようだ。例の消えた年金問題。当時の社会保険庁のずさんな管理を問題にされた事件が多発していた。
先に「40年で支払った保険料」=「20年で受け取る年金」としたが、実際にはお金の価値は変動している。50年前なら、1杯30円~50円で食べられたラーメンやカレーライスが今では300~500円、多分それ以上出さないと食べられない。日本は今までインフレ社会で物価も賃金も毎年上がっている。年金代わりにタンス預金で老後の準備をしたとしたら、全く少額で生活の糧にならないでしょう。だから年金数理官達は、年金積立金を常に現在価値に直して時々刻々評価し直している。コンピュータを使って複雑な計算をしている訳だ。年金支給額も毎年変化する。でも原理は簡単。次の式を見れば分かる。
FV=PV(1+r)n
PV=FV/(1+r)n
ここで、FVは将来の予測価値、PVは現在価値、rは国全体の平均金利、nは年数という訳。だから集めた積立金は適切に運用しないと目減りしてしまう。そこで、財テクをやろうとするのですが、間違えた投資をすると集めた積立金が消えてしまう羽目に。
「年金定期便」と言うもの、一度ゆっくり眺めてみる必要があるかも知れない。
上の式は、例えば今100万円持っていたら、将来はそれ以上の見返りがありますよと言うことだ。長生きしていれば。でも、今は金利が零に近く、タンス預金とあまり差がないと言われるかもしれない。でも、将来金利が上昇する可能性もある。また、予想以上に長生きしてしまうリスクもある。所詮保険とはリスクに対応すべきものだ。
§4. 保険料は税金
保険料の支払いは、義務である。滞れば罰則も待っている。徴収する主体は、今は厚労省であるが、税ならば財務省が管轄すべしとの意見もある。多分厚労省も簡単には利権を手放さないでしょうが。
逆に、言えば年金を受け取るのは国民の権利であり、よく言われているように今の年金は若い人が負担しており、そのおかげで老人は年金をもらえるというのは嘘八百と言うこと。たまたま手持ちの積立金がないから、若い人たちが収めた保険料を流用しているだけで、当然、若い人たちの年金も同様に次世代の若者たちの積立金で賄われる。これが賦課方式と言われるものだ。
老後のリスク(長生きする)の回避は、本来自己責任と捉えるべきかもしれないが、実際にはそんなリスクに対処できる人はほとんどいない。だから国民全部を強制的に保険に加入させ税として保険料を取り立てることに。保険料は義務であり誰も免除されない。
§5. 日本の年金は賦課方式である。
賦課方式では、現役の人が収めた保険料は、すぐに高齢者の年金に回される。これを「世代間の助け合い」或いは「親への仕送り」と呼んでいる。つまり、政府が積立金を持つ必要がない良い制度な訳。しかし、保険料を治めなければ将来年金は貰えない。保険料を納めておれば将来の年金が保証されているのであれば、現役の人が収めた保険料は自分のためであり、何も人助けしている訳でもない。つまり、「世代間の助け合い」という説は大嘘と言うことだ。本来高齢者の年金は同世代の無くなった高齢者の分で辻褄が合うように作られているはずだ。積立金が底をついたということは厚労省が財テクに失敗したことの言い訳でしかない。現役の人が収めた保険料を高齢者に年金として回すことは賦課方式の性質から言ってまっとうな行為であり、保険業務とは本来そのようなものである。
つまり、賦課方式は、早く亡くなった人の収めた保険料で、長生きした人の年金を賄っているだけです。今までの日本は人口がピラミッド型で保険料の積立は十分にあったので、現役世代の収めた保険料に手を付けずに済んだだけ。
では、国民みんなが長生きすれば?確かに保険制度は崩壊か? でも、制度自体が人口統計など基にして作られたもので、人口や死亡率の推移はゆっくりとしか進まない。だから、これ等の変化は予測可能であり、キチンと年金数理担当官等によって把握されており、保険料や年金額の計算に繰り込まれている。だから保険料も年金額も毎年少しずつ変わっているはずだ。
だから、積立金が底をついたので消費税を値上げして補填しましょうなんて言うのもとんでもない大嘘の訳。年金と消費税は全く何の関係のない問題なのです。
賦課方式は、日本に限らず多くの国で実施されている。積立金が無くても制度を始められる利点がある。日本の年金も国民年金、厚生年金とも当初から賦課方式となっていた。
賦課方式とは異なった方式として積立方式がある。確定拠出型の年金などがそうだ。積立方式は相互扶助の原理はない。あくまでも個人の資産。積み立てた拠出金はいつでも残金がある限り降ろせる。シンガポールなどが積立方式らしい。でも、積立方式の欠点としては、もらえる年金の給付額は、賦課方式に比べて相当少なくなりそうだ。
§6. まとめ
この本読んで日本の年金制度は破綻寸前と思いますか。今の年金制度は問題が多く改良すべきと思いますか?年金の財源を確保するために消費税を引き上げは必要でしょうか。どうも、今の制度をキチンと守っていく方が大切なのではないでしょうか。今までの話は年金の中で国民年金と厚生年金の話です。
でも、考えて見ると、国が行っている保険事業には年金の他に医療保険なんて言うものあった。こちらも保険だ。こちらの方は年金と比べ本当に破綻寸前の可能性は無いだろうか?
「国民全体が支払う保険料」=「国が支払う医療費」
この関係は成り立っているのか。「自分が払う医療費」<「自分が収める保険料」。
実際医者に行ってみれば保険適用の治療以外に保険適用外の治療を進められることが多くなっている。「自分が払う医療費」<「自分が収める保険料」はある意味、制度が存続するためには必要かも知れない。しかし、保険適用の範囲が狭まることはある意味、保険制度破綻の兆候を示していることを意味しないだろうか。風をひいてもほとんど無料で診察を受けれるのに、生死を伴う大手術が必要な時は保険適用外ですとなる。これはこれでやはり問題でしょう。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話
同性結婚
同性結婚(same-sex marriage)は、同じ性別同士(男性と男性、女性と女性)が結婚すること。同性間結婚(どうせいかんけっこん)もしくは同性婚(どうせいこん)ともいう。ここまでは言葉の意味は誰でも分かる。でも、今何故これが政治問題になっているのだろう。
そもそも結婚とは、配偶者と呼ばれる人々の間の、文化的、若しくは法的に認められた繋がりの事で、配偶者同士、その子との間に権利と義務を確立する行為である。それはほぼ普遍的な文化であるが、結婚の定義は文化や宗教によって、また時間の経過とともに変化する。
配偶者とは、婚姻届を出した婚姻によって生じる地位であり、法律上は親族となるが、親等はない*??。婚姻の届出がなされていない内縁関係の場合は、法律婚とは異なり、法律的に「配偶者」と呼ばない。配偶者の地位は、婚姻の解消(離婚)で失われる。
同性結婚が認められれば、どんな男同士、女同士も互いに配偶者となることが可能で、配偶者としての権利を主張できる。一体どんな権利があるか。また、同性婚が認められなければ誰でも与えられる配偶者としての権利が損なわれるからこれは人権侵害の差別だというのが、同性結婚推進派の主張らしい。
日本においては、法律上、「配偶者」を規定する条文、用語の定義はなく、行政機関によって、慣例上恣意的に、法律上の婚姻関係(戸籍上の婚姻関係)にある者を指すと解釈、運用されている。このため、例えば、相続権は戸籍上の婚姻関係にある配偶者にのみ認められており、戸籍上の婚姻関係にない事実婚や同性カップル等の配偶者にはない(ただし、内縁上の配偶者に遺贈することは可能である)。この点は欧米ではどうか、その他人口の大多数を占める非欧米諸国ではどうか。
一方、内縁関係にある相手方を「内縁配偶者」として戸籍上の婚姻関係にある配偶者に準じて扱う場合もある。例えば交通事故が発生した場合の加害者に対する損害賠償請求権は内縁上の配偶者にも認められている。ただし、戸籍上の配偶者が別にいる場合には賠償額は減額されうる。
生物学においては配偶とは、2つの個体が互いの遺伝子を交換する生殖行為であるから、普通の多細胞生物なら2つの性、オスとメスが互いに配偶者となることは明白かも。だだし、単細胞まで遡れば性を有しない繁殖方法もある。
同性結婚と称される行為や関係―どうもこれはパートナーシップ制とか言うらしい―には、男女の夫婦と同じく、ある種の社会的な権利が付与され、法的な保障や保護が行われているとされる。多くの場合、性別のカテゴリーが同じ者同士が男女の夫婦のように家族としての親密さを基礎として、社会的にも経済的にもパートナーシップを築き、それを維持することを指す。国連加盟国は196カ国ある中、2023年3月現在では34ヶ国で同性婚が認められ、30ヶ国で同性カップルに対して婚姻とほぼ同等の代替制度が認められている。と言うことはまだ、ほとんど大部分の国では全く認められてないわけだ。これを人口比率に換算すればもっと少ない。つまり認めているのキリスト教国(正教を除く)だけに絞られるようだ。
仏教や神道では同性愛に対して言及は無いために宗教由来の同性愛者への刑罰は無かった。逆に、一神教宗教(ユダヤ教、キリスト教、イスラム教)における旧約聖書『創世記』では、ソドムという町の住民たちが男性同性愛者であったことから神(ヤハウェ)により滅ぼされたという伝承を載せ、キリスト教圏、イスラム教圏、ユダヤ教徒、更にはヒンズー教徒からは同性愛そのものが宗教的異端・刑事罰対象とされてきた。しかし、キリスト教圏において1989年にデンマークは世界で初めて、同性カップルに異性カップルが結婚している場合に認められるものとほとんど同じ権利が認められる「登録パートナーシップ法」が作られた。2001年にはオランダで初の同性結婚制度が始まった。そしてユダヤ人が建国したイスラエルでも、ユダヤ教ではタブーであるために同性結婚は導入しないもののシビルユニオンの形で同性愛を容認し、ヒンズー教徒が多数派であるインドの最高裁判所も2018年、同性間性行為者を処罰する刑法の規定がインド憲法に違反するとの判決を下した。こうした動きと対照的に、イスラム教国においては、同性愛者は今も異端視され、特に憲法や自国の司法をイスラム法(シャリーア)に義務付けている40前後の国・地域では、同性結婚の禁止と刑罰が憲法に規定されるだけでなく、同性愛自体を犯罪化されている。特にイランなどでは同性愛者は死刑対象となっている。
この制度の利用者は同性愛者(男性:ゲイ、女性:レズビアン)なので同性愛結婚や同性愛者の結婚と呼ばれることもある。また英語(en:same-sex marriage)では主に「same-sex marriage(同性結婚)」もしくは「gay marriage(ゲイの結婚)」と表記される。
同性愛者と言う考え方自体が、かなり一神教的なもののようだ。一方、自然人類学(霊長類学)の研究からは、同性愛者と言うものは決して異常なものではなく、猿やオオカミと言った哺乳類の社会にも頻繁に起こり得る、自然なものでそれなりに群れ内部で受け入れられているらしい。
日本では、男(女)同士2人或いは複数が同棲して共同生活していても、別に近隣に怪しまれることはないだろう。そうでない国とはルールが異なるのは当然だ。
社会学の部屋PartⅡへ
経済の話